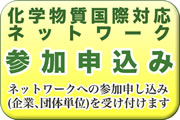改正化審法の対自的対応―産業界の診方・観方・味方―
- このコラムは、化審法(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を指す。以下同様。)見直し合同委員会のメンバーでもあった北村卓氏に、化学産業界の第一線で過ごされてきた豊富な経験に基づき執筆をいただいたものです。
- このコラムに記載されている内容に関し、法的な対応等を保障するものではありませんのでご了承ください。
- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
→ご意見・ご感想電子メール送付先:
化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@env.go.jp)
目次
- 第1回 改正化審法の背景
- 第2回 化学物質の特定手段
- 第3回 用途の把握
- 第4回 エッセンシャルユース
- 第5回 良分解性物質
- 第6回 少量新規化学物質
- 第7回 高分子化合物(ポリマー)
- 特別号1 今後の課題:法規制と自主管理
- 特別号2 今後の課題:化学物質の自主管理
- 特別号3 今後の課題:リスクコミュニケーション
1.改正化審法の背景
改正化審法が成立しました。リスク管理の考え方を積極的に取入れている点が大きな変化であり、海外規制(条約)との整合も考慮されています。
化学製品が広く社会生活に浸透し、快適な生活を維持するためには不可欠のものとなっている現状を踏まえ、今回の改正は実現が可能で最も効果的な規制方法を採用したといえるでしょう。製造・輸入事業者だけでなく、取扱(購入・使用)事業者も配慮すべきことが含まれていることも特徴です。
事業者の果たさなければならない役割と、その手順の説明は次回以降に記しますが、その前に改正の背景を整理したいと思います。というのも、法律の改正直後は規制をする側もされる側も、運用の詳細は手探り状態で、妥当性の判断が難しいときでもあります。法律への適切な対応を考えるうえでは、改正の基本的な考え方と背景を理解していることが重要でしょう。
今回の改正の重要な背景の一つは国際整合性です。2002年に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)」における「2020年までにすべての化学物質による人及び環境への影響を最小化する」という世界的な合意に基づき、各国は化学物質の法規制の整備に着手しました。これからの化学物質の管理では、WSSD合意に合致しているかどうかが重要で、そうでなければ改正化審法への対応にも適切ではないことになります。
現行の化審法は、ハザードを基本にしたいわゆる「蛇口」規制で、第一種特定化学物質はその製造・輸入・使用を認めない立場をとってきました。しかし、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」では、規制物質でも特別の用途に限り認めることがあります。この条約を担保するため、国内法(=改正化審法)では、エッセンシャルユースとして極めて厳しい制限つきではあるものの第一種特定化学物質の製造・使用・販売を許容する運用に変わります。化審法規制にリスク管理の考え方を導入したことになります。
広く使用されている物質を、ハザードのみの基準で性急に全廃にすれば、代替物質のリスク評価に時間的余裕が無く、ハザード(リスク)不明の物質に転換することもあるでしょう。今回の改正は、厳格な管理と科学的な知見でリスクを最小化する方法での化学物質管理を選択したことになります。
その背景には、安全性データの取得やリスク管理手法の開発が進み、リスク管理が現実のものになってきたということもあるでしょう。
改正化審法は、規制する側にもされる側にもリスクの評価とそれに基づく管理を求め、使用時のリスクを考えることで取扱事業者にも社会の信頼を裏切らない責任ある配慮を求めているといえるでしょう。
キーワード:「ハザード管理からリスク管理へ」「国際整合性」
2.化学物質の特定手段
今回の化審法の改正で、事業者にとって大きな変化は、化学物質の特定手段として化審法番号とともにCAS番号が利用されることでしょう。既に「化審法化学物質」(化学工業日報社)にはCAS番号の記載がありますが、これは事業者のための参考で、網羅性と正確さを保証してはいません。なお、CAS番号とは、米国のChemical Abstract Serviceが学術誌や特許などから抽出して物質毎につけた通し番号で、届出で番号をもらうこともできます。
今までの約3年毎の承認統計でも化学物質の製造・輸入量を報告していましたが、これからはCAS番号(なければ化審法番号)を付して、一般化学物質等の正確な製造・輸入量届出が義務化されます。国はCAS番号と化審法番号の対応付けという大変な作業に着手しています。同じ化審法番号に異なる炭化水素鎖長の物質が含まれている事例もあり、それぞれの物質には異なるCAS番号が付されています。公開される対応表に取り扱う化学物質のCAS番号が漏れていることがあるかも知れません。製造・輸入事業者は前もってCAS番号の確認をしておけば、使用するCAS番号が正しいか、リストに漏れていないか、ということが容易に判断できます。CAS番号が確定すればその後は海外の化学物質インベントリーとの対照が容易で利便性があがるメリットもあります。
CAS番号の使用で注意すべきことがあります。(1)多くの物質はCAS番号と一対一に対応しますが、必ずしもすべての物質ではありません。CAS番号があっても単一の化学物質ではないこともあります。ナフサ系の溶剤はそれ自身が数多くの炭化水素(化学物質)の混合物であるにも係らず一つのCAS番号を持つことがあります。(2)同じ化学構造や組成でも製造者毎に異なる番号が使用されることもあります。化学構造の特定が難しい物質では、製法が異なれば結果として同一の化学物質でも異なるCAS番号が使用されることがあります。製造・輸入事業者は自身の判断で、最も適切なCAS番号を使用することが必要です。(3)さらにCASの命名法が通称やIUPAC(国際純正応用化学連合)と異なるので、複雑な構造の化学物質ではCASの名称から同一性の判断が難しい場合もあります。特に高分子化合物では、CASの命名法はほとんど利用されていないので、CAS番号での特定は難しいでしょう。高分子化合物が製造・輸入数量の報告対象になるかどうかは、事業者にとって関心のあるところです。
改正化審法における数量報告の目的が「環境を経由した」ばく露によるリスク評価のための基礎データの収集ですので、相対的にリスクが低いと考えられ、低分子化合物を放出しない高分子化合物は、化審法における報告対象から除外されてもよいのではないでしょうか。
キーワード:CAS番号、化審法番号、物質の特定
3.用途の把握
化学物質をCAS番号で特定できれば、次は用途と用途毎の数量の把握が必要になります。用途は製造者が容易に推測できる場合もありますが、数量の把握には顧客(使用者)からの情報が必要になる場合があり、情報の収集が難しくなる場合もあるでしょう。これまでは、顧客が供給者に用途(数量)情報を提供する習慣がないので、情報の開示をためらう顧客もあるでしょう。
用途情報は改正化審法の化学物質の評価では重要な役割を担っており、数量情報とともに「環境リスク」の判断に用いられます。一般化学物質がスクリーニング評価の結果で優先評価化学物質になり、さらに詳細なリスク評価で懸念があるとされれば、特定化学物質になり厳しい管理が製造・輸入(供給)者と使用者に求められます。
優先評価化学物質は製造・輸入や使用に制限を受けませんが、ブラックリストに掲載された印象を持たれるので、事業者は指定を避けたいところです。一般化学物質のばく露評価では、用途情報が無ければ実態よりも高くリスクが評価されることにもなります。用途が明確であれば、それに応じた排出係数が用いられるので著しく過大なリスクを示すスクリーニング評価結果を避けることができるでしょう。
規制に直接つながる優先評価化学物質のリスク評価では、用途情報はさらに重要です。適切な管理が講じられていれば、環境放出の割合はさらに低いことを産業界は証明できます。企業の化学物質管理の適切さが問われているということができます。十分な情報が無いと実態以上に高リスクと判定され、製造や使用にさまざまなに制約がかかり、これまでどおりに使い続ける事ができるなくなることもあるので、製造・輸入者にとって顧客からの用途(と使用方法)情報が重要であることが理解できるでしょう。このように化審法のリスク評価では用途情報は極めて重要な役割を果たします。物質の特性ではなく用途等の情報不足が原因で必要以上の規制を受けることは、製造・輸入者だけでなく使用者も避けたいでしょう。
化学物質のリスク低減に、製造・輸入(供給)者と使用者のコミュニケーションの重要性はますます高まり、わが国の商習慣もそれによって変わる可能性もあるのではないか、と思われます。これからは、製造者・使用者の双方にとって、化学物質に関する互いの情報交換とそれぞれの立場での適切なリスク管理が重要になります。
キーワード:用途の把握、コミュニケーション
4.エッセンシャルユース
これまでは、今回の化審法改正の全体像を簡単に説明しました。これからは、具体的に取り扱いが変わるいくつかの化学物質カテゴリーについて説明しましょう。 最初は厳しい管理を前提にエッセンシャルユースとして限られた用途が認められるようになった第一種特定化学物質です。
難分解性・高蓄積性で長期毒性の懸念がある第一種特定化学物質は、環境中に長期間滞留し低濃度でも環境生物に蓄積されれば、食物連鎖等を通じて、ヒトや哺乳類・鳥類などの高次捕食動物にも影響が懸念されます。そのような物質が厳しい管理のもととはいえ、製造・使用が認められるようになるのは、リスク管理へ考え方が変化していることによります。わが国が化審法で担保するストックホルム条約は、残留性有機汚染物質(POPs)の製造・使用を禁止しますが、条約は代替品がなく廃絶することでむしろ他のリスクが増大し、社会経済的な負担も増加するときは、エッセンシャルユースとして一部の用途を認めています。これまでの同条約の対象物質は条約発効以前に化審法で第一種特定化学物質として製造・使用が禁止になっていたので、条約の規制も実質的に影響しませんでした。しかし、新たな対象物質のPFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)は事情が違います。
PFOSは現在第二種監視化学物質で、代替物への転換努力が産業界で進められています。しかし、優れた界面活性効果と水にも油にも溶けないという特徴で、代替物が見いだせない特別な用途に少量が用いられています。例えば、この物質なしでは高精細の半導体が生産できません。ストックホルム条約の対象物質は第一種特定化学物質に指定されることとなりますが、現在も使用されている物質が代替物なしで全面的に禁止されることは社会経済的な損失があまりにも大きいので、厳格な管理下での使用を認めようというものです。代替リスクが明らかでない代替品を安易に使用するよりも、リスク管理を強化して使用を継続するほうがよい、という現実的な考えもあるでしょう。
しかしこのような例はやはり特別で、これまでの第一種特定化学物質が市場に復活することも、新規化学物質がエッセンシャルユースを認められて、第一種特定化学物質として市場に登場することもないでしょう。どちらも、「なくても現実の社会は不便をしない」からです。エッセンシャルユースは「規制緩和」ではなく、産業界の生産者と使用者に、リスク評価と具体的で厳格な管理を義務付けたものと考えるべきで、リスク評価された代替物が現れるまでの経過的な措置と考えるべきです。
キーワード:エッセンシャルユース、リスク管理
5.良分解性物質
これまでの化審法の規制対象は、環境中で容易に分解されない(難分解性)物質でした。しかし、分解されやすい(良分解性)物質も環境中で検出されることがあります。そのような物質でも排出量が分解量を上回れば環境中に蓄積するのではないか、その影響を無視できるのかという懸念から、今次改正により良分解性物質も化審法の規制対象物質になりました。環境中で分解しやすい化学物質も含めて、実際に私たちの身の回りにどんな化学物質がどのくらいあり、どこから来るのかということは誰にも関心のあることでしょう。
リスク評価には、用途・数量情報とともに、環境モニタリング結果やPRTR排出量データなども用いられるようになりますが、環境中の化学物質は必ずしも工業化学品だけに由来しているのではないことに注意が必要です。PRTRの推計によれば、良分解性物質のうち、平成19年の全(推定)排出量では、ベンゼンの85%、ホルムアルデヒドの91%、アセトアルデヒドの85%、1,3-ブタジエンの90%、トルエンやキシレンの約20%が移動体(自動車等の輸送機関)から排出されたものでした。
環境中の化学物質が工業化学品由来でないにもかかわらず、化審法で工業化学品のみを規制し製造・輸入・使用を制限することは不充分であるだけでなく、産業上重要な化学物質の製造等に影響を与え社会経済的な損失を生じることにつながりかねません。環境中の化学物質がどのようなものに由来しているのかを見究め、化審法による規制の効果を正しく見積もることが重要です。
良分解性かどうかとは別に、化学物質の取扱事業者には、適切な管理と無害化処理などでできるだけ環境に放出しない努力が求められていることは言うまでもありません。
キーワード:良分解性物質、PRTR
6.少量新規化学物質
少量新規化学物質(以下「少量」という。)は、毒性データが十分になくても、類似物質の知見や化学構造等を参考として、環境汚染の懸念がないと判断されれば、国が製造・輸入総量の上限を1tに調整して確認しています。本格的な使用が始まる前の段階で多額の試験費用をかけずに製造・輸入が認められるのは、有用な新規化学物質の開発には重要な制度で、化学物質の規制法を持つどの国にも類似の制度があります。
化審法見直し合同委員会(以下「合同委員会」という。)の結論では、「少量」については総量1tから、「申請者毎に1t以下となるように確認することが基本」になりました。これで国は全体(約20,000件)の8割を占める一者からの申請物質を含めて、全ての物質毎に申請数量を集計し、申請者毎に確認数量を割り振る作業が軽減されるだけでなく、申請者も申請数量どおりに確認されるかどうか、前年度の確認数量が確保できる(減らされない)かどうか、という心配をしないで済みます。
しかし、現行のように「少量」の確認を低生産量新規化学物質(以下「低生産」という。)の前に行った場合、「少量」と「低生産」の確認数量の合計は最大10tですので、「少量」の申請件数が多くなると、「低生産」の確認数量に影響が出るのではないかという心配があります。試験費用をほとんど負担する必要がない「少量」の確認数量次第で、分解性試験と蓄積性試験の費用負担が必要な「低生産」の必要量が確保できなくなるという矛盾が生じる可能性があります。しかし「低生産」の確認を先に行えば、今度は「少量」の確認数量が保証されないので、ビジネスに支障が出て、新規化学物質の開発が進みにくくなると考えられます。
この矛盾は合同委員会で議論されている段階で実務担当者からは指摘されていたものですが、残念ながら現在の法体系では解消できないようです。そのため国は「少量」の上限を申請者毎に1tとすることを断念し、総量を1tとする運用を継続することにしたようです。
「少量」の制度は改正化審法においてもこれまでどおりですので、規制の強化ではありませんが、総量から事業者毎への運用の変更は新規化学物質の開発を加速する制度として産業界は期待するところが大きかっただけに残念です。
合同委員会の結論との違いが運用上の問題点によっているだけに、今後の化審法改正では実現を望みたいものです。リスク評価に必要なデータの収集やリスクの推計方法も進歩していますので、このような物質も数量管理だけでなく入手可能なデータからリスクを考えるようになることが期待されます。
キーワード:少量新規化学物質、低生産量化学物質
7.高分子化合物(ポリマー)
ポリマーは大きな分子量を持ちます。そのため、特別にデザインされたポリマー以外は、生体膜の透過性や水への溶解性に乏しく、環境中で低分子量物質に分解されにくいので低ハザード(毒性、環境影響)と考えられています。1987年に採用された化審法の簡易的な試験方法(高分子フロースキーム)はポリマーのこの特徴を考慮しています。
ポリマーは平均分子量や分子量分布、製造方法等で特性が変化し、化学構造式だけからでは物質の特定や同一性の証明が難しく、世界の化学物質規制法でも取扱いが異なります。EU(REACH)は登録が不要で、米国(TSCA)には免除規定があります。しかし化審法では既存物質のみで成立つ共重合体も、組み合わせが新規であれば新規物質の届出が必要です。
ポリマーはポリエチレンやポリスチレン等の重合系とポリエステル等の縮合系に大別できます。多種多様な物質がモノマーに用いられる縮合系では、モノマーの一部置換(変性)で新規の組み合わせになれば新規物質となりますが、試験や手続きに時間的猶予が無い場合は実用化を断念することもあるでしょう。しかし、変性には既存の汎用物質や生物由来物質も多用されるので、分解性や溶解性などに特別の機能を持たせたポリマー以外で変性量の少ないポリマーは届出を簡略化することが現実的でしょう。これにより新規機能材料の開発が加速されることが期待されます。
OECDの化学品プログラムは、世界の共通認識として低懸念ポリマー(PLC)という考え方を提案しています。分子量、安定性、溶解性等で一定の要件を満たすPLCの届出を不要にすれば、新規材料の開発に一層の加速が期待されます。データは必ずしも十分ではないがポリマーの有害性は高くないだろう、という考えがPLCの前提ですので、物質毎のデータ取得・報告や該否判定ではなく、製造(輸入)者自身によるPLC基準への適合の確認と保証で届出を不要とすれば、わが国と海外の制度の違いが緩和されます。
ポリマーの特定と同一性の証明が難しいことは既に記しました。実質的に同一のポリマーが異なる名称で表現されたり、逆に分子量(分布)等の違いで性状や毒性が異なっていても同じ範疇(名称)に分類されることがあります。新規届出物質の約70%がポリマーで今後もその比率の高まりが予想されますが、実質的に低リスクと考えられるポリマーに、物質としての製造(輸入)量報告を求めても、製造(輸入)者に負担がかかる一方で、リスク管理上の有効性が期待できないように思われます。
キーワード:高分子フロースキーム、低懸念ポリマー(PLC)、国際的な規制制度
特別号1 今後の課題:法規制と自主管理
これまでは化審法改正の背景と実務的対応を説明してきましたが、これからは化学物質管理の将来像を考えてみます。化審法改正の合同委員会の議論を参考とした、筆者の感想と思っていただければ幸いです。
化管法改正時にも、化学物質のリスク低減に法規制と自主管理のどちらが有効か、ということが議論されました。「法に触れなければよい」「法で基準を決めてほしい」という「法」に依存した考え方が根強くありますが、変化する社会の要求に応える化学物質管理はそれでよいのだろうか、という思いがあります。
罰則のある法規制は最も強制力がある反面、守ろうとすればそれが可能な規定にならざるを得ないでしょう。守れない規定は空文となります。ハザードやリスクの評価で無条件に廃絶すべきとされる物質や、第一種特定化学物質のエッセンシャルユースのように国際的枠組みが明確であれば法規制は有効ですが、そのような物質は決して多くはありません。将来を予見することは難しく、多くは被害が表面化してからの後追いの法規制になるのが現実でしょう。規制で影響を受ける不特定多数の利害関係者の誰もが納得できるためには、科学的に明らかにされた事実の集積と因果関係の証明が必要ですが、それには長い時間が必要です。代替物質や代替手段の探索やリスク評価とともに、重要ではあっても考慮されない被代替物質とのリスク比較も必要で、リスクが想定されるという理由だけでの規制は、コストと時間の浪費に終わることもあるでしょう。
「法規制と自主管理のベストミックス」という言葉があるように、近年は自主管理への期待が高まっていると言えるでしょう。自主管理が功を奏した例として「有害大気汚染物質の自主管理計画」があります。大気汚染防止法の改正を受け平成9~11年度と13~15年度の二期にわたり、対象12物質の総排出量で60%に近い削減実績をあげました。またPRTR法の施行では多くの物質で環境排出量が削減されています。どちらもきっかけは法律の制定・改正でしたが、削減手段は事業者に委ねられ、費用対効果が最良と思われる方法を採用しました。
ハザードデータの収集とリスク評価では、日本の化学企業も積極的にJAPANチャレンジやOECDのHPV活動に参加して貢献しています。
このような事業者の自主管理活動成果は社会の共有財産として環境リスク低減に貢献するだけでなく、事業者自身も環境放出や消費者暴露を抑制した製品開発や材料・工程の改良につなげています。しかし、法規制で同じ効果を上げようとすれば、取扱方法や用途の一つ一つに細かい規定が必要で法制化は難しい作業になります。事業者がリスク評価結果を自らの判断で製品開発や使用方法・用途に適用する自主管理は、効率的な化学物質管理と言えるでしょう。
キーワード:法規制、自主管理
特別号2 今後の課題:化学物質の自主管理
事業者の自主管理活動が環境リスクの低減に有効であることを記しましたが、実績だけでなく、活動それ自体が社会から信頼を得ることも重要です。
化審法見直し合同会合では、自主管理活動の成果事例として、有害大気汚染物質の自主管理計画や化管法の制定を契機とした事業者の排出削減活動が上がりました。化学産業界の「レスポンシブル・ケア」や塗料工業会の「コーティング・ケア」などの自主管理活動も、環境汚染の防止、製品や輸送への安全配慮、労働災害の減少など、事業活動の全ての側面で社会貢献を目指していますが、残念ながらどれも社会に広く知られているとは言えません。産業界の自主活動は「なんとなく信用できない、どうせ手前味噌」などと思われがちですが、企業はかけたコストに見合った程度には、活動が社会に認知され信頼を得ることも必要でしょう。
あまり知られていない理由として、情報発信の不足があげられるでしょう。環境報告書やCSR報告書への記載だけでは十分に理解されないだけでなく、どこまで「真剣に」取り組んでいるのかもわかりません。公表された成果がその企業や社会にとって妥当かどうか、ということは判断が難しいものですが、具体的な目標と成果を対比させれば、活動の「真剣さ」が伝わり理解されやすくなるでしょう。「不言実行」は美徳ではなく「有言実行」、すなわち事前の情報公開が重要ではないかと思います。
化管法の制定で個別事業場のPRTRデータが入手可能になることの影響を産業界は心配しました。データが事業場の実態を反映し、公表は企業秘密の漏出になると考える人もいました。しかし実際にはデータの開示請求も少なく、そのデータから特定の工場が批判を受けたという事例も聞きませんし、今ではデータの公表が企業秘密の漏出になると考える人もいないでしょう。化管法の改正でデータは公表されますが、これからも事業活動に大きな影響があるとは思われません。ただし、その事業場や企業が別の要件で反社会的と見なされなければの話ですが。
化学物質の自主管理は、目的により利害関係者が変わるので情報公開の内容も手段も変わります。取扱作業者にはハザードとばく露(作業環境)状況から健康リスクの説明、PRTRでは環境影響を最少化する企業活動の市民への伝達、製品中の化学物質であれば用途を考えたリスク評価と不適切に使用されないための配慮などが必要です。法規制とともに化学物質管理の両輪をなす自主管理活動が社会の理解を得るには、実績や情報公開とともに事業者からのリスクコミュニケーションが求められているといえるでしょう。
キーワード:自主管理、情報公開、リスクコミュニケーション
特別号3. 今後の課題:リスクコミュニケーション
化学物質のリスク管理としての事業者による自主管理では、実績とともに利害関係者からの信頼が重要です。化学物質のリスクへの社会的関心は高まっており、一方的な「安全・安心」の繰返しでは説明責任を果たしたことにはならないだけでなく、かえって不信を買うことにもなり、利害関係者への情報伝達の重要性が指摘されています。
リスクコミュニケーションは、企業・行政・市民の間で交わされるものと理解されています。しかし、化学製品には溶剤・触媒のように最終製品(消費財)には含有されないものの生産には重要な原材料や加工工程で非化学製品に変わるものがあります。最近では成型品中の化学物質にも規制がかかるようになり、消費財の生産者にも化学物質のリスク管理や説明責任が求められるようになっています。そのため、サプライチェーンの上流にある化学製品の供給企業(川上)と下流の顧客企業(川下)の間で情報伝達とコミュニケーションが必要になっています。
今までは川上は最終製品が何かということにあまり関心を持たず、ハザード情報としてMSDSを配付し、特に顧客からの要求があれば追加情報を提供してきました。インターネットの普及で以前より容易に誰もがハザード情報にアクセスできるようになりましたが、どの情報をリスク評価に用いるべきか、得られた情報は信頼できるかどうか、という判断には専門性が求められます。化学企業には化学物質のリスク評価の力量が求められています。製品開発の初期にリスク評価を行えば不適切な製品開発も避けられます。川上のリスク評価への参加や協力が必要になることもあるでしょう。安全性(リスク)情報はサプライチェーン上で双方向性を持つようになることが考えられます。
我が国の「ものづくり」は、品質を「管理」し「造りこむ」ことに優位性があると言われています。たとえ輸入原料が安価であっても国産原料を選ぶことや海外に生産拠点を移さずに国内で生産供給を継続することは、品質の安定した材料と「顔の見える」供給者への信頼が、翻って自社の生産・管理コストを低減させるからです。安全も品質と同じです。安全性に責任を持つ生産者の原料を使用して、消費者の安全安心に応えることは、リスク管理の選択肢の一つで、事業者間の協同による「安全・安心」の造りこみといえます。製品リスクとともに改良製品では代替リスクの評価も必要になりますが、事業者間の協力・連携が不足すれば、時間やコストの浪費や誤った判断につながることもあります。これからのリスク管理では、個々の事業者が評価能力をつけるだけでなく、協力(リスクコミュニケーション)が求められます。このような活動が発展すれば、化審法合同会合で論じられた「サプライチェーン」を通じた総合的な化学物質管理につながるものと思われます。
キーワード:リスクコミュニケーション、安全性情報、化学物質総合管理