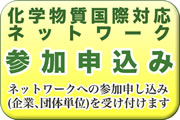国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)と化学物質管理のこれから
- このコラムは、化審法(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を指す。以下同様。)見直し合同委員会のメンバーでもあった北村卓氏に、化学産業界の第一線で過ごされてきた豊富な経験に基づき執筆をいただいたものです。
- このコラムに記載されている内容に関し、法的な対応等を保障するものではありませんのでご了承ください。
- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
→ご意見・ご感想電子メール送付先:
化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@env.go.jp)
目次
- 第1回 SAICMと化学物質管理のこれから
- 第2回 各国政府の役割
- 第3回 産業界の取組(1)化学品の製造事業者(化学企業)
- 第4回 産業界の取組(2)化学品を使用する事業者(非化学企業)とリスク管理
- 第5回 産業界の取組(3)化学品(物質)の法規制とリスク管理の関係
- 第6回 NGOの役割
- 第7回 マスメディアの役割について
- 第8回 リスクコミュニケーション(1)
- 第9回 リスクコミュニケーション(2)
第1回 SAICMと化学物質管理のこれから
2002年のヨハネスブルグサミットで、「2020年までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境への悪影響の最小化」を目指すことが合意され、そのために「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)」というプログラムが始まりました。このコラムをお読みの方々は、SAICMについて既に十分な理解をお持ちのことと思いますが、本稿ではSAICMがこれからの化学物質管理をどう変えるのかということを考えたいと思います。
包括的方針戦略(OPS)に挙がっているSAICMの目的を5項目の表題のみを記すと次のとおりです。A.リスク削減、 B.知識と情報、C.ガバナンス、D.能力向上と技術協力、E.不法な国際取引の防止、です。それぞれの項目で求められる関係者の活動は、本稿の関連部分で必要に応じて触れますが、相互に密接な関係がありグローバルなビジネスではその連関を意識せずにはいられないことを指摘したいと思います。5項目はこれからの化学物質管理の主要部分ではありますが、特に化学物質(製品)を取り扱っている事業者にとって、何に配慮しなければならないのかという点に関しては別の形で整理ができるでしょう。
5項目に共通のキーワードとして、次の4つが挙げられます。I.リスクベースによる化学物質の管理、II.国際化(グローバル化)、III.情報の公開と関係者群の拡大、IV.弱者対策、です。このうちIからIIIはビジネスの組み立てや戦略に大きな影響を及ぼす可能性があり、同時に化学物質管理で発想の転換を迫っているかのようです。本稿では、この4つのキーワードに沿ってSAICM以降に各関係者に求められている活動あるいは考え方を整理したいと思います。
I. リスクベースによる化学物質の管理
化学物質管理は、従来のハザードベースからリスクベースに変わっています。化学物質の持つ固有の危険有害性(ハザード)だけでなく、使用方法、生産量や環境中での検出量などを考慮した管理への転換です。ハザードベースの管理ではどちらかといえば新規化学物質の規制が中心で、上市前に危険有害性の試験の実施を求め、その結果から重篤な危険有害性を持つ物質を予防的に製造・輸入禁止としてきました。そして、一度認可を受けると余程の理由がない限り、製造や販売に制約がありませんでした。既存の化学物質の安全性に対しても同様の考え方を取っていましたが、実質的に製造・使用が禁止という最も厳しい規制を受けたのは、改正前の化審法の第一種特定化学物質のように、もはや使われる見込みがなく既にその役割を終えた物質でした。製品に広範に使用されその物質特有の性状が重要な要件になると代替物を求めることも難しく、その物質を禁止することは化学産業界だけでなくそれを使用している産業や消費者の利便性を大きく損なう可能性がありました。また、誰もが製造・輸入できる既存化学物質では、その物質の安全性に責任を負う事業者が特定できず、国が安全性を点検することになりましたが、膨大な種類の既存物質があり、その点検作業が遅れがちになったことも事実です。
リスクベースの化学物質管理では、代替物がなくその物質でしか実現できない機能を活かした用途では、許容できる範囲にリスク管理が可能であれば製造・使用が認められます。反面、それができなければ、機能の低下があっても代替物の選択が求められます。そのため規制当局だけでなく企業もまた自らの責任でリスクを評価し、徒に混乱を引き起こさないようにその化学物質の使用の可否判断が求められるようになるでしょう。
II. 国際化(グローバル化)
SAICMは化学物質管理を地球規模で行うことを求めています。発展途上国や経済移行国には化学物質管理の法制度が未整備の国も多く、先進国の支援で整えられることが望まれています。法制度のある先進国間でも法規制の基準と内容に違いがあり、企業はその違いを考慮しながらグローバルビジネスを進めているので、どのような形で各国の法規制が整備されるのかということは、企業活動の視点からは重大な関心事です。日本と同じ形で発展途上国や経済移行国の法規制が進められることが日本企業には望ましいのですが、どのような形に収まるのでしょうか。
一方、SAICMは危険有害性(ハザード)の表示制度でGHSのシステムを進めようとしています。共通の簡略化した絵表示でハザードをわかりやすく表示することは、安全を確保する上で重要なことですが、GHSは「グローバル」と言いつつも各国の法制度あるいは閾値の適用、情報のジャッジメント等が異なることもあり、実際は国・地域ごとに若干の違いがあります。この違いが解消されずにシステムが行き渡ると、企業はどのような対応をするのか選択が迫られます。事故が起こった時に、製品にその国で求められるよりも低いハザード表示をしていると、生産者責任を追究される可能性があります。それを避けて、全世界に共通するが、一部の国・地域によっては求められる表示よりもより高いハザードを示す可能性のあるラベル表示を選択するのでしょうか。あるいは、仕向け地に対応して製品ラベルを張り替えたり、SDSを書き改めたりするのでしょうか。それとも多少の違いには目をつぶって(リスクを背負って)、最も出荷量の多い地域(大部分の製品は日本国内でしょう)向けの表示で済ませるのでしょうか。本当の意味でのグローバルシステムが流通することが望ましいのですが、各国・地域の事情もあり実現は難しい問題のような気がします。
III. 情報の公開と関係者群の拡大
これまでの化学物質規制では、新規物質の安全性データは関係者である規制当局と製造者の間でやり取りされるだけで内容は公表されませんでした。リスクベースに管理が変化すると、関係者の範囲は化学物質を使用する産業界、消費者、市民などに拡大します。企業の持つ安全性データやリスク評価用の各種データ類の開示・公表が求められることが考えられます。製造事業者だけでなく使用事業者にも当てはまりますが、企業秘密に近いデータの開示には躊躇があり、どこまで公表すればよいのか判断に苦慮することもあるでしょう。市民や消費者などからの質問等に適切に回答することにも慣れていません。企業にはリスクコミュニケーションを含めて総合的な化学物質の管理能力の向上が求められるようになるでしょう。
IV. 弱者対策
弱者として、子供・乳幼児(胎児を含む)、女性(特に妊婦)への格別の配慮が求められています。これまでも弱者対策としては必要に応じて、製品ごとの対応が取られてきました。例えば、特定の物質は子供用玩具等への使用を制限するという自主規制がそれです。限られた物質や製品だけを考えるのであればそのような個別対応も可能ですが、対象が拡大すると対応も難しくなります。また、弱者に特有の障害があるかどうかを見極めるための毒性試験を必要とする場合もあるかも知れません、そのときには多額の試験費用が必要になるでしょうし、新しい試験方法を開発する必要が出てくる可能性もあるので相当の準備期間が必要となります。それを避けるために既存データを活用し弱者に外挿することで十分なのかという点については、議論の余地があるように思われます。
一方、貧困層への有害物質による影響の問題はどちらかといえば政治の問題です。法制度が未整備の国で化学物質により環境が汚染される問題も同様です。しかし、中には違法・脱法行為によるものもあり政治だけの問題として片付けることができないこともあります。一般的な意味で弱者とはいえませんが、ばく露量が多くなる可能性のある労働者の安全の問題については、途上国・経済移行国に限らず先進国でも考える必要があります。
このようにSAICM(とそれ以降)では化学企業だけでなく全ての関係者が化学物質の安全性に関する見方を変えざるを得ないことに気がつきます。そのためには関係者それぞれに何が求められ、どう行動すべきかという点を、次回以降に記したいと思います。
第2回 各国政府の役割
ハザードベースの化学物質規制のもとでは、化学製品の生産者がそれを遵守することが第一で、使用する事業者や消費者は公正に取引されている原料・製品を使用する限りは、規制をあまり考慮する必要はありませんでした。法規制が危険有害な物質を市場に出さないので、流通している化学物質は「とりあえず安全」と考えようとしていました。しかし、規制がリスクベースに変わると化学製品を製造する企業だけでなくそれを使用する企業もまたそれぞれの立場でリスク管理が求められるようになります。このようにリスクベースの化学物質管理ではこれに関わる主体が拡張されますが、今回は最も主導的と思われる政府の役割を考えます。
政府には、SAICMの2020年のゴールに向かって各国内で課題の解決が期待されています。日本政府の活動方針は9月に公表されたSAICM国内実施計画にまとめられています。詳細はそれを参照して頂きたいのですが、①持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)2020年目標の達成、②「包括的な化学物質対策」の確立と推進、③様々な主体によるリスク削減のための行動、④国際協力・国際協調の一層の推進、の四点が挙げられています。具体的な取り組み事項は、(1)科学的なリスク評価の推進、(2)ライフサイクル全体のリスクの削減、(3)未解明の問題への対応、(4)安心・安全の一層の推進、(5)国際協力・国際協調の推進とされています。
化審法の改正はSAICMの意図する方向に一致させていますが、それにあわせて官民の協力による自主管理活動なども進められており、目標の達成には更に継続し発展させることが期待されます。
国・地方公共団体、事業者、国民・NGO/NPO、労働者などのさまざまな主体の連携がどのような形で進められるのかということも重要です。ハザード管理からリスク管理に変わると安全・安心への発想の転換が求められますが、この転換を自然発生的な動きに求めることは難しく、先導的なセクターが必要になるでしょう。誰がその役割を果たすのかは先の国内実施計画では明確には記されていませんが、わが国では相応の権限を持ち中立的な立場をとることができる政府にこの役割を期待することが自然と思われます。
セクター間の連携では、リスクコミュニケーションが重要になるでしょう。リスクコミュニケーションの開催の機会も増えましたが、まだ社会で市民権を得ているとは言いがたい状況です。これが今後どのように社会に定着するかということが、これからの社会における化学物質管理で重要な鍵になるように思われます。
目標と取り組み事項の最後に記されている国際協力・国際協調は、専ら政府の活動ですが、その結果はこれからの日本企業の海外ビジネスに影響を与える可能性があります。政府の施策には、日本企業にとって重要な取引先であるアジア地域に対して、日本からの情報発信、国際共同作業、技術支援などを通じて適正管理の推進と制度手法の調和を図ることがあげられています。中でも化学物質管理の法制度が十分でない各国への支援がどのような結果になるのか、ということに関心が持たれます。世界には色々なタイプの化学物質管理の法制度があります。日本の化審法はその中で最も早く整備された法制度の一つですが、その考え方は必ずしも世界標準というわけではありません。世界の環境保全に対する考え方は化審法の制定以降に大きく変化し、欧州は第七次修正指令(67/548/EEC)の改正でREACHを制定しました。その後世界が注目したことでREACHでなければ化学物質のリスク管理ができないといわんばかりの雰囲気が生み出され、国内でも同様の法制度でなければリスク管理ができないという風潮すら一部に見ることができます。しかし、法制度には一長一短があり、どの制度が優れているのかは簡単に結論は下せません。REACHは環境を守る側面だけでなく、環境を梃子にしてEUとEUの産業が世界的な競争力を取り戻すための方策の一つでもあります。このような背景もあり、域外企業はEU域内企業に比べて、実務的に対応が難しい制度となっています。一方、それに比べれば改正化審法は域外・域内企業の実務的なハンディキャップはほとんどない形で、これから化学産業を育成し、法制度を検討する国々にとっては導入しやすい形のように思われます。
アジア各国における化学物質管理の法制度の整備では、日本の制度に類似していれば日本企業は対応が容易です。法制度は法制度、実態はまた別、というように割り切ることができる国では、どのような形の法規制を導入しても形式上は運用できるのでしょうが、まじめに化学物質のリスク管理を法制度に則って実行しようとすると、アジア地域の各国にREACH型の法制度が導入されれば、日本企業だけでなく現地の企業にとっても対応は大きな負担になるのではないか、と懸念されます。
同じことは化学物質の危険・有害性を表示するGHSの仕組みについてもいえます。GHSはグローバルと言いつつも、その実際の運用は各国・地域によって微妙に異なっています。制度が日本のものに近ければ日本企業の対応はそれだけ容易ですが、そうでなければ大きな負担になる可能性があります。表示のルールは製品に直結しているものだけに利用者や消費者に対する影響は大きく、広く流通する製品に適用されている形がデファクトスタンダードになることもあります。アジア各国の工場にストックされている原料などのラベルは、それを販売する企業のある国の仕組みに沿った表示がされていました。グローバル化が進んでアジアの国々には工業生産の中心として世界中から化学品・原料が集まるようになるでしょう。その地域で日本企業が将来にわたって円滑なビジネスを進めるためにも、日本に近い法制度を定着させるだけでなく、日本のシステムがデファクトスタンダードとして通用するような緊密な関係も重要になるように思われます。日本に近い形で制度の導入は出来ても、流通する製品の多くが欧米企業のものであれば、その地域での標準は欧米型になります。そのようにならないように、政府には化学物質管理の制度の調和化に向けた積極的な国際貢献と並行して、日本企業のアジアビジネスへの支援も期待したいと思います。
第3回 産業界の取組(1) 化学品の製造事業者(化学企業)
SAICMの目標達成には産業界の貢献が欠かせません。ハザードベースの管理では化学物質規制は製造段階に対してのものでしたが、リスクベースでは化学物質(化学品)の使用者も含めた産業界全体での自主管理が強く求められることになります。
今回は、リスクベースに転換してもなお直接的な影響を受けると思われる化学企業の課題を考えます。化学企業は法規制への対応に加えて化学物質管理に必要な情報の発信源として重要な役割を担うことになるでしょう。
化学企業といっても「化学物質」を生産しているとは限りません。むしろ、購入した原料(化学物質)を配合して「化学品」を生産する会社の方が多いでしょう。化学品として消費者製品となるものもあれば、加工され成型物となって化学品とは見なされなくなってから市場に出ることもあります。どちらの場合でも、化学品を提供する化学企業は化学物質の安全性に責任を持つことは当然ですが、製品の形態や用途によって安全を確保するための活動にはいささかの違いが出てくることも考えられます。
日本化学工業協会(日化協)は、国際化学工業協会協議会(ICCA)のGlobal Product Strategy(GPS)を、日本での活動としてJapan Initiative of Product Stewardship(JIPS)として2009年から始めました。JIPSは1995年から日化協を中心に自主活動として進められているResponsible Care(RC)活動を、さらに発展させたものということができます。JIPSは、(1)リスクベースの化学品管理、(2)サプライチェーンを通じた化学品のライフサイクル全体にわたる管理、(3)化学品の安全性情報の公開、を具体的な活動の柱としています。参考として詳細にわたるガイダンス文書が公開されていますが、それでも経験や知識がないと簡単ではないように思われますし、それ以前に法規制だけでなく自主的なリスク管理に考え方を変えることが必要と思われます。
リスクベースによる化学品管理には、その前にリスク評価が必要です。しかし、消費者製品のリスクを考えるうえでは、化学企業自身が直接生産販売している場合でなければ、どのように使用されてどんな製品となって市場に提供されているかということを把握しているとは限りませんので、サプライチェーンの最上流にある化学企業は想定可能な誤用を含めて一般的用途でのリスク評価を行うことになります。その結果から判断される好ましくない使用方法等を供給先に伝えることになるでしょう。それ以上に化学品とそれを使用した製品の安全を確保するには、さらに詳しい用途情報が必要になりますが、我が国には供給先と販売元の間でそのような情報を交換する商習慣がなく、用途情報を企業秘密の一部と考えることもあります。供給先自らがリスク評価・管理ができる場合には、情報の相互共有化というよりも販売元である化学企業には安全情報の開示が求められるでしょう。化学企業も製品組成が絶対的な企業秘密であるという考え方を変える必要があるでしょう。また、何よりも化学企業には化学物質のリスク管理手法を身につけなくてはならないでしょう。
ライフサイクル全体の管理に関与することはさらに難しく、化学企業はどのように対処すべきなのか基本的な考え方を整理する必要があります。配合の繰り返しで組成は変化しても消費者製品が「化学品」であり続けるものは、直前までSDS(安全データシート)があるので、どのように取り扱うかをラベル等に記載することは可能ですが、多くの化学物質は成型品に取り込まれた形で消費者製品となり、まれには加工段階で化学変化が起きることもあります。このように、化学品が成型品に変わる時に化学物質に関する情報伝達が途切れる可能性もあります。ライフサイクルの最終段階である廃棄物になるまで、どうすれば化学物質に関する情報が保持し続けられるのでしょうか。なかなか難しい問題と思われます。
このような情報公開のために、日化協は「安全性要約書」という書式を提案しています。ハザードの伝達手段として広く使われているSDSは、初期には書式や記載内容は作成者の自由意志に任される部分もありましたが、その後、法規制に組み込まれJIS化されることで次第に自由裁量の余地が失われ、現在ではページ数も多く、専門的な用語が使用され、内容も法規制情報への配慮にウェイトがかかるようになりました。そのために安全性に関する情報の伝達文書としては、やや使いづらい形になっています。安全性要約書はSDSにある安全性に関する情報を抽出しリスク管理に役立たせることを目的にしているものと考えることもできます。対象物質は1トン/年を超える生産量の化学物質について、各社がICCAのポータルサイトに載せることになっています。
日化協は、公開される安全性要約書の利用方法の一つに、ウェブ上で公開しサプライチェーン全体で情報を共有化して、加工業者や組み立て業者などもリスク評価とリスク管理に使用することを想定しています。しかし、現実には法律で配付が義務付けられているSDSが十分に活用されているとは言えない状態なので、どこまで有効活用されるかどうかが課題ではないでしょうか。そのためには内容のわかりやすさが鍵になるように思われます。安全性要約書は、配合で混合物製品を生産する化学企業にとっても、自社製品のリスク評価には有力なツールになるでしょう。しかし、この文書の作成とリスク評価にはある程度の専門的知識が求められるので、人材リソースの限られている中小の化学企業や加工業者・組み立て業者等には日化協や専門家などによる支援と協力が必要になるでしょう。安全性要約書の普及でサプライチェーンを縦断したリスク評価が進むことを期待したいと思います。
ここまでは、化学企業がSAICMへの対応で自社製品に関して求められることを記しましたが、日本には途上国・経済移行国に化学物質管理を普及・教育をする重要な役割もあります。主として政府の関与になりますが、実務に関する部分では日化協や国際化を進める日本企業による先導的な役割が期待されます。化学物質管理手法もビジネスモデルの一部ですから、技術的ノウハウの教示だけでなく日本の管理手法が定着すれば、これらの地域とのより緊密な経済関係の形成が期待されます。
第4回 産業界の取組(2) 化学品を使用する事業者(非化学企業)とリスク管理
前回は、SAICMの目標実現に向けて、化学品を製造する事業者の課題について考えました。今回は、化学品を購入・使用する事業者の役割と課題を考えます。
何度も記しているように、化学物質の管理がハザードベースからリスクベースになると化学品の使用者もリスク評価を行い、その結果に基づく適切な管理が求められます。リスク管理を法律が明示的に要求することもありますが、企業の社会的責任や製造者責任の見地から事業者の自主的な対応も重要になるでしょう。
1. 化学品を使用する工程でのリスク評価
化学品を使用する作業現場では、工程のトラブルや事故から作業者が高濃度の化学物質にばく露されるだけでなく、低濃度であっても定常的なばく露の可能性もあります。管理が不十分であれば慢性的なばく露から重大な健康障害を発生させるおそれもあります。残念ながら化学物質に起因する労働災害はなかなかなくならないばかりか、次から次へと新たな問題が発生しています。取り扱い作業者の化学物質ばく露による問題は、SAICMだけでなくILOでも未解決の課題とされています。日本の労働安全衛生法はリスク管理の考え方を導入しました。リスクアセスメント指針(「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年))では法規制対象に限らず、全ての使用する化学物質のリスクを評価し安全な取扱い方法を自ら定めることを求めています。しかし、実際には必ずしもそれに十分対応できでいるとは言えず、法令に従った規制物質への対策が中心となっているのが現状でしょう。化学品のハザード情報を活用したリスクアセスメント手法の定着が望まれますが、その前に化学品を使用する事業者に化学物質のリスクアセスメントの重要性・必要性を啓発することが必要と思われます。
SDS(安全データシート)にある危険有害性(ハザード)情報の理解からリスクアセスメントがはじまりますが、化学品の取扱いを専門としない事業者にはそれは決して易しい作業ではないでしょう。最近のSDSは法制化にともなって記載内容が多くなり内容も理解が難しくなっています。SDSのみから使用者が適切にリスクアセスメントを実施できることを期待することは難しいのではないでしょうか。そのためのリスクアセスメント手法の定着には、SDSとは別に化学品の取扱いに慣れない使用者でも使えるリスク管理に直結した事項を抽出した文書が必要であるのかも知れません。SDSの理解のための教育も必要ですが、化学品の供給者と使用者の間のコミュニケーションから化学品の特性を理解することも有効ではないかと思います。化学品の供給者にはそれに応えられる能力が求められるようになるのは前回記したとおりです。
2. 化学品を使用する工程から発生する環境汚染
化学品を使用する現場から化学物質による環境汚染を生じることがあります。排ガスによる大気の汚染、漏洩や事故で土壌汚染や廃水からの用水の汚染などです。自社工場敷地内や認められた最終処分場への埋立処分が適法の時代もありましたが、そのような埋設廃棄物から周辺に汚染物質が拡散することもあれば、工場の撤退・移転や土地の形態や用途の変更などで汚染の事実が明らかになり社会問題化することがあります。過去の負の遺産が明るみにでるような事例です。排気ガス処理装置や排水処理装置の不具合からの有害物質の大気放出や汚染排水の公共用水への放出事例もあります。たとえ現在の行為が適法であったとしても、将来の法規制で違法の行為と認められれば、道義的な責任から何らかの負担が強いられる可能性があります。化学物質による環境汚染には現在もそしてこれからも事業者は十分に配慮しなければならないでしょう。無害化しないで化学物質を環境に放出することは許容されませんが、無害化のための適切な処理のためには化学物質の物性を知らなければならず、その情報はSDS等で供給者から使用者に与えられ、使用者はそれに従った処置が求められます。ここでもまた事業者間のコミュニケーションの重要性が理解いただけるでしょう。
3. 成型品に含まれる化学物質による消費者製品のリスク評価
食品衛生法(食品用包装資材や子供用玩具など)・建築基準法(シックハウス関連物質)などは特定の消費者用製品中の化学物質を規制しています。産業界は自主管理活動として、対象物質の拡大、厳しい規制値の採用、含有物質の試験方法の提案などを行っていますが、どちらかといえばこれまでの自主活動は法規制に上乗せした対応が一般的で、法規制から独立した自主管理活動は限られています。そのため現在の成型品中の含有化学物質による消費者へのリスク低減活動対象は限定的ですが、将来は幅広く成型品においてリスク評価・管理が求められるようになるでしょう。
これらの成型品中の化学物質に対するリスクアセスメントでは、サプライチェーンを通じてどんな情報をどのような形で伝達することが有効なのか考える必要があるでしょう。含有化学物質とその含有量の全てを伝えることがリスクアセスメントとして最も有効な手段でしょうか。どんな化学物質であっても、ある一定の量以上にばく露されれば何らかの影響を及ぼすことは明らかです。結果として発生する障害が重篤でなければ障害の発生が許容されるということでもないので、障害の重篤度に関する情報も必要ではありますが、それよりもばく露させないための使用方法や取扱方法を的確に伝えることがリスクアセスメント情報として重要と思われます。
製品が誰によってどのような使い方をされるかによってばく露経路とばく露の対象は変わりますし、リスク評価では製品の誤用や不適切な用途への転用も想定しなければなりません。製品から消費者や環境などのばく露対象へどのようにそしてどのくらい移行するのかを評価することが、成型品(消費者製品)の生産者に求められるようになるでしょう。最近は(拡大)製造者責任が厳しく問われますので、自社製品のリスク評価は事業者の経営リスクを低減する意味でも極めて重要になるものと思われます。
今回は、化学物質の使用者によるリスク評価と管理に関する課題を記しました。しかし、製品中の化学物質管理では、対象の化学物質(元素)が法令で明記されている場合や特に指定しなくても明らかな場合があります。そのような場合の管理の課題と解決方法は今回のものとは異なる部分がありますので、次回に触れたいと思います。
第5回 産業界の取組(3) 化学品(物質)の法規制とリスク管理の関係
今回は化学品(物質)の法規制とリスク管理の関係を考えます。適切に取り扱われなければ何らかのリスクが想定された化学物質が法律で規制されているのですから、法令遵守は事業者にとってリスク管理の第一歩ともいえます。法令記載の化学物質の名称は、化学に親しんでいないとわかりにくく、遵守には格段の配慮と注意深さが必要で、日頃から自社製品と規制の関係を考える習慣が必要でしょう。特に事業内容や取り扱い製品種が変わるときには、それまでとは異なる法令への配慮も必要になることがあります。法令違反では、仮に実害が生じない場合でも、法的あるいは社会的な制裁が加えられることもあり、それとともに事業者には直接・間接の経済的な負担が求められることもあるので、適切な管理と法令の遵守は経営リスクの回避でもあります。リスク管理への転換は製造業者だけでなく使用事業者にも影響が及んでいます。
わが国の代表的な化学物質規制法である化審法は、改正で罰則が厳しくなりました。第一種特定化学物質に関わる違反には、法人に対して最大一億円が定められています。筆者はこれまでに化審法違反でペナルティが科せられた実例は聞いたことがありませんが、多額の罰金が規定されるくらいに社会の化学物質の安全管理に対する関心が高くなっていることは承知しておくべきでしょう。米国有害物質規制法(TSCA)の罰則はさらに厳しく、最近の環境保護庁(EPA)のホームページには、報告義務のある動物試験データを報告しなかったことで330万ドル、IUR(製造輸入量)報告義務違反で230万ドル、短鎖塩素化パラフィン(PBT物質)の製造で140万ドルといった事例が挙がっています。TSCA違反は1日当たり最大で37,500ドルを科すことができますので、長期にわたる違反が悪質と見なされると莫大なペナルティになる可能性があります。TSCAの例だけでなく、一般に化学物質に関する法令違反の摘発事例の多くは、対象が化学品の製造・輸入者でしたが、化審法やTSCAだけでなく欧州REACH規則なども使用者を含めた全ての取り扱い者が対象になります。
消防法などでは化学品の物理化学的性質に基づいて規制していますが、多くの法令では化学物質名称をリストに掲げて製造販売の禁止や用途制限などで規制しています。混合物の化学品や成型品では含有量の閾値が規定されることもあります。含有物質がわかり、規制物質のリストがあればこれと対照させて、製品の該否や用途の適切さを判定すればよいのですが、必要な含有物質情報の入手が困難なときもあります。一般には化学品の購入者はサプライチェーンの上流に遡及して含有物質情報を入手するので供給者の協力が必要になります。製品組成の全てがわかれば対応ができるはずですが、欧州RoHS指令が施行された際の適合性調査では、対象が4種の重金属と2種の臭素系難燃剤に過ぎなかったにも関わらず、日本国内に混乱を起こしたことを思い出しますし、それほどまでして得られた調査結果も、依頼した側とされた側の双方にとって必ずしも納得できるものではなかったように思われます。その原因はいろいろ考えられますが、主として以下の二点にあるのではないかと思います。
第一点は、配合によって製造される化学品の組成・配合比率は、生産者にとって重要なノウハウの一つであることです。いわば製品の設計図に相当するものですので、生産者はそれを開示するには躊躇があります。国内法規制への対応に必要であれば事業者への強制力も強いので、例えば化管法に対応するための情報開示は進んでいますが、海外の規制にしか対応しない物質に関しては、供給者が直接の影響を蒙らないので、回答が得られないかあるいは遅くなることがあります。時には、情報が必要である理由を、需要者は説明することが求められました。分析値等の裏づけ証拠や保証が求められれば、回答を得ることはさらに難しくなることは予想されたところです。また、情報開示には供給者と需要者の関係が重要で、親密な取引が継続されており、互いに信頼の置ける取引先への情報提供は進んでも、取引先の生産拠点の海外移転等から第三国に情報が漏洩することになれば、世界には技術上のノウハウの盗用・転用に躊躇しない国もあるので、情報の開示にはより慎重になることもあったでしょう。
第二点は、含有化学物質の情報伝達に関するルール(コンセンサス)とシステムができていなかったことにあると思われます。既に記したように含有化学物質情報の生産者における重要性・秘匿性から、情報の伝達は供給者と需要者の二者間の関係のみに頼っていては難しいときがあります。円滑な情報の伝達には、サプライチェーンを縦断した仕組みと合意された手段が必要になります。わが国では2007年にアーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)という組織が設立され、MSDS、MSDS plusあるいはアーティクルインフォメーションシート(AIS)という書式が提案され使用されています。JAMPはREACH規制への対応を進めるために活動が始められましたが、化学業界・電機電子業界・自動車業界といった輸出に関係する特定の業界に限らず、広範な業界を取り込んで情報伝達一般の仕組みが整備されることも必要になるでしょう。ルールとシステムの整備で、REACH規則対応ではSVHC候補物質が現在138物質と多数に上っているにも関わらず、RoHS指令への対応に比べてはるかに円滑な情報伝達が進んでいるように思われます。
製品含有化学物質情報の伝達は、ICCMのEmerging Issuesの一つである“Chemicals in Products(製品中の化学物質)”とも関連します。ICCMの関心はサプライチェーンを通じてその情報を伝達するにはどのような仕組み作ればよいのか、といった点にあるように思われます。欧州のRoHS指令やELV指令という既存の製品に関する規制だけでなく、廃棄物処理に関する情報も関係してくる可能性が有ります。共通のルールもシステムも整備されていないと、かつてのわが国のRoHS指令対応騒動以上に大規模でグローバルな混乱を生じることもあるでしょう。グローバルシステム(国際標準)は、これからのビジネスの進め方に大きなインパクトがあります。世界でも類をみないほど複雑で錯綜したサプライチェーンを持つ日本での経験と実績を踏まえた製品含有化学物質情報伝達の仕組みを国際標準とすることができれば、わが国製造業の国際競争力強化の手段とすることにもなるように思われます。
第6回 NGOの役割
SAICMの包括的方針戦略には、化学物質管理の実施プロセスと意思決定の過程では、各国政府、地域的経済統合機関、政府間機関、非政府機関および個人などの関与とともに、公衆の参加が鍵となることが示されています。ここで、「個人」には消費者、処理業者、雇用者、農業者、製造者、規制者、研究者、供給者、輸送業者、労働者を含むものとされているように、単に生産や販売だけでなく、ライフサイクルの全般にわたって適切な管理を求めていることがわかります。SAICMでハザード管理からリスク管理に転換したことはこのコラムで何度も記しましたが、ライフサイクル全般にわたってのリスク管理では、ここにあげられた関係者も、考え方をこれに対応して変えていくことが期待されていると言ってよいでしょう。
今回は化学物質(化学製品)からの影響に対して受動的な立場である市民あるいはNGOのかかわり方を考えます。NGOといえば文字通り非政府機関を意味しており、業界団体などもNGOとして取り扱われますが、ここでは主として市民あるいは生活者の利害を代表する民間の消費者団体や環境団体を考えることにします。
政府・行政機関は、どちらかといえば大気環境や飲料用水などの広域的でばく露対象が不特定多数の問題に関して、リスク評価結果に基づいて環境濃度などを規制するとともに、その原因を排除・軽減するような施策を考えることになります。しかし、地域的な、あるいは個々の製品のリスクに関しては、政策的にはある程度幅広い領域や多様な製品に共通して適用できる基準とせざるを得ないので、その結果限られた地域や特定の製品からのリスクについては必ずしも十分とはいえない結果になることも考えられます。そのような場合に対応して、例えば消費者製品を供給する事業者が製品の使用状況を想定して、好ましくない影響が出ないように配慮するなどの、自主的なリスク管理対策が求められることは既に記したとおりです。しかし、受動的な立場の市民・生活者や消費者が必要な情報を受け取ることができたとしても、自分自身に関係するリスクを適切に判断することは易しい作業ではないでしょう。
わが国のNGOは、化学物質管理政策の立案に際して関与を強めたいと考えているようです。政府の検討会・審議会へのこれまで以上の参加と政策立案への参画などを意味しているようですが、一方で、政府はパブリックコメントなどを政策立案に生かすことで、規制への消費者・生活者の意見を反映させたいと考えているようです。市民・生活者が自らの安全に関わる事柄に対して政策立案に関心を持つことは好ましいことですが、「リスク管理」による化学物質管理政策にNGOが建設的な提言ができるかどうかについては、筆者はいささかの疑問を持っています。
なぜなら、NGOは依然として「有害化学物質」という、あたかも「化学物質」には有害なものと無害なものとに分類できるかのような表現を取っているからです。SAICMではどんな物質も使用方法や管理方法によっては人や環境に対して有害にも無害にもなるので、それを承知してリスクを最小化しようとしています。そこでは物質を「有害」と「無害」に分けてはいませんが、それにも関わらず「有害物質」の削減を中心命題としているグループがあるように、リスク管理の考え方がNGOに定着しているようには思えないからです。むしろ生活者としての市民の方が、直接の利害が及ぶだけに「リスク感覚」では優れているように思われます。ハザード管理では、物質の持つ有害性(ハザード)とその程度の見極めが規制の要件でしたが、リスクベースではハザードだけでなく用途や生産量などの要因も考慮することになり、基本的な考え方をリスク管理に変えなければ政策決定に積極的な関与ができるようになるとは思われません。
日本では、国あるいは自治体の規制に市民・生活者の安全を委ねる考え方が行き渡っていますが、リスク管理への転換は市民・生活者にもリスク判断が求められるようになったと言うことができます。
リスク管理で重要な要素になると考えられていることの一つに「リスクコミュニケーション」があります。市民が生活者の立場に立ったときにはリスク感覚があるように記しましたが、それは直感的であることが多く、化学に関して専門教育を受けているわけでもなく、リスクを想定することについても訓練されているわけではない市民が、適切に「リスク」を理解するためには専門家の協力も必要でしょう。NGOにはその様な場面で、リスク管理に必要な事項の説明を期待したいと思います。行政でも産業界でもそれは可能ですが、共感や親近感などの点で、NGOの方が適当と思われます。ハザード管理からリスク管理への考え方の転換は易しいものではないでしょう。これまでに物質の化学的あるいは物理的な有害性の問題点を考えてきたNGOには、市民や生活者のオピニオンリーダーとして活動していただきたいと思います。
第7回 マスメディアの役割について
今回は化学物質の管理がリスクベースに変わろうとしている中での、メディアの役割を考えます。メディア自身はSAICMの主体にあげられてはいませんが、市民は社会的関心事を知るきっかけは、新聞・テレビなどの報道です。メディアは客観的事実を伝えていると思われがちですが、得られた情報の全てを報じることは物理的に不可能ですので、そこにはある種のフィルターがかかっています。しかし、市民にとって予備知識のない段階での第一報は、その後もリスク判断に大きな影響を与えるでしょう。市民はリスクコミュニケーションなどからも情報が得られますが、それはリスクを認識してから積極的に情報を求めるときです。予備知識がない段階では、報道からの第一報の印象は強いものがあるということができます。
市民がリスクを考えるためには、これまでのハザードベースの管理に比べて多くの情報が必要になります。一般にメディアは何か変わったことや予期されない意外な事実の報道を優先し、さらにその物質のハザードが重大であればあるほど取り上げ方はセンセーショナルになります。ハザードベースで考えるのであれば、このような報道でも社会に警鐘を鳴らす意味はありましたが、リスクベースで解決策を求めるのであれば、このような結論(それが規制当局、専門家あるいは報道機関自身の物であってもいいのですが)を伝える形の報道でよいのでしょうか。市民自らがリスクを考えるヒントを提供するような物が必要になるのではないかと思われます。「誰がどう語った」あるいは「国はどう考えている」という結論を報じるだけのメディアの報道姿勢には批判も出てきていますが、化学物質やそのハザードあるいはリスク評価に慣れていない一般市民にとっては、リスク管理の考え方の参考になるようにその結論に至ったプロセスもあわせて伝えることが望ましいと思います。リスク対象を誰(何)に考えるのかということで、その管理方法が変わりますが、市民には自らとその周辺の人々あるいは地域にどのような影響があるのかということが最大の関心事です。多くの市民に等しく関わりがある広域の大気環境の問題もあれば、特定の地域あるいは集団に対してのリスクを重点的に考える必要がある場合もあります。自らのリスクを判断しなければならない市民にとっては、考え方の過程を示すことで、その問題とどのような関わりを持ち、何を考えなければいけないのか、ということがわかりやすくなります。
今の報道内容は報道機関としての独自のリスク評価に基づくものもありますが、多くは当局や専門家の見解を市民にわかる言葉に直して要約しているだけに留まっています。取材先の見解を伝達することよりも、報道機関自身のリスク評価についてプロセスを含めて記述すれば、読者(市民)のリスク評価の参考になるでしょう。そのためにはメディア自身がリスク評価のできる力量を持つことが求められます。
リスク評価結果は新たな知見で変わることがあります。再評価結果が当初の評価結果よりも安全サイドに変わることもあります。それも市民のリスク判断には重要な情報ですが、より安全であるとの推論結果は危険有害性を指摘する見解よりも報道価値が低いからか、あるいは第一報から時間がたっているのでニュースの鮮度が落ちているからなのか、全く報道されないあるいは目立たない扱いになることがあります。ニュースを商品として提供し、読者(視聴者)をより多く獲得とすることを目指す商業メディアにとってはある意味でやむを得ないことなのでしょうが、第一報の衝撃的な印象が強く残り市民の適切なリスク評価につながらないことや、風評被害が継続する事例がありました。冒頭に記したように、メディアの報道が市民のリスク判断に対して有力なあるいは唯一の情報の提供媒体で、一般市民よりも早くそして多くの情報を入手できる立場にあります。環境に関する課題は一般に解決に時間を必要とするので、市民が適切な対応を取ることができるような継続的な報道も、報道機関の社会的責任の一つであるように思います。
私たちはメディアを通じて専門家のコメントを知ることができますが、そのコメントの多くは断定を避け、「危険性がある」あるいは「おそれがある」という発言で締めくくられることが多いように感じます。しかし、全ての化学物質には何らかのハザードがあることを思えば、これでは具体的な警告にはなっていないばかりか、かえって不安感を残すだけに終わっています。リスク管理の立場からはもう一歩突っ込んで、誰(何)に、どのようなリスクがどの程度で及んでいるのかまでのコメントが欲しいと思います。専門家の見解の多くは、私たちは直接ではなくメディアを通じてしか知ることをできません。そのときメディアによる編集が入っているので、どのような脈絡からの発言であるのかわかりません。専門家の趣旨に添わない形で引用されていることもあるでしょう。専門家の見解は市民のリスク判断には極めて有力な発言です。もし、趣旨と異なって発言が引用されていれば、何らかの形で訂正を求めることが必要ですし、そのように恣意的に引用されないような発言が望まれます。
第8回 リスクコミュニケーション(1)
この連載コラムの最後に、リスクコミュニケーションの問題を考えます。
SAICMの世界行動計画では、「…業者はデータを評価し、正確で信頼できる情報を使用者に提供すべき(127)」や「エンドユーザーに適切な情報を知らせ、既存のリスク評価の利用を改善する(135)」などのように、情報提供の重要性が指摘されています。それとともに「教育と訓練(154,155)」による市民・消費者のリテラシーの向上もあげられています。
ハザード管理の改正前の化審法は、特定の物質(第一種特定化学物質)については、製造・販売を許さない、微量であっても混入を認めていなかったので、使用(事業)者は、流通している化学品は化審法の規制を受けていないと考えていました。しかし、分析技術の進歩で、実質的にほとんどリスクが想定されない極微量の不純物として規制物質が混入することもあることがわかり、一部の化学品では流通に支障をきたす状況となったことから、リスク管理が合理的で現実的であると認識されるようになりました。
リスク管理では、すべての物質には何らかの危険有害性があるということを前提とし、そのリスクが受け入れられるかどうかを考えますので、関係者は立場に応じて関心のある分野のリスクを考えます。わが国でも、食品衛生法や建築基準法には、用途やばく露対象と経路を考慮した、法律によるあるいは業界による自主規制対象物質があります。これからはすべての用途で危険有害性情報やばく露情報をもとにリスクを考えることになります。
化学品の供給者が、取扱時の注意事項や不適切な用途などの情報を需要者に提供しなければならないことは変わりませんが、さらにどのような形で使用されるのかということにも無関心ではいられなくなるでしょう。また、化学品の購入事業者は、提供された情報に基づいて適切に取り扱うだけでなく、用途が適切であるかどうかという配慮も必要になりますし、消費者製品であれば消費者からのリスクに関する問い合わせに応えることが求められることもあるでしょう。さらに、消費者も必要に応じてその製品のリスク情報を入手して適切に使用することが望まれることになります。食物アレルギーを持つ子供の食材には特別の注意を払いますが、同様のことが一般の消費者製品にも必要になることもあり、妊産婦や乳幼児・子供用の製品には格別の配慮が必要になることもあります。このような仕組みが円滑に動くためには、リスク情報の共有化が求められるでしょう。
これまでは、物質の持つ危険有害性からは法規制で私たちの安全は守られていると考えていました。しかし、ゼロリスクの物質はないので、私たちは自らの問題としてリスクを考えることになります。これは、危険有害性の高い物質が数多く流通するようになったというのではなく、これまで気付かずにいたものの科学的な知見の集積で、とりわけ弱者に対してのリスクが無視できないことが次第にわかってきた、ということができます。ハザード管理で必ずしも安全・安心が実現されていたわけではありませんが、危険有害性の高い物質が順次規制対象として追加されることで、私たちはより安全となったと考えようとしてきました。しかし、そのようなやり方ではどうしても対策は後追いの形をとり、法規制物質の追加が対策として問題の未然防止に有効であるかどうかを十分に吟味する前に新しい課題が次から次へと生成しました。
確率に基づくリスクの考え方では、ゼロリスクを目指すのではなく許容できるかどうかを判断します。リスク管理とハザード管理のどちらが科学的であるかということは明らかです。リスク管理を進めるためにはすべての関係者にこれまでの安全・安心に対する発想の転換が必要ですが、この考え方に慣れることにはある種の難しさがあるでしょう。もちろん、すべての関係者がリスクに対する認識を持つことは望ましいことですが、科学的な知見や定量的なリスク評価方法を学んだとしても、教育や訓練からだけで体得することは難しいでしょう。そこで、立場の異なる関係者が一堂に会する共通の問題に対して意見交換ができるリスクコミュニケーションが有効ではないか思われます。リスクコミュニケーションではテーマに対して何らかの関心や利害を持つ関係者が集まるのですから、具体的な形で互いの考え方を知ることができます。また、リスクコミュニケーションは双方向的な取り組みで、消費者庁の検討会資料1)にもあるように、「消費者自身による安全・安心に係わる社会的決定への参加にもつながる」ことも期待できるので、SAICMの目標達成にも欠かせないことのように思われます。
しかし、リスクコミュニケーションの考え方が日本に導入されてから久しいのですが、未だに社会的な認知度も上がらず、必ずしも有効に機能しているとはいえない状況と思われるのは、まだ多くの問題点が残されているからなのでしょう。次回は、リスクベースの化学物質管理を目的としたリスクコミュニケーションはどのような形が好ましいのかということを考えたいと思います。
1)第9回消費者安全に関する検討委員会 平成21年3月16日(月)
資料5 消費者安全教育、リスクコミュニケーションに関する論点整理案
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/anzen9/file/
shiryo5.pdf(消費者庁)
第9回 リスクコミュニケーション(2)
リスクベースの化学物質管理を進める過程で、リスクコミュニケーションが必要となる可能性があるものの、そこにはまだ課題が残されていることを指摘しました。リスクコミュニケーションを効果あるものにするためにはどうしたらよいのでしょうか。
リスクコミュニケーションにも様々な形式がありますが、消費者用製品中の物質のリスクに関して、消費者と製造(販売)者で交わされるものを考えてみます。日本でも食品安全では食品安全委員会がリスクコミュニケーションを度々開催していますが、消費者用製品ではそれほど開催頻度が多いとはいえないでしょう。体内への摂取が目的の食品と違い、製品中の化学物質による消費者へのリスクは差し迫った問題とは思われていなかったのでしょう。消費者製品では使用形態により経口・経皮・吸入の多様なばく露経路を考える難しさがありますが、製品中の化学物質は世界的にも規制強化の動きがありSAICMでも課題の一つとなっています。
工業用の原料化学品も消費者の手に渡るときには多くが成型品となっています。加工工程で原料化学品中の物質が化学変化を起こす場合とそうでない場合がありますが、成型品の製造(販売)者がリスクコミュニケーションを行うときは、原料化学品の情報とともに加工工程で起こりうる化学変化を知ることも必要です。事業者は製品の使用方法や原料化学品の性状(物性や毒性など)などの多くの情報を持つので、説明責任があります。それとともに製品中の物質がどのように、誰に、ばく露の可能性があるのかといった点を踏まえてリスク評価を行い、その結果を示すことも求められます。化学物質の健康・環境影響を考える機会が少なかった成型品の製造(販売)者には、それはおそらく簡単な作業ではないでしょう。原料化学品の供給者からのハザード情報とともに、リスクに関する情報交換も必要になることもあるでしょう。このように事業者間で行われる情報交換もまた、一種のリスクコミュニケーションと考えることができます。
製品中の化学物質の性状を知ることは重要ですが、その情報をもとに詳細にリスクを説明しても消費者が十分に理解できるとは限りません。消費者の化学物質や製品に関する予備知識は無いに等しいので、専門的な情報をわかり易く伝えることは難しく、事業者もリスクをわかり易く伝える訓練を受ける機会もあまり無いので、説明が詳細にわたればわたるほどかえってわかりにくくなるともいわれています。
そこで、リスクコミュニケーションではファシリテーターやインタープリターという役割の人を起用することがあります。ファシリテーターはリスクコミュニケーションを円滑に進める司会役で、議論が偏らないようにしたり主題から逸れないようにしたりします。インタープリターは専門的な事項の解説・説明を担当します。化学物質やその健康影響評価に詳しいだけでなく、化学品の製造・使用のプロセスや必要性などを化学物質の知識をあまり持たない人々にも誤解されないように、わかり易く正確に伝えることが役割ですが、これをできる人材は限られています。SAICMの世界行動計画に人材の育成が上げられていますが、その中にはインタープリターを務められる人材も含まれるでしょう。専門家と一般の人々ではリスク認識の違いは大きいといわれており、リスクを伝えるのは難しい役割です。インタープリターには専門家の言葉を消費者に伝えるだけでなく、逆に消費者の不安や疑問を専門家に伝えることも必要になる場合がありますが、一人で両方の役割を果たすことは難しく、そのため逆の立場のインタープリターが必要になるかもしれません。
製品の使用者と事業者(製造、販売)はある意味で利害を共有しています。使用者は製品の使用にメリットを感じますし、事業者は広く使用されることが製品化の目的です。消費者は「安心」を感じれば使い続けるでしょう。「安全」であることが必ずしも「安心」につながらないといわれています。事業者には消費者が信頼感をもとに「安心」を感じられるような説明をすることが求められます。そのためには、情報の透明性を確保して消費者の疑問・不安に正面から答えることを心がけるべきでしょう。
事業所の使用する化学物質による環境リスクについてリスクコミュニケーションが開催されることがあります。化学物質管理促進法によって事業所から報告された化学物質の排出・移動量は環境省のホームページで公表されています。環境をテーマとしたリスクコミュニケーションでは、それが事業所の環境パフォーマンスを示す指標として引用されます。一般にはそのデータだけから事業所が周辺に及ぼす環境影響を推測することは不可能で、そのために事業所の責任が追及されることはほとんどありませんから、どれだけ真摯にわかり易く説明するかが重要になります。
SAICMでも取り上げられているように廃棄物中の化学物質のリスクも事業者にとっては気になるところです。廃棄物の処理は専門業者に委託することが多いのですが、廃棄物処理法には排出者責任が規定されているので、信頼できる業者に委託するだけでなく法に従って中間処理・最終処分が適切に行われていることを確認して、リスクコミュニケーションの場でその結果を報告するのがよいと思われます。
事業者の化学物質管理では作業者の健康管理も重要です。社員は会社と利害をともにしますから、リスクとその軽減策を適切に説明すれば理解されるでしょう。残念ながら労働災害の発生は後を絶ちません。労働安全衛生法の規定する事業所内の安全衛生教育や訓練などだけでなく、取り扱い物質の安全性に関する事業所内のリスクコミュニケーションがもっと盛んに行われるようになることが期待されます。
問題が顕在化し因果関係が科学的に証明されたり、事故や不祥事を起こしたりしたときの説明会はもはやリスクコミュニケーションではありません。影響の有無が明確でない段階で開催されるリスクコミュニケーションの目的は共通の結論ではなく、互いの考えかたを理解しあって信頼関係を築くことにあります。相手に不信感があったり情報隠しが疑われたりするようでは、コミュニケーションはうまく進みません。事業者は日頃から利害関係者との間で良好な関係を保つことができるような関係を築いておくことが必要です。
「リスクコミュニケーション」は、リスク管理に不可欠のツールとなるでしょう。もっと盛んに行われれば、それがすべての利害関係者のリスク感覚を育むことにつながり、ひいてはリスク管理が進展するでしょう。前回も記しましたが、リスクコミュニケーションが消費者自身による安全・安心に係わる社会的決定への参加につながれば、社会のリスク管理へのコンセンサス形成に重要な役割を果たすものと思います。