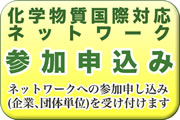グローバル化の中での化学物質管理
- このコラムは、化審法(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を指す。以下同様。)見直し合同委員会のメンバーでもあった北村卓氏に、化学産業界の第一線で過ごされてきた豊富な経験に基づき執筆をいただいたものです。
- このコラムに記載されている内容に関し、法的な対応等を保障するものではありませんのでご了承ください。
- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
→ご意見・ご感想電子メール送付先:
化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@env.go.jp)
目次
- 第1回 はじめに
- 第2回 情報の共有化
- 第3回 海外で本格生産を始める前に
- 第4回 排水管理 -アンケート結果から-
- 第5回 排ガス規制 -アンケートの結果から-
- 第6回 産業廃棄物対策 -アンケートの結果から-
- 第7回 土壌汚染対策 -アンケートの結果から-
- 第8回 労働安全衛生 -アンケートの結果から-
- 第9回 まとめ
第1回 はじめに
現代はグローバル化の時代と言われています。製造業は広く市場を海外に求めるだけでなく、生産コストを低減させるために製造拠点の海外移転も進んでいます。グローバル化は欧米巨大企業の世界戦略の一つと考えられていましたが、日本を含めて先進国の生産活動がコスト高となり、中小の企業もまた好むと好まざるとに関わらず、海外の生産拠点から地球全体を市場とすることに活力を求めるようになっています。グローバル化の前は国際化がキーワードでした。ビジネスの拡大を海外に求めることは同じでもその中身は異なっているようです。
国際化では、国内生産の製品を海外市場に販売するとともに、海外の生産拠点を顕在化している市場の近くに置くことは、市場の拡大を期待しながら製品を周辺に供給するための最も有利な解として選択されていたと言うことができるでしょう。部品産業のように国内顧客が生産拠点を移したので、そこへの対応から海外に進出せざるを得なかったというケースもあります。一方、グローバル化では、海外の顕在化した市場に寄り添うというよりも、生産の最適化を求めて海外に進出しているように思われます。製造業は形のある「モノ」を市場に運び販売することで事業が成り立つので、ITを駆使して地球上のどこからでも取引が可能な金融業などとは異なり、地理的に市場との関係がほとんど期待できないところに生産拠点を置くことはありませんが、製造コストの低下を期待して海外に移転する動きは加速しています。
グローバル化によって製品が自由に世界中を移動する印象がありますが、国や地域の間には、いろいろな格差(原料費、人件費、輸送費、税金など)があり、それを計算に入れての選択ですから、国(国境)があってのグローバル化と言えるでしょう。しかし「モノ」が国境を越えるときは様々な規制があります。本稿で取り上げる「化学品」「化学物質」には、どの国(地域)でも社会からの安全・安心に高まる要求に応えるために環境や有害物質の規制があり、将来はさらに厳しくなることはあっても緩和されることはないように思います。その規制には国や地域の特性が反映されるので、世界共通の基準に収斂するとは限りません。現在でも、化学物質には各国各様の規制がありますが、法制度の整備が進められている途上国や経済移行国では、先進国の制度を参考にしながらも、それぞれの国や地域に特有の規制となることが予想されます。そのため、製品の輸出や生産では化学物質の持つ環境・製品・安全衛生に対するリスクに対する国あるいは地域ごとの異なった規制を考えることが必要になります。仮に規制の背景に政治経済的な側面があったとしても、国民の健康や環境を守ることを主たる目的に掲げられると、技術的な非関税貿易障壁としてそれを無効にすることは難しいでしょう。生産活動の各段階に係わる規制、例えば労働安全、廃棄物規制、生産活動からの環境汚染、排水規制などもあります。その規制に対応するためには現在はどのような法規制があるかということだけでなく、今後どのような形に整備されるのか想定しておくことが必要になるでしょう。
日本で事業を立ち上げるときを思い浮かべれば、海外でも生産活動を開始するときには、準備段階を含めて次のような規制を想定することができるでしょう。なお、かっこ内に記したものは、対応する日本の法律です。
1) 生産拠点の立地を考える段階
・ 化学物質の登録制度 (化審法、労働安全衛生法)
化学品生産では、使用・生産する化学物質に制約がないかどうかを知ることが必要です。化学物質の登録制度は化学物質規制のある国や地域では一般化しており、未登録物質は事前の登録が必要です。これに必要な費用は国によって異なります。さらに、登録に必要な準備期間も無視できず、この作業に手間取るとビジネスの立ち上がりに支障をきたすこともあるでしょう。
近年は非化学品(成型品)に含まれる化学物質に対しても制約を設ける法規制が施行されるようになっているので、この問題に対応しなければならないのは化学企業だけではありません。
・ 環境汚染対策 (土壌汚染対策法、ダイオキシン対策特別措置法、廃棄物処理法など)
化学品の取扱いは環境汚染の懸念を常に抱えています。規制基準に適合した除害設備などで対応を図りますが、予定以上の設備が必要になったり、コストがかかったりすることがありますし、除害設備を運転するインフラが整備されていなければ、自らが用意することになりさらに負担が増えます。
化学品の取扱いでは取得する用地の土壌汚染の有無を知っておくことも必要です。土壌汚染に対しては世界のどこも厳しい姿勢を取っています。十分に調査しないで汚染された用地を購入・借用すると、工場の撤退時に多額の浄化費用が発生することもあります。海外の工場用地は未来永劫所有し続けるとは限らないので、汚染の疑いのある土地を十分に調査しないで購入・借用すると将来に禍根を残すことになります。
生産で発生する廃棄物の処理も考えておく必要があります。日本では、許可なく廃棄物の中間処理や最終処分することはできませんが、海外では廃棄物処理のインフラが整っているとは限りません。廃棄物処理に手間取れば生産活動そのものに影響を与えることもあります。
2) 生産活動に伴う化学物質対策
・ 環境汚染の抑制 (大気汚染防止法、水質汚濁防止法など)
どこで生産活動を行っても、環境汚染(大気、排水、土壌など)の抑制は必要です。環境基準が定められていないところもありますが、将来はどこにでも環境基準が設定されるでしょう。既に規制のあるところも将来は強化されると考えたほうがいいでしょう。そのように考えると、世界のどこに工場を設置しても、環境汚染抑制のためのコストは世界で最も環境対策が進んでいると言われるわが国の技術を用いるのと同程度あるいはそれ以上の費用がかかるものと考えたほうがよいのではないでしょうか。
・ 労働安全・労働衛生 (労働安全衛生法、労働基準法)
事業者が化学物質を取扱う労働者の安全や衛生をどのように確保すべきなのかという基準は、国や地域によって異なります。国民性やその国の安全に対する考えかたの違いもあり、事故災害の発生のしかたもその原因も日本とは異なることがあります。公表される統計数字からだけでは、その国・地域の労働安全衛生の実態を知ることは難しいときがあります。事故災害の発生では事業者に問われる責任にも違いがあります。労働安全衛生の確保のために事業者が予防的に取るべき対策は国や地域で異なりますが、労働者保護の法律に対する違反と見なされれば多額の罰金や経営者や管理監督者に罰則が適用されます。
3) 安全保障貿易関係 (外為法輸出貿易管理令)
外為法輸出管理令の規制は、大量破壊兵器やその原料が世界各地に拡散しないための仕組みの一つで、化学物質や原材料にも規制があります。納入先が日本企業の関係会社であっても、立地する国によっては法律の適用を受けます。外為法違反に対する罰則は、法人の輸出業務が一定期間禁止されるものもありビジネスに対する影響は大きいものがあります。規制対象の原料や中間体を日本から海外関係会社に送ることになれば、そのための手続きが必要になります。
4) 消費者用製品からの消費者の保護 (食品衛生法など)
海外生産の製品に限られることではありませんが、各国では消費者用製品とりわけ非化学品(成型品)に含まれる化学物質の規制が強化されています。これまでは化学物質の規制は化学品を主体に考えてきましたが、これからはそれでは十分ではないでしょう。長いサプライチェーンを経由した後に、規制に抵触する製品(成型品)を出荷すれば、輸出した企業は勿論のこと原料を供給した化学企業にも原料の納入が止まるなどの影響が及ぶことがあります。
グローバル化で化学物質の問題を考える、あたかも鋭利な日本刀で小さな魚を料理するようなもので、そこまで大上段に構えることもないような気もしますが、個々の企業には対応を誤れば大きな問題となる可能性もあり、今年はこの問題について考えたいと思います。海外との関係を深めれば深めるほど避けることができない問題ですし、人材をそのような問題に振り向ける余裕のない企業や、顧客が海外に生産の比重を移したことで、十分な準備期間を持たずに自らも海外に生産拠点を持たざるを得なくなった企業にとって、海外の規制への違反は企業の存亡に直結する大きな問題となる可能性もあります。海外展開は企業にとっては新たな経営リスク源となっていると言えるでしょう。
第2回 情報の共有化
危険有害性のある化学品の管理を疎かにすれば、環境・安全・コンプライアンス(法規制への対応)などで経営リスク要因となります。しかし、大量の化学品を生産・使用する場合でなければ、事業の拡大・発展の過程で新しい事業所や施設を建設するときに、化学品の管理が高い優先度を持って事前の検討課題となることは少ないように感じます。国内工場の新増設でもこれらの課題に十分な解決策が用意されないままに事業化計画が進行する、言い方を変えれば事業化後でも配慮することでリスクの回避が可能と思われているようです。国内でも管理不十分から法令違反や行政指導の対象となることがあり、それとともに企業の社会的責任が問われる場合がありますが、海外では日本で許容されることも、法制度・国民性や社会習慣などの違いから認められないあるいは好まれないことがあります。これまで、比較的化学物質の管理に対して鷹揚だった途上国や経済移行国でも不適切な管理からの化学物質による環境汚染や事故災害には厳しく企業責任を問うようになっているので、海外でも国内と同等あるいはそれ以上の化学物質管理レベルを考えるだけなく、進出する国や地域の事情を考慮した対応が必要になることがあります。法令違反に対しては日本とは比較にならない高額のペナルティが課せられることもあります。
海外の法規制が日本のそれと異なることは容易に想像がつきます。日本企業の熟知する日本の法規制が世界標準というわけではないので、国内の規制遵守の手法をそのまま海外に移転するだけでは、十分ではないことも予測できるでしょう。しかし、海外の事業展開に慣れていないときには、このことを忘れがちになることがあります。海外で会社の経営責任を持つ(多くの場合は)日本人トップだけでなく、海外事業所を日本から後方支援をするときにも、このことを考えておくことが必要です。
日本のマザー工場に比べて一般に海外関係会社の工場は規模も小さく、また、従業員は現地の人々ですので法規制遵守に限らず、工場の環境・安全管理の面でも日本のやり方がそのままでは海外に適用できないことがあります。
化学物質に関係する環境管理・労働安全・保安防災・コンプライアンス・品質管理などの諸課題に対しては、いずれもISO 9001に代表されるマネジメント手法(規格)を効果的に応用できますが、小規模工場では分野ごとに専任担当者を配置することは工場経営の視点から難しいことがあります。さらにマネジメント手法を効果あるものとするには、仕組みの導入だけでなくそれを活用する人材も必要になりますが、人材の採用だけでなく担当者を専任とすることも難しいことがあります。そのような状況では、どのように必要な人材を育成し良好な管理状態を維持するかということが事業開始後の大きな課題になります。
専任・兼任を問わず、これらの課題の担当者が配置されても、工場のパフォーマンスを良好な状態に保つためには、彼らの善意と熱意と努力だけに任せきることはできません。事故やトラブルは頻発するものではないのですが、不幸にして発生したときに適切な対応が取れるかどうかということは、頭で考えるよりも類似の事故災害の体験(あるいは擬似体験)を持つかどうかということと密接に関係します。
情報の共有化には、その擬似体験と考えるヒントを提供する意味があります。近年はインターネットの普及で、文書化された事故災害情報を電子掲示板に掲載するだけでなく、テレビ会議やe-mail等の様々な情報伝達手段があります。しかし、情報の共有化がリスクの回避や低減に直接つながるのではなく、それをツールとして活用できる人材と効果的に運用できる体制やシステムがあって、その仕組みが生かされます。情報の共有化は事故災害やトラブルの再発や未然防止に万能というわけではありません。不祥事のあとの再発防止策として必ずといっていいほど挙げられる施策の一つである「情報の共有化」では、どんな情報を共有しどんな人材がそれをどのように生かすのかということが重要であることは言うまでもありません。情報の共有化とその運用の仕組みの活用には各社各様の方法を採ることができますが、それを有効にする組織の体制整備と企業風土の改革・醸成が同時にされなければ、効果が上がらないあるいは時間の経過とともに効果が薄れていくでしょう。ハードだけでなくソフトの整備が同時にされなければ効果は上がらないということです。
海外事業所は距離的に遠いので、日常的な日本からの支援も難しいので、情報の共有化を効果あるものにするためには工夫が必要になります。
1) 共有化情報を生かす人材の確保
日本からの情報を咀嚼し現地の作業者に勘所を指導できる人材を確保することです。そのような人材が採用できれば理想的ですが、それが難しければ育成します。それには、日本で実地に即した教育・訓練を行うことが最も効果的でしょう。現地のコンサルタントに教育・訓練を託すことも方法の一つですが、海外工場がマザー工場と同様の製品を同様の工程で生産するのであれば、現場的な教育・訓練のほうが効果的です。しかし、全ての教育訓練についていえることですが、教育・訓練の効果を持続させることは難しく、定期的継続的な活動が必要になります。
人材の流動的な海外では、教育・訓練を行った担当者が短期間でその業務から離れることがないような配慮も必要になります。日本と異なり離職・転職が頻繁ですから、確保した人材がそうならないような施策も必要になることもあります。「やる気」を常に維持させるような工夫や、絶えず刺激を与え続けることもその手段になります。一方的に情報を送るだけでなく双方向的であることが効果的ではないでしょうか。
海外工場では工場長のような経営トップとその補佐役である副工場長、総務部長、製造部長などの要職に日本人を配置し、実務担当に現地採用のスタッフを配置することが多いようです。経営トップにはリスクマネジメントの最終的な責任が要求され、万一トラブルが発生すればその対応の過程で現場の声を聞く必要もありますし、日常的に配信される事故災害などのトラブル情報を処理するには、経営トップは多忙すぎるので、現地の専任スタッフが欲しいところです。
2) わかり易く具体的な共有化情報
トラブル発生に対して、「なぜなぜ」の繰り返しで原因を追究すると、「人」や組織の問題に行きつくことがあります。直接原因に対して再発防止のために管理システムを改めたり守れるルールへの見直しなどは必要ですが、人や組織の問題では「国民性」や「社会観」の違いに気が付かされることがあります。日本で当たり前のように守られているルールがなぜ現地では守られないのかを考える必要がでてきます。(もっとも、なぜか日本ではなかなか守られない逆の事例もありますが)。このような理由から、共有化情報として直接原因とその直接原因に対する再発防止のため対策や結論だけを配信するだけでは情報が活用されないおそれもあります。事故災害やトラブルに関する調査で明らかになった経過などを含め、起こった事実関係の共有化が必要になります。国民性や社会観が異なると、効果的な対策もそれに合わせて修正が求められることもあるでしょう。
3) 言語の問題
海外との情報共有化では言語の問題を無視することができません。これまでは、意思疎通に何の問題も無いかのように記してきましたが、実際には使用言語の問題を解決しておく必要があります。
一般的には英語を共通語とすることが多いでしょう。しかし、初等教育を受けただけで英語の使用に問題がない国もあれば、高等教育を受けた人材でなければ英語での意思疎通が難しい国もあります。後者であれば、その様な人材を確保することが必要になります。
言語の壁による問題の有無にかかわらず、共有化情報では言語情報とともに可能な限り視覚的情報の併用が効果的です。言葉の理解が難しくても写真・イラストレーション・図表などの利用は理解の大きな助けになります。通達文を回付するだけでなく、さまざまな情報伝達ツールを活用して現場の作業者の理解を少しでも助けるようにすれば、共有化された情報が考えるヒントになります。個人的な体験になりますが、中国語を全く解しない私でも、中国出張時に図やイラストレーションの多い資料を利用し、説明に用いられている漢字を頼りとして、問題点の共有ができました。
ここまでは、インターネット等を利用した情報の共有化の有用性を記してきましたが、これは実務担当者が一堂に会する会議体の有用性を否定するものではありません。異なる事業所で同じような業務につく担当者が集まることは、その後でヨコの情報交換の助けになることは間違いありません。国内でも名前だけでなく顔も知っていれば、情報の交換がはるかに容易になることは私たちも経験しています。インターネットを利用した情報の双方向的な共有化を後押しするものということができます。ただし、幅広く召集して異なる業務の担当者を多数集めてもなかなか話で噛みあわず、結果として会議の密度が低下するなどの問題も発生するので、焦点を定め適切な人材を多すぎない程度に集めるようにして開催するようにしたほうが良いでしょう。
第3回 海外で本格生産を始める前に
海外に生産拠点を設立あるいは買収しても、製品の仕様は日本で決定されることが多いでしょう。拠点を移すだけで製品には日本生産品と同等のものを求めることもあります。本格生産の前には日本との間でサンプルや技術情報の交換が必要になりますが、今回はそのような準備段階に考えたいことを記します。
本格生産には至っていないので、もし立地国でコンプライアンス上の問題が起こったとしても、適切にそして誠実に事後処理を行えば、その計画の継続に致命的な打撃を蒙ることを避けることができるでしょう。しかし、ビジネスは時間との戦いでもありますから、何らかのトラブルで事業の立ち上げのスケジュールに齟齬を生じることは避けたいものです。海外に関わらず、一般的に新工場・新プラントの立ち上げでは、立地場所の事情を考慮して環境・安全・品質などの課題を解決しておくことが必要ですが、国内であれば既存工場と異なる新たな問題は起きにくく、起こっても対応は容易です。国内では規制当局は違反の摘発というよりも、法令遵守の状態を求めることに目的があるので、故意でなければ行政指導に従うことで解決するでしょう。しかし海外では法規制の仕組みも異なるので、その国や地域で受け入れられる解決手段を選択する必要があり、それは日本国内で採用した方法とは異なる場合もあります。また、規制当局が違反の是正だけでなく、摘発そのものを目的とすることもあります。化学物質規制への違反に対する罰則の適用が日本より厳格であったり、罰則が日本とは比較にならないほど厳しいこともあります。いずれにせよ、海外の事業化は計画段階からコンプライアンスを配慮しておくことが必要になります。
化学品は生産・販売時だけでなく、輸送やものあるいは情報として国境を越えるときにも規制(制約)を受けることがあります。数量に関わらず適用されることもあり、少量のサンプルの取り扱いでも規制が無視できないことがあります。
1) その化学品は日本から立地国に出す(輸出する)ことができるか
日本では外為法の輸出令があります。化学品の性状を確認するために分析用あるいは比較対象としてサンプルを送ることがあります。自社製品であれば、輸出令の対象であるかどうかは承知しているはずですが、品質確認などで購入原料をサンプルとして海外に送るときには、予め購入先に輸出令への該非確認をするほうがいいでしょう。輸出令は先端技術材料やいかにも化学兵器などの大量殺戮兵器に使用されることが予想される化学品を規制対象としていますので、よほどのことが無ければ規制品となることは少ないのですが、比較的汎用性の高い化学品が規制対象となっていることもあるので事前の確認は無駄ではありません。
輸出令に関しては、むしろ化学プラント・設備に注意が必要なのかも知れません。立地国で日本と同等の設備が調達できず、やむを得ず必要な設備・部品を日本から送りたいと思うことがあります。それまで使用していた手馴れた設備を使用して海外子会社の生産を円滑に立ち上げたいと思うこともあります。しかし、化学設備はいろいろな用途に転用できるので、特殊なものでなくても大量殺戮兵器の製造に利用されるおそれのある設備・部品と見なされることもあります。化学品の生産会社にとっては、本業ではない機械・設備の輸出令への該非判断は難しいときがあります。
このようなときの対応方法の一つは、機械・設備を生産(本業と)する会社に海外子会社から直接発注し入手することです。これは交換部品でも同じです。輸出令でいかなる場合でも輸出禁止の物品は限られており、規制の対象であっても多くの場合は許可を受ければ輸出ができますが、許可を受けるには日数を要しますので、該非の判定結果がグレーであれば早めに手続きを行って問題を解決しておきます。この手順を省略したために貨物が通関できずに止まることが無いようにしたいものです。
2) 輸出時の容器と輸送手段の問題
危険有害性のある化学品を輸送する手段には制約があります。「危険有害性のある」と書きましたが、ほとんどの化学品には何らかの危険有害性があるので、すべての化学品についてこの問題は関係する可能性があり、一度は正確に確認することが必要でしょう。
国内の化学品の陸上輸送では、消防法・毒劇法・道路法などへの対応が必要になります。このことは、化学品を自社製品とする会社は承知しているでしょうし、いずれも企業には馴染み深い法律ですので、うっかりしての違反という事態は起こらないでしょう。委託する運送会社に製品の法規制の該非を正しく伝えればいいのです。
しかし、海外に船舶あるいは航空機で送るときには、国内の問題とは別に輸送手段や容器などの正しい選択が必要になります。危険有害性を持つ化学品の輸送には国連容器が使用されており、輸出品を国内用容器から国連容器への詰め替えが必要になることもありますが、その作業は面倒でもあり危険性のある場合があります。船舶輸送では国内輸送と国内輸送でほぼ同じルール(船舶安全法の規則)が適用されますので、自社製品であればそれを認識しているでしょうが、他社製品(購入化学品)であれば、その都度知りえた情報から判断することになります。判定に自信が持てないときには、信頼できる乙仲(注)を介して送る方法があります。乙仲は輸送を本業としているだけあって、正確な判断を下すことができますが、成分や物理的化学的特性を聞かれたときには、正しく(ごまかし無く)答えなければなりません。海外への送付試料が他社からの購入品のときは、生産会社に確認をとることも一つの方法です。容器の詰め替えで品質上あるいは安全上の問題が懸念されるのであれば、海外子会社から生産会社へ直接発注する方法もあります。国連容器の使用は仕向け地内の輸送に関しても問題が起きることを避けることができます。
海外への試料は多くの場合は船便が利用されますが、船便は日数がかかります。緊急時で極少量であれば航空便で送ることもありますが、航空法(ということはIATAの規則)の規制は船舶輸送に比べて格段に厳しいものです。海上輸送であれば、少量の化学品による火災や爆発への対処は可能ですが、航空機内では致命的であることは容易に想像できます。少量の危険物を厳重に容器にいれ、念入りに包装したサンプルを手荷物で持ち込もうとして搭乗が拒否されたことがあったそうです。航空機の利用は時間の節約になりますが、このような事例になると「もとも子もない」、ということです。化学品の送付には、少量であっても必要な時間には余裕を見ておくことが必要です。
3) 仕向け地や立地国での化学物質の規制
今では世界の多くの国に化学物質を規制する制度がありますが、その仕組みは千差万別で、仕向け地の規制の内容は個別に考える必要があります。一言でこのように対応すべきだ、ということはできません。法律をよく読んで個別に理解するしかありません。化学品への規制は労働者の健康安全衛生、環境汚染、製品安全に対する規制など多岐にわたっているので、いくつもの法律を調べることになりますし、バーゼル条約・ストックホルム条約・ロッテルダム条約・モントリオール議定書などの条約もまた、化学品の国境をまたぐ移動を規制しています。化学物質の規制法律が整備されていない国に対しては、これらの国際条約のほうが重要な場合もあるでしょう。世界の国・地域における化学物質の法規制の概要については、稿を改めて記したいと思います。
(注)乙仲(おつなか):戦前の「海運組合法」で規定された定期船貨物の取次をする仲介業者の「乙種海運仲立業」の略です。1947年に廃止されましたが、現在でも昔の名残で「乙仲」と呼ばれています。
第4回 排水管理 -アンケート結果から-
この度、化学物質国際対応ネットワークの参加団体の御協力で、海外の事業所における「環境管理」、「労働安全」、「法規制」などに関する考え方を問うアンケートを実施しました。このような補完的業務は、製品の販売や利益の確保に直接関わるものではありませんが、適切に行うことが事業の安定的で継続的な拡大につながります。回答数はそれほど多くはなかったのですが、どのような部分に注意を払われているのか、という点は窺い知ることができました。生産拠点を海外に求める動きは活発ですが、進出先の規制の実態や進出の動機・ポリシー・取り扱う化学品(物質)により重視する課題とその対策は変わるでしょう。
生産工場の設立・稼動が、立地場所の周辺の環境に何らかの影響を及ぼすことは避けられません。現在ほど多種類大量の化学品ではありませんでしたが、かつては日本でも化学物質を適切に無害化処理しないで廃棄・放出して、環境汚染が問題となったことがありました。環境意識の高まりはもはや地球上のどこでもそのような行為を許容しませんし、そのための法制度も整備されています。これから工業化を進めようとする経済移行国や途上国では、化学物質による環境汚染に対する規制の整備を進め、経済の発展と環境保護を両立させようとしています。この流れに反することは、社会的には環境リスクを高めることになりますが、事業者にとっては法規制への対応や社会的責任という意味で経営リスクに直結するとも言えるでしょう。
アンケートでは、進出先として東アジア(中国、韓国、台湾、香港など)、東南アジア(タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ベトナム、インドネシアなど)、南アジア(インド、パキスタン、スリランカなど)が挙げられており、日本の製造業が海外展開するときの特有の傾向を反映しています。途上国や経済移行国では、運用状況は異なるものの環境規制の制度化は進んでいますが、静脈系のインフラ整備はまだまだこれからという段階ですので、環境対応の目標のおき方によっては、それなりの初期費用と維持費がかかり、日本国内よりも負担が大きくなることもあります。筆者の考える海外展開の特有の傾向については、今後のコラムで取り扱うテーマとも関係しています。ここでは長くなりますし、この連載の最終回でわかりやすく述べようと思います。
アンケートでは、多くの会社から評価基準に現地の規制値とする排水水質の環境アセスメントと、操業後の排水モニタリングを実施するとの回答を頂いております。今回は、通常の事業活動による環境負荷のうち、排水の環境負荷に対する影響について工場からの排水規制を考えます。
日本の法規制では水質汚濁防止法に関係します。この法律には健康項目と生活環境項目があり、健康項目は長期間飲用した場合に人の健康に害を及ぼすかどうかが要点で、その毒性(健康影響)が問題となります。わが国では、重金属や砒素・セレン・ホウ素・フッ素などの無機化合物などとともに、農薬、ハロゲン化物などの有機化合物も健康項目として規制対象です。生活環境項目は人の健康だけでなく水生生物の保全にも関係します。
海外の排水規制も同様の考え方で、特に重金属と無機化合物では、多くの国に排出規制がありますが、規制値は日本のそれよりも厳しいものもあります。重金属や無機化合物は、使用の段階で原材料に含まれているかどうかがわかリますので、環境中への放出は排水か廃棄物の形をとることが想定されます。したがって、操業時の排水管理項目として設定できます。当該国で日本の規制値よりも厳しい規制値が設定されていても、日本での実績が海外の基準に余裕を持って適合できていることが確認できれば、同じ技術を海外に移転することで対応できるでしょう。
有機化合物に対する規制にも、日本とアジア各国の間に違いがあります。日本ではトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素など、多くのハロゲン化炭化水素で排出基準が定められていますが、アジア各国でこれらの物質の排出基準を定めている国はまだ少ないようです。一方、わが国では上記以外の有機化合物で個別の排水基準が定められている物質はベンゼンとジオキサンで、どちらかといえば総量に関連するBODやCODの規制が主体ですが、例えば中国ではBODやCODとともに多種類の個別物質が規制の対象ですし、ホルムアルデヒドを規制物質とする国もあります。 わが国の技術を海外に移転する場合、わが国の規制にない化学物質は国内事業所での実績把握が必要になるでしょう。有機化合物の場合は、無機化合物と異なり、使用しているかどうかだけでなく、非意図的な工程中での副生にも注意が必要です。汎用性が高く複数の現場からの排出が予想されるトルエン・キシレンなどの溶剤類と、特定の製品を製造する工程からのみ排出可能性のある物質とでは対応方法が異なってくるでしょう。後者であれば、重金属などと同様に発生源対策が有効です。アジア各国では、現在は規制対象とされていないハロゲン化炭化水素も、そのハザードが明らかになり、使用量が増加し汎用性の高さへの認識が進むと、社会的な関心の高まりから、将来はわが国と同様に規制対象になる可能性もあり、少なくともわが国の排出削減実績をもつ技術を海外に移転させることが必要でしょう。
以上のことから、現在、規制がないことを理由に排出抑制を緩和させたプロセスを海外に持ち込むことは避けた方がいいように思われます。
水質汚濁防止法の生活環境項目には、個別の化学物質だけでなく、BOD、COD、水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量(SS)、n-ヘキサン抽出物質(鉱油類、動植物油脂類含有量)、窒素・リン含有量などがあります。マレーシア・タイ・フィリピンなどのBOD、COD、SSの規制値は、わが国の基準よりも厳しい数値を定めているようです。これらの国々は日本と比較して水質汚染への関心が高いのでしょうか。むしろ、上水道の整備が遅れ、浄水場の能力が十分でない国では、わが国以上にこれらの項目への配慮が求められるのでしょう。
汚染の定義、測定方法、前処理方法やサンプリング方法が異なれば、規制数値の比較だけからは排水規制の厳しさがはっきりしない場合もあります。しかし、余裕を持った排水実績であるならば、このような条件の違いを考慮しないでも規制への対応への可否を判断できるでしょう。規制値に対して余裕のない実績であれば分析要件を考慮した精度の高い分析・判定が必要となります。
一般に、排水基準は公共用水域に放出するときに適用されるので、工業団地などでまとめて排水を浄化処理する場合には、処理場の能力により個々の事業所からの排水の量と質が問われます。大量の排水を放出しかつ浄化しづらいものであればあるほど、処理場への費用負担が増えます。処理のできない排水であれば、事業所の稼動ができなくなります。安定的な稼動のためには、可能な限り環境負荷の少ない排水として排出できるように、日本国内の排水管理実績を実現できるような技術を移転することが対策の一つになるでしょう。
環境規制は国や地域の事情を反映して定められので、わが国のものとは異なる場合もあり、細かい条文だけでなく規制の枠組みの理解が必要です。そのうえで、対応策を決めるのは会社のポリシーです。現在だけでなく十分に予測できる将来の規制を含めて万全の対応がとれることが望ましいのですが、海外に設立する事業所の規模はそれほど大きいものではないことが多く、人的にも資金的にも完璧な対応を前もって準備しておくことは難しいでしょう。しかし、環境対策では施設・設備の整備に投資が必要になります。このコラムが環境・安全・法規制などに関係して、どのような状況までの対応を想定するのかという点を事業化の早い時期に考え、予定外の設備投資や効率の悪い追加投資を避けることにつながれば幸いです。
第5回 排ガス規制 -アンケートの結果から-
工場の稼動による環境影響は事前の予測に一致するとは限りません。そのため重要な項目については、稼動後にモニタリングでの実態把握が必要になります。法律がそれを求めることもありますが、そうでなくても規制は新しい科学的知見と社会の関心を反映して制定・改定されるので、モニタリング結果を参考にして早めの対策を考えることが必要でしょう。化学物質国際対応ネットワークの参加団体の御協力で、海外の事業所における「環境管理」、「労働安全」、「法規制」などに関する考え方を問うために実施したアンケートでは、モニタリング予定項目として、工場排水に続いて大気と廃棄物の回答を頂きました。
排ガスのモニタリングでは流路中に検知器を置く連続的な測定や、サンプリングによる分析を行います。作業現場では有害物質の滞留防止のために、給排気口と給排気設備を設置しますが、将来の排ガスのモニタリングを考えればその作業が容易になるように排気系の仕様を考えるでしょう。排ガスのモニタリング結果は法律が義務化したときの対応だけでなく、工程の改善などの自社内での活用や、住民や行政との関係を良好な状態に維持し社会からの信頼を得る上での有力なコミュニケーションツールにもなります。
日本における大気環境の保全では、人の健康を維持するための大気環境基準と、有害物質を排出する施設・設備からの排出基準が定められています。特定の工場からの排出ガスによる周辺の大気環境への影響評価は簡単ではありませんが、有害物質の排出は抑制するほうが好ましいことは言うまでもなく、事業者には可能な限りの排出量の削減による環境負荷の低減が望まれています。大気環境の保全は国全体の問題であるとともに、地域ごとの課題も異なるので日本では地方自治体の条例の規制があります。海外でも国の規制だけでなく、立地場所に特有の規制も考えなければならないでしょう。
大気環境基準は、燃焼施設、自動車、工場などから排出される有害物質などに設定されます。日本の大気汚染防止法も改正を重ねるたびに、この順に規制対象を拡張しました。海外の大気環境を守る法規制も同様です。環境規制の開始が遅れた途上国でも、急激な経済の発展は大気環境の劣化を招き、規制の対象はばいじんや浮遊粒子状物質(SPM)から化学物質まで広がっています。
海外で予想される将来の規制の強化には、日本企業は国内でこの問題に対処してきた経験と知識を生かすことができるでしょう。規制の強化への対応には除害設備の更新や能力増強が必要になることもあります。
燃焼施設から大気環境への排出物には、重金属を含むこともあるばいじん、窒素・硫黄等の酸化物、さらに水分との反応で副生する硝酸・硫酸などの各種無機酸や、燃焼処理しきれなかった揮発性有機化合物(VOC)などがあります。このうち固形の微粒子状の排出物に対しては、日本のダイオキシン対策特別措置法で規制される燃焼施設の性能があれば、将来的に途上国でダイオキシン類に大気環境基準や排出基準が設定されても、生成と排出の抑制で適切な対応が可能でしょうし、そこで使用される高性能フィルターには日本の大気汚染防止法では、ばい煙に分類され、海外ではばいじんあるいは個別物質として規制の対象とされることのある重金属化合物類の固形微粒子の除去が期待できます。
化学品を使用する工場から大気に排出される有害化学物質にVOCがあります。わが国の大気汚染防止法は、塗装や印刷などを行う特定の工場からの炭素換算排出量としてVOCを規制しています。業務の種類によっては規制対象に含まれないことがありますが、海外では業務の種類に関わらず全ての事業所に適用されることがあります。VOCは光化学オキシダントや微小粒子状物質(PM2.5)の原因物質とも考えられています。この法律では低濃度でも長期的な摂取で健康影響が生ずるおそれのある物質を「有害大気汚染物質」とし、248物質がリストアップされています。そして、優先的に対策に取り組むべき「優先取組物質」として23物質を選定しています。日本で個別物質として排出抑制基準が定められているのは、当時早急に排出抑制を行わなければならなかった3つの指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)に留まっていますが、海外では個別物質の排出基準を詳細に定めている例もあり、ベトナムでは約100種の物質に排ガスの国家技術基準があります。これらの化学物質を製造あるいは使用しているのであれば、排出の実態を調べる必要があるでしょう。日本の大気汚染防止法は個別物質の排出状態の把握を求めてはいませんが、VOC全体の炭素換算排出量を知るためには結局個別物質の実態把握が必要ですので、事業者の実務上の対応では個別物質の規制と炭素換算総排出量の規制の間にはそれほど大きな違いはない、と考えることもできます。
日本のVOCの排出抑制対策は、VOCの排出量が多い施設については大気環境への影響が大きく、社会的責任も重いことから法規制により確実に排出抑制を進めることとし、排出量が比較的少ない施設については、個々の事業者が柔軟に自主的な取組を行うことにより効果的な排出抑制を図ることとしました。これとともに産業界も二期にわたって自主管理計画を進め、双方の適切な組み合わせが相乗的な効果を発揮させる(法規制と自主的取組のベストミックス)取組が行われてきました。更に、事業者は化学物質排出把握管理促進法の「PRTR制度」においても、一定の成果をあげてきました。どちらも事業者の自主的な活動に委ねられたことに特徴があります。事業者は自らの工程の実態を考慮して最も適切な方法を選択しました。大気放出への前処理には、燃焼・吸着吸収・化学的物理的分解による無害化などの方法がありますが、VOCの性状、使用方法や量、共存VOCとの関係などで最適な方法は変わります。
自主的な活動で実現可能な方法を採用することで、実質的にVOC削減に大きな成果をあげた活動の経験は、日本企業の成功体験として海外にも展開されることが期待できます。
日本企業が海外に持つ工場では、国内工場と類似の工程から類似のVOCが発生することが考えられますので、国内で採用したVOC削減手法が適用できるでしょう。
自動車からの排ガスの問題は、急速にモータリゼーションの進む途上国でも無視できない問題となっています。自動車排ガスには芳香族炭化水素など、燃焼施設から排出されるものと同じ種類の有害物質も含まれており、日本のPRTRの推計排出量によれば工場などの固定発生源からの量に比べても無視できないことがわかっています。このような物質が、仮に大気環境基準を超えて検出されたとしても、工場排出によるものかどうかはわかりません。まして、特殊な物質でない限り発生源の工場を特定することは極めて困難です。しかし、事業者は社会的責任として最低限は法律の定める基準を守り、さらには可能な限りのVOC削減を図ることが望まれています。プロセスで使用する化学物質は化学的・物理的特性を考慮して採用されるので、代替物質を選ぶことは容易でありません。どんな物質にも危険有害性の可能性があることを考えれば、有害性のわからない代替物を求めるよりも、使用する化学物質の特性と使用方法を考え、実績のある排出抑制策と後処理方法を採用することが環境負荷の低減には有効でしょう。
第6回 産業廃棄物対策 -アンケートの結果から
工場を稼動させると廃棄物が発生します。日本では廃棄物を処理する仕組みが整備されているので、事業者は産業廃棄物(不要物)どのように処理するのか選択できます。しかし、途上国でも日本と同様に処理できるとは限りません。
近年は途上国でも環境問題としての廃棄物に関する法制度の整備が進んでいますが、先進国からの廃棄物や廃棄物に近い中古製品が途上国に流入する現実を見ると、新しい南北問題にもなっているように思われます。環境関連の法制度の整備は地球環境全体の問題と考えれば好ましいのですが、ものを生産する事業者には大きな制約条件にもなります。
日本のリサイクルシステムを含めた廃棄物処理の仕組みが整えられるには、長い時間と社会的なコンセンサスが必要でした。途上国では、廃棄物処理のインフラが以前の日本と同じような状態であるにも関わらず、先進国にならった法規制が先に進み、現実との間にギャップを生じているところがあるようです。安定的で継続的な事業の維持・発展には、社会インフラがある程度整備されていることが望ましいのですが、適切な委託処理業者が見つからず廃棄物の処理が進まないにも関わらず、法律は廃棄物を自社工場に留め置くことに時間的な制約を設けている、ということで、出口の無い廃棄物が生産活動に影響を及ぼすことが考えられます。
日本では、排出者に産業廃棄物の処分責任があり、多くの場合は許可を有する処理業者に委託しますが、海外でも事情は同様です。途上国では廃棄物処理業者の処理能力が不足しているように見受けられるのにも関わらず廃棄物の問題が事業継続の支障になっているという話はあまり聞かないので、実際には不法な処理も行われていると思われます。現地の事業者がそのような業者に委託して事業を進めているのだから、日本からの企業も同じようにすればいいのかと言うと、それはそうではないように思われます。現地の事業者は資本力も弱く、自国産業の育成のために行政は見て見ぬ振りということもありますが、進出した日系企業にも同じように対応するとは限りません。
日本の廃棄物処理法は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物とし、通常の廃棄物よりも厳しい管理を要求しています。化学物質関連ではPCB使用部品、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなどで、中でも特定の施設から排出され、有害な元素や化学物質を含む廃石綿、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリは特定有害産業廃棄物です。このように廃棄物を分類し排出施設を特定して危険有害性の高い廃棄物(国によって名称は異なります)を指定する方法は、多くの先進国や途上国でも同様の方法が運用されています。詳細は国や地域により異なり、その国の特別の事情を加味したり、途上国では先進国の枠組みをモデルに導入したりすることもあります。そのような廃棄物は特別の管理が必要で、処理費用が高くなることは日本と同じです。
規制の基準値が化学物質の含有量や危険性や有害性を示す指標で定められていると、事業者の対応は煩雑になることがあります。製品であれば定められた規格に収まるように設計・生産されているので、適切なサンプリングと分析で製品の特性を知ることができますが、廃棄物には品質規格の考え方が無いので、雑多な種類の廃棄物がまとめられることもあります。ロットの概念がなく均質性にも保証されない廃棄物では、予め規制に応じた分別が必要になります。勿論、原材料の残余物のように一定組成で数量もある程度まとまったものであれば、まず回収・再利用で廃棄物の有効利用を考えるのは、日本での対応と同じでしょう。
今回は、日本の廃棄物処理法にある特別管理産業廃棄物の分類を参考として、途上国での対応方法を考えてみます。
1) 金属・重金属
日本では水銀、カドミウム、鉛、六価クロム等を一定以上含む産業廃棄物が特定有害産業廃棄物ですが、東南アジアの途上国・経済移行国にはそれ以外にも多種類の金属・重金属に規制があります。代替ができなければ、金属・重金属などに限らず全ての廃棄物は3R(リデュース・リユース・リサイクル)の適用で排出量の削減を考えることになります。金属元素では他成分からの分離技術の確立が必要となることもあります。日本で規制の無い重金属で汎用性の高いものに、ニッケル・銅・コバルトなどの鉄族の遷移金属などがありますが、これらの場合を含めて金属・重金属が化学原料として使用されるのは限られていますし、有機化合物などと違い工程から非意図的に生成することも無いので、使用者はどの工程からどのような形で廃棄物となるかということを特定しておくことは可能です。前々回に記した排水への対応と並行して排出削減を進めることになるでしょう。ただし、分離技術の開発に成功し、これらの元素を含有する廃棄物全体の量は削減されたとしても、リサイクル・リユースができなければ、残念ながら金属・重金属分の排出量の削減にはなりません。
2) 有機溶剤
日本で特別管理産業廃棄物として規制される溶剤は、特定のハロゲン化炭化水素類やベンゼン、1,4-ジオキサン等ですが、途上国の中にはさらに多くの溶剤を規制対象としていることがあります。溶剤類は廃棄物対策としてだけでなく、排水・排ガスの規制と併せての対策が必要でしょう。
溶剤によっては、毒性だけでなく物理危険性の問題があります。適切な焼却設備により無害化・減量化が可能ですが、外部委託では可燃性による危険性(火災・爆発)を考え、可能な限り廃棄物に含有させないような工程管理が必要です。揮発性の高い溶剤は作業環境の悪化にもなりますので、廃棄物の減量を考えるだけでなく、発散源近くで効率的な処理を考えることも重要です。溶剤類を含んだウエスや容器などの扱いも同様です。
日本でもハロゲン含有の廃溶剤の一部は、特定有害産業廃棄物の廃油として規制されますが、海外ではさらに多くの種類が危険有害性の廃棄物とされていることがあります。ハロゲン含有溶剤は作業者の健康影響や環境影響を考えて使用を控えるようになってきています。ハロゲン含有量が高い溶剤は燃焼処理が難しく、処理費用が高くなることも考えておくことが必要でしょう。後処理の費用も考えて使用の適否を判断しますが、健康や環境への影響や、規制の動向も考えれば、可能な限り使用を控えることが、化学物質管理としては好ましいように思われます。
3) 有機化合物
日本で特別管理産業廃棄物として廃棄物処理法の対象となる有機化合物は、農薬類を除けば有機リン化合物です。しかし、海外では健康影響(毒性)や環境影響を考慮して、多種多様な有機化合物を含有する廃棄物を危険有害廃棄物として特別に規制することがあります。
急性毒性だけでなく、CMR(発がん性、変異原性、生殖毒性)物質なども規制されることがあります。環境影響では、環境残留性(難分解性)物質やオゾン層破壊物質なども考慮されることがあります。日本では、これらの物質は廃棄物になる前(製造・使用)の段階で化審法・オゾン層保護法などの規制の対象となっているので製造又は使用が禁止あるいは控えられています。また、縮合多環芳香族化合物は海外で規制対象となることがあります。ベンゾピレンなどが代表的な化学物質ですが、海外では廃棄物だけではなく土壌汚染の規制対象となっていることがあります。この縮合多環芳香族化合物は、化学原料として使用されることは少ないのでしょうが、芳香族化合物中の不純物として混入したり、まれに化学反応の副反応として生成したりすることがあります。発がん性が疑われる物質もあり、環境中で分解されにくく生体内に蓄積しやすいので使用原料への混入の有無や工程中で生成されないことを確認しておきたい物質です。
4) 農薬
日本でも海外でも農薬、特に環境残留性の高いものについては、廃棄物としての特別な規制があります。農薬が化学原料として用いられることはほとんど無いので、この規制はそれを生産する事業者や農業廃棄物を対象としていると考えられます。日本での規制対象は失効農薬が多く、将来的には新たな廃棄物として発生する可能性はほとんど無いのですが、途上国ではまだ使用が続いていることがあります。
5) 非意図的生成物
非意図的生成物はそれ自体の生産を目的としない物質で、反応工程などから発生する物質です。代表的な物質は焼却処理の過程で生成する塩素化ダイオキシンなどです。多くの国が規制の対象としていますが、事情は日本でも全く同様なので国内での廃棄物処理法やダイオキシン対策特別措置法への対応を海外に移転すれば対応は可能でしょう。
6) その他の国際的に規制される物質
廃棄物中の化学物質として規制されている例は少ないのですが、先に記したオゾン層破壊物質(モントリオール議定書)や残留性農薬などの環境残留性物質(POPs= ストックホルム条約)等は、近い将来海外でも廃棄物中の汚染物質として規制対象となることが考えられます。日本では既に化審法の特定化学物質としての規制があり、厳格な管理が求められますが、海外でも同様の状況になることが考えられます、国や地域によって事情が異なるので、日本で実施している管理と同様のことを行えば十分であるのか、それでは不十分であるのか、ということは予想できません。可能な限り代替物や代替技術の適用で、海外でもこのような物質の使用を控えることが好ましいように思われます。
最後に、発生する廃棄物の管理ではありませんが、関連する注意事項を記します。それは、リサイクル原料の使用です。リサイクルは資源の有効活用ということで、日本や先進国だけでなく途上国でも積極的に進められていますが、リサイクル原料の中には、使用が法律で禁止されている物質(元素)を含むことがあります。製品寿命の長いプラスチック製品をリサイクルすると何十年も前に使用され現在は禁止されている物質・元素が含まれていることがあります。日本などの先進国でもリサイクル原料は品質管理が難しいのですが、海外、特に途上国では未だに使用が許容されているものもあり、そのような物質を含有するリサイクル原料を用いた製品を国外、とりわけ先進国に輸出しようとするときは注意が必要になります。リサイクルは資源の有効利用の点で好ましいことはいうまでもありませんが、規制物質が基準値を超えて含有されていれば法律違反に問われることもあり企業にとって大きな打撃となるでしょう。海外、特に品質管理が十分でない国でのリサイクル原料の使用には十分な配慮が必要でしょう。
第7回 土壌汚染対策 -アンケートの結果から
アンケートでは、土壌汚染に関して何らかのアセスメント活動をされていると回答された会社は少数でした。しかし、土壌汚染はこれまでの排水・排ガス・廃棄物などとは異なった形の環境側面で会社の経営に影響を及ぼす可能性があると思います。事業活動に伴う環境負荷は排出を止めればとりあえず周辺への影響を低減させることができます。一方、土壌汚染は汚染物質がいつまでも残留するので、浄化・除去などの対策を採らなければ本質的な解決にはなりません。地下水などを経由して汚染拡散の可能性があれば対策の実施には時間的猶予が無いこともあります。浄化・除去には多額の費用と時間を必要とするだけでなく、インフラが整備されていなければ事業者は汚染土壌の最終処分にも困ります。
日本の土壌汚染対策法の目的は、汚染土壌を直接にあるいは地下水を通じて飲料水からの摂取で人の健康に影響が及ぶことの防止にあります。対象物質は、1)重金属・無機化合物、2)有害有機化合物、3)農薬やPCB等の環境残留性の強い物質などの三種類に分けられ、どの国や地域の規制物質もこの分類で整理できます。日本の法律は汚染土壌の除去・浄化、覆土や封じ込めによる対策を行うこととしていますが、このようなばく露防止対策だけでは当面のリスクは下がっても汚染物質がその場に留まり続けるので根本的な問題の解決は先送りとなります。
東南アジア諸国には、土壌汚染対策法に相当する法制度が整備されていないところが多いのですが、土壌の汚染は地下水を経由して飲料水の質の低下を懸念させるので、現在土壌汚染規制の無い国や地域でも排水規制に準じた土壌環境保全が法制化される可能性があリます。排水規制と土壌汚染規制の両方を持つ国では、対象物質の多くは共通しています。既に記したように排水・排ガスなどは、排出を止めることで法令違反は回避できますが、法律の施行時に既に存在している土壌汚染も規制対象であることを免れませんので、何らかの対策無しでは違反状態が解消できないことになります。
土壌汚染物質は以下のように分類できます。
1) 重金属・無機化合物
日本では、カドミウム、水銀、六価クロム、鉛、ヒ素、シアン、セレン、フッ素、ホウ素及びこれらの化合物です。タイ、中国あるいは欧米などでは、マンガン、ニッケルなどの各種重金属を含めることがあります。日本では、定められた試験法によって水で抽出されたときの抽出水中の濃度と、土壌中の含有量の二つが基準ですが、海外ではもっぱら乾燥土壌中の含有量と地下水濃度で規制されていますので、試験方法の違いから、同じ土壌サンプルでも規制に対する該否の判定結果は異なることがあります。次の2及び3では日本は抽出した濃度のによる基準(土壌溶出量基準)しか無いものが多いのですが、海外では同様に土壌含有量や地下水濃度を基準とします。国や地域によって土壌汚染に対する考え方の違いが窺われます。日本は土壌から地下水への溶出移動に懸念を持っているといえるでしょう。日本企業が進出先としている東アジア・東南アジア各国の排水規制は、国や地域の特性を考慮して対象物質(元素)を選択し、さらに適宜欧米の基準を参考にしているので、土壌基準が法制化されるのであれば同様の考え方となることが予測されます。
2) 有害有機化学物質
日本では脂肪族ハロゲン化合物とベンゼンが対象物質です。欧米では、その他に脂肪族・芳香族炭化水素、芳香族ハロゲン化物、各種エステル・アルコール類、フェノール類、窒素化合物なども規制の対象となることがあり、アジアでもこの考え方を取り入れて対象物質とする国があります。この中で溶剤類は地下の埋設タンクに保管されることがあり、その周辺は漏洩等により汚染されやすいと考えたほうがよいでしょう。
3) 農薬あるいは残留性有機化学物質(POPs)
かつて使用されていた、あるいは途上国では現在でも使用されている農薬の中には、POPsに指定されており、土壌中で分解されにくいものがあります。そうでなくても、取得した土地の履歴が農地であれば規制対象の農薬による汚染の可能性があり、しかも2)と異なって特定の場所ではなく、用地全体にわたる広範囲な土壌調査になる可能性があります。
稼動中の工場の土壌汚染に気付くきっかけは、汚染物質の漏洩などで当局からの指示により行った土壌調査などです。そのときは当局もそれを承知していますから、速やかな対処と情報の開示・共有が必要となります。土壌中の汚染物質のリスクを許容範囲内に留める対策を行えば、工場稼動の停止が求められることはあまりありません。汚染物質の完全除去や浄化などの本質的対策まで要求されることも少ないでしょう。しかし、用地がそのような状態にあれば、将来は何らかの本質的な対策が求められる可能性があり厄介な課題を背負い込んだことになります。仮に、過去の負の遺産に対して所有者(占有者)に責任が無いことが認められても、これが必ずしも将来の浄化まで免責されるとは限りません。事業の廃止時や所有地を売却・譲渡時には、汚染土壌の除去・浄化が求められることがあります。
土壌汚染の調査結果が規制(基準)値を越えた場合、汚染かどうかの判断が必要になります。土壌中の化学物質(元素)が自然要因で基準値を越えることがあります。海外では、 このような状態は「汚染」とは見なされず、浄化を求められないこともあるのですが、それを決めるのは規制当局であり、十分な理解を得るためには当局への速やかな報告と情報の共有化が必要になるでしょう。理解が得られれば、将来にわたる厄介な問題の解決になるだけでなく、将来の土地の売却・譲渡時の不利な要因を解消できます。
このように土壌汚染は将来の工場経営に影響を及ぼす問題ですので、工場用地の取得時には法律の有無に拘わらず土壌の分析が必要でしょう。取得後に土壌の汚染が分かり、さらに真の汚染者が分かったとしても、そこに土地の浄化を求めることは実際には極めて困難です。土壌調査はM&Aではデューディリジェンス(DD)の一環として行われます。文書によるPhase 1(土地の履歴調査)だけからは、汚染の可能性があることを知ることはできても、汚染が無いことの確証を得ることはできません。土地の履歴で化学物質を相当量使用していたことが分かれば、当然汚染の疑いは避けられませんし、前歴が農地であっても農薬の汚染が懸念されることは既に記したとおりです。続くボーリング調査のサンプリング方法には用地を碁盤目状に仕切る日本の手法を応用できますが、分析項目には日本と世界の標準の間に相違があるので、その国や地域の特殊性や排水規制の状況を加味して欧米の項目を参考にすることが実際的でしょう。日本の方法による水を用いた抽出分析も必要となることもありますが、どちらかといえば乾燥土壌中の含有量や地下水の分析が主体となるでしょう。地下水への移行の可能性を知るために、土壌中の深さ方向の分布やその土地の地下水位と流れ方向に関する情報も必要になります。買収による用地取得で既に建造物があり、碁盤目状のサンプリングが難しければ、Phase 1の調査結果を参考として、ボーリング調査を省略したり、近接場所のサンプリングで済ませたりすることもあります。化学原料として用いられた物質の汚染範囲は限定的であることが多いので、使用・貯蔵した場所を重点的に調べる方法もあります。このようにして分かった土壌汚染に対して、用地の売買では汚染責任者に浄化責任を負わせる、あるいは購入価格を減額するなどで購入者は対処することになるでしょう。
このように土壌汚染は土地の資産価値を下げるので、土地の売却・譲渡時にも影響があります。国内工場と異なり、海外の工場は経済的な理由あるいは事業方針などの変更で、売却・譲渡となるまでの時間は短くなる可能性が高いでしょうから、そのときのことを考えておく必要があります。そのときに当局から「汚染」ではないことあるいは浄化の必要が無いことの判断が示されていれば、土地の売買交渉は円滑に進めることができますが、そのような当局の判断を受けるまでには相応の時間を必要とします。土地の売買交渉が始まってからの土壌調査では間に合わないこともあり、時間的制約のあるB to Bの取引では、事前に情報を用意しておけば有利に交渉を進めることができるでしょう。土壌汚染は工場の従業員の健康リスクや周辺への環境リスクであると同時に、経営リスクにもなることを考えておくことが必要だと思います。
第8回 労働安全衛生 -アンケートの結果から-
本コラムのために昨年1月、化学物質国際対応ネットワークの参加団体に対して行った、海外進出に関するアンケートの調査結果では、現地企業の買収の際の事前調査として、労働安全衛生に関しては労働法令の遵守状況と労働災害を原因とした刑罰や行政処分の有無、続いて事故災害事例を調査対象とするとの回答を頂きました。法令遵守と無事故無災害への営みは企業の社会的責任であると同時に、各社とも事業の確実な継続性には不可欠の条件と考えていることが窺われます。
労働安全衛生法に、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」とあるように、労働者の安全と健康を守ることは事業者の責務ですが、法令の定める事項は「最低基準」と理解する必要があります。法令を遵守しないことが労働災害発生の原因とされれば、事業者は厳しく労働安全衛生法違反が問われます。化学物質へのばく露に関係する事例としては、法定の環境測定の不実施や判定結果からの管理区分に求められる対策を怠った場合などがあります。
しかし、最近の労働災害事例からは、化学物質に起因する労働者の疾病・災害の予防には、法令に明示的に記されている事項の遵守や法規制対象物質の管理だけでは決して十分ではないことがわかります。
海外の多くの労働安全衛生法規では、作業環境を許容濃度以下に確保することを事業者に求め、ガイドラインなどを公表していますが、それを実現する手法の選択は事業者の自主的な判断に委ねることが多いようです。このような、事業者の自主的な対応を重視する考え方は、日本でも2014年の労働安全衛生法の改正にも取り入れられ、世界的な労働現場での化学物質管理の主流になっています。ばく露許容濃度を法律に基づき定める場合もあれば、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)のような非政府機関の勧告値を採用することもありますが、いずれにしても事業者には実現可能な最善の手段で労働者への化学物質の可能な限りのばく露低減が求められます。途上国も先進国のばく露許容濃度値を参考にしつつ、同様の仕組みで良好な作業環境の確保を求めています。
日本では労働安全衛生法によって約90種の物質に管理濃度を定め、これとの重複を含めて産業衛生学会が約200種の許容濃度を勧告しています。海外では、ACGIHが約700種、英国安全衛生庁(HSE)が約300種(職業曝露限界WEL)、中国が約360種(許容曝露限界PEL)、マレーシアが約640種(許容曝露限界PEL)、シンガポールでは約160種の物質に許容濃度(勧告値)があります。海外では、我が国の粉じん障害防止規則の規制に相当する微小粒子についての規制では、適用外物質を示しながら化合物(物質)を特定せずに全ての金属塩や酸化物などを対象とすることもあるので、物質数の多寡を比較することは難しいのですが、許容値を設定している国ではいずれも日本と同じかそれ以上の物質が対象で、その種類も国によって異なります。個別の物質やプロセスごとに対応を考えることは大変な作業のように見えますが、実際には労働者の化学物質ばく露の低減のために選択できる設備的な対策は限られており、それぞれの国のガイドラインも細かい点を別にすれば労働安全衛生法が示すものと同様ですので、日本のばく露抑制策を海外でも応用することができるでしょう。その上で、規制値があってばく露濃度が推定できれば、ばく露抑制策の適否が合理的に判断できますし、推定が難しければ実際の環境濃度測定から判断します。
規制値がない場合でも事業者は次に記す自主的な安全性評価活動(リスクアセスメント)で対策の適否を判断することが望まれます。事業者が自主的なリスクアセスメントとそれに基づくマネジメントを適切に実施していれば、万一の事態でも事業者に瑕疵がない、あるいは可能な限りの対策を取ったことの証になります。労働安全衛生法の改正で事業者はリスクアセスメントの実施を求められるようになりましたが、ハザード管理からリスク管理への移行は、むしろ海外が先行したように思われ、それは先進国から途上国にも広がっています。リスクアセスメントでは毒性とばく露可能性を考慮しますが、化学物質の全ての健康影響が必ずしも明らかにされているとは限らないこと、どんな化学物質も好ましくない影響を及ぼす可能性があることを考えれば、労働現場では化学物質の物理的特性、とりわけ呼吸器系のばく露からの影響と関連付けられる揮発性・揮散性を考慮してばく露の最少化を考えることになるでしょう。
リスクアセスメントは日本でも普及が端緒についたところですので、本格的な取組みはこれからという企業もあるでしょう。リスクアセスメントには定量的で精緻なものから定性的・簡易的なものまで各種提案があります。定性的・簡易的なものは比較的習得が容易ですので、施設・設備の改修などに際しては現場でも実施可能でしょう。ただし手法が簡易的であればあるほど、評価結果は安全サイドによったものになりがちです。
ばく露防止の設備対策を行っても、実際の作業が適切でなければ意味がないので、そのためには現場の管理監督者の教育と育成が必要です。アンケート調査結果では、現地の担当者を日本に呼び寄せて教育する、日本の安全担当を随時現地に派遣する、日本人の安全担当を常駐させる、現地のコンサルタントを起用するといった順に回答がありました。このうち現地のコンサルタントを起用する方策以外は、いずれも日本の安全管理システムを海外の関係会社に展開するものです。さまざまな課題は残っているものの、総体的には高い労働安全衛生のレベルにあるといえる日本企業が、生産現場の特性を理解してプロセスとともに実績のある安全衛生の仕組みを現地に移植することには相応の効果が期待できますが、単発で終わらない定期的で継続的な教育プログラムが必要です。さらに、化学物質の管理に限らず、安全確保には工場のガバナンスも重要となるので、安全担当者への技術的な事項の教育とともに、現地の経営層には安全重視の考え方の理解と指導的な実践が求められます。そのためには日本でも普及が進んでいる労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の適用も有効となることがあるでしょう。労働安全衛生に限らず品質や環境などのマネジメントシステムが機能するためにはガバナンスの有効性が必要で、逆に安全・環境・品質が適切に管理されていることは、ガバナンスの有効性の証明にもなるでしょう。
労働安全衛生の確保は、「人」に関わる事項ですので、単に制度的な対応策だけでなく、進出先の国民性や習慣なども配慮する必要がありますが、この問題については稿を改めて記します。
第9回 まとめ
前回までは化学物質国際対応ネットワークの参加団体様の御協力を得たアンケート結果を参考にして、グローバル化に付随する化学物質管理の個別の問題を考えました。
近年、開発途上国や市場経済移行国でも法整備が進められている新規化学物質や特定の用途に対する化学物質の登録制度については、今回の連載では触れませんでしたが、海外の進出先で該当する化学物質が入手・使用が可能か、事前の登録や届出等の作業が必要か、使用上の制限はあるのか、という点を考慮することが必要であることは言うまでもありません。化学物質の登録制度を持つ国や地域では、日本の労働安全衛生法や化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)と同様に、新規化学物質の製造・輸入は、事前に健康影響・環境影響を考えるうえで必要なデータや物質情報を提出し登録することで可能となりますし、国や地域によってはリスクアセスメントの結果が必要になることがあります。日本の事業者が国内でその手続を済ませていれば、多くの場合はそのデータや物質情報が利用できますが、それだけでは不十分である場合や、多くの国や地域で既存化学物質とされていても進出先では登録を必要とすることもあるので事前の調査は欠かせません。自らが製造する物質でなければ、製造者・供給者に協力を求めることになります。日本を含めて複数の国の登録があれば進出先でも登録物質としての扱いを受ける、あるいは簡易的な登録で済む制度があれば、事業者には負担が軽くなるのですが、問題が環境や人の健康に関わることであり、国や地域によって考え方、懸念事項や影響が同じとは限らないので、そのような形で「グローバル化」が進むのは容易でないように思われます。
化学物質の登録には、少なからずの準備期間と相応の費用を必要とします。しかし登録が終了し製造・輸入・使用が可能となれば、例えばストックホルム条約の対象物質のように、有害物質として世界的に認識が共通して廃絶が求められない限り、その後に禁止されることは滅多にないので、登録作業は最初の通り過ぎなければならない関門と考えます。
それに対して、化学物質に関する環境規制はこれからも世界的に広がるだけでなく、より厳しくなるでしょう。そして、事業を継続するために予想外のコスト負担が必要となる事態も生じる可能性があります。この連載で、事業を開始した後に規制への対応として予想される事態を考えてきたのは、化学物質管理では、化学物質を取り扱うための準備作業よりも、事業を開始した後に対応することの方がはるかに多くの問題を含んでいると考えたからです。
開発途上国や市場経済移行国の環境規制は、先進各国の制度を参考としていることもあり、対象物質の種類や規制値(濃度)の両方でわが国の規制に比べても決して緩いものではありません。むしろ「本当に守ることができるのだろうか」と思われるほど厳しいものもあります。実際、必ずしも基準に適合した事業活動を進められず「野放し」の状態にあることを散見することもありますが、そのような状況でも日本企業が海外に進出する場合には、規制値をクリアすることを前提としてプロセスを検討し事業化を考えるしかありません。これまでも度々記してきましたが、多くの場合は日本の規制をクリアできるプラント能力であれば現地の規制もクリアできる可能性が高いと思いますが、このことはプラントの建設費用が海外で軽減されることを期待してはならないことを意味しています。海外の規制や取締りが緩いことを期待して、プラント能力の劣った状態で事業を進めることは望ましくありません。
海外における環境や安全に関して事業者への法令違反に対する責任の問い方には、日本とは異なるものを感じることがあります。国や地域によって法令違反にどのような形で罰則が適用されるのかは異なります。労働安全衛生に関する箇所でも触れましたが、日本とは異なり一般的な安全管理義務違反、すなわち事故や災害を起こしたことに対して罰則が適用されることがあります。
事故や災害は法令の遵守だけではゼロにすることは不可能で、無人化・自動化されていない現場では、作業者の判断に委ねる割合が高くなればそれだけ人に起因する事故災害の発生確率は高くなり、事業者には高い経営リスクとなります。国や地域によって変わりますが、国民性あるいは気質の違いがあることを考えれば、日本では曖昧な関係でいわば阿吽の呼吸で進められているプラントの管理に対してマネジメントシステムの考え方を取り入れて、事業者と労働者の責任範囲を明確にしておくことが望ましいでしょう。マネジメントシステムの運用ではシステムを作るよりも維持する方が難しいので、メンテナンスと教育・訓練を継続的に行うことが求められます。マネジメントシステムは、日本でも定着しつつありますが、海外で事業を円滑に進めるためには、不可欠ではないかと思われます。
アンケートでは、環境・安全に関する教育は、「日本に呼び寄せて」あるいは「日本からの教育担当者の随時派遣」という回答が寄せられました。「日本人担当者の現地常駐」や「現地のコンサルタント会社に委託する」との回答が少なかったのは、この分野の専門家を常駐させるだけの人材を確保していない、あるいはコストがかかりすぎるという判断によるものなのでしょうが、同時に日本での環境管理や安全管理の仕組みを現地にも定着させたいという考え方が根底にあるものと思われます。
日本流の安全管理・環境管理の仕組みは相応の成果を収めており、それを開発途上国や市場経済移行国に移植するのは成功体験をもとにする効果的な方法ですが、それにマネジメントシステムの考え方を加えて、化学物質に起因する環境汚染の防止と労働衛生の確保を図ることが現実的な対策ではないでしょうか。