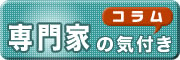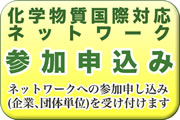PFAS対策の国際状況と今後の動向
- このコラムは、国内事業者において特に近年非常に関心が高まっているPFASについて、国内外のPFAS規制動向について調査し、ウェブサイトやセミナーにより情報発信されてきました日本フルオロケミカルプロダクト協議会の松岡康彦氏に、PFAS対策の国内外の状況及び動向について情報を整理いただき、今後の事業者に求められる対応について専門的知見から執筆をいただきました。
- このコラムに記載されている内容に関し、法的対応等を保障するものではありません。また、化学物質国際対応ネットワークまたは環境省の見解を示すものではありません。あらかじめご了承ください。
- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もございます。あらかじめご了承下さい。
→ご意見・ご感想電子メール送付先:
化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@oecc.or.jp)
目次
第1回 PFAS対策の国際状況と今後の動向 (1)
1.はじめに
有機フッ素化合物の歴史は、1930年代前半に空調機用冷媒の商業生産、また同後半のフッ素ポリマーの開発で始まった。これら有機フッ素化合物は耐熱性や耐薬品性などユニークな性質を有することから、様々な分野で使用され、第二次世界大戦後の社会生活の進化を支えてきた。然しながら、有機フッ素化合物を含む製品が寿命を終え廃棄されると、その卓越した耐久性から環境下での残留性が指摘され、また、一部の化合物は生物蓄積性や毒性が懸念されたことから、近年ではPFASという総称で、各国及び地域で規制が議論されるようになってきた。
本コラムでは、PFASとはどのような化合物であるか、その特性と用途に加えて、欧米を中心とした最近の規制の状況を紹介する。
2.PFASについて
- PFASの種類
PFASは、Per and
Polyfluoroalkylsubstancesの略であり、構造の中に2つ以上のフッ素原子を有する有機フッ素化合物の総称であるが、定義される構造は国や機関によって異なる。現在、経済協力開発機構(OECD)で提案されている定義
*1)は炭素数が一つ以上、米国環境保護庁(EPA)の規則 *2) に規定された定義では炭素数が二つ以上の化合物が対象となっている(いずれも炭素原子に結合する元素によって定義に非該当となる物質がある)。
このように定義上、PFASは空調機用冷媒として使用される低分子量のガス状物質から、航空機電線の被覆材に使用される高分子量のポリマーまで含まれ、その数は10,000を超えるとされており
*3)、様々な物理化学性状を有する多様な化学物質群である。
全てのPFASに共通する要素は、炭素原子とフッ素原子が結合した構造を有することだけであり、全てのPFASが水や油を弾いたり、水に溶けて水源を汚染したりする訳では無い。PFASの中には、難分解性、生物蓄積性、毒性が懸念され、POPs条約で規制対象となっているPFOS(パーフルオロスルホン酸:C8F17SO3H)やPFOA(パーフルオロカルボン酸:C7F15COOH)のような物質があるが、これらが全てのPFASを代表するものとして報道されることがあるため、今後は規制されているPFOSやPFOAなどを「特定PFAS」と表現し、フッ素ポリマーやフッ素ガスなど、他のPFASと区別していくことが必要と考える。
- PFASの用途
全てのPFASに共通する要素となっている炭素原子とフッ素原子の結合構造は、例えば一般的な炭素原子と水素原子の結合と比べてとても強固であり、その結果として、耐熱性、耐薬品性、難燃性、耐候性、高摺動性、耐電圧性など、様々な機能を発現する。
PFASが多くの分野で採用される理由は、これら様々な機能を一つの素材で発現できるためである。例えば、難燃性の材料としてはPVC(ポリ塩化ビニル)などが挙げられるが、難燃性に加え耐候性が求められる場合は、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)やETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体)などのフッ素ポリマーの独壇場となる。
PFASの様々な産業分野での採用事例について、日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)のサイトをご覧頂きたい
*4)。PFASは現代の主要産業のみならず、これからの社会資本の構築に不可欠であり、例えばデジタルトランスフォーメーション(DX)の分野では半導体の各製造プロセス、また6Gなどの高速通信装置の電子基板などに使用されている。またグリーントランスフォーメーション(GX)の分野では、スマートフォンやEVに使用されるリチウムイオン電池の電極、また電気分解による水素の製造装置や燃料電池の基幹部材である電解質膜に必須の素材である。
3.国際条約
- POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)
POPs条約では、 難分解性(環境での残留性)、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念される残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic
Pollutants)について、製造及び使用の廃絶・制限、非意図的生成物質の排出削減等を規定している。その対象となる物質は残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)において議論されたのち、締約国会議(COP)において決定される。
2023年6月時点で、既にPFASとしては、PFOS、PFOA及びPFHxS(パーフルオロヘキサンスルホン酸:C6F13SO3H)の製造及び使用の廃絶もしくは制限が決定されている。このうち、PFOS及びPFOAについては、日本においても国内担保法である化審法において、第一種特定化学物質として規制されている。
これら3物質以外では、炭素数が9から21までの長鎖パーフルオロカルボン酸(C9-C21 Long-chain perfluorocarboxylic
acids;PFCAs)のPOPRCでの議論が2022年より始まっている。パーフルオロカルボン酸については、鎖長が長くなるにつれて、生物蓄積性が上昇することが知られているが
*5)、炭素数9から21の間の一部化合物においては、議論に必要な情報が無いことが指摘されている。
4.欧州REACH規則(化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則)
- REACHにおける認可と制限
欧州において、化学物質はREACH規則の認可プロセスと制限プロセスで規制される。REACH規則の詳細については、環境省のサイトを参照頂きたい
*6)。認可プロセスにおける対象物質の候補であるSVHC(高懸念物質:substances of very high concern)リストには、2023年6月時点で13種類のPFASが登録されている。
一方で、制限リストに、同6月時点で登録されている主要なPFASは、C9-C14の長鎖パーフルオロカルボン酸である(PFOS、PFOA及びPFHxSはPOPs条約のEUでの担保法であるEU-POPs規則のリストに掲載されている。)。また同6月時点で、制限プロセスでは、PFHxA(パーフルオロヘキサン酸:C5F11COOH)とその塩及び関連物質、消火剤用途のPFAS
及び 全てのPFAS化合物(Universal PFAS) の3件の審議が進んでいる。このうち、PFHxA制限案およびPFAS制限案について以下に現在の状況を紹介する。
なお、REACHにおける制限の審議プロセスの流れについては、FCJの第二回及び第三回のウェビナー資料をご参照頂きたい*7)8)。
- PFHxA制限案
欧州におけるPFHxAに関する規制は、ドイツがSVHCの提案を取り下げ、2018年12月に制限の意図の登録(Registry of
Intention)をECHA(欧州化学物質庁)に提出し、2020年初には提出された制限案が公開された。ドイツはPFHxAの制限理由として、難分解性に加えて、水相への移動性や界面活性能が高いことから、地下水や表層水への汚染懸念を挙げている。
この制限案に対しては、ECHAの専門委員会であるRAC(リスク評価委員会)とSEAC(社会経済性分析委員会)での審議と併行して、パブリックコンサルテーションが二度実施され、2021年12月にはSEACによる最終意見が欧州委員会に提出された
*9)。その後、欧州委員会にて通常よりも時間を掛けて作成された法案が2023年6月に公開されたが *10)、その内容はこれまでに提案と大きく変わるものであった。
ドイツの制限案からSEACの最終意見まで、制限案はPFHxAとその塩及び関連物質を原則全面禁止とし、特定の用途に規制免除を与えるという骨子であったが、欧州委員会法案はPFHxAとその塩及び関連物質を一般消費用の繊維/皮革/紙製品など一部の用途で禁止するという内容となった。欧州委員会はこの法案の内容に至った理由として、排出量、リスク低減、社会経済的影響等のデータが不確実であるため、特定されたリスクへの対処には、広範な制限ではなく、対象を絞った制限が最も適切であると説明している
*10)。
この欧州委員会法案は、欧州委員会内のREACH委員会で2023年末まで審議された後に採択され、2024年上半期には、欧州議会及びEU理事会の精査を経て、法律が発効される見通しである。
- PFAS制限案
欧州で有機フッ素化合物をPFASとして一括で規制する考えが示され、2020年5月に5ヶ国(オランダ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー)から、制限案作成のための情報提供(Call for
Evidence)が呼び掛けられた。続いて2020年10月には、欧州委員会が発表した持続可能な化学物質戦略(Chemicals Strategy for
Sustainability)の中で、PFASの制限について言及している。その後、5ヶ国により2021年7月に制限の意図の登録が提出された後、2023年3月に制限案が正式に公開され
*11)、この制限案に対するパブリックコンサルテーションが2023年9月25日まで実施されている。
欧州5ヶ国がPFAS制限案を提案した理由として、PFASが非常に難分解であること、加えてその多くが生物蓄積性や移動性などの懸念を有することを挙げている。また提案の内容は、PFASの使用・製造・販売を主には医薬及び農薬を除き全面禁止とし、特定の産業分野の用途にのみ、一定期間(移行期間を含め6.5年もしくは13.5年)の制限の執行猶予を与えるというものである。制限案の詳細については、FCJの第三回のウェビナー資料をご参照頂きたい
*8)。また、2023年9月30日までは第三回ウェビナーの映像をウェブで公開している *12)。
今回の制限案に対して、FCJでは見解書
*13)を公開し、パブリックコンサルテーションでも同意見を提出している。意見書の中では、制限案の主要な理由である難分解性であることが、REACH規則68条に記載された化学物質の制限理由である“社会全体で対処する必要がある人間の健康または環境に対する許容できないリスク”に整合するかについて言及している。また、制限理由の一つとしている生物蓄積性や移動性については、全てのPFASに該当するものでないため、今回提案されているような全てのPFASを一括に規制するのではなく、例えばOECDで提案されているように
*14)、フッ素ポリマーやフッ素ガスなど物理化学等の性状に併せてサブカテゴリー化した方がより適切にリスクを評価可能ではないかと提案している。
この制限案について、ECHAは、パブリックコンサルテーションのINFO NOTE
*3)の中で、制限案には取り上げられていない産業分野や用途があること、またPFASに対する代替案等に対する情報が一般的であること(一例として、制限案の附属書eにおいて、PFASを使用するリチウムイオン電池の代替として、鉛蓄電池が提案されている
*15))から、関係者に対し、コンサルテーションでの意見出しを呼び掛けている。現在、制限案で取り上げられていない産業分野や用途において、もしも情報が提供されなければ、そのまま制限が発効してしまう可能性があるため、関係者の皆様には是非コンサルテーションへ応答頂きたい。コンサルテーションの応答については、FCJがパブコメ応答ガイダンス
*16)を公開しているので、こちらを是非ご参照頂きたい。2023年6月時点で公開されているコンサルテーションの総数は約600件であり、その内5割弱が日本からの提案であり、その中には経済産業省からの意見
*17)も含まれている。
最後に繰り返しとなるが、PFASとは有機フッ素化合物の総称であり、その中にはフッ素ポリマーやフッ素ガスなど様々な性状の化合物が含まれている。中には、難分解性、生物蓄積性、毒性等が確認され、POPs条約で規制されているPFOSやPFOAのような“特定PFAS“があり、これら及び同様の性状を有する化合物の使用は適切に管理もしくは規制されるべきと考える。一方で、難分解性のみを取り上げると、素材として耐久性が高いことを意味し、これは望ましい特徴である。然しながら、製品として廃棄された後には、環境中に排出され、その残留が懸念されるため、使用済みの製品の回収、再生を進めることで、循環型のサプライチェーンを構築していく必要があると考える。
次回は、米国や英国など他の海外地域におけるPFASの規制動向、および最近得られたPFASに対する新たな知見について紹介する予定である。
※1 Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances:
Recommendations and Practical Guidance:
https://one.oecd.org/document/ENV/CBC/MONO(2021)25/En/pdf
※2 Per- and Poly-Fluoroalkyl Chemical Substances Designated as Inactive on the TSCA Inventory;
Significant New Use Rule:
https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/26/2023-01156/per--and-poly-fluoroalkyl-chemical-substances-designated-as-inactive-on-the-tsca-inventory
※3 Consultation on a proposed restriction on the manufacture, placing on the market and use of
per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS):
https://echa.europa.eu/documents/10162/cad38c27-ede8-2268-00c6-939ea066743c
※4 FCJ第一回ウェビナー資料:
https://cfcpj.jp/pdf/Lecture_materials_20220420.pdf
※5 Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 4, 995–1003:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es070895g
※6 REACH関連情報:
https://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html
※7 FCJ第二回ウェビナー資料:
https://cfcpj.jp/pdf/Lecture_materials_20221130.pdf
※8 FCJ第三回ウェビナー資料:
https://cfcpj.jp/pdf/No3_webiner_Document-20230407.pdf
※9 Committee for Risk Assessment (RAC) Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) Opinion on
an Annex XV dossier proposing restrictions on undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related
substances:
https://echa.europa.eu/documents/10162/97eb5263-90be-ede5-0dd9-7d8c50865c7e
※10 COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006
of the European Parliament and of the Council as regards undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and
PFHxA-related substances:
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/090483/1/consult?lang=en
※11 ANNEX XV RESTRICTION REPORT PROPOSAL FOR A RESTRICTION: SUBSTANCE NAME(S): Per- and
polyfluoroalkyl substances (PFASs):
https://echa.europa.eu/documents/10162/1c480180-ece9-1bdd-1eb8-0f3f8e7c0c49
※12 FCJ第三回ウェビナー動画(2023/9/30まで公開):
https://youtu.be/pSPs20elu5Y
※13 欧州PFAS制限案に対するFCJ見解書:
https://cfcpj.jp/pdf/japan_pfas_comments_submission.pdf
※14 Fact Cards of Major Groups of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs):
https://one.oecd.org/document/env/cbc/mono(2022)1/en/pdf
※15 Annex to the ANNEX XV RESTRICTION REPORT(本文416頁):
https://echa.europa.eu/documents/10162/8de11d7c-c56f-e204-5072-e89f11071219
※16 欧州PFAS制限案に関するパブコメガイダンス資料:
https://cfcpj.jp/pdf/fcj_pbcm_guidance.pdf
※17 経済産業省の意見については、リンクのWORDファイルをダウンロードし4344番を参照ください:
https://echa.europa.eu/documents/10162/9ba5761c-5046-3ed8-2c30-ea9473651de2
第2回 PFAS対策の国際状況と今後の動向 (2)
1.はじめに
前回のコラム(前編)では、PFAS(Per and Polyfluoroalkyl
substancesの略)の種類と用途、国際条約および欧州におけるPFASの規制動向について紹介した。その後、欧州のPFAS制限案については、1回目のパブリックコンサルテーションが締め切られ、世界の50を超える国と地域から、5600件を超えるコメントが寄せられた*1)。この件数は、過去に実施されたマイクロプラスチックス制限案に対するコメント数477件と比べても桁違いに多く、ステークホルダーからの関心が高いことが窺える。この欧州PFAS制限案に対するパブリックコンサルテーションの解説については、日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)がまとめているので、興味をお持ちの方はご参照いただきたい*2)。
今回のコラム(後編)では、米国におけるPFAS規制動向について、主要な連邦および各州の状況に加え、英国およびカナダの規制状況、更には日本で進められているPFASについての科学的知見等の充実を図る取り組みを紹介する。
2.米国におけるPFAS規制について
- PFOS、PFOAの規制
米国においてはPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸:C8F17SO3H)やPFOA(パーフルオロオクタン酸:C7F15COOH)について、1990年代後半から2000年代にかけて規制の議論がなされた。PFOSについては、1999年に3M社から生物学的影響に関するデータをまとめたレポートが作成されている*3)。この中で、PFOSが人体の中で長い滞留時間を有することが報告されている。翌2000年に3M社は、EPAと協議の結果、PFOS関連製品の生産中止を発表し*4)、2002年に米国環境保護庁(EPA)はPFOSに対して米国有害物質規制法(TSCA)の重要新規利用規則(SNUR)を適用し、新規利用について事前の届出を義務付けて、使用および製造の制限を開始した*5)。
PFOAについては、2006年にEPAが2010/2015PFOA Stewardship
Programを発表した*6)。これは、PFOAを製造、使用する製造事業者が2010年までにPFOAの排出ならびに製品含有を基準年(2000年)に対して95%以上削減し、2015年までにその使用を全廃することに自主的に取り組む活動であり、プログラムに参加した日米欧の8社は全て目標を達成している。
その後、EPAは2020年に炭素の数が7から20までの長鎖パーフルオロアルキルカルボン酸類(PFOAを含む。)についてのSNURを発行し、制限を実施している*7)。
- EPAによるPFAS Strategic Roadmap
2010年代に入ると、消火泡剤などに使用されるPFASによる飲料水の汚染や健康調査が米国有害物質疾病登録局(ATDSR)等で進められた*8)。2019年にEPAがPFASに関するアクションプランを発表し*9)、2021年には更に戦略的な取り組みとして、PFAS Strategic Roadmapを発表した*10)。この活動は、2021年から2024年にかけてのEPAの全庁的な取り組みとして、活動方針の一つに科学的根拠に基づく意思決定を挙げており、この点は欧州における予防原則に基づくPFASの一括制限提案とは対照的である。現在、EPAが目標として設定した“研究”、“規制”、“環境修復”の三分野において、主要な約30のプログラムが進行中である。その中で代表的な取り組みをいくつか紹介する。
- PFAS試験戦略:研究
PFASは有機フッ素化合物の総称でありその化合物数は多いため、それらの人体および環境に対する評価を個々に行うことは膨大な時間を要することとなる。そこでプログラムにおいて、EPAはPFASの構造や物理化学的性質の類似性等に基づきPFASを分類し、代表的な物質に対して試験を行うことをその製造業者に要請するものである*11)。第一段階としては24の化合物が公表され、試験が進んでいる。
- 報告規則:研究
PFAS Strategic Roadmap では、EPAはPFASのライフサイクルを通した検討を進めており、本プログラムにおいて、今後のPFASの調査、監視、規制の取り組みのために、米国内で製造されたPFASの発生源と量をより正確に把握することを目的としている。具体的には、TSCA 第8章(a)(7)に従って、米国におけるPFASの製造者、輸入者に対して、PFASの物質情報、使用分野、数量、不純物および廃棄方法などの情報の報告を義務付けている*12)。報告対象期間は2011年1月1日から2022年12月31日であり、規則発効日から1年後の2024年11月12日から2025年5月8日(6か月間)の期間にEPAに報告する必要がある(成形品輸入のみを行う小規模事業者は2025年11月10日まで報告期間が延長)。一度限りの報告義務ではあるが、PFASを用いた成形品も対象となっており、報告対象者が、知っているまたは合理的に把握できる範囲で(known to or reasonably ascertainable by)、情報を報告する必要がある。2023年11月に最終規則が発行されたが、2021年に公開された規則案から、対象となるPFASの定義が変更されているので注意が必要である。EPAでは当該報告手順のガイドラインを作成しており、詳細はこちらを参照頂きたい*13)。
- 飲料水に対する取り組み:規制
EPAでは飲料水中に含まれるPFASの健康勧告値として、2006年に初めてPFOA(500ng/L)、また2009年にPFOS(200ng/L)を設定した。その後2016年には、PFOSとPFOAを合算して70ng/Lという基準に改訂されている。このときのPFOAの有害影響を判断するエンドポイントとしては、マウスの発生毒性を挙げており、一日当たりの許容摂取量(参照用量)として20ng/kg日が提案されていた*14)。
PFAS Strategic
Roadmapにおいては、国家一次飲料水規制(NPDWR)に基づく、PFOAおよびPFOSの飲料水中の最大汚染基準を設定することを目標としている。最大汚染基準の設定に向けて、2022年にPFOAおよびPFOSの健康勧告値の改訂が行われたが、両物質とも2016年の勧告値を大きく下回る提案となり、PFOAではエンドポイントして免疫毒性(破傷風)が挙げられ、参照用量は0.0015ng/kg日が提案され、飲料水として0.004ng/Lの健康勧告値が発表された。PFOSについても、免疫毒性(ジフテリア)をエンドポイントとし、参照用量は0.0079ng/kg日、飲料水として0.02ng/Lの健康勧告値が提案された*15)。これらエンドポイントとして取り上げられたのは交絡因子の影響が懸念されるフェロー諸島での調査結果であったため、その適正を疑問視する意見も出されている*16)。EPAは2022年の勧告値をもとに、最大汚染レベルの目標としてはゼロとしつつ、分析能力などを考慮した規制可能なレベルとして、PFOAおよびPFOSともに4ng/Lの規制値を提案した。
併せて、他の4種類のPFAS化合物:PFNA(パーフルオロノナン酸:C8F17COOH)、PFHxS(パーフルオロヘキサンスルホン酸:C6F13SO3H)、PFBS(パーフルオロブタンスルホン酸:C4F9SO3H)、HFPO-DA(ヘキサフルオロプロピレンオキシド二量体カルボン酸:C3F7OC(CF3)FCOOH)についても、合算したハザードインデックスによる規制を提案している*17)。2024年1月時点で、これらに関する最終規則は発行されていない。
また、上記6物質を含むPFAS 29物質に対して、第5次未規制汚染物質モニタリング規則(UCMR 5)にて、全米でのモニタリングが2023年から2025年にかけて実施されている*18)。
- PFASの化学物質登録および審査:規制
米国において、化学物質はTSCAで規制されており、既存化学物質はTSCA Inventoryに収載されている。PFAS Strategic
Roadmapの中で、EPAはPFASの登録や審査に対して、管理を強化する方針を打ち出している。
化学物質を新たに登録する際に、通常は90日間の審査を要する製造前届出(PMN:Pre-Manufacture Notice)の手続きが必要となるが、少量の場合(LVE:Low Volume
Exemption)や環境放出または人への暴露が低い物質の場合(LoREX:Low Environmental Releases and Human
Exposure)には、より短期間(30日間)での審査が適用される届出が認められている。これに対して、EPAはまず2021年に600を超えるPFASのLVE届出に対して、届出者に自主的に撤回を求めるPFAS Low
Volume Exemption Stewardship Program
を発表した*19)。更に、2023年には新規に登録されるPFASに対して、LVEやLoREXによる届出の対象外となることを発表した*20)。この理由として、PFASの人体や環境への影響を適切に審査するためには、両免除の届出に適用される30日間では不十分とあるとしている。
2024年にはTSCA Inventoryに収載されているが INACTIVE(製造、輸入、加工の報告実績が無い)となっているPFAS
329物質について、SNURを適用する最終規則を発行した*21)。
EPAは、PFASの新規登録のためのPMN手続きや、既存のSNUR対象のPFASについて重要新規利用届出(SNUN:Significant New Use
Notice)手続きを行う場合に、効果的かつ効率的に審査し、適切な決定を行うことを確実にするための枠組み(Frame
Work)を公表した*22)。これによると、次のようなステップで対象となるPFASが審査される:1)審査対象物質の構造のPFAS定義への該非、2)物質のハザード情報の評価ならびにP(Persistent:難分解性)B(Bioaccumulation:生物蓄積性)、T(Toxic:人や環境に対する有害性)特性の特定、3)PFAS(その代謝物や分解物を含む)がPBT判定された場合に環境放出と労働者への暴露の両方を評価。詳細については、EPAのウェビナー資料を参照頂きたい*23)。PBT特性の目安は、1999年のPBT方針声明(64
FR 60194)および2018年のPoint to
Consider方針文書における新規化学物質プログラムにおけるPBTsの特定基準として定められている。このフレームワークについても、欧州の予防原則に基づく一括規制とは異なり、米国は科学的根拠に基づくアプロ―チを志向していると考えられる。
- スーパーファンド法適用:環境修復
米国では、有害物質の浄化のために、「包括的環境対策・補償・賠償責任法」(CERCLA:Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act ― 別称
スーパーファンド法)が制定された。同法は、有害廃棄物が投棄され、環境汚染が生じた場合、又は有害物質が環境に放出された場合に、その浄化のための適切な措置を講ずる権限を大統領に与え、そのために要する資金を賄うための基金を設立するとともに、一定の範囲の当事者に対し対策実施又は費用負担の責任を負わせることとするものである*24)。
PFAS Strategy
Roadmapでは、PFOAおよびPFOSをスーパーファンド法の有害物質に指定することを進めており、2022年に最終規則案が発表されている(2024年1月時点で最終規則は発行されていない*25))。
- 他の米国行政府の動向
米国の国防予算を決定する国防権限法(NDAA:National Defense Authorization
Act)にて、2018年度よりPFAS問題への取り組みが毎年規定されている。その内容は、前述のPFASの飲料水基準や報告規則等に加えて、PFASを使用した消火泡剤の処理や国防総省における家具やワックスなどPFAS不使用品の調達などの規制に関する項目が殆どであったが、2023年に入ってPFASの重要用途を調査する項目が盛り込まれた。これは、半導体やバッテリーなど米国の国家安全保障にとって重要なPFASおよびその使用方法に関する内容であり、2023年8月に報告書が提出されている*26)。
また、2023年度のエネルギー・水資源開発歳出法にて、フッ素ポリマーのライフサイクル評価(LCA)に関する調査報告を規定している。これは、フッ素ポリマーと競合技術の比較を含み、自動車、半導体、建築インフラなどが対象分野となっている*27)。
- 米国州政府の規制動向
米国州政府によるPFAS規制としては、2000年代より飲料水の汚染対策が進められた。その後、東海岸、西海岸を中心に、消火泡剤や食品包装容器などの用途規制に拡がっていった。Enhesa(Chemical
Watch)の調査によると、2023年には133の法案が提出され、そのうち10法案が成立している*28)。
最近では、欧州のように包括的なPFAS規制が議論される動きがあり、2021年にメイン州で法制化(詳細を後述)されたのち、ミネソタ州等でも成立している。
一方で、立法化後の規制の実効状況が課題となる点があり、カリフォルニア州では規制当局による監視体制が不十分であることを理由に、州知事が拒否権を発動した法案も出ている*29)。
- メイン州
メイン州でPFASを包括的に規制する法(H.P. 1113 - L.D.
1503)*30)が2021年に成立した。本法において、PFASは少なくとも一つの完全にフッ素化された炭素を有する有機フッ素化合物と規定されており、欧州PFAS制限案より対象物質の定義が広くなっている。また、規制事項として2023年1月1日以降に意図的にPFASを添加したカーペットやラグ等のメイン州内での販売、流通等の禁止に加えて、2030年1月1日以降にPFASが現在避けられない用途(CUU:Currently
unavoidable
use)であると当局が判断した場合を除き意図的にPFASを添加した製品のメイン州内での販売、流通等を禁止としている。また、2023年1月1日以降に意図的にPFASを添加した製品をメイン州に販売する製造者は州当局に必要事項の情報を届け出る報告義務を課している。
このうち、報告義務については、PFASを用いた加工製品の製造関係者(延期要請実施者)に、メイン州当局が6カ月間延期を認めていた。その後、2023年に報告義務の施行を2025年1月1日に変更する改正案が成立した。
PFASの現在避けられない用途は、「健康、安全、または社会の機能に不可欠であると同省が規則により判断し、代替手段が合理的に利用できないPFASの使用」と規定されているが、その適用に向けてのパブリックコメントを2024年3月1日まで募集している*31)。
- 英国、カナダにおけるPFAS規制動向
欧州、米国以外のPFAS規制として、英国およびカナダの動向を紹介する。詳細は後述するが、英国ではPFASのリスクに対処するために用途や使用の一部にUK REACHによる制限および認可を適用することを提案しており、一方カナダでは欧州同様にPFASを物質のクラスとして規制することを提案している。
- 英国におけるPFAS規制動向
2023年に英国健康安全局(HSE:Health and Safety Executive)が、UK
REACHにおけるPFASのリスクに対する管理方法を検討するために、規制管理オプション分析(RMOA:Regulatory Management Option Analysis)を発表した*32)。
この中で、HSEは消火泡剤や洗浄剤等の特定のPFASの使用に関する一つ以上の制限の導入やフルオロポリマーの製造・加工における加工助剤に使用されるPFASに対するUK
REACHの認可の適用などを提案している。また、危険性が低い、あるいは安全に使用できるという包括的で信頼できる証拠を提供できるPFASについては、個々の物質またはグループ(例えばフルオロポリマー等)での適用除外の検討について言及している。UK
REACHのRolling Action Planでは2024年から2025年にかけて詳細を評価する計画である*33)。
- カナダにおけるPFAS規制動向
2023年にカナダ環境・気候変動省および保健省が、PFAS調査報告書草案を発表した*34)。この中で、個々のPFASまたはPFASの小グループのリスク評価と管理を継続することは非現実的であり、クラスとしてのPFASがカナダ環境保護法(CEPA:Canada Environmental Protection Act)64条の有害物質に該当すると報告している。報告書草案に対するパブリックコンサルテーションは終了しており、今後当局は有害物質リストへのPFAS掲載の要否を決定し、掲載する場合は規制案が2024年半ばに公開される見通しである。
3.PFASに対する科学的アプローチ
PFASを一つのグループとして一括で規制する議論の背景には、PFASについての科学的な理解が不足していることが挙げられる。ここでは、PFASの特性解明や分析破壊の研究開発の取り組みについて紹介する。
- SDA(Stratified Dipole-Arrays:階層双極子アレー)理論
PFASの耐熱性や耐紫外線性などの耐久性は、炭素(C)とフッ素(F)の結合に起因するところが大きく、撥水撥油性能についてもこのC-F結合に起因する低い分子間力に基づくと考えられていた。しかしながら、京都大学化学研究所の長谷川健教授はこのPFASの特異な性質はSDA理論によって説明されるPFAS分子の集合構造に基づくとしている*35)。直鎖のアルキル化合物の水素が全てフッ素に置換されると、フッ素は水素よりも大きいため、炭化水素では平面的なジグザク構造であったのに対し、ねじれた構造を取るようになる。フッ素化された炭素の数が7以上になると、双極子同士が配向することにより二次元集合構造をとることになる。このフッ素化された炭素が二次元的な集合構造を取ることにより、特異的な撥水撥油性やフッ素ポリマーなどの高融点を発現すると考えられる。今後、分子毒性学へ展開することでPFASの有害性発現の解明が期待される。
- 産業総合研究所によるPFAS対策技術コンソーシアム
国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)環境創生研究部門 では、PFASの分析/処理技術や関連評価技術に関する情報交換及び利用促進と、産学官が連携して推進する体制を構築するとともに研究成果を広く社会に普及することを目的に、2021年にPFAS対策技術コンソーシアムを設立した(会長:山下信義上席主任研究員)*36)。2023年10月には、東京で国際講演会を開催し、PFASの分析や環境修復などの分野で世界各国から30を超える講演が行われた*37)。産総研では、最大39種類のPFASの一斉分析を可能とするISO21675を国際標準化しており、今後更に日本発の技術が国際展開されることが期待される。
4.まとめ
欧州委員会のブルトン委員はPFAS規制に関する議会での質問に対し、「PFASによる汚染は、人間の健康と環境にとって深刻な問題であると同時に、PFASは医療やエネルギー分野など重要な用途で必要とされている」と回答し、また「規制が便益に比べて社会的コストが高いPFASの重要な用途については、想定される規制からの適用除外を検討する」ことに言及しており*38)、PFASの必須性に対する理解が拡がっている。
日本においては、PFOSやPFOAが公共水域より検出されて問題となっている。これら“特定PFAS”は難分解性、高蓄積性、長距離移動性及び人や生物への有害性を持つものとしてPOPs条約ならびに日本の化審法において、原則として製造および使用が禁止されている。しかしながら“特定PFAS”の性質が全てのPFASに共通するものではなく、PFASの中には、性質上安全性の極めて高いものや、法令で管理され安全性が確認されたものもあり、このような合物について科学的な根拠なく規制がかけられることのないようにするべきと考える。そのために、個々の物質もしくは代表となる物質群毎に異なるリスクを定量的に評価し、規制の要否、もしくは排出・回収・廃棄管理の仕方などの議論を行うことで、全てのPFASに対する不安を払拭していくべきと考える。
※1 ECHA receives more than 5 600 comments on PFAS restriction proposal:
https://echa.europa.eu/-/echa-receives-5-600-comments-on-pfas-restriction-proposal
※2 FCJ HP 第4回ウェビナー詳細情報:
https://cfcpj.jp/webiner-detail_0004.html
※3 Perfluorooctane Sulfonate: Current Summary of Human Sera, Health and Toxicology Data:
https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPPT-2002-0043-0007
※4 EPA and 3M ANNOUNCE PHASE OUT OF PFOS:
https://www.epa.gov/archive/epapages/newsroom_archive/newsreleases/33aa946e6cb11f35852568e1005246b4.html
※5 Perfluoroalkyl Sulfonates; Significant New Use Rule [SNUR] Posted by the Environmental Protection Agency on Dec 9, 2002:
https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPPT-2002-0043-0001
※6 Fact Sheet: 2010/2015 PFOA Stewardship Program:
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/fact-sheet-20102015-pfoa-stewardship-program
※7 Significant New Use Rule: Long-Chain Perfluoroalkyl Carboxylate and Perfluoroalkyl Sulfonate Chemical Substances. Posted by the Environmental Protection Agency on Jul 27, 2020:
https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPPT-2013-0225-0232
※8 ATSDR HP Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) and Your Health:
https://www.atsdr.cdc.gov/pfas/resources/index.html
※9 EPA’s Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Action Plan:
https://www.epa.gov/sites/default/files/2019-02/documents/pfas_action_plan_021319_508compliant_1.pdf
※10 PFAS Strategic Roadmap: EPA's Commitments to Action 2021-2024:
https://www.epa.gov/pfas/pfas-strategic-roadmap-epas-commitments-action-2021-2024
※11 EPA HP: National PFAS Testing Strategy :
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/national-pfas-testing-strategy
※12 TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances:
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/tsca-section-8a7-reporting-and-recordkeeping
※13 Instructions for Reporting PFAS Under TSCA Section 8(a)(7):
https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-11/tsca-8a7-reporting-instructions-10-11-23.pdf
※14 Guideline levels for PFOA and PFOS in drinking water: the role of scientific uncertainty, risk assessment decisions, and social factors : Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (2019) 29:157–171:
https://urldefense.com/v3/__https://www.nature.com/articles/s41370-018-0099-9__;!!OzAIPA!HyeptNXDfQMsi1ZwzEtCg3NT4wh-AR3LZErsShd8sm1qKFd1v0BexlDklxtcZkfBl3zGrb3-yewAq8TWBL2A6YdgISGSjQ$
※15 Drinking Water Health Advisories for PFOA and PFOS:
https://www.epa.gov/sdwa/drinking-water-health-advisories-pfoa-and-pfos
※16 U.S. Environmental Protection Agency Science Advisory Board Summary Minutes for the Public Meeting held on July 18, 2022 and July 20,2022 :
https://sab.epa.gov/ords/sab/r/sab_apex/sab/0?mmin_id=975&request=APPLICATION_PROCESS%3DMINUTE_FILE&session=13900901990508
※17 Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Proposed PFAS National Primary Drinking Water Regulation:
https://www.epa.gov/sdwa/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas
※18 Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule:
https://www.epa.gov/dwucmr/fifth-unregulated-contaminant-monitoring-rule
※19 PFAS Low Volume Exemption Stewardship Program:
https://www.epa.gov/reviewing-new-chemicals-under-toxic-substances-control-act-tsca/pfas-low-volume-exemption
※20 Biden-Harris Administration Proposes Reforms to New Chemical Review Process to Protect Public Health, Promote Efficiency and Consistency:
https://www.epa.gov/newsreleases/biden-harris-administration-proposes-reforms-new-chemical-review-process-protect
※21 Federal Register/Vol. 89, No. 8/Thursday, January 11, 2024/Rules and Regulations:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-11/pdf/2024-00412.pdf
※22 Framework for Addressing New PFAS and New Uses of PFAS:
https://www.epa.gov/reviewing-new-chemicals-under-toxic-substances-control-act-tsca/framework-addressing-new-pfas-and
※23 Framework for TSCA New Chemicals Review of PFAS Premanufacture Notices (PMNs) and Significant New Use Notices (SNUNs):
https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-09/13313_PFAS%20Framework%20Webinar_9-12-2023_508.pdf
※24 平成4年版環境白書:
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h04/8292.html
※25 Proposed Designation of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctanesulfonic Acid (PFOS) as CERCLA Hazardous Substances:
https://www.epa.gov/superfund/proposed-designation-perfluorooctanoic-acid-pfoa-and-perfluorooctanesulfonic-acid-pfos
※26 Report on Critical Per- and Polyfluoroalkyl Substance Uses:
https://www.acq.osd.mil/eie/eer/ecc/pfas/docs/reports/Report-on-Critical-PFAS-Substance-Uses.pdf
※27 ENERGY AND WATER DEVELOPMENT AND RELATED AGENCIES APPROPRIATIONS BILL, 2023117th Congress (2021-2022):
https://www.congress.gov/congressional-report/117th-congress/house-report/394/1
※28 How are PFAS regulations developing across the globe?:
https://product.enhesa.com/944724/how-are-pfas-regulations-developing-across-the-globe
※29 AB-727 Product safety: cleaning products and floor sealers or floor finishes: perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances.:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240AB727
※30 PFAS in Products:
https://www.maine.gov/dep/spills/topics/pfas/PFAS-products/
※31 PFAS in Products: Currently Unavoidable Uses:
https://www.maine.gov/dep/spills/topics/pfas/PFAS-products/cuu.html
※32 Analysis of the most appropriate regulatory management options (RMOA) :
https://www.hse.gov.uk/REACH/assets/docs/pfas-rmoa.pdf
※33 Rolling Action Plan (RAP) for UK REACH 2023-2025:
https://www.hse.gov.uk/reach/reports/rap/rap2325.htm
※34 Draft state of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) report:
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/draft-state-per-polyfluoroalkyl-substances-report.html
※35 パーフルオロアルキル化合物のバルク物性の統一的理解: オレオサイエンス 第 16 巻第 3 号(2016) 129:
https://www.jstage.jst.go.jp/article/oleoscience/16/3/16_129/_pdf/-char/ja
※36 PFAS対策技術コンソーシアム:
https://unit.aist.go.jp/mcml/rg-org/pfasconsortium.html
※37 FAS対策技術コンソーシアム国際講演会 (10月17, 18, 19日) :
https://unit.aist.go.jp/mcml/rg-org/pdfjs/web/viewer.html?file=A26.CAR_PFAS_summaryHP.pdf
※38 Answer given by Mr Breton on behalf of the European Commission:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-002394-ASW_EN.html