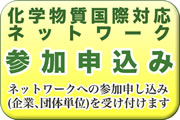化審法の改正を考える
- このコラムは、化審法(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を指す。以下同様。)見直し合同委員会のメンバーでもあった北村卓氏に、化学産業界の第一線で過ごされてきた豊富な経験に基づき執筆をいただいたものです。
- このコラムに記載されている内容に関し、法的な対応等を保障するものではありませんのでご了承ください。
- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
→ご意見・ご感想電子メール送付先:
化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@env.go.jp)
目次
- 第1回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
- 第2回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
- 第3回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
- 第4回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
- 第5回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
- 第6回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
- 第7回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
- 第8回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
第1回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
はじめに
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」が改正されました。規制内容に大きな変更のない省庁再編に伴う改正を除けば1973年の制定以来4回目です。労働安全衛生法・消防法・毒劇法・食品衛生法などは化学物質の特定の用途や取り扱い方法を規制し、大気汚染防止法・水質汚濁防止法・土壌汚染対策法などは環境汚染の防止を目的としますが、化審法は国内に特定の有害性の強い化学物質が存在することを禁止・制限する、いわゆる「蛇口規制」があることで、化学物質の製造・輸入事業者には最も関心の高い法律の一つです。化審法は化学物質規制の基本的な法律のように考えられることもありますが、規制対象は「一般工業化学品として用いられる物質」とされています。一般工業化学品は原材料としてだけでなく、多くの工業製品の製造プロセスを支える副資材としても用いられるので、直接の規制対象ではない消費者用製品なども化審法と無関係というわけではありません。
A. 生産量の少ない新規化学物質の届出と確認
生産量の少ない新規化学物質の届出には、「少量新規化学物質」と「低生産量新規化学物質」の二種類があります。化審法の新規化学物質の登録制度が始まった時には「少量」のみでしたが、2003年の改正で「低生産量」の制度ができました。どちらの制度も、製造・輸入量の国内総量の上限という制約がありましたが、通常の新規化学物質の登録に比べれば手続きが簡便で、事業者には使いやすい制度です。新製品の上市の時点では製造・輸入量も少ないので、正規の登録を行うための2,000~3,000万円にものぼる試験費用をその化学物質の売り上げから回収することは簡単ではありません。また将来の需要の拡大が確実に見込まれるわけでもないので、筆者の経験上、新規化学物質の開発・上市では、まず「少量」で市場の動向を伺い、その後製品として本格的に製造できると判断できれば、「低生産量」あるいはその段階を省略して通常の新規化学物質の登録に移行していました。「少量」は正規の登録に必要な安全性試験を必要とせず、届出により既知見をもとに、強い有害性を持ち人の健康又は生活環境動植物の生息・生育に係る被害が生じるおそれがあるとは考えられない場合には、国の確認を受けて製造・輸入ができます。この制度がなければ、試験費用の問題だけでなく、安全性試験に一年近くの時間を必要とするので、新製品(新規化学物質)の開発が加速化している中では、時間的な制約から製品化を断念せざるを得ないこともあったでしょう。
2003年の改正で導入された「低生産量」の制度は、分解性と蓄積性に関するデータを必要とするものの、人の健康影響と生態影響の試験結果を必要としないので審査の特例とされています。これに必要な試験費用は1,000万円未満で、国の確認を受ければ10tまでの生産が可能です。
「少量」及び「低生産量」の新規化学物質の確認制度は、国全体で製造・輸入総量の枠があり、複数の事業者が同一の物質を届け出た場合には数量調整を受けることがあるので、必ずしも次年度に同量あるいはそれ以上の製造・輸入が可能となる保証はありませんでした。一方、規制する側の国でも毎年の製造・輸入量調整の煩雑な作業が強いられていたと思います。公表資料によれば、「少量」ではおよそ36,000件の申し出に対し、数量調整が必要となったものはおよそ4,400件(12%)、「低生産量」では、およそ1,500件に対しておよそ230件(15%)ということです。
「低生産量」の制度ができてからは、二つの制度を合わせた製造・輸入量の調整作業が必要でした。分解性と蓄積性だけとはいえ安全性の試験を実施した「低生産量」と、何の試験も行わず届出をするだけの「少量」の合計の総量が10tとなったときに、「少量」で1tが確保されると「低生産量」で10tの枠を確保できず、9tにとどめられるケースも出てくるので、その時には「低生産量」の届出者は割り切れなさが残ったのではないでしょうか。
製造・輸入量の少ない化学物質は、国の資料によれば、①電気・電子材料、②中間体、③フォトレジスト材料・写真材料・印刷版材料などに用いられ、工業技術のイノベーションと新製品の開発に寄与してきましたが、化学物質の製造・輸入事業者は需要が増加しても国から確認を受けた量を超える製造・輸入はできませんでした。増産のためには通常の新規化学物質の届出を行いますが、それには多額の試験費用だけでなく長期の試験期間が必要で、急な需要の増加には対応できなかったことは既に記したとおりです。
今回の化審法の改正で、製造・輸入量の総枠が環境への排出量となりました。環境への排出量を合理的に見積もることはやさしいことではありませんが、化審法のリスク評価用の排出係数を基礎として人の健康と環境へのリスクをより安全サイドに見積もるための、少量・低生産量新規化学物質に適用する算出方法が平成29(2017)年9月の環境省化学物質審査小委員会(経産省の安全対策部会と厚労省の化学物質調査会との合同会議として開催)に提案されています。それによれば排出係数は、電気・電子材料は0.006, 中間体は0.004, フォトレジスト材料・写真材料・印刷版材料は0.04とされています。少量・低生産量新規化学物質が上市後にどのように使用されるか将来の姿を正確に見通すことは難しいのですが、提案された排出係数を用いれば少量新規化学物質の1tの環境排出量には、電気電子材料で167t、 中間体で250t、 フォトレジスト材料・写真材料・印刷版材料で25tの製造・輸入が可能となります。同一の化学物質を多数の事業者が製造・輸入するとは思われないので、実質的に国による数量調整が必要となるケースは大幅に少なくなり、国の作業は軽減されるでしょう。少量・低生産量新規化学物質の実質的な製造・輸入可能量の増加は、化学物質が多様な用途に用いられていることを見れば、特に技術的なイノベーションが急速に進んでいる分野を中核として、「事業者が事業機会を逃すことなく競争力を高めることを可能とする」ことにつながることが期待できます。
しかし、製造・輸入量が増加する反面、個社の生産量の上限が変わらないことによるビジネス環境の変化を、その物質の製造事業者は考えておくことが必要でしょう。これまでは、ある少量新規化学物質を先行的に開発し他社に先駆けて1t枠を確保し、後発の事業者の参入を抑制しながら継続的な製造・輸入ができましたが、今回の改正で後発他社も少量新規化学物質として製造・輸入への参入が可能となります。海外からのコストダウンした同一物質の流入が可能になることで、とりわけ特殊な製品に強みを持つ日本の中小の専業ファインケミカルメーカーが、製品の立ち上がりの初期段階から国際的な価格競争状態に置かれる可能性があることを危惧します。日本の技術力で開発した新規化学物質が、海外で製造され低価格で輸入されることも可能になります。化学物質の製造技術は、途上国や経済移行国でも飛躍的に高まっているので、現在では日本でしか製造できない化学物質はないといえます。
技術の先進性・先行性を確保するには知的財産権(特許)という制度がありますが、技術の進歩が著しい分野では、知的財産権が成立した時には既に陳腐化し権利確保の意味が失われるという場合もあるので、残念ながら知的財産権だけに頼って先行技術の優位性を保つことが難しい場合があります。
B. 毒性が強い新規化学物質の管理の見直し
新規化学物質の登録では、分解度試験・濃縮度試験、反復投与毒性試験、生殖・発生毒性試験および生態毒性試験の結果とともに、融点・沸点・水溶解度などの物性を報告します。「毒性が強い」の毒性の意味には、健康有害性だけでなく生態毒性も含まれています。
新規化学物質の登録に必要な試験のうち、被験動物を用いる試験は外部機関への委託では高額となるので、登録を予定する事業者は、特別の理由が無ければ、発がん性試験よりも変異原性試験を、一般毒性試験は90日よりも短期間の28日間の反復投与試験を望むことが多く、生殖・発生毒性は反復投与毒性との併合試験で実施されることが多いでしょう。
新規化学物質が監視化学物質の要件の難分解性・高蓄積性であることがわかれば、その時点で多額の試験費用と時間を必要とする長期毒性試験や発がん性試験も求められるため、事業者は第一種特定化学物質になる可能性があると考えて物質の登録を断念し、実質的に新規化学物質が第一種特定化学物質はもちろん監視化学物質になることもありませんでした。
新規化学物質は登録直後の製造・輸入量が多くないので、第二種特定化学物質の「広い地域にわたって環境中に存在する」ことや、優先評価化学物質の「排出量が多くなる」という要件に合致することは考えられないことより、毒性が強くてもこれまでは一般化学物質に位置付けられてきました。しかし、製造・輸入量が増加すれば優先評価化学物質に、さらには第二種特定化学物質になる可能性があります。そこで、今回の改正でそのような新規化学物質に対して、環境を経由した人の健康への影響の可能性を事業者に注意喚起する意味で「特定新規化学物質」であることが通知され、適切な管理を促す仕組みが導入されました。「特定新規化学物質」は名称公示後に「特定一般化学物質」となりますが、ここでは「特定新規化学物質」として記します。
「特定新規化学物質」となる要件はいずれ公表されると思いますが、一般化学物質から優先評価化学物質の候補を抽出する時の考え方が参考となるように思われます。一般化学物質は五段階に区分された有害性(ハザード)とばく露量(全国排出量)からなる優先度マトリックスからリスクが判定され、専門家による詳細なリスク評価で高いリスクのおそれがあると判断されたものが優先評価化学物質となります。製造・輸入量がそれほど多くない新規化学物質は、当初はばく露クラスの位置づけは最も低い5あるいはそれ以下となると思われるので、優先度マトリクスから高いリスクの可能性が指摘されるのは有害性クラスが1の物質と思われます。特定新規化学物質の区分は、「毒性が強い」化学物質と表現されていますが、改正法の起点となった先述の中環審の答申では「非常に強い毒性を持つ化学物質」と表現されているので、有害性クラスは1あるいはその中でも特別に強い有害性を持つ物質ではないでしょうか。
①一般毒性・生殖発生毒性
優先度マトリクスの有害性クラス1にガイドライン値の設定はありませんが、クラス2の有害性評価値(NOAEL等を不確定係数積で除したもの)は0.005mg/kg/dayとされています。特定新規化学物質は「特に強い」有害性ということですので、クラス2よりも格段に高い有害性を示すもの、あるいは有害性評価値が無毒性量(NOEL)ではなく最小毒性量(LOAEL)を用いてクラス2のガイドライン値に合致する場合などが考えられるでしょう。この有害性評価値の不確実性係数積は、種差の10、個体差の10、90日未満の試験期間の6を用いれば少なくとも600となるので、これはNOAEL=3mg/kg/dayに相当します。GHSの区分1と対比すれば、一般毒性(特定標的毒性:反復ばく露)のガイダンス値 ≦10mg/kg/dayよりも強い健康有害性を示す物質となります。
②変異原性・発がん性
発がん性では、優先度マトリクスではIARC の1、産業衛生学会の1、ACGIHの1などの評価があり、人に対する影響が明らかにされている物質が有害性クラス1とされていますが、新規化学物質に公的機関の判定結果があるというケースは考えにくいと思われます。
変異原性では、「人生殖細胞に経世代突然変異を誘発することが知られている」物質やGHS区分1Aの物質が有害性クラス1とされていますが、化審法登録時に用いられることの多いIn vitroの変異原性試験結果からだけでは、GHS区分1にはなりません。
このように考えると、新規化学物質が発がん性・変異原性を理由に「特定新規化学物質」に分類されることはあまりないように思われます。
③生態毒性(水性環境有害性)
生態毒性の有害性評価には、藻類・甲殻類(ミジンコ)・魚類の三種の水生生物を用いた毒性試験の結果を用います。急性あるいは慢性毒性試験として実施されます。有害性クラス1は三種の生物に対して慢性毒性試験結果があればPNEC(予測無影響濃度)≦0.001mg/Lであり、NOEC(無影響濃度)がわかっていればその中の最少の値の1/10がPNECとなります。一部に急性毒性試験で求められた毒性値が使用する場合は、急性・慢性毒性比(ACR)など除した値と慢性毒性値にも安全側にたった判断を加味してPNECが算出されます。GHSで区分1となるのは慢性NOECが≦0.01mg/L(水中急速分解性あり)または≦0.01mg/L (水中急速分解性なし)とされています。化審法では急速分解性を考慮しませんが、それぞれPNECは0.01mg/Lあるいは0.001mg/Lとなり、GHSの区分1が化審法の有害性評価値であるPNECの上限と一致します。このように考えれば、生態毒性では、おおむねGHSの区分1の物質が化審法の区分1に相当すると考えることができるでしょう。
「特定新規化学物質」には、① 情報伝達の努力義務、② 国からの指導及び助言、③ 国への取り扱い状況に関する報告が定められています。①に関しては、化学物質の危険有害性情報はSDSによる伝達が一般的ですので、SDSの第15項「適用法令」にその旨を記載することになるでしょう。ただし、この規程は「努力義務」ですので必ずしもすべてのSDSに記載されるとは限らないのが課題ではあります。②については、国は不用意に環境中に排出されないように、事業者に適切な取扱いを求めることになると思いますが、法律の改正主旨を考えれば製造者から顧客(使用者)にもそのことが適切に伝達されることも必要と思います。生態影響に関しては、製造事業者は化審法に基づいて実施した生態毒性試験の結果から、その物質がGHSの水性有害性の区分1であることを知ることができますので、これに対応して安全対策として「環境への放出を避けること」、応急措置として「漏出物を回収すること」という定型文言が選択されるはずですので、GHSに沿って作成されたSDSには、国からの指導と同様の主旨が記載されるものと思われます。
中環審の答申では、取り扱いは製造・使用・運搬等を意味するものとされています。化審法で「運搬」について言及することは異例のことです。製造や使用に対しては有害性情報の伝達はSDSが用いられますが、化審法の着目する有害性は人に対しての長期毒性と生態毒性です。運搬時の事故で化学物質が漏出したときに現場で問題となるのは、引火や爆発火災などの物理的危険性や、人に対しては長期毒性というよりも急性毒性や呼吸器・皮膚への障害であり、漏出した化学物質が公共用水や農業用水などに流出した時には、生息する水生生物への影響や用水を利用する農業用地ひいては農作物の汚染などが懸念されます。また事故時に対応が求められる可能性があるのは、輸送していたトラックの運転手だけでなく警察・消防・道路の管理者あるいは事故現場周辺の住人などですが、このような不特定多数の関係者に危険有害性情報を適切に伝達することは極めて難しいことがあります。一般社団法人日本化学工業協会は、タンクローリーやコンテナ等を用いた危険有害性化学物質のバルク輸送では、SDSあるいはイエローカードを携行することを推奨しているので、それを参考として適切な対応を考えることができますが、個品包装された化学物質の混載輸送では、漏出化学物質を特定したうえで適切な対応を考えなくてはなりません。事故処理対応の緊急作業時には、SDSやイエローカードを丁寧に読む時間的余裕もないので、必要な対応が直感的にわかる簡素な仕組みの情報伝達が必要でしょう。容器ラベルに事故時の対応を記した容器イエローカードの提案もありますが、「非常に強い生態毒性」が理由で指定された特定新規化学物質とGHSの危険有害性区分1の対応を考えれば、「水生環境有害性」のピクトグラムがラベルに記載されていれば、公共用水・農業用水への流入を抑止することがわかりやすく伝わるものと思います。既に、ラベル・SDSをJISに準拠している事業者であれば、その作業は既に済んでいると思います。
第2回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
2月8日から、特定新規化学物質の判定基準案に関するパブリックコメントが募集されました。新規化学物質は届出直後には製造・輸入量も少なく、ばく露の可能性を考えれば一般的にはリスクの懸念も低いのでしょうが、優先評価化学物質にならなかった一般化学物質のうち、毒性の「極めて高い」物質は、不適切な取扱いなどによる環境汚染への懸念が指摘されたこともあり、予防的な措置として特定新規化学物質という枠組みが設定されたことは前回に記したとおりです。今回の判定基準案は、「毒性(ハザード)」の要件を示していますが、「毒性」には人の健康に関わるものだけでなく、環境中の動植物に対する好ましくない影響(生態毒性)も含まれます。
Ⅰ. 人の健康影響に係るスクリーニング毒性試験に基づいた判定基準
化審法の新規化学物質の届出に必要なスクリーニング毒性試験からは人の健康影響を考えます。28日間あるいは90日間の反復投与試験又は反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験から一般毒性や生殖発生毒性を考慮します。変異原性試験は、がん原性のスクリーニングと考えられていたときもありますが、現在ではそれだけでなく遺伝子損傷の可能性を見る試験と位置付けられています。化審法で前者は有害性の指標(有害性評価値)を用いてクラス分けしますが、後者は数値ではなく情報の確からしさを判断基準としています。この考え方はGHSの分類・区分と同じと考えることができます。どちらも有害性クラスを1から4とクラス外の五段階に分けています。
A. 一般毒性・生殖発生毒性の有害性クラス
有害性評価値は、毒性試験の結果から得られる数値(NOEL:無毒性量等)を不確実性積で除して得られ、それにより有害性の大きさ(クラス)が見積もられます。最も高い有害性クラス1には、基準数値は設定されていませんが、クラス2は0.005mg/kg/day以下としています。今回の判定基準案は、特定新規化学物質に対する有害性評価値を0.0005mg/kg/day以下としています。この毒性はクラス4から順に一桁ずつ高い有害性評価値でクラス分けされているので、有害性評価値が0.0005mg/kg/dayということは、有害性クラス1あるいはそれ以上の有害性を示す物質に相当すると考えることもできます。しかし、判定基準案にもありますが有害性評価値とともに総合的な判断にもとづくものであることには留意しておきたいと思います。優先評価化学物質の選定過程でも、有害性評価値とばく露クラスからなる優先度マトリックスでは高リスクの範疇には入らなかったものの、取扱方法や用途などのその物質に関係する様々な状況を勘案した総合的な判断から優先評価物質の候補となった物質もあります。特定新規化学物質の抽出過程でも専門家による総合的判断がされるでしょう。
B. 変異原性 (がん原性)
化審法の新規化学物質の届出で実施される変異原性試験は、①細菌を用いる復帰突然変異試験と、②哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験またはマウスリンフォーマTK試験があります。今回の基準案はどちらかの試験の結果が「強い陽性」、他方で「陽性以上」の結果とされています。有害性クラス2は、いずれかで「強い陽性」と判定されるものですから、二つの試験結果の両方で「陽性・強い陽性」ということになれば、変異原性を持つことは有害性クラス2よりも確からしいと考えることができます。がん原性については、特に理由が無ければ新規化学物質に多額の試験費用を必要とするがん原性試験を実施することはないと思いますので、判定基準案でも全く触れられていないことにも納得できます。公的機関ががん原性を認めた場合に、優先度マトリクス中の有害性クラスが決められますが、新規化学物質にそのような評価が定まった物質があるはずもなく、仮にあったとしても日本の事業者が海外の公的研究機関でがん原性が確定している物質をあえて新規物質として登録しようと試みることも考えられません。
以上のように、スクリーニング毒性試験から考察される人の健康影響では、特定新規化学物質の判定では、おおむね有害性クラス1、あるいはその中でも特に強い有害性が懸念される物質が候補になると考えてよいのではないかと思われます。
Ⅱ. 生態毒性による特定新規化学物質の判定
生態毒性はPNEC(予測無影響濃度)を判定の基準にしていることは、優先評価化学物質の優先度マトリクスと同じ考え方です。化審法の目的は、化学物質による人あるいは動植物への長期的なばく露による影響の抑制ですが、動植物への影響といっても実際には試験の対象は三種(藻類・甲殻類・魚類)の水生生物であり、甲殻類・魚類では急性毒性試験結果を届出に使用することができます。
判定基準案では三種の水生生物の慢性毒性結果(NOEC; 無影響濃度)があれば、そのうちの最小の値の1/10をPNECとし、判定基準値は3X10-4mg/Lとしています。しかし、新規化学物質の届出で三種とも慢性毒性値が届け出られることは少なく、急性毒性値を含めた形で届出がされていると思いますし、その場合の判定基準値案はPNEC=3x10-5mg/Lで、三種の慢性毒性値から導かれるものよりも低い値ですが、どちらにしても優先度マトリクスの有害性クラス1の0.001mg/Lよりも厳しい値です。(PNEC算出の手続きの詳細は、平成23(2011)年4月の「新規化学物質の判定及び監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」を参照してください) これらの値を旧第三種監視化学物質の公表されているSDS(注)に記載される生態毒性値と比較すると、多くは判定基準値よりも高い値となっています。それゆえ、今回の特定新規化学物質は、極めて高い生態毒性を持つものということができるでしょう。そのような化学物質はGHSの分類・区分では、間違いなく水生環境有害性の区分1となると思われます。新規化学物質の届出事業者には新規化学物質として届け出る時にはそれがわかっているはずですので、少なくとも環境汚染を未然に防止するために必要な注意書き文言は、GHSに従って記載されることになるでしょう。
「特定新規化学物質」には、製造・輸入や使用を制限する規制はありませんが、製造・輸入事業者は環境汚染の未然防止のために情報の提供・伝達が求められていることを理解して、必要な対応をとりたいものです。
(注) SDSに記載される毒性値は発行者によって異なることがあります。今回の旧第三種監視化学物質とそのPNECの算出には主として中央労働災害防止協会安全衛生センタ―のホームページに記載されているものを利用したことをお断りします。
第3回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
― 2009年の改正(1) ―
筆者は前回(2009年)の改正に先立って開催された合同見直し検討会に参加しました。その時にはあまり気にも留めなかったのですが、後から考えればこの改正は化審法の枠組みの大きな転換点でした。「リスク管理」と「国際的な化学物質管理への対応」がこの時のキーワードだと思いますが、「リスク管理」は2002年の「持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)」の「2020年までにリスク評価・管理手順を用いて、化学物質が人の健康と環境にもたらす悪影響を最小化する」という合意、さかのぼれば1992年のリオデジャネイロの環境サミットを受けての活動でもあるので、「国際的な化学物質管理」の流れの一側面でもあると言うことができます。しかしそれだけでなく、2001年の欧州白書に始まる欧州REACH規則の制定などのように、世界各国・地域の化学物質管理の法規制も変化しており、このような動向も化審法改正に影響を与えたと考えることができます。
化審法は、制定以来、基本的にハザード(難分解性・高蓄積性・長期毒性)に基づいて対象物質を定め、製造・輸入や使用を規制してきましたが、この改正では基本的な枠組みは維持しながら、世界的な化学物質管理の動きに同期させた形になりました。2003年の改正でもハザード管理からリスク管理への方向性が示されていましたが、2009年の改正でそれが具体化したものと思います。
今回は2009年の改正で、それまで製造・輸入が原則禁止だった第一種特定化学物質が厳格な管理の下に置かれるものの、特定の用途(エッセンシャルユース)について許容されるようになった背景と、化審法における第一種特定化学物質に関するトピックスを取り上げます。
Ⅰ. 第一種特定化学物質が原則禁止から一部は制限物質に
2009年のストックホルム(POPs)条約の第4回締約国会議で、ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩が附属書Bに加えられることになり、この条約の担保法の役割を担っていた化審法でこれに対応することが必要になりました。附属書Bは製造・使用を制限(特定の条件下で許容)する物質です。それまでに唯一収載されていたDDTは、化審法の施行時には既に失効農薬であり、わが国には存在が許容されない物質となっていたことから、第一種特定化学物質としてストックホルム条約よりも厳しい措置として、製造・輸入の禁止を継続しても実質的に不都合が生じませんでした。しかし、新たに附属書Bに収載されたPFOSは日本で重要な分野で用いられており、すぐには代替物質を用意することが難しいこともあって、附属書Bの要件に合わせて、禁止(廃絶)ではなく制限物質とする必要が生じました。これは化審法の国際整合化と見ることもできますが、直ちに廃絶することが先端的な技術の分野の国際競争力の点で不利を被る可能性があったこともその理由の一つということができます。
化学物質のリスク管理では、一般に必ずしも完全とは言えない安全性情報をもとにリスク評価を行わざるを得ません。そのため化学物質の物性と用途や使用方法をもとに、ばく露あるいは環境への排出量の制御方法を考慮してリスクが許容できるかどうかを考え、さらには代替物質を使用することによる代替リスクを評価・比較することになります。第一種特定化学物質のように極めて有害性が高い物質を、厳格な管理のもとで使用を継続するときには、適切なシナリオのもとでのばく露の状況を想定しながらも、さらに安全サイドに立ったリスク評価が求められます。
PFOSの例では、X線フィルムの乳剤に添加して高精細の写真画像が得られることは、より正確な医学的診断を可能にして、人の健康管理に極めて有用と考えられました。これはペルフルオロ化合物に特有の極めて低い界面張力によるもので、2009年改正の時点では容易に代替物を求めることは難しいことでした。画像の高精細化は高密度のパターンのフォトレジストを作成することをも可能にして、IT技術の進展を支えるうえでもPFOSはその時点では欠かすことができないものと考えられました。これが政令で指定された許容される用途の、「エッチング剤の製造」、「半導体用のレジストの製造」、「業務用写真フィルムの製造」に対応しています。
ぺルフルオロ化合物を用いた消火薬剤は主として大量の引火性物質を扱う事業所などで業務用として用いられていましたが、2003年の十勝沖地震で石油製品タンクに着火した際には、十分な量と質の消火薬剤が不足して、消火に長期間を要しました。消火が進まなければそれだけ消火作業を行う消防隊員へのリスクが大きくなりますし、長時間にわたってタンクから漏れ出る化学物質による環境汚染のリスクも考えなければなりません。消火薬剤は確かに環境中に放出されて使用されるので環境への負荷も懸念されますが、消火廃液中にはタンクに保管されていた化学物質も大量に含んでいるので、実際には回収して廃棄物として処分されているようです。このときに消火薬剤も併せて回収されるので、環境への拡散は可能な限り少なく抑えられることになります。消防研究所の検討では、大型タンクの消火に用いられる大容量泡消火器では、フッ素系界面活性剤を含む消火薬剤が最も優れた性能を持つことが示されました。第一種特定化学物質の指定に伴ってPFOSを使用した消火薬剤の生産は停止し、その後の研究で環境負荷の少ない界面活性剤を用いた新しい消火薬剤が開発されていますが、2009年改正の時点では希釈された濃度でフッ素系界面活性剤を含む大量の消火液が石油コンビナート等に存在しており、消火液は日常的に使用されるものではなく、品質保持期間も長いので、あえて大量に備蓄されている消火薬剤を回収し処分する必要はないとされました。順次PFOSを含まない新しい消火薬剤への置き換えが進んでいます。このようにPFOSには人や生態系への有害性というハザードがあるものの、使用しないことによるリスクの増大、あるいは代替物の使用による新たなリスクの発生を考慮して、適切な使用方法により許容できるまでのリスク低減ができるものと判断されました。
この改正は規制緩和と見ることもできますが、事業者には製造予定量と実績の報告や用途及び出荷先の情報を毎年国に報告するとともに、技術基準の策定で使用にあたっても細かい要件が定められているので、実質的には規制当局の管理下に置かれたということもできます。
Ⅱ. 不純物として製品に混入した第一種特定化学物質
2009年の改正内容には直接の関係はありませんが、ここ十年ほどの間に不純物として第一種特定化学物質が非意図的に混入した製品の扱いが問題となりました。第一種特定化学物質は、本来わが国には存在しないとされていた物質ですので、閾値あるいは許容含有量はありません。しかし、目的とする製品の製造工程で微量の副生成物として混入することもあり、また極微量であるために、それを完全に除去することは経済的に合わないことが多いので、この問題の合理的な解決方法が検討されました。
例えば、顔料中のPCBでは、該当製品とそれを用いた消費者用製品の用途について、ばく露経路によるばく露量を推定しWHOの一日耐用摂取量(TDI)などを参考としてリスクを評価しました。詳しくは「有機顔料中に副生する PCB の工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書」(平成28年1月29日)に記載されていますが、一つのばく露シナリオを除いて、現状の使用方法では人の健康に対しては、問題が生じないとしています。例外は、クレヨンを子供が誤食した場合の顔料中のPCBのばく露量がWHOのTDIを僅かに超える可能性があることを指摘しています。「子供のクレヨンの誤食」をばく露シナリオに入れたにもかかわらず、そのような事例は、「実際には想定できない事故」として健康障害の可能性の結論を棄却しています。シナリオに入れたにもかかわらず「想定できない」とすることは、リスク評価の手法として問題が無いとは言えないと思いますが、そもそも顔料中に含まれるPCBの量を現実にある状態に比べ、極めて過大に見積もっていることなども考えれば、「実質的にリスクは許容できないレベルではない」という結論には頷けるものがあります。この報告書を受けて、工業技術的・経済的に低減可能なレベルが、製品の使用者等に健康リスクが生じないレベルであれば「自主管理値」とし、すべての製品ロットを確認してこれに合格する製品の出荷を可とする形で運用することになりました。リスク判定に用いられるばく露シナリオは、含有量にしてもばく露条件にしても事実上ありえないほどの高い水準を設定しているので、この自主管理値に合格する製品のリスクは許容できるものと考えることになります。
第一種特定化学物質が不純物として製品に含有されることは、最近になってから初めて起こった事例ではなく、以前からもあったことだと思いますが、社会的な化学物質の有害性への関心の高まりと分析技術の進歩で表面化したものと考えることができます。近年になって整備されたリスク評価の手法を用いて、これまでの製品においても許容できるリスクであったことが明らかにされたことは、社会の安心につながる結果といえるでしょう。将来、類似した問題が発生する可能性はありますが、同様の手順でリスクが評価され対応が図られていくものと思います。
このように化学物質の管理がリスクベースに変化すると、事業者はこれまでの国の定めた規制値を守るだけの活動から、安全性に関する情報を入手し、それをもとに自社の製品の取り扱い方法や用途などを判断することが求められるようになります。
Ⅲ. 第一種特定化学物質を使用した製品の輸入
第一種特定化学物質を使用した製品で、政令で定められたものは輸入禁止です。化審法は化学品中の化学物質を規制しますが、政令の製品には、塗料・接着剤などの化学品であることが容易にわかるものがあるのに対し、潤滑油・切削油などの日常的には化学品であることを意識しないものだけでなく、化粧板・コンデンサーなど化学品が含まれていることが容易にわかりにくい成形品(Article)もあります。この規制への違反には化審法としては厳しい罰則が定められているので注意が必要です。政令は、第一種特定化学物質ごとに対象製品を示していますが、同一の製品に対して複数の第一種特定化学物質が該当することもあるので、政令に挙げられた製品を輸入するときには、該当する第一種特定化学物質が使用されているかどうかを輸入者が確認しなければならないことになります。
Ⅳ. 化学物質の蓄積性
化審法は熱媒体が食用油に混入し、継続的な摂取から生体内に蓄積して好ましくない影響を与えたことを契機に成立した法律で、通常の化学物質を規制する法律で着目される毒性だけでなく、環境中での分解性と生体内の蓄積性も併せて評価するという点に特徴がありました。一般に化学物質は体内の脂肪分に蓄積すると考えられています。この考え自体は現在でも妥当性を持ちますが、PFOSの蓄積性の検討では、これまでの蓄積性物質と比較して体内濃度がなかなか飽和に達しないなどの特異な挙動を示しました。高蓄積性と判断されたのは、体内への高い濃縮度を示すというよりも、容易に飽和に達しないこと、すなわちどこまで濃縮されるのか予測ができず、その結果、高い濃縮度に到達する可能性があることが懸念されたからと思われます。蓄積性物質は、生体内の脂肪分に蓄積するものと考えることが一般的でしたが、PFOSの生体内蓄積の挙動は、これまでの蓄積性物質とは異なっている可能性があります。PFOSは水にも油にも溶けにくい物質ですので、試験の実施は容易ではなかったものと思いますが、生体内の蓄積を考えるうえでは、このような特異な挙動を示す物質があるということについての示唆的な事例ではないか、と思われます。
第4回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
― 2009年の改正(2) ―
2009年の改正で、良分解性物質を含めてすべての化学物質がリスク管理の対象となりました。これは2002年の環境サミットの合意である「2020年までに、すべての化学物質による人の健康や環境への影響を最小化する。」への対応が必要となったことを受けています。
Ⅰ. 優先評価化学物質と一般化学物質
化審法に優先評価化学物質と一般化学物質の区分が新たに設定され、第二種と第三種の監視化学物質が廃止されました。化審法の規制対象は、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質と第一種から第三種の監視化学物質がありましたが、いずれも難分解性でした。分解されやすい物質は、環境を経由して人や生態系に好ましくない影響を与えにくいとの考えに基づいたものと思います。しかし、容易に推測できるように、環境中で分解される物質も分解速度を上回る排出があれば環境中で検出されることもあります。事実、環境省の黒本調査(*1)では、このような物質の環境濃度が測定され報告されています。リスクを最小化するという国際合意の実行には、良分解性物質もまた化審法の制度の中でリスク管理することが必要になりました。分解性の良否に関わりなく、環境中に滞留した化学物質は人の健康あるいは生態系に影響を及ぼす可能性(リスク)が無いとは言えない、ということです。特定化学物質を除けば規制当局に製造・輸入の行為やその数量に関して許認可を求めることは必要としないので、「規制」といっても事業活動への影響は比較的少ないのですが、事業者は将来の規制の強化の可能性を想定して、適切な対応を考えておくことが必要です。
一般化学物質の製造・輸入事業者は、毎年の製造・輸入実績数量と二桁のコードによる用途とその分類別出荷数量の届出をします。用途は対応したスクリーニング用の排出係数を用いてばく露量推定の基礎データとなります。一般化学物質は有害性クラスとここで算出されたばく露量からなる優先度マトリクス(以下、単に「マトリクス」とする)からリスクが判定され、その後必要に応じて専門家の判断から優先評価化学物質が指定されます。優先評価化学物質の製造・輸入事業者は、一般化学物質に必要な作業に加えて、二桁の用途コードとアルファベットからなる詳細用途コードを用いて、用途分類別の出荷数量を都道府県別に報告することが求められます。製品の使用者に直接販売している時には、二つの追加要件は事業者にとってそれほど過大な作業ではないでしょう。しかし、代理店を通じての販売のように、製造者が最終の顧客を把握していない時には、双方向の情報伝達方法に工夫が必要と思われます。
優先評価化学物質では、製造・輸入事業者だけでなく、これを購入し使用する事業者にも使用方法と用途の報告が求められることがあるので、日常的に化学物質の管理を念頭に置いて取り扱う習慣があまりない事業者には、新たな化学物質管理の仕組みが必要となることも考えられます。購入(使用)事業者からの報告事項もまた優先評価化学物質のリスク評価に用いられることになるので、購入(使用)事業者には供給者からその物質に関する情報を伝達することが必要です。優先評価化学物質の情報提供は化審法では努力義務とされていますが、実質的に情報の伝達、すなわちSDSの提供は必須と考えることができます。
優先評価化学物質の人または生態系に対する有害性情報は、国は事業者に対して要求するだけでなく、必要があれば有害性調査の指示を出すことができるようになりました。事業者からの取扱状況の報告と有害性情報から、国はリスクを評価し環境残留量と有害性から被害のおそれがあると判断されれば第二種特定化学物質として指定することになります。第二種特定化学物質に対しては、事業者は製造・輸入予定数量の届出を行い、必要があれば国は予定数量に対して変更命令を出すことができるので、製造・輸入事業者だけでなく、購入・使用の事業者もまた事業活動に制約を受けることがあります。
有害性には、人の健康と生態系に関する影響がありますが、それぞれ1~4のクラスと区分外の五段階にわけられ、有害性クラスとばく露量クラスからなる「マトリクス」でリスクが高い可能性のある物質から優先評価化学物質の候補が抽出されます。事業者からはどの物質が優先評価化学物質となるかを予知できる場合もありますが、優先評価化学物質の指定には専門家による判断も入ります。化学物質固有の性質である有害性はSDSなどから知ることが可能ですので、ここではどのような有害性を持つ物質が抽出されるのかという点を見ていきます。有害性情報は現在ではGHSの分類・区分を用いたSDSで伝達することが一般的になっているので、可能な限りGHSの分類・区分と関係づけて考えます。
A. 人の健康に関わる有害性
化審法では一般毒性、生殖発生毒性、変異原性、発がん性を考慮します。疫学調査などから人に対する影響が明らかになっていればその知見・情報も用いられますが、そのような事例はそれほど多くないので、化審法やOECDのテストガイドライン(TG)に即した試験の結果などから人への影響が外挿されます。
一般毒性は28日あるいは90日間の反復投与試験から考察され、生殖・発生毒性はそのための専門の試験が実施されることもありますが、反復投与試験との併合による簡易生殖・発生毒性試験も用いられます。変異原性は細菌を用いる復帰突然変異試験および哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験またはマウスリンフォーマTK試験を用いて評価されます。発がん性は情報があれば考慮されますが、高額な試験費用と長い試験期間を必要とするので、発がん性試験のデータを事業者が持つことは少なく、これまでのところ国が事業者に試験の実施を要求することもありません。
1) 一般毒性の有害性クラス
一般毒性は、GHSの分類では特定標的臓器毒性(反復投与)に対応し、試験動物の臓器の形態や機能などへの影響が有害性の判断基準となります。「マトリクス」の有害性クラスは有害性評価値を基準とします。最も有害性が高いクラス1には基準値は設定されていませんが、クラス2は≦0.005mg/kg/dayで、クラス3、4はそれぞれ一桁高い値です。
有害性評価値は有害性試験から得られるNOEL(無影響量)、LOAEL(最小毒性量)などを不確実性積で除したものとして算出されます。人と実験動物の違いを考慮した種差(不確実係数=10)、人による感受性の違いを考慮した個体差(不確実係数=10)、試験期間の長短によって決まる不確実係数 (28日間の反復投与であれば6、90日間であれば2など)、NOELでなくLOAELを用いたときの不確実係数(10)などを用います。
「マトリクス」の有害性クラス2と3には、旧第二種監視化学物質の28日間反復投与のNOEL(<25mg/kg/day)が示されていますが、これに種差・個体差・試験期間の不確実係数積(10X10X6=600)を用いれば有害性評価値は<0.042mg/kg/dayとなり、有害性クラス3と同程度であることがわかります。GHS区分1のガイダンス値は、90日間反復投与でLOAEL≦10mg/kg/dayですので、これに種差・個体差・90日間の試験期間およびLOAELの使用による不確実計数積の10x10x2x10=2000を適用すると、有害性評価値は0.005mg/kg/dayとなり、有害性クラス2と一致します。
2) 生殖発生毒性
「マトリクス」の有害性クラス1には基準の設定が無く、有害性クラス2では≦0.005mg/kg/day、クラス3、4はそれぞれ一桁ずつ高い値が設定されていることは一般毒性と同じです。「マトリクス」にはTSCAのハザードスコアも引用されており、High、Moderate、Lowはそれぞれ有害性クラス2、3、4およびクラス外に対応しています。例えば、ハザードスコアHighのLOAEL<50mg/kg/Dayは、種差(10)、個体差(10)、LOAEL(10)および簡易生殖毒性試験・一世代生殖試験の採用(10)による不確実計数積(10x10x10x10=10,000)を用いれば有害性評価値は0.005mg/kg/dayとなり、化審法のクラス2と一致していることがわかります。
一方、GHSでは生殖発生毒性の区分は、人に対する影響を示す情報の確からしさを用いるので、人における証拠を基にした人に対して生殖毒性が知られている物質(1A)、動物データから人に対して生殖毒性があると考えられる(1B)と生殖毒性作用の証拠が十分でない物質(2)に区分されるので、GHS区分と有害性クラスとの間に直接の対応はありません。
3) 変異原性
変異原性試験は、高額・長期間を必要とする発がん性試験のスクリーニングと考えられることもありますが、現在では遺伝子毒性を考える試験にも位置付けられています。対応するGHSの分類は生殖細胞変異原性です。有害性クラス1にはGHS区分1Aが該当しますが、これは人生殖細胞に経世代変異原性を誘発することが知られている物質で、疫学的調査による陽性の証拠が必要であるため、この区分に位置付けられる物質はほとんどないでしょう。クラス2は、①GHS区分1B、2とともに、②化審法判定の強い陽性、③化管法の変異原性クラス1、あるいは強弱不明の陽性結果を持つ物質とされています。数値の基準が無いことから、化審法でも情報の確からしさで有害性クラスを分けていることがわかります。(化審法の陽性、強い陽性あるいは陰性の判定の詳細は公表されている「判定基準」あるいはその他の化審法の試験法に関する文献等を参照してください。) 化審法の新規化学物質の届出で実施される変異原性試験だけからは、物質が生殖細胞に突然変異を誘発するか否かの判定は行わないので、GHSの区分1 (1A、1B)になることはなく、区分2に分類されます。
「マトリクス」では、化審法で用いられる試験のいずれかで「強い」陽性であればクラス2、いずれでも陽性であればクラス3、いずれかで陽性であればクラス4となります。旧第二種監視化学物質(さらにそれ以前であれば「指定化学物質」)との対応では、クラス2は変異原性試験結果だけから、クラス3に相当する「いずれかで陽性」を示す物質は反復投与毒性試験結果と合わせて考えることで第二種監視化学物質への該否が判定されていました。
4) 発がん性
化学物質による発がん(化学発がん)は、古くからの化学物質の人の健康に対する障害として社会的に関心が高かった分野ですし、現在でも特に労働衛生の分野では「がん」は最大の関心事の一つです。
「マトリクス」では、発がん性の有害性クラスの1にはGHSの区分1A(人に対する発がん性が知られている:主として人での証拠によりここに分類する) が引用されており、これと合致するIARCの区分1、産業衛生学会の区分1、米国ACGIHの区分1も例示されています。有害性クラス2には、GHSの区分1B、2(人に対しておそらく発がん性がある/疑われる物質)が対応しており、研究機関の区分では、IARCの2A/2B、産業衛学会の2A/2B、ACGIHのA2/A3となります。発がん性試験には多額の費用と試験期間が必要となるので、事業者がこれを行うのは特にその必要があるときで、他の健康有害性試験と異なり、自発的あるいは任意に実施することはほとんどないでしょう。有害性クラスの1、2に区分されるためには、その試験結果の妥当性の評価が厳格に行われる必要があり、試験データの報告から評価の確定には長時間を要します。
日本では、化審法だけでなく労働安全衛生法でも発がん性を有する物質は、特定化学物質障害予防規則(特化則)で規制されるだけでなく、「健康障害を防止するための指針(がん原性指針)」の対象物質も注意喚起されています。しかし、身近な事例でいえば近年胆管がんの発生で問題となった1,2-ジクロロプロパンは、労働安全衛生法の下で発がん性試験が実施されたことで、特化則の規制物質となっているだけでなく、日本の産業医学会も区分1に分類されていますが、IARC等のその他の国際的ながん研究機関では現在のところ、発がん性の区分は与えられていません。
Ⅱ. 生態毒性の有害性クラス
2003年の改正で、それまでの環境を経由した人の健康に対する影響だけでなく、環境中の生態に好ましくない影響を及ぼす可能性のある物質も規制の対象となり、第三種監視化学物質という枠組みができました。新規化学物質の届出でも生態毒性試験が実施されますが、試験の対象は三種(藻類・甲殻類・魚類)の水生生物です。
生態毒性の有害性クラスは、その物質のPNEC(予測無影響濃度)から決まります。有害性クラスの1から4に対応して、それぞれ0.001、0.01、0.1、1(単位はmg/L)を上限とします。化審法は慢性的なばく露による影響を考えるので、生態毒性試験では慢性毒性データを取得して影響を考えることが本旨なのでしょうが、慢性毒性データを取得することはコスト的な制約および安全性試験に要する時間の制約があるので、急性毒性データからPNECを求めることも行われます。
PNECの算出では、先の三種の水生生物のすべてに慢性毒性があれば最も低いNOEC(無影響濃度)の1/10がPNECとなりますが、急性毒性を使用した場合には、例えば一種類の慢性データ(その他は急性データ)しかないときには、慢性NOECの1/10と二つの急性毒性値をACR(急性慢性毒性比; 10~100)で除した値の中で最も低い値をさらに1/10したものをPNECとすることになります。急性毒性値を用いた場合のPNECは慢性毒性値がそろっている場合に比べて低い値となる可能性がありますが、これは不十分な(本来慢性データを用いるべき作業に急性データを用いる)データの採用による、より安全側に立ったPNECの算出と考えることができます。PNECを指標とした生態毒性の見積もりでは、「マトリクス」では有害性クラス1と2が旧第三種監視化学物質に相当し、GHSでは慢性毒性区分1に対応するとしています。
Ⅲ. その他の改正点
最後に2009年の改正で化学物質のハザード管理からリスク管理に転換したことで、事業者の活動にどのような変化が生じたのか考えます。
リスク評価は、ハザード(有害性)とばく露の両面から好ましくない影響が起こる可能性を見積もる作業です。ハザードは社会的な安全への関心の変化を受けて重視する項目が変わりますし、研究の進展で有害性の評価も変わりますが、基本的には物質固有の性質です。しかし、ばく露はその化学物質を取り扱う方法や処理方法の選択で低減が可能です。これにより、ハザードベースでは規制の主体は製造者(供給者)でしたが、リスク管理では購入・使用者を含めたすべての取扱者に拡張されることになります。このように、リスク評価では事業者の果たす役割が大きくなり、欧州のREACH規則では、環境の側面だけでなく取り扱う労働者への影響(労働衛生)やそれを使用する製品からの消費者への影響も含め、リスク評価はすべて事業者の責務とされていますが、化審法ではリスク評価の実施者は国であることに大きな違いがあります。
改正にあたって、サプライチェーン全体における管理の重要性が指摘されました。例えば第二種特定化学物質では、使用されている製品を取り扱う事業者にも技術上の指針が公表されるようになり、優先評価物質では国が製造事業者にスクリーニング毒性試験の実施を求めることや有害性情報提供の指示もできるようになっただけでなく、使用事業者に対しても国は取扱状況報告を求めることができるようになりました。
サプライチェーン全体にわたる化学物質の管理を可能にするためには、情報の伝達が欠かせません。化審法ではこの情報伝達は努力義務にとどまっていますが、化管法・安衛法・毒劇法ではSDSの義務化対象物質が定められているので、事業者の自主的な活動から化審法の規制対象物質についてもSDSによる情報伝達が行われることが望ましいでしょう。なお、優先評価化学物質の半数近く、汎用性の高い物質に限れば多くは化管法の第一種指定化学物質となっているので、三法によりSDSの提供が行われていれば、多くの優先評価化学物質の情報提供は可能になるはずです。現実には必ずしもそのようになっていない状態と思われますので、SDS提供の商習慣化の進展が望まれます。
2009年の改正では、入手した有害性情報を国に報告することの努力義務や、国から必要に応じて有害性情報の調査指示が出されたときの対応も定められましたが、全社に対してはどの情報がこの規定に対応するのか適切に判断するには専門的な知識も必要とするので、とりわけ製造・輸入業者にとっては課題となるように思います。不明な点があれば国や専門家に相談することも一つの方法でしょう。
(*1) 化学物質の環境調査結果をまとめて公表する環境省の年次報告書
第5回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
― 2003年の改正 ―
2003年の改正で、化審法に生態毒性評価とリスクベースの化学物質管理の制度を取り入れました。日本国内で化学物質に起因する特別の問題が生じたからというよりも、国際的な化学物質管理の動きに即したものと考えることができます。化審法は世界で最初に化学物質を規制する法律でしたが、その後海外でも異なる枠組みの化学物質の規制が始まり、化審法も国際的な動向を配慮した改正となりました。今回はその中で、生態毒性評価の導入とリスク管理を取り入れた制度の導入を取り上げます。
Ⅰ. 生態毒性評価の導入
化審法の目的が、「人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染の防止」になり、生態毒性の評価が取り込まれました。前年のOECDによる日本の環境成果レビューで、「化学物質管理の政策に生態系の保全を含むように規制の範囲を拡大すること」とした勧告への対応となりました。これにより、難分解性の新規化学物質の届出で、濃縮度試験・変異原性試験・反復投与とともに、生態毒性試験の結果が求められるようになり、生態毒性が懸念される物質が第三種監視化学物質に指定されることになりました。
1962年にレイチェル・カーソンは「沈黙の春」で、化学物質が野生動植物の生息や生育に影響を与える可能性を指摘しました。記載された事例の中には、後の研究では必ずしもすべてが化学物質と関係すると考えることの科学的な妥当性を持つとは限らないものもありますが、それまでは摂取(ばく露)された化学物質からの直接的な人の健康影響のみに注意が向いていたのに対して、難分解性の物質の中には生態系への、そしてひいては間接的に人の生活環境にも影響を及ぼす可能性があることを示したことで、化学物質の管理に新しい考え方を提示し、それが日本の化審法やその後の世界各国・地域の法規制にもつながりました。
化学物質による生態系への影響の評価は、人の健康影響と同様に毒性試験を行い、被験動植物の生死や行動・生育・繁殖などの異常の有無を指標とします。生態毒性は、動植物個体への影響というよりも、特定の地域に生息する野生動植物群の持続性や種の存続のリスクを考えるということで、人の健康影響を考える場合と異なります。また極めて多くの種類の動植物への影響を、限られた動植物種を対象とした試験結果から外挿することになるので、それだけ不確実性が大きくなります。日本で用いられることの多いメダカやコイを用いた生態毒性試験からは、メダカやコイの生育・生息への影響を評価するのではなく、生態系一般への影響の可能性(リスク)の指標と考えることになります。このように考えると、OECDのテストガイドライン等の試験方法に即しているのであれば、試験に用いられる欧米と日本の魚種の違いを論じることには、魚種である限りはあまり意味が無いことがわかります。
生態系へのリスクを、先行的に規制する方向を示したEUでは、保全すべき対象として、①水生生態系、②陸生生態系、③高次捕食者(食物連鎖)、④排水処理施設中の微生物、⑤大気環境を挙げています。この区分に従って生態毒性を評価するためには、①から⑤の保全対象を代表する動植物種を用いて、影響する環境媒体ごとに実験的にあるいは経験的ではあっても科学的な裏付けのある知見をもとにした評価が適切だと思いますが、残念ながらそれを満足する生態系のリスク評価手法は確立していません。OECDは、化学品プログラムで、生態毒性を含めて化学品の危険有害性を判定する多くのテストガイドラインを公表していますが、実際に生態毒性試験で広く使用されているものは、淡水の水生生物に対するもののうちのいくつかに限られています。そのため「生態毒性を考える」とはいっても、多くの物質については淡水の水生生物に対して試験が実施されているのが現状です。欧州REACH規則では、それまでの欧州の化学物質を規制する指令を受けて、昆虫・ミミズあるいは鳥類などの陸生動植物に対しての毒性試験を規定していますが、現在は製造量が年間100tあるいは1000tを超える高生産量の物質についてどのように進めるべきか、事業者の提案を求めている段階です。
2003年の化審法改正で導入された新規化学物質の登録に必要な生態毒性試験も、三種(藻類、甲殻類、魚類)の水生生物に対する急性毒性試験であり、それに加えて同じ改正で導入された有害性情報を入手した場合の国への報告義務があるのは、ミジンコ(甲殻類)の慢性毒性試験(50%遊泳阻害濃度;EC50、無影響濃度;NOEC)、魚類延長毒性試験(慢性影響)、魚類初期生活段階毒性試験(慢性影響)、ユスリカ毒性試験であり、いずれも淡水系の水生生物が対象です。
生態毒性でも容量-反応曲線から化学物質の毒性(あるいは影響)の強さを評価することは同じですが、リスク評価では安全(リスクアセスメント)係数に個体差に基づく係数を用いるか否かという点に、人の健康影響の評価との違いを見ることができます。生態系に影響を及ぼす、すなわち野生動植物の健康に影響があれば、人も「動物界」の一員であるので同様の影響があってもおかしくない、と考えることもできますが、種の存続あるいは生物多様性の確保を目的とする生態系への影響評価と、人(個体)への健康影響評価は目的が異なるので、区別して考えることが必要でしょう。
生態系への影響の問題は、2003年の化審法改正あるいは欧州のREACH規則の制定以前から提起されていました。日本でも、2000年の環境基本計画の中で、生態系への考慮が必要であることを指摘していました。欧州では、化学物質を規制する1992年の理事会規則(92/32/EEC; 67/578/EECの第7次修正指令)では、事業者が収集すべき基本的な危険安全性情報の中に、魚類・ミジンコの急性毒性と藻類の成長阻害試験が挙げられています。製造量の増加した場合に追加で求められる情報として、ミミズなどの陸生生物や鳥類への毒性試験もあります。生態系の保全を目的の一つとする2006年からの欧州REACH規則に先立って、2001年の欧州白書にその方向が示されています。
広く生態系への影響を考える契機の一つに、1995年出版の「失われた未来」の中で、内分泌系に作用する化学物質があるのではないか、という問題提起があります。欧州白書では「海洋性哺乳類で内分泌かく乱の疑いのある難分解性化学物質が高濃度で検出された」と記載されているように、内分泌かく乱作用だけでなく難分解性であることが問題であるとしています。内分泌系は体内で生産される極微量の物質(ホルモン)により生命維持に大きな役割を果たしていますが、疑似的にホルモンと類似した作用を持つ化学物質はホルモンに比べてはるかに有効性が低くても、それが大量に摂取され生体内に蓄積されれば、意図しない形で内分泌系に作用する可能性があるという指摘につながります。その後の研究結果は、「失われた未来」に記述された事例も、必ずしも化学物質の内分泌かく乱作用によるものではなく、化学物質の他の有害性あるいはその他の一般的な環境要因などに基づく可能性が高いことを示していますが、この問題提起によりOECDなどでも内分泌かく乱作用を検出するための試験方法の開発が始まりました。出版から20年以上が経過しましたが、ホルモンと類似した作用を目的として使用されている薬剤を除いて、工業的に使用される化学物質で内分泌かく乱作用から生態系に影響を与える可能性を示唆する研究結果は未だに得られていないのが実状でしょう。多くの物質に改めて綿密な毒性試験が行われ、それまで安全性があまり疑われていなかった物質でも、可塑剤のフタル酸エステル類のように生殖毒性の疑いが示されたものがあり、日本を含め世界で規制につながったものもありますが、それはいわゆる内分泌かく乱作用によるものではないと考えられています。このように「失われた未来」に記載された事例についても、まだ科学的な裏付けが十分にはとれていませんが、この本は環境中の化学物質からのリスクとして、内分泌系というこれまで想定していなかった経路からも生体に影響を与える可能性を提起したもので、その後の世界各国・地域の生態毒性による化学物質の規制につながっているということができます。
2003年の化審法改正で、新規化学物質の届出に必要な生態毒性試験は、甲殻類(ミジンコ)と魚類の急性(又は慢性)毒性試験と藻類の毒性試験になりました。藻類の場合には、独立した二つの試験から急性毒性と慢性毒性を求める方法論が確立していないことから、便宜的に成長阻害試験のEC50を急性毒性値、NOECを慢性毒性値と見なしています。魚類の急性毒性試験は、化審法の改正以前から蓄積性試験のための濃度設定のための予備試験として実施されてきたこともあり、実質的に新たな毒性試験は甲殻類と藻類を対象とした二種類といえるでしょう。
化審法は新規化学物質の届出に必要な安全性試験として、世界のどこよりも40年以上も前から分解性試験と蓄積性試験を取り入れていることを特徴としています。REACH規則はどちらも生態毒性試験の一つに位置付けており、生分解性試験は化審法と同様に、1t以上の製造・輸入で求められます。しかし蓄積性試験は100t以上の製造・輸入で必要になるように、安全性試験としての位置づけが化審法と異なっているのは、化審法が環境を経由した人の健康(2003年改正では環境それ自身)への好ましくない影響を規制することが目的であったのに対して、REACH規則は化学物質の想定されるすべての危険有害性を規制しようとする姿勢の違いによるものと思います。蓄積性試験に要する費用は少なくなく、日本の事業者には大きな負荷になっている場合もあります。
Ⅱ. 化審法の規制へのリスク管理手法の導入
この連載の第三回で、筆者は2009年の改正で化審法が「ハザード管理からリスク管理に変化した」と記しました。そして、その動きはその前の2003年改正から始まっていたことも記しました。以下は、リスク管理を制度として導入した化審法の2003年改正の要点です。
A. 第一種監視化学物質の区分の設定
新規化学物質の届出では、難分解性であれば蓄積性試験が必要で、さらに高蓄積性となれば、高額の試験費用と長期試験期間を必要とする長期毒性試験の実施が求められます。その結果、長期毒性が認められれば第一種特定化学物質の要件に合致するので、事業者は難分解性で高蓄積性の新規化学物質は届出を控えてきました。一方で、既存化学物質には難分解性・高蓄積性であっても規制の仕組みはありませんでした。そのような規制の間隙を埋める形で、2003年の改正で第一種監視化学物質の区分ができました。難分解性・高蓄積性物質を規制する考えは、欧州のREACH規則のvPvB物質の区分設定に対応しているということができます。日本の第一種監視化学物質と欧州のvPvB物質の判定基準には違いがあるので同列には論じられない部分もあり、現在の監視化学物質(2003年では第一種監視化学物質)の中で、欧州のvPvBであることだけの理由で認可物質あるいはその候補物質となった物質は少ないのですが、毒性試験によらずに化学物質の化学的・物理的特性から環境影響を懸念して毒性の詳細が判明する前に予防的に規制しようとする考えは一致しているといえるでしょう。
B. 低生産量新規化学物質の区分の設定
従来からあった生産量の少ない少量新規化学物質の確認申請に加えて、難分解性であっても低蓄積性であれば、スクリーニング毒性試験と生態毒性試験の結果を必要としない「低生産量新規化学物質」の区分ができました。製造・輸入量に制約はありますが、製造・輸入の行為が可能となるので、化審法では審査の特例とされています。環境モニタリングの結果から、10t未満の製造・輸入量の物質は、一般環境から検出された実績が無いこと、すなわち不特定多数の国民へのばく露が想定されないことから、これが上限とされました。制度が始まった2003年時点では、国内の製造・輸入総量の上限の規制でしたので、これを超える時には数量の調整により必要量の全ての製造・輸入ができないこともありましたが、2017年の改正で上限が国内の環境排出量の予測値の総量に変わったことで、数量の調整が必要になることは極めてまれになるのではないかと思われることは、連載の第一回目に記したとおりです。
この低生産量新規化学物質の制度を利用して確認される物質は年々増加しており、制度の開始時点では200件程度でしたが、現在では1600件に及んでいます。このことは、この制度が事業者にとって使い勝手のよい仕組みであることを示しているものと思いますし、その用途も、電気・電子材料、フォトレジスト材料、写真材料、印刷材料という比較的環境への排出が管理しやすい、別の言い方をすればリスク管理のしやすい用途で先進的な技術・材料開発に貢献しているものと思います。低生産量新規化学物質の制度は、新規化学物質の開発を行うことの多いファインケミカルメーカーには、新製品の開発を進める上では使いやすい制度ということができます。
C. ばく露の管理によるリスクへの対応
低生産量新規化学物質の制度の新設は、2003年の改正がハザードベースからリスクベースへの管理に移行する一つの現れですが、同様にばく露の管理の視点から、以下の特定の用途の化学物質は事前審査の対象から外されることになりました。
1) 全量中間物
2) 閉鎖系等の環境放出の可能性が極めて低い用途で使用される物質
3) 輸出専用品
これらの適用除外を受けるには、規制当局による事前の確認と事後の監視や予測環境放出量が基準を満たしていることを説明する資料の提出などが必要になりますが、承認されたプロセスで使用される限りでは、新規化学物質としての事前審査の必要がなくなりました。これらの化学物質は、(日本の)環境から国民へのばく露の可能性がないと判断されたことによります。輸出専用品では、国際的な化学物質管理の責任から、輸出仕向け地で日本の化審法と同等の化学物質管理に関する法規制制度が運用されていることが条件になります。
なお、このような化学物質でも、労働安全衛生法の新規化学物質に該当する場合には、取扱う労働者に対するばく露の可能性を否定することができないので、新規化学物質登録を免れないことには注意が必要です。
第6回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
― 事業者とリスク管理 ―
化学物質のリスクベースによる管理は、2002年のWSSDの国際合意で世界の潮流となりました。化審法では2003年と2009年の二回の改正でその考えを導入しましたが、事業者にはリスクベースの管理を義務化していません。しかし、労働安全衛生法では、対象物質は限られているものの、取り扱う事業者にリスク評価と管理を義務化し、危険有害性を持つすべての化学物質については努力義務としました。リスクベースの管理では、ばく露の視点が入るので、輸入・製造事業者だけでなく、購入・使用する事業者も関係することになります。
今回は「化学物質のリスク管理」を取り上げますが、「リスク管理は必要」と感じているものの、まだ着手されていない事業者や化学品の製造・販売を主な事業とする化学企業だけではなく、専ら化学品を購入して使用するサプライチェーンの川中・川下に位置する事業者の方にも参考になればと思い、記しています。
事業者の化学物質のリスク管理は、① 環境を経由した人や野生動植物への影響(環境リスク)だけでなく、② 業務として取り扱う作業者のリスク管理(労働安全衛生)や、③ 製品から最終消費者へのリスク(製品リスク)、④ 廃棄物中の化学物質による廃棄物処理業者や環境への影響、などの多方面にわたって考える必要があります。この中でも、取扱量の多寡にかかわらず、局所的に労働者への高いばく露濃度となる可能性のある労働安全衛生リスクが最大の関心事である場合もあると思いますが、ここでは化審法との関係が深い「環境リスク」を主体に考えます。しかし、事業者には可能であれば他のリスクと合わせて一体化したリスク評価・リスク管理をシステム的に進めることが合理的かつ効率的と思います。
ハザードベースの規制では、特定の重篤な危険有害性を持つ物質を対象としますが、そのような性状を持つ物質は数えきれないほどたくさんあります。ある基準を超えた有害性を持つ物質を一律に製造・輸入・使用などの規制対象にすると、実質的に好ましくない影響を制御できるプロセスで使用される有用な物質や優れた機能を持つ物質も規制対象物質となり、技術革新に大きな制約となることがあるので、製造や使用の禁止などの強い規制対象物質は個別に指定されることになります。そのため、顕在化した事故・災害の再発防止のための「後追い」規制になりがちです。リスクベースの規制では、有害性物質のばく露量を予測し、そのリスクが許容できないときに規制の対象になるので、取扱う事業者の管理の実態は規制を考えるうえで重要な要因となります。リスク評価は、どの物質が、誰(何)に対して(リスク対象)、どの程度のばく露量となるのかを、ばく露シナリオに沿って見積もりますが、このシナリオが実態に即して描けていなければ適切なリスク管理は難しいでしょう。
リスクが評価されていることでリスクベースの管理が可能になるので、化学物質を取り扱う事業者にはその手法を理解し、使いこなすことが求められます。ばく露の視点を入れることで、事業者の化学物質の管理活動も発想を変えることが必要になることもあるでしょう。そのため化学物質のリスク評価やリスクベースの管理活動は未だに手探り状態の事業者も多いのではないかと思います。本稿では、事業者の化学物質のリスクベースの管理活動の起点となるリスク評価の要点を記します。
Ⅰ. リスク評価の方法
化審法では大きく分けて二種類の手法でリスクが評価されます。一つは一般化学物質から優先評価化学物質を抽出するときに用いられるスクリーニング評価で、もう一つは第二種特定化学物質が優先評価化学物質から指定される時に用いられる数次にわたる詳細なリスク評価です。後者は、環境汚染が進行している、あるいは将来的にそうなることが確実であるかどうかを判断するもので、最終段階では必要に応じて個別の事業者から詳細な用途情報等の収集や有害性調査の指示ができることになっています。ハザード情報やばく露情報とともに環境モニタリング結果なども用いて規制の要否が判断されることになります。国が行うリスク評価が規制を根拠づけるものということができます。
スクリーニング評価は定性的、詳細なリスク評価は定量的ということもできるでしょう。リスク判定で利用できる情報が少なければ、それだけ規制は事業者にとって厳しい安全サイドの判断にならざるを得ません。事業の継続に支障を来す可能性がある過度の規制を避けたければ、それが規制の緩和に有効に機能するかどうかは別として、事業者は自社製品の取扱い方法に関する情報を、社内だけでなくサプライチェーンにわたって入手し、資料として準備しておきたいと思います。そのようなばく露情報とSDSにあるハザード情報を用いれば、事業者もリスクが評価できることになります。製造(販売)者から一方的に危険有害性や法規制の情報が伝達されるだけのハザードベースの管理と異なり、リスクベースの管理では、製造(販売)者と購入・使用者の間の双方向的な安全性情報の伝達が好ましいことになります。
事業者が詳細にリスク評価を行うために、事業所からの排出が事業所周辺の地域の環境に及ぼす影響を見積もるソフトウェアが公表されています。しかし、これを使いこなすためには相応の知識と経験が必要です。前提条件が自社製品の実態とは異なる場合があれば、その部分を調整することも必要になります。得られた結果の妥当性の確認はさらに難しい作業といえるでしょう。公共用水系への排出では、排出口の数は限られているだけでなく、大規模の排出水処理施設からは比較的平準化した排出となります。そのため、水系への環境影響は評価しやすいのですが、多くの排出口から大気中に放出される物質は、あらゆる方向に拡散するだけでなく、その後の挙動は気候、季節、風向、地形などの複雑な要因とも関係するので正確に推測することは難しくなります。また、バッチ式で取り扱われる現場から間欠的に排出された環境濃度は時間に依存します。このように不確定的な要因が多いので、特に大気系への排出では特定の地点や狭い領域の環境影響を見積もることはますます難しくなります。実測の環境濃度があっても、それは自事業所だけでなく周辺の他事業所、あるいは事業活動以外のさまざまな要因を含めた結果でもあるので、特別な場合を除いて自事業所からの排出物の環境負荷への寄与を見積もるのは困難です。
そのような困難さはあっても、環境基準等の基準値が設定されていれば、それと比べることで汚染の程度と有無を判断することができます。しかし、大気汚染防止法で大気中の環境濃度、あるいは水質汚濁防止法で水系の環境基準値や排出基準値が定められている物質は限られているので、自主的な管理活動ではそれ以外の物質には、有害性の指標となる値から自主管理の基準値を設定することになります。近年、有害性を示す試験データはインターネットの普及で取得が容易になってきていますが、入手情報から評価に用いるデータを選びだすことや、それから合理的に自主管理基準値を決めるには、専門的な知識と経験が必要です。周辺環境に対する事業所からの環境影響と安全性の判断には専門家の作業が必要になりますが、それができる人材を持たない事業者には、このような定量的なリスク評価を日常的に行うことは難しいでしょう。
事業者にとってのリスク評価の意義は、自らの環境活動で不十分な部分を探し、限られたリソースを用いて効果的な環境負荷低減の対策を進めるための優先順位を決めることにあると思います。そのため、これまでリスク評価の必要性を感じつつも実際には着手できていなかった事業者は、国のスクリーニング評価に相当する定性的な方法から始めることが一つの方法と思います。労働安全衛生リスクを見積もる労働安全衛生法のリスク評価でも同様の方法が示されています。
スクリーニング評価では、いくつかの区分された有害性と排出量からなるマトリクスを作成してリスクを定性的に判断します。ばく露対象への正確なばく露量を求めることが難しいので、代替指標として(推定)排出量を使います。有害性としては、SDSにあるGHSの分類・区分や化審法で優先評価化学物質の抽出に用いる有害性(発がん性・変異原性・発達発生毒性を含む長期毒性と生態毒性)の区分を用いることができます。化管法の第一種指定化学物質については、排出量データを持つ事業所も多いでしょうが、それ以外の物質は同じプラントやプロセスで使用されていて環境への放出経路も同じであれば、そこにある防護設備の防護効率も同じと仮定することや、蒸気圧、水への溶解性、LogPowなどの環境放出に関係する物理的性状を参考とすることにより、排出量の推測ができるでしょう。排出口からの濃度を積算した実測値や連続的に検知された正確な数値でなくても、およその数値から前述のマトリクスに割り付けてリスク評価ができるので、数値の精度にこだわる必要はないと思います。当然のことですが、排出量の区分は化審法に用いられている数値ではなく、事業所の規模に応じた境界値を用いることになります。このような定性的なリスク評価は、事業者が環境活動として優先して行うべき方向を示してくれるでしょう。
Ⅱ. リスク評価実施のメリット
リスクベースの管理を行うことは、これまでのハザードベースの管理から新しい仕組みを採用することで、事業者には何等かの追加の負担が発生しますが、社会が環境の保全と改善に関心を高めている中では、事業者のリスクベースの化学物質管理にはそれを超えるメリットがあると感じています。以下に簡単にまとめます。
| ① | GHSの分類・区分を用いるのであれば、リスク評価に必要な化学物質の危険有害性はSDSに記載されており、化学物質の危険有害性に詳しくなくても実施できます。取引先から提供されるSDSの情報が不十分であると感じるのであれば、SDSの作成者に追加情報を求めることになるでしょう。危険有害性の情報は絶えず更新されているので、最新の情報を用いることが重要です。 |
| ② | 異なる有害性分類から生じるリスクの比較と優先度を決めることが可能になります。化学物質の持つ有害性を比較することはやさしい作業ではありません。限られたリソースを用いてどのリスクへの対策を優先させるのかを決めることは、事業者にとって重要なことだと思います。特に混合物化学品を使用する際の異なる化学物質のリスクや代替物質を使用する際の代替リスクの見積もりでは、リスクを比較することが必要になります。マトリクスを用いる方法ではそれが可能です。使用する有害性データが取得されたときのばく露条件とリスク評価のシナリオから推測されるばく露経路との整合性を考慮することも必要になりますが、それが難しければその部分はとりあえず無視してリスク評価を進めることも一つの方法と思います。 |
| ③ | リスクはハザードとばく露の二要因から判断されるので、適切な区分とマトリクスが設定されており、その方法が特定されていれば、評価結果は人に依存しません。ハザードベースの管理では、環境安全の担当者や取り扱い現場の熟練作業者の知識や経験に依存していた環境安全活動が、システムの中で実施者によらない形で進められます。熟練の作業者が定年退職を迎え、そのノウハウや経験に依存してきた部分が使えなくなる可能性があるとき、あるいは人員の削減などにより専任の環境安全管理者の指名が難しくなることが予想されるときは、システム化された仕組みでリスク評価ができることは事業者には好ましいことといえるでしょう。 |
| ④ | 会社あるいは事業所がISOの環境マネジメントシステムの認証を取得しているのであれば、その枠組みにリスク評価を組み込めば、他の環境安全活動と統合化した形で実施できます。スクリーニング評価のためのマトリクスの妥当性の検証には、知識や経験を有した社外の専門家の助力が必要になることもありますが、定期的に行うマネジメントシステムの検証時に実施すれば、日常の環境安全管理活動で行う必要はないでしょう。 |
| ⑤ | システム化されたリスク評価結果は、事業所周辺の利害関係者との間で交わされるリスクコミュニケーションに用いることができます。リスクコミュニケーションに参加する利害関係者は化学物質やその有害性に関して十分な知識を持つとは限らないので、理解が難しい有害性情報をその場で徒に羅列することは、未消化のリスクコミュニケーションになり本来の役割が果たせないことになりかねません。理解が難しい専門的な内容でリスクコミュニケーションを試みるよりも、システム化されたリスク評価とリスク管理の基本的な考え方を提示することは、実質的な対話を可能にし、互いを理解するための適切な資料となるでしょう。予備知識を持たない利害関係者に専門的な部分で理解と共感を得ることは難しいですが、どのような考え方で取り組んでいるのかという事業者の姿勢が理解されることが、信頼性を得るためには重要であると思います。 |
| ⑥ | 化学物質の法規制がリスクベースに移行する中で、事業者自身も自主的なリスク評価を行うことは、法規制の詳細な部分を詰める段階で、規制する側に実態が理解されやすくなるでしょう。これもまたリスクコミュニケーションの一種ということができます。規制する側も、必ずしもその化学物質が使用されている実態を熟知しているとは限らないので、単に求められた情報を提供するだけでなく、それを用いたリスク評価結果を併せて提示することは、規制を考えるうえで参考になるでしょう。日本では規制する国と規制される事業者の間で、リスク認識に対してどのような意見交換がされるのかは筆者自身にも経験が無くわからない部分があります。リスクベースの考え方を先行的に取り入れた米国のTSCAでは、論理的に正しいリスク評価結果をEPAに示すことによって、ビジネスの継続に支障を来すことなく解決を図ることができます。 |
リスク評価は環境側面だけでなく、例えば化学品を取り扱う現場の労働安全衛生に係る部分でも事業者には必要になっています。厚生労働省もマトリクスを用いた定性的な手法を公表しているように、この方法は初めてリスク管理を行う事業者にとっても入りやすい方法と思います。製品や廃棄物のリスクも同様に考えることができます。
リスクベースによる化学物質の管理は、事業者にとってこれまでとは異なった手法が求められ、日常的で継続的な作業が必要になりますが、安全にそして安心して化学物質を使用する上では、効果的な管理活動と考えることができるでしょう。
第7回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
― 1986年(昭和61年)の化審法の改正 ―
化審法の事前審査制度は、新たに製造・輸入される化学物質(=新規化学物質)は、国に届出を行い審査により規制対象となるか否かの判定を受けるまでは、製造・輸入ができないとする制度です。化審法に続いた米国のTSCA(1976年)や欧州の「危険な物質の分類・包装及び表示に関する理事会指令(67/548/EEC)」の第六次修正指令(79/831/EEC;1979年)」でもこの制度を採用しました。しかし、欧州のREACH規則(2006年)は、「既存」と「新規」を区別せずに、製造・輸入事業者は販売する物質のリスク評価を行い、ECHAに届出て事業者ごとに登録することを義務づけました。REACHに類似した仕組みが世界に広がり始めていますが、EUほど統治領域も広くなく、人口も少なく、事業者によるリスク評価の歴史が浅い国や地域で、事業者に大きな負担を求めるこのような仕組みがうまく機能するかどうか、推移を見守りたいと思います。
化審法は1974年の制定から12年が経過した1986年に最初の改正が行われました。規制物質に第二種特定化学物質と指定化学物質が加わりましたが、この改正の全般にわたって、世界的な化学物質管理とその制度化の進展の影響を見ることができます。化学品(物質)は国境を越えて流通・販売される可能性があるため、国や地域の化学物質の規制の違いは貿易障壁となることもあります。今回は世界の化学物質管理の進展と1986年改正の関係を見ていきます。
Ⅰ. 第二種特定化学物質と指定化学物質
難分解性で高蓄積性の物質は、環境を経由して人の健康に影響を及ぼす可能性があるということから、化審法では長期毒性が認められれば「特定化学物質」として規制しましたが、1980年代に入ってからの環境庁による環境モニタリング調査などで、広範な地域の地下水や土壌からトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの、難分解性ではあるものの蓄積性は高くない塩素系炭化水素類が検出されました。これらの物質は発がん性などの長期毒性が指摘されていたので規制が必要と考えられ、「第二種特定化学物質」という新たな区分ができました。環境中で検出されたので、後に大気汚染防止法・水質汚濁防止法などの環境法でも規制されましたが、汚染が広範な地域で認められたので、製造・輸入数量の制限ができる化審法で「蛇口規制」が可能となるようにしたものと推測します。合わせて難分解性・低蓄積性で長期毒性の疑いがある物質を「指定化学物質」として、製造・輸入・出荷量等の把握で環境汚染の未然防止が図れるようにしました。新規化学物質の登録時に求められる安全性試験として、この改正で加えられたスクリーニング試験の変異原性試験と反復投与(亜慢性)試験の結果からだけでは、第二種特定化学物質の要件である長期毒性の判断には至りません。既存化学物質も含めてスクリーニング試験結果等から長期毒性のおそれがあると考えられる時には、第二種特定化学物質の候補物質としての位置づけで「指定化学物質」となりました。
2003年の改正で「指定化学物質」は「第二種監視化学物質」となり、さらに2009年の改正でこの区分は廃止され、旧指定化学物質からは60物質あまりが優先的なリスク評価の対象である優先評価化学物質に移行しました。
Ⅱ. 化学物質の有害性評価への国際的な流れへの対応
化審法では、1986年の改正で難分解性の新規化学物質の届出に、スクリーニング毒性試験が必要になりましたが、米国のTSCAや欧州の第六次修正指令では、新規化学物質の登録には、有害性試験結果を必要としました。TSCAは必要な試験項目を定めず、事業者の手持ちのデータを提出することとしていますが、データを全くつけずに申請するとかえってその後の対応で混乱を招くおそれがあるので、日本からは分解性試験、蓄積性試験、そして条件設定に用いられる魚類の急性毒性試験結果などの、化審法の届出に用いた試験結果やその他手持ちの有害性試験結果を提出したものと思います。米国EPAがリスク評価のために情報が不足していると考えれば、追加試験が求められることがあります。追加試験結果の有無にかかわらず、EPAがリスクありと判断すれば、同意命令(Consent Order)により製造・輸入が制限されることになるので、追加試験の要求にどのように対応するかを事業者は判断することになります。
世界を市場とする化学品(物質)の登録に必要な有害性項目が統一されていなければ、化学品の流通に大きな障害となることが懸念されたので、有害性データの取得(項目と試験方法)の整合化がOECDで進められました。それが上市前最小安全評価項目(MPD)とテストガイドライン(TG)の制定です。
MPDはその後高生産量化学物質(HPV)の安全性点検プログラムのSIDS項目にもなり、現在はGHSの分類にも対応しています。これにより、事業者は原則として新規物質の登録にはMPDにある項目を準備することになりますが、全項目の試験には極めて多額の費用が必要となります。そこで製造・輸入量が少ないときには、どこの国・地域でも必要な有害性試験は軽減されますが、その項目は国・地域によって異なります。化審法の新規化学物質に必要な有害性試験は限られているので、急性毒性や感作性などの試験結果を追加することもあります。新規化学物質の届出に限らず、事業者に求められる有害性試験は、MPDの項目にあることが望ましいのですが、稀には個別の化学物質に対してMPDの枠組みにはない追加試験データが求められることもあります。また、TGの中でアルファベットの添え字がつくものの中には、既に特定の国・地域で使用されていた試験法をOECDに取り込んだものがあるので、仕向け地で使用されていた従来の試験方法による追加データを求められることもあります。このように、国際整合化が進んでいるとはいえ新規物質の登録をはじめとする化学物質の法規制には、必ずしも法律に記載された事項のみへの対応だけで解決するとは限りません。ビジネスが立ち上がるときは時間との競争でもあるので、通関時に無用の手間や時間がかからないように、輸出先の規制の実状をあらかじめ調査しておくことが必要と思います。
OECDのTGを代表として有害性の試験法は整合化が進んでいますが、試験結果が信頼のおけるものでなければデータの受け入れが難しくなります。そのため、OECDはGLP(優良試験所基準)をつくり、相互のデータのやり取りが円滑に進むようにしています。国内でも化審法だけでなく安衛法の新規物質登録ではGLPで取得された有害性試験データを用います。
有害性試験データの国・地域の相互受け入れの体制は進んでいますが、ハザードやリスクの評価結果までは統一されていないので、日本の評価結果が他の国・地域でもそのまま受け入れられるとは限らないことに注意が必要です。
Ⅲ. 高分子(ポリマー)フロースキーム
高分子(ポリマー)は低分子化合物と異なり、どのような命名法を用いても化学構造の完全な記述が困難なことがあります。近年は、化審法や欧州のEINECSの番号や物質名称とTSCAで用いられるCAS番号との対照も整備が進んでいますが、異なった命名法とルールで表現された番号・物質名称から、ポリマーの同一性を確認することは簡単ではないことがあります。さらに、モノマーが同じでもポリマーは製造条件のわずかな違いが物性を大きく左右することがあることも、同一性の担保と確認を難しくしていると言えるでしょう。
化審法では、ポリ-XXあるいはYY・ZZ共重合体のように、単量体部分(XX、YY、ZZ)の名称を用いて記述されることが多いのですが、「AとBとの重縮合物」のように、原料と製造方法からポリマーの名称とすることもあります。前者の場合には、製品としてのポリマーは必ずしも名称が記載されている単量体を原料としているとは限らず、その誘導体などが使用されることもあり、それが微量の残留モノマーとして検出されることもあります。同じ名称でも平均分子量や反応の確率分布に依存した分子量分布や、頭尾結合などの化学結合様式や立体規則性などに違いを生じることがあります。そのような違いが、結晶性や溶融粘度などの使い勝手に係る物性を左右することもあります。ポリマーは融点・沸点・蒸気圧などの明確な物理的定数を持たないこともあるので「純物質」というよりも「混合物」に近いと考えたいのですが、化審法ではそのような違いは原則として考慮せずに、繰り返し単位と重合様式が同じであれば区別しないこととしています。化審法はモノマーの組み合わせが新規であれば「新規物質」になり原則として届出が必要ですが、運用上は1%あるいは2%ルールなどによって、組み込まれる構成モノマーの使用比率が低ければそれを除外して既存(公示)物質と見なすことができます。
多くの国や地域では、基本的にOECDのポリマーの定義(1991)を採用しているので、そこには実質的な違いはほとんどないと言えるでしょう。化審法やTSCAは新規ポリマーも物質登録が必要ですが、EUは「危険な物質の分類・包装及び表示に関する理事会指令」で登録を不要としていました。REACH規則ではポリマーの登録を不要とする制度は継続する一方で、構成モノマーの登録が必要になりました。解重合性のポリマーなどの特別な事例を除けば、ポリマーからモノマー単位が遊離されるとは限らないので、この変更は化学物質の安全性の考慮というよりも、欧州域内企業を保護する政策的なものと言えます。同じモノマーからなるポリマーでも異なる物性を持つことが多いため、同一性を確定して複数の事業者が共同で危険有害性情報を収集するSIEF(物質情報交換フォーラム)の結成が困難になり、登録作業が遅延することを回避した結果ということもできるでしょう。
化審法にはポリマーの安全性を評価するために、ポリマーフロースキームという独特の仕組みがあります。それによれば、① pHの異なる緩衝液中の安定性試験、② 水や溶媒への溶解性試験、③ GPC(ゲル排除クロマトグラフィー)による数平均分子量(Mn)の測定を行います。この手法では試験前後の重量変化、試験液中のDOC(溶存有機炭素)測定、IR(赤外線)吸収スペクトルによる構造変化とGPCによる分子量の変化を測定します。いずれも判定基準よりも大きな変化を示していなければ、ポリマーフロースキームの結果で事前審査と確認を求めることができます。分子量測定で分子量が1000以下の成分が1%未満であれば、それ以上の試験を必要としませんが、1~10%であれば濃縮性試験が必要で、10%を超えると高分子としては見なされません。ポリマーフロースキームで用いられる機器分析のGPCやIRは多くのポリマー製造者が保有しているでしょうから、製品の設計・試作の段階でポリマーフロースキームの要件に適合するかどうかを容易に判断できるので、製造者には使いやすい手法です。適合しないことが分かれば、製品の設計や製造工程の見直しで対応を図ることができる場合もあります。有害性試験や分解度試験・濃縮度試験を求めず、ポリマーフロースキームで安全性を評価するのは、高分子に低分子化合物と同じ試験を求めることは馴染まないと考えられることと、ポリマーは相対的に有害性が低いとする考え方があるからということができるので、試験の過程で低分子化合物が生成することが分かれば、その物質の安全性試験も必要になることは当然のことと言えるでしょう。
ポリマーフロースキームはGLPのもとで実施する必要が無いことも事業者にとって使いやすい方法にしています。製造・輸入事業者にはポリマーフロースキームの安全性試験は通常の試験よりも簡略化されていますが、審査する国では新規物質の中でもポリマーは届出件数が多く、手数がかかっていたのではないかと思います。そこで化審法はTSCAの免除ポリマーと同様に国の安全性審査と確認を必要としない低懸念ポリマー(PLC)の区分を導入しました(2003年)。これは事業者が基準を満たすことを証明する資料を提出して国の確認を受けるだけで製造・輸入が可能となります。PLCにはポリマーの要件の他にいくつかの基準が付け加わっていますが、ポリマーフロースキームと同様にGPCによるポリスチレン換算数平均分子量(Mn)や重量変化の測定は自社で確認できます。特定の官能基や金属元素の含有はポリマーの開発・設計の時点でわかっていることなので、PLCであることを前提とした製品設計が可能で、製造者には非常に使いやすい制度です。
このように相対的に有害性が低いと考えられているポリマーに対して、簡略化された安全評価の手法が順次整備されていることは、高機能の新規高分子材料の開発を加速させているのではないかと思います。
第8回 2017年の化審法改正と化学物質管理の課題
― 化審法制定の背景とその意味 ―
1974年の化審法の制定は、1968年にポリ塩化ビフェニル(PCB)が混入した食用油を摂取した人に健康障害が生じたことが契機になりました。その後の調査で母乳からもPCBが検出されたことで、健康障害が次世代にも受け継がれる可能性があることが指摘されました。そこで化審法は、難分解性・高蓄積性のPCBと同様の性状を持ち、人に長期毒性を有する物質を特定物質として規制対象としました。1960年代に遡れば世界の各地で魚類や鳥類の体内からもDDTやPCBなど、後に第一種特定化学物質となる物質が検出されており、環境中の生物にも影響を与えることが示されていましたが、化審法が人の健康被害の防止に加えて野生動植物の生息と生育に影響を及ぼす可能性のある物質を規制対象としたのは2003年の改正でした。
「蛇口規制」で製造・輸入を禁止できる化審法を、危険有害性を持つ化学物質を規制する基本的な法律と考えることもありますが、ばく露経路を環境に限定して規制する仕組みの化審法を、そのように位置付けることは難しいと思います。今回は化審法と、危険有害性の発現を環境経由のばく露に限定していない米国のTSCAや欧州REACH規則などと比較しながら、化審法の持つ意味を考えたいと思います。
Ⅰ. 化審法の目的
化審法は第1条で、「人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため」に、① 新規化学物質の事前審査制度と、② 性状等に応じ製造、輸入、使用等に必要な規制を行うこと、としています。
これは2003年改正によるもので、制定時の「特定化学物質(現在の第一種特定化学物質)」は、難分解性・高蓄積性の性状を持ち、継続的な摂取で人に長期毒性を持つものでした。そこでは高次捕食動物である人が食物連鎖を通じて影響を被る可能性を想定しています。健康影響として最も考えやすい短時間のばく露(接触・摂取)から生じる急性毒性は考慮されていません。また、環境中で容易に分解される物質は、分解生成物が規制物質に相当する有害性を有しているかどうかを考えることになります。環境に放出された物質のうち、大気・公共用水・土壌などを経由した間接的なばく露を通して人に長期毒性を持つ物質が、規制の対象でした。1986年の改正では、高蓄積性でなくても環境中に存在する量で長期毒性を示す可能性のあるものが第二種特定化学物質として規制対象となりましたし、2003年には環境中の動植物の生息・生育に障害をもたらす物質もまた第二種特定化学物質として規制されるようになりましたが、環境を経由するばく露経路が化審法の基本的な規制の考え方であることに変わりはありません。
TSCAもREACH規則も有害性だけでなく物理的危険性も考慮しますし、有害性については特定のばく露経路や取扱方法に限定することなく、人の健康と環境の保護を目的としています。化審法との目的の違いは、例えば新規化学物質の登録で事業者に求められる安全性情報の項目などに見ることができます。TSCAは試験項目を定めていませんが、化審法の通常申請となる新規物質の登録と同じ生産量(>1t)の場合に、REACHで報告が必要な毒性学的・生態学的情報と比較すると次のようになります。
- 化審法とREACH規則で報告が必要な項目
変異原性試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、藻類生長阻害試験、分解度試験 - 化審法で報告を必要とする項目
28日間反復投与毒性試験、魚類急性毒性試験、濃縮度試験 - REACH規則で報告を必要とする項目
急性毒性試験(経口)、皮膚刺激/腐食性試験、眼刺激性試験、皮膚感作性試験
Ⅱ. 適用範囲の違い
① 元素
「化学物質」という言葉に普遍的な定義は無いので、化審法、TSCA、REACH規則はそれぞれ法律の中で定義しています。化審法は第2条第1項で、「元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。」としています。ここで「元素」とは、単一の元素からなる物質、すなわち化学の用語に従えば「単体」を意味していると理解でき、具体的には酸素原子のみからできている酸素やオゾン、純金属とその混合物として理解される合金類や、炭素からできているダイヤモンド、グラファイトが化審法の対象外と考えられます。炭素の同素体として近年ナノ材料として注目されているフラーレンやカーボンナノチューブなども、化学的な修飾が施されていなければ、これに該当することになります。
これらの物質も、REACH規則あるいはTSCAでは「化学物質」と扱われていますし、日本の労働安全衛生法でも「化学物質」の定義は「元素および化合物」としています。
② 天然物
化審法の「化学物質」は、人為的な化学反応から生成する化合物としているので、化学反応を伴わずに物理的な分離・精製などの操作のみから得られる天然物は対象外となります。動植物油や天然鉱物繊維などがこれにあたり、アスベストも天然鉱床から採掘した鉱石から粉砕・分級などの物理的操作の選鉱の工程を経て、繊維状の部分を取り出したものなのでこれにあたります。アスベストは化学的にはマグネシウムやその他の金属のケイ酸塩や酸化物の複塩として表現され、構成するケイ酸マグネシウムや酸化マグネシウムなどはそれ自身がCAS番号を持つとともに、アスベストに分類されるクリソタイルやアモサイトなどの鉱物種もそれぞれが独立するCAS番号を持っています。TSCAやREACH規則はその鉱物種のCAS番号に基づいて規制を行っています。日本では、労働安全衛生規則や石綿則あるいはじん肺法、廃棄物処理法、建築基準法などで、法令の関与する用途・取扱方法の中で、ばく露の形態を想定して規制しています。
Ⅲ. 化学物質の特定方法とインベントリー
化審法は、法の制定時に用いられていた物質(既存化学物質)のインベントリーを作成し、そこに無い「新規化学物質」の上市に際しては、安全性確認結果を添えて登録する事前審査制度を採用しました。このインベントリーでは物質を特定する既存化学物質番号を付し、その後新規化学物質として公示された物質には、これに倣って官報公示番号が与えられています。TSCAは物質の特定をCAS番号で行い、REACHではEUの化学物質番号(EINECSあるいはELINCS)も用いられますが、CAS番号からも規制の状況を知ることができます。
化審法の官報公示番号と物質の間には必ずしも一対一の関係にあるとはいえず、例えばアルキル鎖長の異なる同族体が一括りの番号に入れられることがありますが、CASの仕組みでは原則としてアルキル鎖長が異なれば異なる物質としてCAS番号が付されます。右旋生・左旋性の光学異性体は、それぞれが独立したCAS番号を持つとともに、同量混合物のラセミ体もそれとは異なる番号を与えられているなど、番号と物質の対応付けは複雑な場合もあります。TSCAとREACHでは、そのような部分は無視して特別の注意事項が無ければ、CAS番号単位で規制されていると考えてよいでしよう。化審法でも官報公示番号とCAS番号の対応付けが進んでおり、規制の状況をCAS番号から知ることはできるようになっていますが、規制は重合度や形状の違いも加味されることがあるので、適用状況は官報公示番号で最終的な確認をすることが必要でしょう。
Ⅳ. 成形品に含まれる化学物質
欧州のREACH規則以来、成形品中の化学物質の規制が注目されています。電気・電子製品中の化学物質を規制するRoHS規則は、対象物質種が限定的であるだけでなく、多くは世界の国や地域で規制が進んでいるものであったため、個々の製品の欧州輸出への対応には注意すべき点もありましたが、規制の方向性は欧州域外からも理解できるものでした。しかし、REACH規則は対象の化学種も多く、欧州独自の考え方で選定され、物質数も増加しているので、対応の困難さは増しているのではないでしょうか。
REACH規則は、附属書17で成形品への使用を含め用途を制限する化学物質を定めています。また、附属書14の将来的に使用が認められなくなる可能性のある認可物質やその候補物質リストにある物質を含有する時には、届け出ることを定めています。これからわかることは、欧州で成形品を上市する事業者には、規制物質に関する情報(含有の有無や濃度など)が確実に伝達されることが必要だということです。
この情報の伝達作業は、欧州域内から原材料(化学品)を調達し、配合・加工・成形などの工程を経て成形品を製造する事業者にとっては、規制物質の情報伝達が必要となっている化学品の商流の延長上で入手すればREACH規則に対応できるのでしょうが、情報伝達の仕組みが整備されていない国や地域から成形品を輸入する事業者にとっては容易ではない作業でしょう。グローバルに商品が地球上を移動する現代では、日本も含めて欧州とは異なる枠組みで化学物質を規制する国もあれば、全く規制のない国もあり、そこでは化学物質の情報伝達の方法が異なる、あるいは全く制度化されていないこともあるので、欧州域内からの調達と同じように化学物質情報を入手するには、輸入業者ごとに必要な調査を行うことやそれを可能にする情報伝達の仕組みを持つことが必要になります。
しかし、輸入業者がREACH規則への対応を目的として化学分析を行おうとしても、成形品では化学物質の分布が製品中で一様でないだけでなく、分析手順も化学品に比べて技術的に難しくなります。そのため、どうしても上流からの化学物質情報の伝達に頼らざるを得なくなります。これにより、域内の成形品調達が優先され、域外からの欧州の輸出が困難あるいは縮小のケースが出てくることを危惧します。
米国のTSCAも2016年の改正で、成形品中の化学物質からの人の健康と環境へのリスクを考慮するようになりました。成形品中の化学物質に限った規制を定めた条文はありませんが、これまでも特定の化学物質の用途や取扱方法の規制に適用されてきた「重要新規用途規則(SNUR)」を成形品中の化学物質に拡張することが考えられます。SNURは個別の化学物質ごとに、それぞれの有害性や物性を考慮したリスクベースの判断で行う規制ですので、別に定める物質を一律に適用するREACHのような形にはなりませんし、そのため対象となる物質種もそれほど多くはならないように思われます。
化審法は施行令第7条で、成形品を含めて製品の輸入時に、使用されていないことの確認を求めることを、該当物質と製品群の対応で示しており、使用されていれば輸入ができません。ここで示されている「使用」の意味は、化学品、成形品を問わずに、特定の機能を実現するために、意図的に混合あるいは添加されている状態と理解することができます。政令で示された製品群はこれまでに該当物質が使用された実績があるものや使用される可能性が高いもので、第一種特定化学物質が使用されていないことの確認が特に必要である製品群と考えることができます。
化審法は環境を通じて人の健康や環境そのものへの好ましくない影響が及ぶことの防止を目的としており、REACHやTSCAが適用範囲としている、取り扱う労働者や製品を通じての消費者への影響は考慮しないので、成形品ではREACH規則やTSCAとは規制の仕組みが異なったものとなります。成形品では有害な化学物質が含まれていても、環境への放出を意図されたもの以外は、環境に大量に放出されることも考えにくく、環境経由の影響というよりも接触や摂取による人への直接の影響や廃棄物からの影響を考えることが現実的でしょう。このような化学物質の有害性の側面は、日本では労働安全衛生法、食品衛生法、住宅基本法あるいは廃棄物処理法で規制されています。
TSCAやREACHと比較しながら化審法の特徴を見てきましたが、法律の目的や制定の背景の違いは、それぞれの法律で留意すべきことが異なることがわかります。法令の定める規制の遵守が、事業者にとって最も重要な対応であることは間違いありませんが、法令に記載された条文のみから規制への該否を判断することは簡単ではなく、解釈上のグレーゾーンが生じることもあります。ハザードベースからリスクベースへの規制の変化でその傾向が強くなっているように思います。事業活動の適法性あるいは社会的責任を考える手掛かりには、法律の目的に照らし合わせることも必要でしょう。ばく露情報については規制側も必ずしも十分な情報を持つとは限らないので、規制方法が妥当であるのか、あるいはもっと効果的な方法はないのか、などという点についての適切な判断のために、事業者は評価に必要な情報を提供するだけでなくリスク評価ができることが求められますし、場合によっては事業者と規制側の情報交換から、よりよい形に原案が修正されることもあります。そうなれば事業活動に大きな影響を被らないでリスクの低減が可能となります。事業者にとっても、規制当局にとっても、そして環境にも好ましい結果を導くためには、事業者にもリスクの評価と管理について十分な力量が求められているように思います。