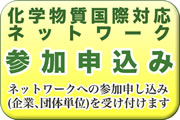リスクベースの化学物質管理
- このコラムは、化審法(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を指す。以下同様。)見直し合同委員会のメンバーでもあった日本ケミカルデータベース株式会社アドバイザーの北村卓氏に、化学産業界の第一線で過ごされてきた豊富な経験に基づき執筆をいただいたものです。
- このコラムに記載されている内容に関し、法的な対応等を保障するものではありませんのでご了承ください。
- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
→ご意見・ご感想電子メール送付先:
化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@oecc.or.jp)
目次
- 第1回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (1)
- 第2回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (2)
- 第3回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (3)
- 第4回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (4)
- 第5回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (5)
- 第6回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (6)
- 第7回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (7)
- 第8回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (8)
第1回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (1)
1. 化学物質のリスク管理の流れ
化学物質をリスクベースで管理(リスク管理)する動きは、1992年のリオデジャネイロの環境サミットから世界的な流れとなっていることは、既に筆者も何回かこのコラム欄で記してきました。その10年後のヨハネスバーグの「持続可能な開発に関する世界首脳会議 (World Summit on Sustainable Development (WSSD)) 」で具体化が進み、世界の化学物質の法規制はハザードベースからリスクベースに転換しています。それとともに新たに化学物質の規制を進める国や地域で制定される法律も、リスクベースの形になっています。大きな目でみれば、化学物質の安全管理は世界が同じ方向に向いているといえるでしょう。
しかし、同じリスクベースと言っても、国や地域ごとにその詳細あるいは運用には異なる部分も多く、化学物質(品)を輸出するときは、仕向地の規制実態を事前に確認しておくことが必要です。欧州のREACH規則は米国のTSCA (Toxic Substance Control Act) や日本の化審法とは異なり、リスク評価を事業者の責務としているので、輸出事業者はリスク評価ができることが望まれます。化学物質の危険有害性(ハザード)をGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の基準で分類・区分することも世界のすう勢となっていますが、これも国や地域によって異なる部分があるため注意が必要であり、国内向けに作成したSDSを仕向地の言語に翻訳しただけでは情報の提供として適切ではないこともあります。ハザードは物質固有の性質ですから、国や地域の違いがあっても同じ分類・区分となるように思われますが、実際には化学物質の健康影響として最も関心の高い発がん性でさえも国や地域によって評価が異なっていることがあります。
さらに、化学物質の法規制を早い時期から進めていた国では、これまでの規制の仕組みを大きく転換することが難しいこともあり、必ずしもハザードの分類・区分がGHSと整合していないことがあります。日本でも化学物質(品)の輸送時に物理的危険性を表示する際に、消防法と国際的な基準に整合した船舶安全法に基づく表示の二本立てとなっていることが身近な例として思い起こすことができますし、海外でも同様の例を見ることができます。
2. 化学物質のリスクベースの管理(リスク管理)
ハザードベースの規制では、重篤なあるいは社会的に関心の高いハザードを持つ物質が対象とされていました。どのハザートを重篤と考えるかということは国や地域によって異なることもあるだけでなく、社会的な関心は時とともに変わることがあります。健康有害性の根拠となるデータは新しい試験結果で更新されることもありますが、より厳しい方向に規制が変わることはあっても緩和されることは滅多にありませんし、ハザードベースの規制では、使い方や使用量などを加味したフレキシブルな運用は原則として考慮されてきませんでした。
日本だけでなく世界の化学物質を規制する法律には、少量(あるいは低生産量)の新規化学物質の登録時には、ハザードデータの報告を軽減あるいは不要とする特例の措置がありますが、これは必ずしもハザードとばく露量のバランスを考慮した結果の制度ではないので、「リスクベース」の規制とは別の形と考えてもよいと思います。
「リスク評価」の結果からリスクの高低を判断し、管理しようとする仕組みが「リスク管理」です。リスクは、ハザードとばく露量の二つの因子から評価され、【リスク】=【ハザード】×【ばく露量】と表現されることもあります。物理的危険性のリスクの判断では、カテゴリー化された【ハザード】(=災害が起こった時の重大性)、【ばく露量】(=事故災害の起こりやすさ、あるいはプロセスの不具合の起こりやすさとその不具合から事故災害に至る確率)の二つの因子を評点化し、それらの演算で導かれる数値化されたリスクで高低を判断する方法もありますが、化審法で国が行うリスクの評価や労働衛生でのコントロールバンディングでは、カテゴリー化した【ハザード】と【ばく露量】のマトリクスでリスクを評価します。この方法ではハザードとばく露量のカテゴリーに応じた数値化・演算は行いませんが、仕組みの理解を助けるために先の乗法で示した式でリスクを表現していることになります。リスク評価ではハザードのカテゴリー化は普及の進んでいるGHSの分類・区分を利用することが一般的となっています。
化審法では環境中の化学物質のリスク評価の主体は国ですが、事業者の活動とも無縁ではありません。化審法や安衛法が事業者に求める事項はそれぞれの法律に関係する部分で記しますが、リスクがハザードとばく露の二つの因子から判定され、このうちばく露は化学物質の物性とともに事業者の使用方法や用途に依存する因子であることを考えれば、リスク評価の主体は国でも、管理活動については事業者にも関わりが少なくないことがわかります。環境や安全に関する事項は、安定的・継続的に事業活動をすすめる上では無視できなくなってきているため、法律の規定とは別に事業者でも適切なリスク管理を用いた環境保全と安全確保の活動は必要なものとなっています。
事業者のこのような活動には資金・人材・スペース等の必要なリソースを確保する上で制約があり、より効率的・効果的に進めたいと考えることは自然なことです。事業者には社会から環境保全や健康影響に関することだけでなく、爆発や火災などの物理的危険性の予防や軽減などの複数のリスクに対しても並行して管理・改善を行うことが求められています。そのためには社会的にも納得できる形でリスクの高低を評価し、それに基づいて対処すべき対策の優先順位づけなどの活動が有効と思います。
リスク評価は単にリスクの大きさを判定するだけでなく、さまざまな異なったタイプで比較が難しいリスクを、定性的であるにしても相対的に対策の優先度を決めることを可能にします。また、リスクの低減のために行う代替措置により新たに発生する可能性のある対抗リスクを事前に見積もることで、その対策が適切かどうかを判断することも可能にします。このようにリスク評価は、国が化審法で行うものとは別に、事業者が企業として管理活動をすすめるうえで有効な手法とすることができます。
近年は労働人口の減少に伴って生産現場でも省人化が進み、それとともに間接部門の人員も少なくなっています。これまで環境や安全を確保する取り組みは、事業所内部のノウハウとして先輩から後輩への伝承などに頼ってきた部分もありましたが、経験と知見を有するベテラン担当者の退職が相次ぐようになると、その方法も時代背景に見合った形で考えることが必要になっています。リスク評価と管理の作業は、定められた手順のもとで進められ、普及が進んでいるマネジメントシステムに組み込んで、他の管理活動と同様に進めることもできます。「なぜ過去にその活動を行ったのか」、「その必要性はどこにあったのか」などの、重要な記録を残しておけば、後日、新たなあるいは追加的な管理活動が必要となった時にも容易に継続的な活動を再開することができます。これはリスク管理活動の利点の一つと考えます。従来の管理活動では、その活動を必要とした背景が時間の経過とともに曖昧となり、担当者が交代などにより環境や安全に対する考え方の適切な伝承がなければ、その都度、環境・安全管理の原点にたち返って対策を検討することになり、継続的な活動がやりにくいこともありました。リスク評価では、前回の評価の時点から、手順・ハザードの評価結果・対象物質・プロセス・用途などの変動した部分を特定し、それがリスクをどのように変化させるのか見積もることになるので、継続的な作業を行うことができます。変動した部分を特定しているので、リスクの管理として必要な措置をどの部分に施さなくてはならないのか、ということも明確にすることができます。
事業者にとってリスク評価・管理の活動は新しい考え方なので取りつきにくい側面があると思いますが、単に国のリスク評価・管理活動と法規制への対応にとどまらず、将来あるいは海外における企業活動を継続的に確保して効率化する手法にもなりうることを、このコラムでは考えていきたいと思います。
第2回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (2)
3. 化審法とリスク管理
化審法は2009年の改正でリスク管理の考え方を取り入れました。①第一種特定化学物質に関する規制の変更、②国のリスク評価に基いて一般化学物資から優先評価化学物質、さらには第二種特定化学物質に指定の道筋が明確にされたことは、化学品(物質)を製造・輸入する事業者にとどまらず、購入・使用する事業者にも影響があったものと思います。さらに2017年の改正では、③少量新規化学物質の製造・輸入数量の上限値の考え方に大きな変更がありました。今回は①と③の二点について事業者の活動に及ぼす影響を考えます。
① 第一種特定化学物質のリスク管理
A. エッセンシャルユース(個別の適用除外)の考え方
化審法が世界に先駆けて化学物質を規制する法律として1973年に制定された頃には、化学物質をリスクで管理するという考え方は一般的ではありませんでした。現在よりも工業的に使用される化学物質の種類もはるかに少なく、PCBに類似した有害性を持つ化学物質を特定化学物質としてハザードベースで規制することで、環境の汚染あるいは環境を通じた人の健康への好ましくない影響の防止が可能と考えられていました。
しかし、その後、上市される化学物質の種類も増え、化学物質はさまざまな形で人の健康や環境に好ましくない影響をもたらす可能性があることがわかってくると、単に有害性が重篤であるかどうかだけを考えて規制するのでは十分とは言えず、リスクベースの管理(リスク管理)が望ましいと考えられるようになりました。前回記した1992年のリオの環境サミットに始まる国際的な流れを受けて、各国の化学物質規制はその考えの具体化としてリスク管理に変わり、化審法も2009年の改正でこれを導入しました。この改正の直接の契機は、ストックホルム条約に追加された対象物質のうち、附属書Bの「制限物質」にPFOSが入ったことによります。2004年に発効したストックホルム条約は、①毒性、②難分解性、③蓄積性、④長距離移動性の性状を持つ「残留性有機汚染物質(POPs)」を世界的に規制しようとするものです。④の長距離移動性以外の要件が化審法の第一種特定化学物質と一致しているため、化審法がこの条約の担保法の役割を担っています。条約の附属書Bの制限物質は、特定の用途に限り製造・使用を認める(いわゆる「エッセンシャルユース」もしくは「個別の適用除外」)ので、それまでの第一種特定化学物質の製造・輸入禁止の措置はこれに整合しないことになりました。
PFOSが入る前の附属書Bには疾病を媒介する生物の防除に用いられるDDTがありました。戦争直後には大量に使用されていましたが、日本ではマラリアの流行が懸念される状況になく、当時既にDDTは農薬として失効しており製造・輸入も終了していました。ストックホルム条約に倣って制限物質にする理由が無かったので、条約の発効時点で製造・輸入が実質的に禁止される第一種特定化学物質としておくことに不都合はありませんでした。
余談になりますが、地球の温暖化が進めば日本でもマラリアを媒介する蚊が発生する可能性があることが指摘されており、その時にはDDTは第一種特定化学物質のままで制限物質となり、蚊の駆除をエッセンシャルユースとして許容することになるのでしょうか。それとも、DDTは禁止物質のままで、蚊の駆除に有効で第一種特定化学物質の要件に合致しない新しい薬剤が開発されるのでしょうか。科学技術の進歩は著しいので筆者は後者の対応のための時間的猶予は与えられていると思いますし、それが第一種特定化学物質に対する基本的な考え方に合致するものだと思います。
PFOSがストックホルム条約の対象物質となった時に、日本でも代替のきかない重要な用途に用いられており、大量の備蓄製品もあったので、直ちに製造・使用を禁止することは現実的ではありませんでした。先端的な技術分野の国際的な競争力にも影響が考えられたので、ストックホルム条約が許容する用途と同じ用途をエッセンシャルユースとしました。この措置は、化審法の第一種特定化学物質に対する規制の緩和と見ることもできますが、第一種特定化学物質の「制限物質」は、国の許可のもとで製造・使用が可能ではあるものの、国は現状よりも製造・使用量が増えるケースを想定していないと思います。また、事業者には用途が限定され厳格な管理と安全な代替物質の開発が求められているだけでなく、将来の製造・使用量の増加やこれを用いた製品の事業拡大も期待できないので、全面的な廃絶までの限られた猶予期間が与えられたと考えるのが適当でしょう。
さて、これもまたPFOSの第一種特定化学物質の指定とは直接の関係はないことですが、化学物質の蓄積性評価に関して新たな課題が浮き上がってきたのではないかと筆者は感じています。第一種特定物質の要件として生物濃縮係数が5000以上とされていますが、PFOSは所定の試験期間ではその値に達しませんでした。通常、化学物質は試験期間内で生物濃縮係数は一定の値に収れんする傾向にありますが、PFOSではいつまでも緩やかな増加が認められました。このことは生物濃縮係数が試験期間内に基準値に到達することがなくても、緩やかな濃縮度の増加は結果として高い蓄積性を示す可能性があると考えることができます。このPFOSの独特な濃縮度試験における挙動は、化学物質の生体内の蓄積は脂肪分への溶解と考える一般的なメカニズムとは異なることを示唆しているとも言えます。PFOSは水にも油にも親和性を持たない反面、生物体を構成する重要な成分であるタンパク質には親和性があると考えられているので、それがこの挙動と関係があると考えることもできます。それが事実であるとしたら、人体の組成でタンパク質は脂肪分と同程度の20%程度を占めているので、新たなタイプの生体内の蓄積性であると考えることが必要になります。しかし、そのようなメカニズムによる生物蓄積性を検出する方法は確立していませんし、脂肪への蓄積に対応したオクタノール-水分配係数(Pow)のような代替指標も提案されていません。PFOS以外にもこのようなメカニズムを持つ物質があれば、新たな有害性の発現パターンとして注意する必要もあるでしょうし、それを検出する試験方法の開発も必要となることもあるでしょう。
B. 不純物としての第一種特定化学物質の他の製品への混入
これも化審法の改正とは直接の関係がありませんが、今世紀に入って化学製品中に不純物として混入する第一種特定化学物質の事例が相次いで指摘されました。副反応等で目的物質以外の物質が不純物として反応工程中に生成することは化学反応では当たり前のことで、多くの場合は経済性を考慮しつつ可能な限り不純物の生成を抑制し、さらに精製工程で除去して純度の高い製品とすることが一般的です。しかし、近年の極微量分析技術の向上は、それまでの検出限界未満の不純物の検出を可能にしました。化審法制定の1970年代の機器分析で工程管理に用いることができる機器分析の精度は今日ほど高いものではなかったのですが、今では分析技術の向上で、ppmどころかppbのレベルまで容易に迅速に定量分析ができるようになりました。
化審法の第一種特定化学物質の含有量には許容量の定めはなく、検出されれば全て第一種特定化学物資の混入と見なされています。近年の微量分析技術の向上により、様々な化学製品で第一種特定化学物質の微量混入が指摘されることになったものと考えられます。もちろん、どのような製品であっても難分解・高蓄積・長期毒性の性質を持つ第一種特定化学物質の混入が好ましくないことは言うまでもありませんが、一方でppb、pptといった極微量の混入でも実質的な有害性につながるのだろうか、それをさらに低減させようとすればもはや製品の経済性が大きく損なわれ実質的に製造できなくなるのではないか、さらにはそのような混入量の許容値を定めること自体が化審法の性格を変えてしまうのではないか、といった新たな問題が発生したことになります。そこで採用されたのが、「適用可能な最良の技術(BAT)」の考え方でした。これによれば、完全に混入量をゼロとすること、すなわちリスクをゼロにすることはできないまでも、実質的に有害性が考えられない状態では、その混入を許容しようとするとともに、常に最良の技術を適用することで技術の進歩を促して混入量を継続的にゼロに近づけようとするものです。同じ化学物質(製品)であっても、製造のプロセスが異なれば不純物の種類も混入量も変わりますので、最良のプロセスの開発と適用を事業者に促そうとする考えです。これも、現実を直視しながらリスクを低減しようとする「リスク管理」の手法の一つと考えることができます。
② 一般化学物質から優先評価化学物質、そして第二種特定化学物質への流れ
これについては、国のリスク評価の手法の概要とそれに係る事業者の対応として、次回触れたいと思います。
③ 少量新規化学物質の製造量の考え方に対する変化
2017年の改正で、少量新規化学物質に対して製造の確認が受けられる量が、従来の「総量1t」から、「環境排出量が1tと推定される量」に変わりました。環境への排出量は用途に応じた排出率(係数)を用いて推定されます。化学物質の中には閉鎖系に近い形で使用されるものをはじめとして環境への排出率が極めて低い用途があるので、1tの推定排出量に相当する物質の製造・輸入量は100t超に及ぶものもあります。このことは、該当する化学物質が製品として使命を終えたときに適正に廃棄物として無害化処理されることや、使用に際して環境に誤って排出されることが無いように配慮されることが確認の前提条件となりますが、それにしても製造・輸入確認量が、多くの少量新規化学物質で飛躍的に増加することになります。新規物質が市場に投入されることへの障壁が低くなることで技術の革新が促される利点があり、産業界としては歓迎できる改正ということができるでしょう。しかし、以前にも記しましたが、この考え方の変化があっても個々の事業者が製造・輸入できる量の上限は1tであることに変わらないということには注意が必要です。
工業製品の市場での独占的な製造・販売は工業所有権で確保することが常道ですが、実際には特許権等は製品化のはるか前に取得することも多く、後にその物質がどのように使用されるのかを的確に見通して特許戦略を構築することは簡単ではありません。また、製品化が実現する前に特許権を確保しようとすれば、将来どのような成果につながるかわからない段階で巨額の費用を投じてその特許を取得して維持することになります。事業者は類似の性質を持つ複数の物質を同時に開発し、将来のビジネスチャンスに備えようとしますが、その中でどれが将来のビジネスの主力製品となるのかということを見通すことも容易ではありません。仮にそれらの候補物質の全てに特許権を確保しようとすると権利の確保に必要なコストの負担は極めて大きくなります。企業は物質特許・製法特許・用途特許などを組み合わせて確実な特許権の確保を図るとともに、特許期間の延長も図りますが、それでも製品化につながったときには権利期間があまり残されていないということもあります。少量新規化学物質では、化審法の製造・輸入確認量の制限があることで、先行的・独占的な市場での優位性を確保することも可能でしたが、化審法の改正で後発他社も工業所有権の制約が無ければ、市場への参入が可能となりました。化審法の製造・輸入量の枠組みは化学物質の環境影響を考慮したもので、市場における事業者の先行権・独占権の確保を目的としたものでは全くありませんが、2017年改正までは、実質的にはそのような役割を果たしていた側面もあります。
法の改正による規制の緩和は、産業界全体の技術的な進歩に対しては間違いなく有力な後押しとなるものですが、個々の事業者は他社の参入や海外品の輸入により早い時期から価格競争などに巻き込まれる可能性があります。法規制の制度の変更で、事業者には新たな難しい対応が求められるようになる一つの事例ではないかと思います。
第3回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (3)
4. 化審法とリスク管理(その2)
1973年の制定以来、化審法の基本的な構成は、①新規化学物質の事前登録制度と、②特定化学物質の製造・輸入・使用の許可制度、から成り立っていたので、専ら規制対象は化学物質の製造・輸入に係る事業活動でしたが、2009年にリスク管理の視点を取り入れたことで、化学品(物質)を購入し使用する事業者を含めたすべての取扱事業者の活動に規制の枠組みを拡張することになりました。既に1999年制定の化管法のPRTR制度も化学物質使用事業者を対象としていたので、多くの取扱事業者に化学物質の環境への排出に対する配慮が必要であることの認識はいきわたっていたものと思いますが、化学物質を「蛇口」部分で規制してきた化審法も、すべての取扱事業者に有害性の配慮が必要であることを示したことになります。
化審法の条文は、リスク評価と管理の主体を国としているため、事業者にはそれを求めませんが、リスク評価の過程では、化審法が義務付けた事業者からの報告事項や自主的な提出資料等も使用されるので、事業者も無関心ではいられません。「有害性評価」と「ばく露評価」から成り立つリスク評価では、物質固有の性質といえる有害性の評価には、国が保有するあるいは公知の情報や事業者からの報告情報などを用います。これに対して、ばく露評価の作業は環境への排出量から始まるので事業者からの情報が不可欠です。環境への排出量が多くなり規制対象となれば、その物質を扱う事業の継続と拡大は影響を受けることもあるので、事業者は環境への排出状況を把握して適切に管理することが必要になります。化学物質の管理活動を進めることが規制強化への回避につながるのであれば、事業の継続性の上では望ましい結果といえるでしょう。
① 国のリスク評価の手順
国のリスク評価の仕組みを十分に理解されている方も多いと思いますが、簡単にまとめると、A. 一般化学物質の「スクリーニング評価」、B. 優先評価化学物質を対象としたリスク評価(一次)、C. リスク評価(二次)、の3段階から成り立ち、B. は、さらに評価Ⅰ~Ⅲに分かれています。リスク評価(二次)を経て、必要であれば第二種特定化学物質が指定されます。
A. スクリーニング評価
この評価で、一般化学物質から優先的にリスクを評価する優先評価化学物質を抽出します。有害性評価には、国が収集した情報が用いられます。スクリーニング評価だけでなく、これに続くリスク評価(一次、二次)でも、評価時点で一定の質(信頼性)が確保されていれば、入手された最新の試験成績を含めて有害性が考慮されます。そのため、評価の段階が進み新たな試験成績を入手することで有害性評価は変わることがあります。ばく露評価は、化審法が製造・輸入者の義務としている事業者から届出のあった一般化学物質の製造・輸入量報告と用途分類から、用途に対応する排出係数を用いて環境への排出量を推定します。この段階は「相当広範な地域」の汚染の評価に先行する「スクリーニング評価」と位置付けられています。
B. リスク評価(一次)
A.で抽出された優先評価化学物質のリスクを、より精緻に評価して次の「リスク評価(二次)」に進むべきかどうかが判定されます。結果によっては、優先評価化学物質の指定が取り消されることもあります。
B-1. 評価Ⅰ
リスク評価Ⅰのばく露評価では、製造・輸入事業者の報告する優先評価化学物質の製造・輸入量と出荷量を、一般化学物質とは異なり、都道府県ごとに報告します。①の一般化学物質の用途分類が約50であるのに対して、優先評価化学物質は約280に細分化されています。国土全体を評価領域とするスクリーニング評価から、評価Ⅰは精緻化が進み都道府県あるいはその周辺地域への排出物質の影響を考慮することになり、化審法のリスク評価の目的に近づきますが、それでも影響の及ぶ地域を特定し、それが広範であるかどうか、化審法での規制を必要とするかどうかを判断するには、更に精緻化が必要です。評価Ⅰの結果でリスクの懸念があれば、次の評価Ⅱに移行します。
B-2. 評価Ⅱ
リスク評価Ⅱでは、有害性評価とばく露評価がさらに精緻化され、ばく露評価の定量化がすすみます。評価Ⅱのばく露評価では、評価Ⅰと同様に優先評価化学物質の製造・輸入量の報告から推定排出量が精査されるとともに、化管法の第一種指定化学物質のPRTR報告も用いることもできます。化審法の優先評価化学物質も化管法の第一種指定化学物質も、常に追加・取消しがあるだけでなく、化学物質の識別方法も異なるので正確な比較にはなりませんが、優先評価化学物質種の約4割程度が第一種指定化学物質に該当します。PRTRデータは環境からの人や環境動植物への影響を考える上では、排出量報告を補完するばく露データになります。
継続的な環境モニタリング結果があればそれも使用され、PRTR報告や製造・輸入量から推定された排出量だけでなく、実際に生活環境中で確認されたばく露量による人と生活環境動植物への影響が考察されます。評価Ⅱでは、評価Ⅰよりも狭い(限られた)地域の環境状態とそれによるリスクを評価することになります。
有害性評価とばく露評価の精緻化によるリスク推計で、さらにリスクの高い化学物質が絞り込まれますが、第二種特定化学物質の指定は、社会的にあるいは経済的に大きな影響を及ぼすことが考えられるので、さらに精緻にリスクを推定します。化管法データの解析結果からは、環境中の化学物質は必ずしも化学品を使用した事業活動のみから排出されるとは限らないことが示されているため、化審法による規制が当該物質の環境からのばく露量の低減に有効かどうかをも検討する必要があります。そこで評価Ⅱの結果から、国のリスク評価の手順には必要であれば「取扱い情報の求め」で取扱事業者からの情報を収集することも入っていますので、製造・輸入者だけでなく購入して使用する事業者も取扱い事業者に含まれることが従来の化審法の運用とは異なります。
B-3. 評価Ⅲ
信頼性の高い新たな有害性情報が公知となる、あるいは事業者から報告されれば、国はそれによりさらにリスク評価の精緻化を行います。評価Ⅱの結果で追加の環境モニタリング調査を行うことがあれば、そのデータもこの評価Ⅲに用いられることになります。
評価Ⅲまで進行してなお有害性情報に不十分な部分がある場合は、必要であれば国は製造・輸入事業者に「有害性調査の指示」を出すことになります。
C. リスク評価(二次)
リスク評価(二次)では、リスク評価(一次)の評価Ⅲの結果を受けた「有害性調査の指示」などによる事業者からの報告を受けて再評価を行い、第二種特定化学物質に指定すべきか否かが判断されます。
② 事業者からのリスク関連情報の提供 - 有害性情報 -
A. 有害性情報の報告(化審法第41条)
2009年改正で、一般化学物質を含めたすべての物質(第一種特定化学物質を除く)で、その物質の製造・輸入事業者が、難分解性・高蓄積性・人や動植物などへの毒性などの化審法の規制に関係する有害性情報を得たときは、国への報告が義務付けられました。それまでの規制対象外である「白物質」は、情報の不足で有害性が明らかにされていない物質を含めて事業者に有害性情報の報告義務はなかったのですが、人や環境動植物が多量のばく露を受ければ好ましくない影響を被る可能性があると考えるリスク管理の一つの表れとして、規制につながる有害性試験の成績を入手したときに国への報告を義務づけました。
この有害性情報報告の義務は、改正法施行以降に入手した情報が対象で、第41条第3項ではそれ以前に保有していた情報の提供は努力義務としました。改正法の施行から10年が経過して、これに該当する事例は少なくなっていると思いますが、このように化審法には法律で義務化されていない自主的な事業者の管理活動や国のリスク評価活動への協力を促す仕組みがあることを認識いただきたいと思います。
B. 有害性情報等に関する資料提出の求め(第10条第1項)
優先評価化学物質については、国は製造・輸入事業者に有害性試験成績を記載した資料の提出を求めることができる、としています。第41条では、改正法施行以前に事業者が保有する有害性情報の国への報告義務が外されていますが、第10条第1項では、国が資料の提出を求めることができるとしています。これは努力義務ですので、罰則の適用はありませんが、有害性情報は事業者にとって企業秘密になるとは思われませんし、情報の提供が事業者にとって不利益につながるものとはならないと思います。
C. 有害性(長期毒性)に関する調査の指示 (第10条第2項)
第10条第2項の「長期毒性調査の指示」は、その物質の製造・輸入事業者に対して調査を行ってその結果を報告することを定めています。「調査」と言っても事業者の手元にそのような試験結果があることはほとんど考えられないので、実質的には多額の費用と長い期間を費やして必要な試験を実施することになるでしょう。この指示に違反した場合には罰則規定もあります。「長期毒性調査の指示」が出るのは、リスク評価(一次)からリスク評価(二次)に移る場合で、対象物質は限りなく第二種特定化学物質の指定に近づいている段階にある、と考えられます。第二種特定化学物質は製造・輸入が禁止される物質ではないので、所定の手続きを経て製造・輸入・使用の事業は継続できますが、規制物質として制約を受けることになれば購入・使用する得意先を含めて、将来の事業の展開に支障が出ることもあるでしょう。
③ 有害性試験の質(信頼性)
ここまでは国のリスク評価の手順中で、製造・輸入事業者の報告する有害性試験成績も用いられることを記しましたが、リスク評価の結果は規制につながる可能性があるので、誰もが納得できるデータを用いることが必要で、試験成績には相応の信頼性が求められます。国はリスク評価に用いる試験成績の信頼性には一定の基準を定めており、事業者から報告される試験成績も同等以上の信頼性が必要となることは明らかです。
リスク評価の技術ガイダンスでは、信頼性にKlimisch コードの1あるいは2を求めています。コード1は信頼性があり無条件で使用できるもの、2は制限付きではあるものの信頼性はそれなりに確保されているものです。簡単に記せば、国際的に認められたテストガイドラインのもとでGLP に適合して実施された試験で、各国の物質登録に使える信頼性を持つことが求められるということになります。このような試験が自社内あるいは関係会社で実施できる事業者は少ないので、一般的には外部の専門の試験機関に委託することになるでしょう。海外の試験機関に委託すれば、化審法とは異なる米国TSCAのプロトコルやOECDのテストガイドラインに従って試験が行われることもありますが、そのような試験成績などもこれに相当する質を備えているので、例えば海外での物質登録に用いた試験成績も国に報告すべき試験成績に該当することになります。
④ ばく露評価と事業者からの情報
ばく露評価の基礎となる環境中への化学物質の排出量は、事業者から提出された製造・輸入量や用途情報から推測されます。改正前は、第二種(旧指定化学物質)と第三種監視化学物質の製造・輸入量と出荷情報を国に報告していましたが、同様の対応が改正後の優先評価化学物質に引き継がれているだけでなく、新たに一般化学物質についても優先評価化学物質に比べれば簡易ではあるとはいえ、製造・輸入量と用途情報の提出が定められました。改正前の「白物質」ではそのような規定はありませんでした。
A. 一般化学物質の製造輸入量の届出(第8条)
化学物質の製造・輸入事業者は、前年度の製造・輸入量の実績と用途などの届出を行い、それをもとにスクリーニング評価で優先評価化学物質が抽出されます。
B. 優先評価化学物質の製造数量等の届出 (第9条)
優先評価化学物質についても、製造・輸入量と用途の届出が求められています。届出情報は一般化学物質よりも精緻化されており、製造事業所の所在地や約280に及ぶ詳細な用途の分類、出荷先の都道府県などが求められています。化学製品の販売で伝票の上では代理店などが商流に介在することがあっても、製造工場から最終的に使用される事業所に直送されていることも多いですし、その時には出荷(製造)元は用途を含めてどのように使用されているのか推測できるでしょう。化審法では化学品がライフサイクル上でどのように使用され、環境に放出されているかという点が関心事ですので、毒物・劇物の意図的あるいは誤用による犯罪や事故の予防を目的とした、販売行為に規制を行う毒劇法とは商流管理の考え方に違いがあります。製造・輸入元が最終使用者の用途や取扱方法を把握できなければ、代理店に協力を求めることになるでしょう。もしそれができなければ、「その他」の用途として最悪の状態を想定した排出係数で排出量が推定されることになります。
C. 取扱状況の報告の求め(第42条)
優先評価化学物質、監視化学物質と第二種特定化学物質を取扱う事業者には、国は取扱状況の報告を求めることができ、これは化学品を購入し使用する事業者にも適用されます。
報告対象の「取扱い状況」には、詳細な用途、取扱いの形態や方法、取扱い数量、環境排出量、取引事業者名などが含まれるとされています。国に提出される情報は、リスク評価(一次)の中で、評価Ⅱの結果を踏まえたリスク評価Ⅲでのばく露評価の精緻化に使われます。この取扱い状況の報告への違反には、罰則は設けられていませんが、報告が得られなければ国は安全サイドに立って排出係数の高い開放系用途であると仮定することになります。したがって、それにより規制を受けて困るのは事業者ですので、情報の収集は可能ということを国は想定しているものと思います。
以上、記してきたように、国の環境リスク評価には、事業者からの情報も重要な役割を担っています。そのことは、とりもなおさず事業者もまた環境リスク評価を行うための情報を持っていることになります。次回は、法には規定されてはいませんが、事業者の自主的な環境リスク評価の意味について考えたいと思います。
第4回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (4)
5. 化学物質の環境リスクと環境基本計画・化審法・化管法
① 環境リスク
1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミット(通称リオサミット)の2年後である1994年に策定された環境基本計画には、化学物質による「環境リスク」という言葉があり、これは「化学物質が環境の保全上の支障を生じさせるおそれ」と定義されています。1999年制定の化管法と2003年の改正化審法は、環境を経由した人の健康だけでなく環境中の生物の生育・成長への悪影響の予防も目的としているので、文言に若干の違いはあるものの、環境基本計画の示した「環境リスク」への対応がこの二つの法で具体化されたことになります。なお、化審法と化管法の「環境リスク」は、すべての有害性ではなく、長期的なばく露からの慢性的な有害性によるものに限られていることに留意が必要です。
化審法と化管法は事業者に環境リスク評価は求めていません。しかしながら、化管法制定時の化学物質管理指針には、「排出状況を含め、事業活動の内容、事業所内における管理の状況等に関し、報告書の作成及び配布、説明会の実施等による事業所周辺の住民等への情報の提供等に努めること」とあり、これは環境報告書の作成や事業所の近隣住民を含めての「リスクコミュニケ―ション」を意味しています。化審法も2003年改正に至る委員会の答申の中で、「事業者にも国際的な取り組みから収集される有害性情報を活用して、簡易評価手法による絞り込みでリスク評価を行う物質の優先順位付けを行う」ことや、「環境汚染に関して安全で安心な社会を実現するためのリスクコミュニケーションなどの実施」を期待していること、さらに2009年改正でも、国のスクリーニング評価の手法の公表で「事業者の自主的なリスク管理に関する意識を喚起する」ことが指摘されています。このことから、国は事業者の自主的なリスク評価とこれに続くリスク管理を期待していると考えることができます。この背景には、国際的な枠組みとして事業者や事業者団体の自主的な有害性情報の取得と整備が進んでいることや、OECDがリスクコミュニケーションのガイダンス文書を作成したことなどがあるでしょう。このような動きから事業者は、社会が事業者のリスク管理・評価を期待しており、事業の継続と発展には自主的なリスク管理が必要であると認識するようになりました。リスクコミュニケーションの説明はここでは省略しますが、「リスクコミュニケーション」にはこれに先立って「リスク評価」が不可欠であることは容易に想像がつきますし、事業者は自主的な管理活動の一環として環境リスク評価を位置付けることになります。今回は国と事業者の立場の違いを比べながら、事業者の行う自主的な環境リスク評価の要点について考えたいと思います。
② 国の環境リスク評価
国は、比較的広域の環境に及ぼす影響を環境リスクとして評価し、関係する地域の事業者からの報告排出量や取扱い方法からの予測排出量などから環境濃度を推測し、有害性評価値と照らし合わせてリスクの有無や高低を考察します。環境濃度としては、環境モニタリング結果も直接利用されます。化審法のリスク評価では、長期ばく露からの影響を考えるため、定常的な取扱工程からの排出量が対象で、工場の近隣住民にとって最も関心が高いと思われる、事故や災害時などの突発的な状況での排出は考慮に入れていません。リスクコミュニケーションでは、このようなケースは消防法や毒劇法などとの関係で取り上げられることになります。化審法では事業所からの総排出量をもとに長期の平均的な環境濃度を推測することになります。環境中の化学物質は必ずしもそれを取り扱っている工程から排出されたもののみとは限らないので、工業的に使用されている化学物質の化審法による規制が環境リスクの低減につながるのかという点を判断した上で、規制の要否が決まることになるでしょう。
有害性評価とばく露評価から成り立つリスク評価では、有害性評価には国が保有するデータだけでなく、既知見情報や化審法の規定に基づいて事業者から報告される情報が用いられ、その上で、必要であれば国が有害性試験を行なう、もしくは事業者に試験の実施を指示することになります。規制につながる有害性の項目は、社会的な関心や有害性の新たな知見によって変わりますが、一般的には追加されることはあっても除外されることはありません。今までにも化審法の亜慢性特定臓器毒性試験である28日間の反復投与試験では、試験終了後に剖検で観察すべき臓器は増えています。化審法と化管法は、主に大気中に拡散した化学物質の吸入と食物連鎖や飲食による経口による暴露経路を考え、皮膚接触からの経皮毒性はあまり考慮されていません。したがって、化学物質を取り扱う労働者の保護を目的とした労働安全衛生法とはリスク評価の視点が異なります。
内分泌系に対する毒性(内分泌かく乱作用)については、有害性の試験方法が確立していないこともあり、亜慢性毒性試験では発達・発生毒性として生殖器などの異常や催奇形性などから判断するようになりました。今後、いわゆる内分泌かく乱作用全体を直接検証する試験方法が確立すれば、それが化審法の試験方法の一つに取り込まれることもあるでしょう。もっと複雑な脳・神経系や免疫系への有害性も作用機作の研究が進み、それを検出する試験方法が確立すれば化審法に導入されることもあるでしょうし、現時点で想定されていない有害作用も新たな試験項目として追加されることもあるでしょう。
世界では「ナノマテリアル」が新しいタイプの有害物と考えられており、有害性検出の試験方法の開発も進められています。しかし、労働安全衛生法と異なり、元素単体は化審法の定義する「化学物質」には含まれていませんし、工業的なプロセスから製造される物質(化合物)であっても、化学組成が同じであれば物理的形状や結晶系の違いに起因する健康有害性は考慮しない形になっているので、「ナノマテリアル」の規制を現行の化審法の枠組みに織り込むことは難しいと思います。
ばく露情報の収集は化審法に基づく事業者からの取扱量と用途情報や化管法に基づくPRTRデータ、あるいは大気汚染防止法などによる環境モニタリング結果などが使用されるので、国の環境リスク評価でも事業者の関与する役割が大きいことは前回に記したとおりです。2009年の化審法の改正時には、事業者による自主管理と法による規制の「ベストミックス」が、これからの化学物質管理では重要になることが指摘されました。「事業者による自主管理」の利点は、取扱いの実状に応じた事業者の創意工夫で効果的・効率的な対策を講じることができるところであるとともに、法規制を超えて化学物質の管理を事業者に促すことが可能であるところにあります。ハザードベースの規制では、同じ物質でも取り扱われ方や用途が異なる場合があるので、それらを一律に必要にして十分な形で法規制することは難しくなっています。
リスク管理への移行の段階で、事業者の自主的な管理活動には、単に環境への排出量削減や相対的に有害性の低い物質への転換だけでなく、有害性情報の伝達(SDSの提供)、化学業界を起点に商流全体を見渡したレスポンシブル・ケアやJIPS (Japan Initiative of Product Stewardship)などの活動も位置付けられていることから、製造(販売)者からの安全情報の公開や伝達だけでなく、用途や取扱方法に関しての製造(販売)者と使用(購入)者の間の双方向的な情報の交換も含めて包括的な化学物質管理を指向しています。これにより、化学品を購入し使用する事業者もリスク評価・管理を行うことができる仕組みの構築が進んでいますし、最終製品を使用する消費者や事業所近隣住民などへの情報の開示も、今後は可能となるでしょう。
③ 事業者の環境リスク評価
1. 事業者にとって環境リスク評価の意味
化学品を取扱う事業者の化学物質による環境汚染の防止は、近年事業活動の中で重視されるようになってきた社会的責任(CSR)の一つと考えられています。事業者は、より効果的・効率的に化学物質の管理をリスクベースで行うためのその第一歩として、環境リスク評価を位置付けることができます。
化管法の「リスク評価のためのガイドブック」には、事業者のリスク評価活動は、1)優先的に排出量削減に取り組むべき物質を明らかにすることで効率的なリスク削減措置を行うこと、2)リスクコミュニケーションを行うことで事業活動に対する理解と信頼を高めること、が期待されるとあります。1)は比較の難しい化学物質のリスクを、社会的に合意された方法(GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)を用いて優先順位をつけることで化学物質管理を合理的に進めることですし、2)からは安定的で発展的な事業活動を円滑に進めることが期待できます。事業者の環境リスク評価の目的は、最終的には規制で表現される国の環境リスク評価とは異なる側面を持っています。
2. 事業者の環境リスク評価の進め方
環境濃度と環境基準などの有害性評価値を比較し、環境濃度の方が高ければリスクの懸念がある、と考えることが環境リスク評価の常道で、事業者もまたこの手法を用いることができます。例えば自社(事業所)から排出される化学物質が、周辺の地域でどのような環境濃度になるのか、ということは、公開されている数理モデルであるMETI-LIS(経済産業省-低煙源工場拡散モデル)などのソフトウェアを用いて推測できます。しかしながら、利用にあたっては、事業者が留意しなくてはならない事項が存在します。
環境濃度の予測には、確定した排出量とともに「アメダス」などからの気象条件を入力するだけでなく、周辺の地形条件などの影響も受けるので誤差が生じることは避けられません。そのため、環境濃度の実測値から推測値の検証が必要となることがありますが、事業所外の多くの地点の環境濃度を自由に測定できるわけではありません。実測値には他の事業所や移動体などの非点源からの排出が影響することも考えられるため、目的とする自事業所からの排出からの環境濃度への寄与を精度よく見積もることができるか、という問題も生じます。実測値も推測値も有害性評価値を大きく下回っていれば、環境リスクはないと考えて排出管理に特段の追加措置は必要なし、と考えることができます。しかし、推測値には誤差が含まれる可能性があり、実測値にも様々なバックグラウンド要因が重なる可能性があることを考えれば、実測値や推測値が有害性評価値を超えるか、あるいは超えないまでもそれに近い値となれば、精査の必要が出てきます。リスクの懸念があると評価された地域の住民の中には、特に不安を感じる方がいる可能性があることを考慮すると、責任の有無や大小に関わらず、事業者にはなんらかの対応が求められる可能性もあります。環境濃度の推測値は排出量に比例するので、仮に1/10にしたければ排出量も1/10とすることになりますが、このような大きな削減は技術的にも資金的にも簡単ではありません。そのような対策を施してもバックグラウンド要因の値によっては有害性評価値を下回るとは限らず、また、その対策の効果が環境濃度にどのような形で反映されているのかということも明らかにはならない場合があります。このように考えると、数理モデルを用いて推定した環境濃度を、リスクコミュニケーションの一端として利害関係者に説明する際には、リスク低減のための方向性や方策を適切に伝えた上で、誤差やバックグラウンド要因についても誤解のないような理解が得られるよう、工夫が必要になります。
環境リスク評価には、国が規制物質の絞り込みの前段階で行う有害性とばく露(排出)量をそれぞれ4段階に区分したマトリックスからリスクの高低を考える方法があります。近年は、GHSに基づいたSDSの普及で、これまでは専門家に頼ることが多かった有害性の区分が専門家でなくても出来るようになっています。この方法からは、事業所周辺の特定の地点の環境濃度の予測はできませんが、事業者はリスク対策の優先順位付けが容易になります。事業者が何を課題と考えているか、どのようにして環境影響や環境負荷の低減を図るのか、という方向性を示しながら、理解と信頼を得ることもリスクコミュニケーションの目的の一つです。したがって、その手順の中で、社会的に認められる恣意的ではない客観的な手法として、有害性とばく露量のマトリックスを用いることは意味のあることでしょう。目的は異なりますが、この方法は労働安全衛生法でも示されており、簡便で使い勝手のよい方法ということができます。
環境リスクの低減で事業者が取り得る方策として、排出量の削減と有害性の低い物質への転換が挙げられますが、既に販売を開始した製品(特に混合物製品)中の成分や製造プロセスで使用する物質を他の物質に転換することは、購入使用者の了解も必要になるなどの点から、煩雑な手続きと予想以上に長い期間が必要になります。そのような理由から、実際には排出量の削減が唯一の現実的な対策とならざるを得ないことも多く、それを補う上では対策の対象とする物質の優先順位付けを容易に行うことができるマトリックスを用いた環境リスク評価の利用も十分に意味のあることと思います。
④ 継続的な環境リスク評価活動
環境リスク評価は一度実施すればそれでよい、ということにはなりません。むしろ、いったん開始した際は事業活動を続ける限り継続することが望まれます。加えて、取扱う化学物質や事業所の周辺環境が変わるだけでなく化学物質の有害性評価も変わるので、そのような変動要因を考慮しながら活動を継続することになります。事業所の環境報告書に記載していれば、理由なく記載を中止することも難しいでしょうし、リスクコミュニケーションの場では環境リスク評価を話題から外すことは信頼性を損なうおそれがあるので、これも難しいでしょう。
このように考えると、環境リスク評価は事業者にとって必要ではあるものの、長期にわたり作業を継続し情報として発信し続けることを想定して、無理のない実施の進め方や、結果を事業活動にどのように生かしていくのかという点を考えつつ、使いやすく目的に合致する環境リスク評価の方法を前もって選択しておくことが必要ではないかと思います。
第5回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (5)
6. 化学物質の環境リスクと大気汚染防止法・水質汚濁防止法
前回は環境基本法・化審法・化管法と事業者の環境リスク評価の関係を考えましたが、今回は環境保全を目的とする二つの法律(大気汚染防止法・水質汚濁防止法)の主旨を踏まえて、事業者に望まれる自主的な対応を考えます。これらの法律はいずれも事業者にリスク評価の自主的な対応を求めてはいません。しかしながら、事業所から放出される化学物質が環境汚染の原因となる可能性があることを考えれば、予防的観点から自主的な対応が望ましいことは言うまでもないことと思います。
Ⅰ 大気汚染防止法
大気の汚染を防止する法律は、1962年のばい煙規制法に始まります。主要なエネルギー源であった石炭の燃焼から発生するばいじん(スス)により大気の汚染が進み、その解決が求められました。その後、エネルギー源が石油に代わると、硫黄や窒素の酸化物もまた健康障害の原因となることが指摘され、これもまた大気の汚染の原因と考えられるようになりました。このことから、国によって抜本的な見直しが行われ、1968年に大気汚染防止法が制定されました。その後、1996年の改正で有害大気汚染物質、2004年の改正で揮発性有機化合物が規制に追加され、現在の規制の対象は、①ばい煙、②粉じん、③揮発性有機化合物、④有害大気汚染物質、⑤自動車排出ガス、⑥特定物質の6分類に及んでいます。
ばい煙には、燃焼で生じるばいじんや窒素・硫黄の酸化物だけでなく、化学反応の工程から生成する有害物も含まれますが、ここでは工業的に用いられる化学物質に焦点を絞った規制である③揮発性有機化合物と④有害大気汚染物質に対して、事業者が考慮しておきたいことを記します。因みに、⑥特定物質は、事故などにより多量に排出されたときの規定ですので、日常の事業活動では、特段の対応を事業者に求めてはいません。
1. 有害大気汚染物質
大気汚染防止法の「有害大気汚染物質」とは、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれのある物質で大気汚染の原因となるもの」とされているので、慢性の有害性(長期毒性)を持つ物質と考えることができます。1996年の中央環境審議会の第二次答申で、「有害大気汚染物質となる可能性のある物質」(以下、「有害大気汚染物質」という)として234物質が提示され、1999年に化管法が施行されたのち、2010年の第九次答申では化管法の指定化学物質との整合を図ることを目的の一つとしてリストが改訂されました。その結果、248物質が有害大気汚染物質として挙げられることになりました。化管法の指定化学物質は、「人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるもの」とされ、生態系に支障を与える(生態毒性)も規制の対象となっているのに対して、大気汚染防止法は、「人への健康影響」が規制の要件となっていることに違いがあります。また、化管法では工業的に使用される物質が規制対象で、例えば、ダイオキシン類などの燃焼過程から非意図的に生成する物質は規制の対象としていないのに対して、大気汚染防止法では環境基本法の環境基準の達成も目的の一つとされていることから、非意図的生成物質も規制の対象としている点でも違いがあります。大気汚染防止法で有害大気汚染物質を選定する際に考慮される有害性は、①発がん性、②変異原性、③生殖/発生毒性(催奇形性を含む)、④吸入慢性毒性、⑤作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性、⑥感作性、⑦経口慢性毒性(吸入毒性の情報が得られたものに限る)、としています。これに対して化管法の指定化学物質の選定で考慮される有害性は、これに吸入毒性情報の有無にかかわらず経口慢性毒性、生態毒性とオゾン層破壊物質が加わっています。大気経由の有害性を考えるのであれば、「吸入によるばく露経路」が重視されていることは当然だとも言えるでしょう。
有害大気汚染物質の有害性分類(大気汚染防止法ではクラスと表現)では各分類でどのGHS区分がこれに該当するのかは明記されていませんが、答申では「化管法対象物質の選定の考え方を活用する」としています。化管法では選定基準(クラス)とGHS区分の対比が示されているので、大気汚染防止法でもこれが踏襲されていると考えられます。そうであれば、事業者は化学製品のSDSを参照して、現在のリストへの収載の有無にかかわらず、将来的かつ自主的な管理の対象とすべき物質がわかると思います。
有害大気汚染物質の中から、「特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)」として23物質が挙げられています。改正大気汚染防止法の施行に合わせて、1996年から通産省(当時)の指針に基づき、二期にわたって事業者団体による有害大気汚染物質の自主管理計画が実行されました。その時に対象となった12物質のうちの多くが、現在、優先取組物質となっています。排出削減量の目標や削減手法は事業者団体に委ねられていたことで「自主」管理計画とされていますが、政府の強力な指導のもとで実施されたが故に、削減目標(35%)を上回る大きな成果(41%)をあげました。これが、のちの化学物質管理における規制と自主のベストミックスという、基本的な考え方につながっていったものと思います。
さらに優先取組物質の中でも、未然防止の観点から早急に排出抑制を行わなければならない物質として、環境基準が設定されている物質のうち、ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンの三物質が指定化学物質とされ、有害大気汚染物質に求められる対応の他に、排出時の抑制基準が設定されています。
大気汚染防止法は「リスクの程度に応じた排出抑制対策のあり方」を考える上で、有害大気汚染物質を三つに分類しています。そして、事業者に対して、「有害大気汚染物質;A分類」では①自主的な排出抑制と②周辺住民とのリスクコミュニケーションを、「優先取組物質;B分類」ではそれに加えて③行政の取組への協力を、さらに「指定化学物質;C分類」では④指定物質抑制基準を踏まえた自主的な排出抑制を求めています。ここで唐突に、リスクコミュニケーションという文言が出てきたことには、大気汚染防止法の改正の履歴を見ると違和感を覚えるかもしれません。しかしながら、化管法が制定時(1999年)に策定した「化学物質の管理指針」にはリスクコミュニケーションも事業者の管理施策としていること、そして有害大気汚染物質の多くは化管法の指定化学物質でもあることを考えれば、化学物質の管理をテーマとするリスクコミュニケ―ションを行う際に、事業者は化管法と大気汚染防止法への対応を併せて説明することが、必要になるのではないでしょうか。
2. 揮発性有機化合物(VOC)
大気汚染防止法のVOCは「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)を、「揮発性有機化合物(VOC)」として定める。」と定義しています。個別の物質名称を挙げなくとも、除外物質以外の大気中に排出される有機化合物は全てこの定義に該当しますし、対象は環境省が例示している100物質に限られていないので、数え方によれば200種類を超えることにもなるでしょう。また、多量に継続的に排出される可能性のある「揮発性有機化合物」はいわゆる「有機溶剤」と考えることもできます。前述のとおり、個別の物質の規制ではないため、排出量の計算は、排出される物質の排出濃度(ppm)にその物質の一分子に含まれる炭素数を掛けた「ppmC」を用います。複数の揮発性有機化合物が排出されていれば、そのppmCを合計して規制値と比較することになります。揮発性有機溶剤は工場などの固定排出源のほかに、自動車などの移動体からも排出されます。しかし、固定排出源からの、中でも特に、塗装・乾燥や固定の貯蔵施設からの排出が多いことが指摘されています。このことを受けて、大気汚染防止法では、これらの施設の中で特定の要件に合致するものを規制の対象と定めており、それ以外の施設に対しては自主的な対応を行うこととなっています。排出物質の一分子中の炭素数が多ければそれだけppmCが多くなるように思われますが、そのような分子はそもそも揮発性が低く、基礎となる排出濃度(ppm)は一般に低いので、全体して揮発性有機化合物のppmCを高めるのは、比較的揮発性の高い低分子量の化学物質ということができます。
国としての揮発性有機化合物の排出量低減の目標値はありますが、個々の事業者は義務的にではなく自主的に削減目標を定めて実行していかなくてはなりません。削減量を設定して計画を実行するには、その前提として排出量の把握が必要になりますが、この揮発性有機化合物の削減が定められたときには、既に化管法のPRTR制度が施行されていたので、事業者はその経験を生かして排出量の推定を行うことが可能になりました。しかし、有機溶剤でも化管法の第一種指定化学物質となっていないものもあるので、この揮発性有機化合物の削減計画に対応するためには、排出量の削減方法や推定手法は、化管法のPRTR対象化学物質(第一種指定化学物質)に用いる方法を、それ以外の物質に拡張して適用することが必要となります。
法律ではどの化学物質の削減を優先するかということは定めていませんが、事業所が自主的な活動を進める上では、法の目的に則して光化学オキシダントあるいは浮遊粒子状物質(SPM)を発生しやすい物質の排出削減を図ることが現実的でしょう。法律に基づいて報告する結果の単位は先のppmCとなりますので、事業者の社会的な責任として、例えばリスクコミュニケ―ションなどの場で、事業者の環境保全に対する積極的な姿勢として利害関係者に示したいのであれば、削減の基本的な考え方を提示することは、社会的な理解につながる可能性があります。
光化学オキシダント(主としてオゾン)とSPMの生成は、環境中で光(主として紫外線)を受けた化学物質がラジカル解離することから始まると考えられています。物質の光化学オキシダントの生成のしやすさはMIR(Maximum Incremental Reactivity)という指標で評価することができます。このMIRという指標は、環境の条件でも変わりますし、研究者によっても異なった値が提案されていることからも分かるように、必ずしも物質固有の性状値とは言えません。したがって、MIRを詳細に比較してどの物質が光化学オキシダントを生成しやすいかということを決めることは難しいですし、それを揮発性有機化合物の排出削減の指標とすることも必ずしも適当ではないと思います。MIR値については、全体として次のような傾向にあると考えることができます。
1.脂肪族炭化水素よりも芳香族炭化水素のほうが高いMIR値を持つ。
2.飽和炭化水素よりも不飽和炭化水素(オレフィン)の方が、中でも末端オレフィンよりも内部オレフィンが高いMIR値を持つ。
3.エステル結合やケトン基などの、炭化水素鎖の他に置換基を持つ物質は類似の分子量をもつ炭化水素と比べてMIR値を増減するという一般的な傾向は無いが、アルデヒド類は相対的に高いMIR値を持つ。
3は、光化学オキシダント生成メカニズムの中にアルデヒドの生成する段階があり、アルデヒドの場合には炭化水素鎖からの光化学的にアルキルラジカル生成のステップを通らずに光化学オキシダントを生成する可能性があるからではないかと思います。
Ⅱ 水質汚濁防止法
大気汚染防止法が化管法のPRTRでは大気放出に対応するのに対して、水質汚濁防止法は公共用水域への排出に対応しています。この法律も大気汚染防止法と同様に、規制の対象となる事業場は、法律で規定されている特定施設を有する事業場(=特定事業場)です。
水質汚濁防止法の排水基準は、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目と、水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)が設定されており、有害物質は29項目、生活環境項目では15項目の基準がありますが、金属化合物や農薬類は一括りにされているものもあるため、実際の対象物質はこれより多くなります。これらの他に「指定物質」という区分もあります。これは公共用水域への排出や地下に浸透したことで人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、排出・浸透の防止の応急措置を行い、速やかに都道府県知事に届け出ることとされており、基準は設けられていません。
水質汚濁防止法の有害物質の多くは化管法のPRTR対象物質(第一種指定化学物質)となっていますので、事業者の対応としては、PRTR対象物質の公共用水域への排出を削減することにつながります。また、水質汚濁防止法の対象物質は、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質に限られていますので、化管法の対象物質の方が広い領域を対象としていることとなり、対象物質も化管法のPRTR対象物質の方がはるかに多いため、事業者は実質的には化管法のPRTR物質の排出を削減することで、水質汚濁防止法への自主的な対応を行っていると考えてもよいでしょう。
このように水質汚濁防止法には、化管法PRTR報告を行っている事業者であれば、特段の新たな対応を考えることにはならないと思いますが、ここで筆者が思い出すのは、ヘキサメチレンテトラミンが河川に流出し下流にある浄水場で塩素滅菌の過程で分解が促進されてホルムアルデヒドが生成した結果、水道水の供給に障害が出た事故です。ヘキサメチレンテトラミンはSDSを見ればわかるとおり、毒性は急性・慢性を問わず極めて低い物質であると言うことができます。しかし、塩素滅菌のように特殊な状況下では、有害性の高いホルムアルデヒドを発生することがあり、このような状況を事前に想定して未然に防止することは非常に難しい課題です。ヘキサメチレンテトラミンのように、ホルムアルデヒドが他の活性水素を有する物質と脱水縮合してメチレン基を架橋基とした物質は極めて多種類あることが知られています。そのような物質に対して、極めて特殊な加水分解条件下でホルムアルデヒドが生成する可能性があることを、提供すべき安全情報としてSDSなどで製品の納入先に通知することは、すべての購入者がそのような要件に合致するかどうかがわからない段階では、一考を要することと言えるでしょう。ヘキサメチレンテトラミンの指定化学物質化が起因となって、大量に河川等に流出した際の通報義務を課したことは、再発防止策の一つとはなりますが、ヘキサメチレンテトラミンによる事故の再発は防止できても、特殊な状況で有害物質を生成する類似物質の全てを規制することは難しいでしょう。このような物質を製造した事業者も、それを購入して使用する事業者も、そのような事態を想定することは難しいものと思います。
このような理由から、事業者の現実的な対応は、使用したあるいは使用するつもりで購入した物質の残存物の全てを環境中に放出しないことを原則とすることでしょう。それが有機化合物であれば、おそらくほとんどすべてのSDSに記載されていることと思いますが、炭酸ガスと無害化技術が確立しているチッソ・硫黄・リンなどの酸化物に分解される燃焼による中間処理が現実的な方策と考えられます。事業者の多くは産業廃棄物の処理は専門業者に委託されていると思いますが、その時はSDSなどを参考として処理委託物の燃焼時の特性を処理業者に開示することができれば、なお一層好ましいことと思います。
第6回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (6)
7. 化学物質の環境リスクと土壌汚染対策法・廃棄物処理法
今回は表題の二つの法律と事業者の環境リスク管理活動の関係を考えます。どちらも目的が明確ですので、それを念頭に置いて事業者はさらに一歩進めた自主的な環境リスク管理活動を進めることができるのではないのでしょうか。
Ⅰ 土壌汚染対策法
2002年に制定された土壌汚染対策法には、リスク管理の考え方が入っています。「リスク」は「ハザード(有害性)」と「ばく露(摂取)」の組み合わせで見積もられますが、この法律の「ハザード」は土壌中の化学物質による人への健康影響です。環境基準に適合しない汚染状態にある土壌から人の摂取(ばく露)経路があり、健康影響のおそれがあると考えられれば、リスクがあるとしてその汚染区域は「要措置区域」(法第6条)となり対策が求められます。一方、同じ汚染状態でも摂取(ばく露)経路がなく健康被害が想定されなければ、リスクはないとして「形質変更時要届出区域」(法第11条)となり、その状況が維持される限りは対策が求められません。これはそれまでのハザードベースの法規制との大きな違いです。
工場用地内の土壌汚染には様々な原因があります。第一に、古くから使用された工場用地には、土壌中に化学物質の存在が認められることがあります。取り扱いの過程からの漏洩や、古くから使用しているタンク類、特に人目に付きにくい地下埋設タンクなどからは、内容物が周辺土壌への浸透・拡散に気が付かず放置されていることもあるでしょう。第二に、その土地がかつて農地であれば環境中で分解されにくい「農薬」が残留していることもあります。第三には、現在では考えられないことですが、不要物が工場敷地内に埋め立て処分された時もありました。これは土壌汚染対策というよりも、むしろ次に記す廃棄物処理法に関係することですが、自社所有の用地内の処分が黙認されていた時もありました。第四には、海に取り囲まれ火山も多い日本ならではの、誰の責任でもない自然要因による汚染状態もあります。
このように様々な理由で土壌中に存在する化学物質は、大気に気化・飛散したのちに吸入・経口で人に摂取される直接ばく露や、土壌表層から地中への浸透・拡散で地下水に混入し地下水脈下流の井戸から飲料水として周辺住民に摂取される間接ばく露などで、健康被害を引き起こす可能性があります。土壌中、特に地中深くに取り込まれた化学物質は、大気(大気汚染防止法)や公共水域(水質汚濁防止法)への拡散と異なり、その場所に長期間滞留することもあり、その影響は長期間続くだけでなく時が経ってから顕在化することもあります。そのため土壌の汚染は、後日事業者(土地の所有者)には「負の遺産」として残ることがあります。土地所有者(事業者)だけでなく、その前のさらにはもっと前の所有者(事業者)の残した汚染状態も、土壌汚染対策法では現在の所有者は責任を免れることはできませんが、これは第四の自然要因による汚染状態も例外ではありません。
土壌汚染の対策では、これまで記してきたことからわかるように地歴(土地利用履歴)等の調査・遡及で汚染者を特定し、汚染の修復に他の環境関連法と同様に「汚染者負担」の原則を適用しようとすると、その作業に多大な労力を必要とすることがあるだけでなく、それでもわからないままになり、その結果対策が全く進まない懸念もあります。そこで土壌汚染対策法は所有者の責任としながらも、汚染の除去(ゼロリスク化)だけが唯一の解決策となる有害物のハザードベースの規制ではなく、周辺に好ましくない影響が及ばないようにする「ばく露管理」も取り入れたリスクベースの規制になったものと思います。経済的・社会的に合理的な方法で、公共財である土地を有効活用するために、発生源・発生時対策で解決をはかる大気や公共水域の問題とは異なったアプローチを採用したことになります。海外の土壌汚染対策を目的とする法規制の多くもこのような手法を採用していますし、2002年には日本で化学物質排出把握管理促進法(化管法)が制定されており、化学物質をリスクで管理する考え方への認識も進んでいたことで、このような形になったものと思います。
この法律はリスク管理の考え方を取り入れていますが、化学物質審査規制法(化審法)や化管法と同様にリスク評価の主体は行政で、事業者は知事からの指示の下でハザード評価に相当する特定有害物質の土壌環境基準への適合性を判定するために、土壌中の有害物質の含有量や溶出水濃度の測定と報告を行います。
直接ばく露となる表層に近い部分の化学物質による汚染の区域の特定は比較的容易であるだけでなく、盛土や舗装による被覆でばく露防止ができます。仮に汚染土を除去するとしても、その作業は比較的容易でコストもそれほどかかりません。しかし、汚染が土壌の深さ方向にも広がっていれば、平面情報だけでなく深ければ10mを超えることもある地下水位まで汚染の深さ情報を取得する必要があります。さらに掘削除去によりゼロリスク化にしようとすれば、技術的・コスト的に大きな負担がかかるので、国は「ブラウンフィールド化」を懸念して、そのような汚染には汚染物質の掘削除去でなく遮水壁等を設けるなどで、汚染水が周辺地域に広がらない方法なども土壌汚染対策として有効であることを示しています。事業者が将来もその場所で事業を続ける予定であればそのような対策は現実的で経済的にも有利であることは容易にわかります。
事業者が土壌の汚染状況の調査を行うのは、法律に基づく知事からの指示・命令だけでなく、法律第14条の自主的な土壌調査から区域の指定を受けようとすることもあれば、単に土壌の実態把握だけを目的とすることもあります。このような自主的な調査は、事業の発展的な拡大や事業内容の変化に伴っての土地の売却を検討する時や、土地の資産価値を見積もりたい時、あるいは企業の社会的責任を意識した自主的な環境管理活動の一環として行う場合があります。土地の売却を前提とする時には、売り手・買い手の関係の中では有害物の完全除去によるゼロリスク的な解決が求められることもあります。そのような状況になってから土壌汚染の問題に着手するのでは、売却完了までの時間的な制約などから合理的な解決策が選択できないこともあるので、日頃から工場用地の汚染状態の実態を把握し、時間的・資金的に余裕のある平時から少しずつでも対処しておけば、土壌汚染の問題は売り手・買い手の双方にとって好ましい形で解決できるのではないかと思います。
土壌汚染対策法の枠組みを念頭に置いた時に、事業者の自主的な土壌汚染への対応はどのような形になるのか考えます。ここでは「汚染」とはどのような状態かということを決めておく必要があります。土壌汚染対策法の施行令及び施行規則で定めている対象物質は、具体的には揮発性物質である第一種特定有害物質、重金属(化合物)である第二種特定有害物質と、土壌中に残留しやすい農薬の第三種特定有害物質だけです。第一種特定有害物質はベンゼンを除けばすべて塩素化炭化水素ですし、重金属化合物もカドミウムや鉛などの9種類に限られています。特定有害物質の有害性は種類も強弱も様々ですが、共通しているのは長期毒性・がん原性・変異原性などの有害性を持つことで、化学物質にはこのような毒性を持つものはそれ以外にもたくさん知られています。そのような物質を取り扱う施設であっても、土壌汚染対策法の「有害物質使用特定施設」ではないので法律の規制対象とはなりません。しかし、海外でははるかに広範な種類の物質が「汚染物質」とみなされていることや、土壌中の石油系炭化水素の影響評価が国際規格(ISO11540)となっていること、日本でも対象物質が拡張される可能性があること、あるいは工場用地の売買では土壌汚染対策法の枠組みを超えた土壌中の化学物質の測定・分析だけでなく掘削除去等による無害化を土地の購入者が望む可能性もあることを考えると、事業者は現在所有し稼働している工場用地の売却計画の有無にかかわらず、土壌の汚染状態を把握しておくことは将来への備えとして必要であると思います。
Ⅱ 廃棄物処理法
廃棄物処理法では、廃棄物処理の受託業者による環境汚染や保管・処理過程での事故災害の防止を目的にして、委託業者から処理・運送受託業者に危険有害性情報を伝達する仕組みがあります。リスク低減には危険有害性情報を知ることが必須の要件ですし、廃棄物処理業者は受託した廃棄物あるいはそこに含まれる化学物質の危険有害性を事前に十分に知りうる立場にはないので、適切な処理を行うには委託業者からの情報提供は欠かせません。
産業廃棄物の委託業者から受託業者には、「管理票(マニフェスト)」の発行が義務付けられていますし、化学物質に関してはそれとともに「WDS(廃棄物データシート)」の作成・提供が望まれています。マニフェストには産業廃棄物の種類を記載する欄があり、危険有害性の高い特別管理産業廃棄物では詳しい分類だけでなく、有害物質の有無や適切な処分方法を記載する欄や水銀・石綿・特定産業廃棄物の有無を記載する備考欄もありますが、環境影響に注意が必要な全ての「有害物質」について名称・含有率などの詳しい情報を提供する形とはなっていないので、WDSはそれを補完する文書になります。多くの廃棄物は中間処理を経て最終的には埋め立て処分となるので、WDSには埋め立て基準が設定されている「有害物質」を記入するようになっています。この「有害物質」の多くは水質汚濁防止法の有害物質・土壌汚染防止法の特定有害物質でもあるので、処分場から水域や地下水への混入による環境汚染の未然防止が目的の一つであることがわかります。廃棄物処理法の特定有害廃棄物は、土壌汚染対策法と同様にカドミウム・水銀などの重金属化合物、塩素化炭化水素類、特定の農薬類とPCB・ダイオキシン類に限られていますので、環境汚染の防止を考えるうえでは、類似の有害性を持つ化管法や化審法の規制物質についてもWDSへの自主的な記載は好ましいことと思います。
WDSの廃棄物の危険有害性情報を伝える書式のもととなっているのは化学品のSDS(安全データシート)と思いますが、化学品は品質・性状などが定まっており組成も多少の変動はあっても大きく変化はしません。しかし廃棄物では発生の都度、品質・性状や注意すべき危険有害性が大きく変わることもあるので、その作成はSDSよりも難しい作業となることがあるだけでなく、危険有害性をWDSだけで完全に記載することも難しいと思います。そのような理由もあり、書式を提案する環境省は排出者と処理事業者の間のコミュニケーションが重要で、WDSの作成は両者の共同作業となる可能性もあることを「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(環境省)の中で指摘しています。
WDSには廃棄物処理法以外の法規制に関する記載欄が用意されています。産業廃棄物処理業もPRTR報告の対象業種ですので、WDSにPRTR該当の化管法第一種指定化学物質の記載は当然のことですが、爆発性・引火性などの物理的危険性や物理的・化学的性状、品質安定性、混合安定性や消防法・特化則・有機則・毒劇法・悪臭防止法などの関連法規への該否を記載する欄があります。これらは、廃棄物の保管・処理の工程での処理作業者の労働災害が発生していることを考慮してのことです。廃棄物処理では様々な危険有害性を持つ廃棄物が持ち込まれるため、排出業者に比べて化学物質の危険有害性に対する教育が十分には行き届かないこともあるので、排出業者からの危険有害性情報の提供は労働災害の防止の観点からも必要なことと思います。
2013年に実施されたWDS書式の改訂では、「水道水源における消毒副生成物前駆物質」の欄も追加されました。これは水質汚濁防止法の稿でも記しましたが、廃棄物として処理を委託されたヘキサメチレンテトラミンが公共水域に流出し、下流の浄水場の塩素滅菌の工程で分解され、ホルムアルデヒドが発生した事件を受けたものです。残念ながらこのような事例が起きることを予測してWDSあるいはSDSを作成することは実際上不可能といってよいでしょう。まれにしか起きない特殊な事例を想定してWDSやSDSを作成すると、記載事項があまりに膨大になり、本来伝わるべき基本的な注意事項が文書から読み取りにくくなることが危惧されます。事故事例が知られていればそれを記載することもできますが、それでは再発防止にはなっても、未然防止にはならないので、何とも悩ましいかぎりです。この事例のように、化学的に均質な購入残余原料をある程度まとまった量で廃棄物として処理を委託する場合には、その化学品のSDSを処理業者に提示するとともに、その化学品の製造業者に適切な処理方法を確認するといった手順をとることなどで、不測の事態の回避を試みることが必要となるのではないでしょうか。
その改訂以前から、WDSには廃棄物処理法の「有害物質」以外の物質、例えば水質汚濁防止法の「有害物質」や、関連法規として消防法・特化則・有機則・毒劇法・悪臭防止法などの関連事項を記載する欄が設けられていました。このように、WDSは環境リスクだけにとどまらない広範な危険有害性情報を提供する形になっていますが、これにより化学物質による環境汚染だけでなく、廃棄物の処理工程の事故災害の発生防止で廃棄物処理業者での労働安全衛生のリスクを考えることができるようになっています。SDSあるいはWDSは化学物質を取り扱う事業者にとって、労働安全衛生を考えるうえで最も重要な文書であるのかもしれません。ということで、次回からは「環境リスク」を離れて、労働安全衛生リスクの考え方を記したいと思います。
第7回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (7)
- 物理的危険性のリスクアセスメント –
化学物質のリスクアセスメントでは、有害性(人の健康と環境への影響)を考えることが多いのですが、大量にしかも汎用的に使用されている化学物質の中には、有機溶剤のように可燃性・引火性を持つものが多いので、火災・爆発などの物理的危険性(以下単に「危険性」と記します。) のリスクアセスメントも考える必要があります。工場で火災・爆発事故が起これば、事業者は人的にも経済的にも大きな被害を受けるだけでなく、火の手・黒煙・異様な臭気・大きな音などで、周辺住民は不安に思うでしょうし、公設消防や警察の出動もあるので事業者には説明責任が求められることがあるだけでなく、対応が不適切であれば、不信感から事業の継続性が問題とされることがあります。
被害が発災現場周辺に限られる小規模事故でも、事業所内の仲間・同僚である作業者には生命への危険や重篤で不可逆的な障害をもたらす可能性があり、規模が大きくなると人的・経済的影響はプラント周辺や事業所内だけでなく、周辺の市民・住民にも及ぶこともあります。セベソ事故(1976年)やボパール事故(1984年)のように、火災・爆発事故が起因となって広大な周辺地域の環境汚染を引き起こした事例からは、環境法規制の整備につながりました。このように、化学物質の危険性に由来する事故災害は様々な形で影響を及ぼすことがあることを考えれば、有害性と同様に「リスクアセスメント」で効率的・効果的に未然防止をはかることは自然な考えでしょう。
化学物質の健康・環境へのリスクは、有害性の重篤さとアセスメント対象へのばく露量から評価されますが、危険性では引火性・可燃性・爆発性・反応性などの大きさと、それが事故災害になる可能性(頻度・確率)及びその結果生じる被害の大きさで評価します。
リスクアセスメントには様々な手法が提案されていますが、実施の時期と目的あるいは想定する事故災害の規模に応じて選択される手法は変わります。適切でないと手間ばかりかかって効果が上がらないだけでなく、そのために次第に実施すること自体が負担となり、形ばかりになってしまうことや、アセスメントの実施そのものが顧みられなくなることが懸念されます。事故災害が発生すると、利害関係者への説明責任が求められることは世界中のどこでも同じですので、海外の関係会社にも同様の展開を図ることが望ましいのですが、その時には手法に国際性を加味することも必要になるでしょう。以下に紹介する国内の手法が海外への展開に相応しくないということではありませんが、国内とは異なる法規制にはそれに応じた修正が必要となります。
Ⅰ 労働安全のリスクアセスメント
A. JISHA方式リスクアセスメントマニュアル(爆発・火災防止) (中央労働災害防止協会、2016年)
このマニュアルは、プラント全体ではなく、一般的に化学物質を取り扱う作業を主な対象としています。GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)による危険性の分類区分による取り扱い物質の一次評点と、作業の環境や条件により爆発(燃焼)の3要素が併存する可能性を考慮した二次評点から、危険要素発生の可能性の評点(P)を求めます。さらに、異常事態の発生する可能性(頻度)の評点(F)と人的・経済的損失の結果の重大性の評点(S)から求められるリスクポイント(=P*F*S)でリスクを評価します。リスクポイント値から5段階に区分されるリスクレベルに対応して、マニュアルには必要な措置方法が示されています。Pの一次評点はSDS(安全データシート)記載のGHS分類区分によりますが、二次評点とFの決定には、現場の経験・知見や専門家の判断が必要となるでしょう。事故災害につながる異常現象の発生頻度(F)を社内データとして保有していることはほとんど考えられませんし、類似災害の前例があってもその時点で何らかの対策が取られているはずですので、Fは社内外のデータからの合理的な推測となるでしょう。社外の類似事例の原因と結果の解析結果から自社での発生予測を行うこともあるでしょうし、社内で収集したヒヤリ・ハット事例からハインリッヒの法則などを用いて、重大事故の発生可能性を推測することもできるでしょう。このことから、リスクアセスメントは従来から現場で実施されている安全管理活動とは別物ではなく、むしろその延長上に位置付けられるものと理解できます。
B. 化学物質による爆発・火災のリスクアセスメント入門ガイドブック(厚生労働省、2016年)
このガイドブックは事業者による労働安全リスクアセスメントの支援ツールで、(1)化学物質、(2)プロセス・作業、(3)設備・機器の順に設問にYes/Noで答えるチェックフローの形式で危険性を洗いだすスクリーニング手法です。(1)はSDSにあるGHSの危険性項目の確認から始まりますが、混触禁止物質などは「10.安定性・反応性」欄の「反応性」や「避けるべき条件」から、取り扱いの実状を踏まえて関連情報を的確に読み取ることが求められます。生産者の作成したSDSには、必ずしも自社の必要とする情報のすべてが記載されているとは限りませんので、記載内容に不明点があれば、安易に自分で判断せずに発行者に内容を確認する方がよいでしょう。
続く(2)と(3)は、その化学物質の取り扱い方法と関連します。製造手順書などの反応系内の温度・圧力・攪拌状態などの物理的条件や原料・製品の特性を記した文書などからリスクアセスメントに必要な事項を抽出します。一般的には現場化の事前確認で安全性を評価していると思いますが、実際に使用する原料(化学品)の沸点・引火点・蒸気圧などの物性が事前検討結果と合致しているかどうかということの再確認にも意味があります。現場化の際にやむを得ず当初の手順やフォーミュラを変更した部分があり、それに応じたリスクアセスメントが不足していれば、この時点で改めて安全性の確認を行うことになります。チェックフローには危険性確認の代表的な項目があげられていますが、自らの取り扱い方法にあわせて設問の追加も必要になることがあります。危険性の洗い出しにはそのほかにもDOW方式や、プロセスのリスクアセスメントを行うための既存の手法なども利用できます。このガイドブックはスクリーニング手法ですので、許容できない重大なリスクがあれば、さらに詳細な手法のリスクアセスメントが必要になります。
なお、厚生労働省は、このガイドブックを発展させたCREATE-SIMPLEを作成し、さらに2019年に改訂(ver.2)しています。このシステムは事業者が必要事項を入力して、GHSの分類・区分と取扱量情報からリスクレベルを推定します。目的は、取り扱い物質の潜在的な危険性をユーザーが「知ること」、「気付くこと」にありますが、基本的な考え方は「設計基準」に記されているので、事業者はそれを参考に「危険性」と「労働安全」の関係を考えることができるでしょう。
C. プロセスプラントのプロセス災害防止のためのリスクアセスメント等の進め方(技術資料)(労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)、2019年第二版)
本資料では、主反応設備だけでなく、付帯設備や配管・備品などを含めたプラントとしてのリスクアセスメントの進め方を示しています。プラントの関係者の参加を求めていることからわかるように、この手法も稼働中のプラントが対象となります。
STEP1(取り扱い物質及びプロセスに係る危険源の把握)では、”B”のチェックリストに相当する質問票に回答する形で取り扱い物質とプロセスの特性に係る危険源を把握するだけでなく、過去の類似事故事例などから起こりうる災害を確認します。
STEP2(リスクアセスメント等の実施) で、潜在的な危険が顕在化する可能性を持つ事象を、作業・操作や設備及び外部要因の引金事象として特定し、そこからプロセス異常(中間事象)やプロセス災害(結果事象)に至るシナリオを同定します。シナリオごとにリスク評価を行い、リスクレベルの高い順にリスク低減措置を検討し実施するだけでなく、作業者への伝達事項もまとめておくことで、現場でのリスク認識と対応を促すことしています。環境リスクアセスメントなどでは、危険源(ハザード)の特定とその影響の大きさの見積もりまでを「リスク評価」とすることが多いのですが、労働安全衛生法ではそれに続けてリスクの低減化方法を選択することまでを含めて、「リスクアセスメント」としており、この技術資料ではSTEP 3「リスク低減措置の決定」以降の部分がそれに対応しますが、ここでは省略します。
「危害の重篤度」は、労働者の死傷者数・休業日数と生産設備へのダメージ(復旧に要する時間)で見積もり、「危害発生の頻度(可能性)」は何年に一度起こりうるかという見積もりを指標としているので、事業者の持つ知識・経験を踏まえた判断や、類似事故事例の調査報告や現場のヒヤリ・ハット記録なども参考として、可能な限り合理的で信頼性の高い推測が求められるのは、”A”の中災防のマニュアルと同じです。作成者がJNIOSHですので、労働者や事業所への影響が適用範囲になっていますが、使い方を工夫すれば事業所外への影響などのさらに大きな規模の事故災害にも拡張できる考え方が盛り込まれています。
D. リスクアセスメント・ガイドライン(高圧ガス保安協会、2016年改訂)
このガイドラインも運転中のプラント全体が対象となります。高圧ガスは噴出・漏洩で急激な体積膨張を起こすので、発災現場周辺にとどまらず予想以上に広い領域に影響が及ぶ可能性があります。化学物質固有の危険性とそれが火災・爆発につながる可能性であるハザードの特定には、HAZOP、What-If分析、ETA、FMEA、DOW方式、チェックリスト方式などの既存の手法を用います。準備資料には、作業手順書、日常点検の結果、ヒヤリ・ハット活動の報告書、KY(危険予知)活動の報告書、自社および他社の事故情報が例示されており、現場の感覚をアセスメントに活かそうとしていることがうかがわれます。労働災害の重篤度による人的被害とプラントの損害・生産損失の経済的被害の両面から考慮する「影響の重大性」と、事故の発生確率(頻度)とのマトリクスからリスクを見積もります。このガイドラインでは非定常作業のHAZOPを取り上げて説明しているので、高圧ガスの使用の有無にかかわらず、反応の進行とともに反応器内の状態が時々刻々と変化するバッチ反応を主な生産工程とする事業者の安全管理活動の参考になるでしょう。事故災害の原因は設備・機器の不調・不具合だけでなく、ヒューマンファクターが多いこともデータを添えて示してあり、ハード面の整備だけでなく教育・訓練などのソフト面の強化も忘れてはならないことを指摘していることには注意したいと思います。
E. DOW CHEMICAL法
この方式は、米国のDOW CHEMICAL社で開発されました。初めに物質の燃焼熱から求められる物質指数(MF)と、危険性をもたらす可能性のある二種のプロセスの危険指数(共通的:F1、特殊:F2)から評価されます。共通的危険指数(F1)は、対象の工程が化学反応を伴うかどうか、連続式かそれともバッチ式かなどの取り扱いの様式で決まり、引火点、爆発範囲、沸点などの取り扱う物質の物性や数量・圧力・温度などの取り扱い条件で特殊危険指数(F2)が決まります。危険性は、MFにF1とF2をかけて求められる火災爆発指数(F&EI =MF*F1*F2)で評価されます。数値範囲で示される係数F1、F2の選択は、ある程度の経験や専門家の助言などが必要とする場合がありますし、私たちの慣れているSI単位系ではないことなどもあり使いづらい部分もありますが、どのような化学物質の取り扱い方法が危険性の要因となるかということを理解するための参考になるでしょう。F1、F2は、”B”のガイドラインではプロセス・作業の要因(2)に相当します。数値の選択に幅はあるものの簡単な計算で求められる数値(F&EI)から危険性が判断できることはわかりやすく、リスクを相対的に比較して理解しやすいことに特徴があります。安全管理(マネジメント)活動の実践では、現場の作業者の経験・知見を取り込むことで実効性が高まるのではないかと思います。
Ⅱ プラントのリスク評価
ここまでは化学物質を取り扱う現場の作業者への危険性のリスクアセスメントが主体でしたが、ここからは多くの設備や機器が配管等で組み合わされた状態(プラント)のリスクアセスメントです。化学プラントのアセスメントでは単位装置の安全性だけでなく、それをつなぐ配管や装備されているバルブ・継手などの部品類からの漏洩や引火、あるいは装置の運転での人為的なミスや機械的な誤作動なども火災・爆発の要因として考えることになります。事故災害は定常状態よりもプラントの起動・停止作業や修理などの非定常状態で起こりやすいことが知られています。どのような危険性を持つ化学物質が使用されているかということを承知しておくことは当然ですが、それとともに本来プラントの閉鎖系内にあるべき化学物質がなぜ系外に漏出するのか、そしてその誘因は何かということを考えることも事故・災害の予防には肝要です。化学物質の環境への排出は環境規制の法規等で厳しく制限されていますし、通常の化学プラントのプロセスでは、系外への適切な排出方法はフォーミュラ等で定められているでしょう。一般的に化学物質は除害して排出されるので、意図しない漏出や漏洩が正常な取り扱い状態ではないことは明らかです。
F. 化学プラントにかかるセーフティ・アセスメントに関する指針(厚生労働省、2000年 第二版)
昭和40年代後半に、石油コンビナートにおいて相次いで発生した火災・爆発事故を受けて、化学プラントの新設・変更時に安全性の事前評価の手法として策定されたもので、2000年に改訂されました。名称はセーフティ・アセスメントですが、実質的には「リスクアセスメント」と同じです。5段階の手順のうち第3段階の定量的評価で、物質、エレメントの容量、温度、圧力及び操作の5項目にそれぞれ四段階のランク付けと評価点を与え、その評価点の総和から危険性の大小を判定します。危険性を判断する数値の導出が乗算ではなく加算であること、用いる数値が物質固有の値ではなくカテゴライズされた危険性の評点であることの違いはありますが、考え方としてはDOW方式のMF、F1やF2に相当するものといえるでしょう。この指針の対象物質は労働安全衛生法施行令別表第一(危険物)だけでなくそこに例示された物質と同等の危険性(爆発性・酸化性・酸化性・引火性・可燃性)を持つ物質も含めています。化学プラント一般に適用しようとすれば、SDSなどを参考として該否を評価者自身で判断することになります。この手法はプラントの新設計画時の事前評価を主な目的としているので、運転中のプラントには適用が難しい、というよりもプロセスの前提条件を大きく変えないかぎりアセスメントの結果は変わらないでしょう。第4段階では危険度ランクによりプロセスの特性を考慮して、既存の手法を用いてハザードの洗い出しから適切な安全対策を決定するとしています。
G. 危険性評価方法(チェックリスト方式)(全国危険物安全協会、2017年)
本方法は、作成者からわかるようにベースは消防法にありますが、化学物質(危険物)の取り扱い手順で留意することだけでなく、事業所の化学物質の管理体制が適切に組織され、それが確実に機能しているかということを、チェックリストで確認することが骨子となっています。このことは、保安方針に「経営トップの責務」が記されているように、リスクアセスメントはマネジメントシステムと密接な関係を持つことを示していると考えられるので、品質・環境・労働安全衛生その他のマネジメントシステムを持つ事業所では、既存システムに組み込んでリスクアセスメントを実行することの参考となるでしょう。化学物質の管理は、安全担当者や作業取扱者だけの業務ではなく、組織として取り組むべき事項でもあります。チェック項目を見ていくと消防法に限らず、労働安全衛生法、高圧ガス保安法あるいは石災法(石油コンビナート等災害防止法)の要求事項を確認できる形となっているので、事業所の法規制への対応にもつながります。
H. 石油コンビナートの防災アセスメント指針 (消防庁特殊災害室、2013年 第二版)
消防庁は平成6年3月に「石油コンビナートの防災アセスメントの策定指針」を示し、平成13年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災を受けて改訂しました。都道府県の防災計画の策定(改訂)では、これを参考にして実態に応じた石油コンビナートの防災アセスメントの実施を求めています。この指針は直接事業者に何らかの対応を求めるものではありませんが、化学物質の危険性のアセスメントでは、事業者の自主的な活動への参考となる事項も含まれています。
指針は平常のプラント運転状態と地震時の防災アセスメントを対象としていますが、事業者には前者の平常時の運転状態のアセスメントが参考となるでしょう。第4章の災害の発生・拡大シナリオの展開の本文と参考資料1(災害の発生・拡大シナリオの一例)には、ETAによる初期事象と事象の分岐から事故・災害へのシナリオ展開が例示されています。
Ⅲ. 海外で提案されたリスクアセスメントの手法
これまでに紹介した国内で提案されている()手法(DOW方式は除く)ではなく、これからは海外で開発提案されている手法のうち、化学プラントで使われることが多く、これまでに紹介した国内の手法で引用されている以下の二つについて簡単に説明します。
I. HAZOP (Hazard and operability Analysis)解析
チームを作り経験と知識でハザードを特定し引き出す手法です。そのため、チームにはそのプラントの運転の知識と経験が必要になります。設計の意図通りに系内が保持され運転されていることが正常で、そこからの「ずれ」はプロセスの不具合、ひいては事故災害の原因となると考えて、「ずれ」の原因を解決することで事故災害を未然に防止しようとするものです。非定常系あるいは時々刻々と反応系の内部が変化するバッチ式の反応系では、予定の状態への到達の遅れ・早まりも「ずれ」の現象と考えることができます。「ずれ」の有無を見出すことが、不具合を表現することの第一歩ですので、もれ落ちなく拾い出すことが必要で、そのためにガイドワードといわれるリストに挙げられている言葉が使用できます。
このことから、稼働中のプラントに効果的にHAZOPを適用するためには運転経験を持つ人の参加が欠かせないことがわかります。HAZOPは化学プラントの安全確保に用いられることの多い手法ですが、フォーミュラからの「ずれ」は事故災害にならなくても、製品品質に影響を与えることもあるので、安定した品質の製品製造を確実にすることの役に立つでしょう。
J. ETA (Event Tree Analysis):イベントツリー解析)
ETAは、ある事象の安全システムへの影響を考える方法で、事故・災害にどのようにつながるのかを明らかにします。一般的にはプラントは事故災害の防止のために、自動・手動の防護対策を持ち、さらにその防護措置が無効となった時には、非常用の退避措置となりますが、それぞれの対策を成功/失敗に分岐したツリー状に書き下ろし、結果の大きさと分岐(成功/失敗)の確率(頻度)からリスクが判定されます。ETAは反応システム中の単位機器・装置の事象に起因する事故・災害の予測になりますが、複数の機器・装置・配管等が組み合わされたシステムでは、部分的な不具合がシステム中の他のユニットにも影響を及ぼすこともあり、そのような関係はFTA(Fault Tree Analysis)などの解析と組み合わされれば明らかにされるでしょう。ETAは事故災害につながる事象とその対策が対になって理解できる形となっているので、どのような防災措置が必要で、あるいは不足しているのかという点が評価されることで、防災システムを考えることに直結した手法と言えるでしょう。他の解析手法より実施は容易ですが、事象から防護対策へ、あるいは事故・災害へのつながりを適切に見いだすには、多様な立場のメンバーによる検討が必要になるでしょう。
Ⅳ. 静電気のリスクアセスメント
燃焼するもの(可燃物)、燃焼を助けるもの(支燃物)と着火源が燃焼の三要素であることはよく知られていますし、実際に可燃性物質を取り扱う現場では、常に念頭に置かれているでしょう。しかし、目視で確認できる裸火や固定設備の電気開閉器と異なり、静電気はどこにでも発生する可能性があります。取り扱い現場の温度・湿度や気流は絶えず変化するので、不十分な静電気対策の状態でも、「運よく」事故災害につながらなければ、それ以上の対策は必要がないと錯覚することもあります。このような背景から、事業者にとって静電気は最も注意すべき着火源であり、日常的な管理を維持・継続しなくてはならないものの一つではないかと思われます。過去の事故災害の事例や体験からだけでなく、リスクアセスメントで必要にして十分な対策で静電気を着火源とする事故災害の未然防止が望まれます。とは言っても、万全を期すあまりに過剰の対策で作業性が低下して別の事故災害の要因となることも避けたいです。
可燃(爆発)性雰囲気の下で、電荷発生⇒帯電⇒放電⇒着火の流れから静電気火災が起こるので、各段階で可能な限り危険性を低減し、リスクアセスメントからその状態のリスクが許容できるかどうかを判定することになります。
可燃(爆発)性雰囲気の回避は火災の予防に共通する最優先の対策ですが、静電気に限れば、流動液体の流速を低下させることでの電荷発生の抑制、導体や作業者の接地・ボンディングによる帯電防止と除電及び起こりうる帯電体からの放電タイプの理解などが静電気火災の未然防止につながりますが、適切な方法の選択とリスクアセスメントは、「静電気安全指針」(労働安全衛生総合研究所、2007年)や「静電気リスクアセスメント」(静電気学会 大澤敦氏、2020年)などを参考とされることをお勧めします。どちらも技術的な内容の理解には予備知識が必要で、誰でも一読すれば容易にわかるとは言えませんが、着火に至る各段階で静電気の危険性に対する考え方が具体的かつ詳細に書かれていますし、後者は一つの章を費やしてリスクアセスメント事例が記されているので、自社の現場の実態に照らし合わせながら対策を考える参考になるでしょう。
リスクアセスメントの概要は、着火までの各段階のハザードを評点化(可燃性雰囲気形成ハザード;HL1、 帯電・静電誘導ハザード;HL2、放電ハザード;HL3)し、これをかけ合わせることで静電気着火リスクを求めます(HL=HL1*HL2*HL3)。帯電・静電誘導ハザードレベル(HL2)は帯電物体の抵抗率と電荷漏洩の有無で評点(0~4)が変わり、帯電促進要因で2倍に補正されます。放電ハザードの評点(HL3)は放電のタイプで変わり、放電エネルギー密度の最も高い火花放電が最も高い評点の6となっています。可燃性雰囲気形成ハザード(HL1)は、着火性(Explosion Group)と雰囲気形成の頻度(Zone)のマトリクスから評点(0~20)が与えられますが、このリスクアセスメントでは国際規格としての”EC/TS 60079-32-1: Explosive Atmospheres – Part 32-1: Electrostatic hazards, Guidance”と整合させており、海外へのシステム移転はやりやすくなるように思われます。しかし、それにより他の危険性のリスクアセスメント手法との評価の区分に差異が生じているようなので、他のアセスメント手法の中でこの静電気アセスメントを運用するときは、あらかじめ考え方を整理しておく必要があるように思います。
同じことは、ハザードレベル(HL)に危害の大きさ(H)を乗じて得られる危険性のリスク評価についてもいえることで、静電気に限らずすべての要因に関係する危険性のリスクアセスメントの中に静電気を着火源とする危険性のアセスメントに組み込んで全体を考えるときには、危害の大きさの評価は、アセスメント手法との間で整合化を図ることが必要となるでしょう。
最後に、汎用性が高く引火性も高い溶剤などの液状化学品の移送・小分け・溶解などの作業時の静電気対策について記します。安全対策の五原則、中でもパイプ・容器その他の導体部からのアース・ボンディングや、作業者からの除電・アースあるいは加湿などによる作業環境の整備などが重要であることは言うまでもありませんが、それに加えてパイプ移送の先端部を移送化学品中に没入させること、没入させるまでは流速を抑えて帯電を抑制することが有効とされています。この方法は化学品の噴霧帯電の抑制になるだけでなく、支燃物(空気)と可燃物の接触機会を少なくするという意味もあります。静電気リスクアセスメント(2020)の第10章や静電気安全指針の第8章にその記載があるだけでなく、船舶安全法危規則第331条や消防法危険物則第40条の7でも移送液中にパイプ先端が没するまでは流速を制限(1m/sec以下)して帯電を抑制すべきことを規定していることを想起して頂きたいと思います。
静電気対策は危険状態が目に見えないので、注意の「抜け」につながりやすいのですが、目視で確認できる作業を手順に入れることで、他の安全対策の手順を思い出すきっかけとなり、合わせて一層の安全性の確保につながるのではないかと思います。
第8回 化学物質のリスク管理 法規制と事業者の自主的対応 (8)
- 人の健康に直接被害を与える化学物質のリスクアセスメント –
ここまでの健康障害に係るリスク評価は、環境を経由の間接的な影響でしたが、今回は労働現場や消費者用製品などの、近接する発散源からの人への直接的な影響を考えます。環境経由のばく露では主として長期・継続的な遅発性影響を考えますが、直接的なばく露では、短期ばく露からの即時的な影響も考えることが必要です。
Ⅰ. 長期的・継続的な遅発性健康影響
Ⅰ-1. 労働衛生
労働安全衛生法は、労働者の安全管理は事業者の責務で、業務で使用する化学品については事前に物性や安全性などに関して安全教育や訓練を受けさせるとともに、リスクアセスメントを行うことを定めています。
労働者への長期毒性に至る主なばく露経路は、従来吸入(経気道)と考えてきましたが、o-トルイジンによる膀胱がんの発生は、皮膚からの吸収(経皮)では接触部位の障害だけでなく、特定臓器毒性を考えることの必要性を示しました。
厚生労働省が2009年に「健康障害防止のための化学物質リスクアセスメントの進め方」という文書(以下「進め方」と略)を作成していますので、これを中心に化学物質からの労働衛生に関する事業者のリスクアセスメントの要点を考えます。
A.ばく露限界値と作業環境濃度の比較からのリスク評価(判定)
ばく露される労働者の健康リスクを考えるうえで基本となる方法で、「健康影響を及ぼす可能性がほとんど考えられないばく露限界値を作業環境濃度が下回っていれば、健康影響は生じない」と考えます。
労働安全衛生法の特別規則は、作業環境測定を義務付けている物質の測定結果(濃度)が、管理濃度を指標として第二及び第三管理区分に区分される場合では、労働者の健康を守るために作業環境を改善し個人保護具の着用などを定めています。これに加えて、例えば、産業衛生学会の許容濃度や米国ACGIHのTLV-TWAなどの、専門機関が有害性の重篤度を考慮して設定したばく露限界値を作業環境管理活動などに用いることは、自主管理活動です。自主的な作業環境濃度の測定(ばく露評価)では、検知管などの簡易的な方法でも個人ばく露測定でもよいのですが、サンプリングから評価までの一連の手順を定め定期的・継続的に行うことが望まれます。
この方法は判断基準が明確でわかりやすいのですが、混合溶剤や作業の都度異なる化学品(物質)を取扱う現場で、複数の化学物質からの混合ばく露をどのように考えるか、という点に関しては定まった考え方はありませんし、取扱い方法の改善や作業時間の短縮で実質的にばく露量を減少させてもその効果はリスクアセスメント結果に反映されません。また、そのような客観的にばく露限界値として用いる指標が公表されている物質の種類も限られているという制約もあります。
B.ばく露限界値未満の作業環境濃度測定値についてばく露評価を行う場合
「進め方」のp.2には、作業環境測定値が管理濃度・許容濃度・TLV-TWA未満でもばく露評価を行う手法があります。混合物からの複合ばく露は、相加的(Σ作業環境濃度測定値/ばく露限界値)に評価します。異なるエンドポイントで設定された有害性から求められるばく露限界値に対する比を加算で考えることの適否は議論の余地があるでしょうが、上記A.で留保した複合ばく露に対する一つの回答と言えるでしょう。
加算された作業環境濃度測定値とばく露限界値の比を5段階(a~e)に区分して作業環境濃度レベル(WL)を求めます。さらに、労働者が対象の化学物質を取扱う労働時間や頻度から作業時間・作業頻度レベル(FL)を5段階(ⅰ~ⅴ)に区分し、WLとFLの5×5のマトリクスから、ばく露レベル(EL)(1~5)を求めます。GHSの有害性の分類区分から5段階(1~5)の吸入ばく露と経皮(皮膚・眼への接触)ばく露(S)でハザード評価(HL)を行います。ELとHLの5×5のマトリクスからリスクレベル(RL)(Ⅰ~Ⅴ)を求め、Ⅰ~Ⅴはそれぞれ、「耐えられない・大きな・中程度・許容可能・些細なリスク」と表現されます。この方法では、作業(ばく露)時間の短縮や作業場の換気の向上による作業環境濃度の低減がリスク評価結果に反映されます。
C.作業環境濃度測定によらない作業方法・取扱い方法・化学物質の物性からの推定(1)
作業環境濃度測定では、測定方法が確立されていない物質もありますし、同じ作業場で多種類の物質が使用されている場合などでは正確さを求めることが難しい場合があります。そのような場合には「進め方」のp.6の手法を使うことができます。
ばく露評価は、取扱量と揮発性(液体の沸点)・揮散性(粉体の粒度)のそれぞれにポイント(1~3)をつけ、その和から作業者の汚染状況のポイント(0,1)を差し引いて推定作業環境濃度レベル(EWL)を求めます。シフト内の接触時間割合又は年間作業時間から作業時間・作業頻度レベル(FL)を求め、EWLとFLの5×5のマトリクスからばく露レベル(1~5)を求めます。
これとは別に、取扱い化学品(物質)のGHSの有害性分類・区分からハザード格付け(HL; 1~5とS)を行い、ELとHLの5×5のマトリクスからリスクレベル(Ⅰ~Ⅴ)を求めます。各リスクレベルに対して事業者が取るべき対策は、上記B.と同様に考えます。
この方法では、適切なSDSを化学品の購入使用者が供給者から受領していれば、記載事項と自らの取扱い方法を考慮してリスクアセスメントが可能です。
D. ECETOC TRA
欧州化学物質生態毒性・毒性センター(ECETOC)は、ECETOC TRA(Targeted Risk Assessment)をリスクアセスメントのツールとして公開しています。欧州の新しい化学物質規制(REACH規則)に合わせて開発されたもので、取り扱う労働者の健康だけでなく、環境や製品中の化学物質によるリスク評価も目的としています。
REACH規則では化学物質の登録時に必要となるばく露限界値や物理化学的性状が、SDSに記載され化学品の譲渡・販売時に提供されることを前提としているので、受領者は自らの作業工程(プロセスカテゴリー)、作業時間、換気条件などをシステムに入力すれば、ばく露推定濃度が計算され、ばく露限界値と比較してリスクを見積もることができます。厚生労働省と化学物質評価研究機構が作成した労働者リスクアセスメントマニュアル(2016)には、労働安全衛生法のばく露調査で例示される作業とECETOC TRAのプロセスカテゴリーの対応が示されているので、ばく露限界値がわかれば欧州の事業者と同様にわが国でもリスクアセスメントができますが、化学品のビジネス慣行では必ずしもばく露限界値が情報として提供されているとは限らないので、リスク評価ではあらかじめ確認する必要があるでしょう。上記A.で作業環境測定値を有していない場合に、ECETOC TRAによるばく露推定濃度が参考になるでしょう。
E. CREATE-SIMPLE
厚生労働省は次に取り上げるコントロール・バンディングを一歩進めた手法としてCREATE-SIMPLEの改訂版を2019年に公開しました。コントロール・バンディングと比較すると、吸入ばく露では、(1)有害性の指標にばく露限界値を用いること、(2)より少量の取扱量(gあるいはmL単位)にも適用できるようにしたこと、(3)作業条件等(含有率、換気、作業時間等)の改善効果を考慮するようにするとともに、経皮の長期毒性のリスク評価方法を提案しました。許容値などの吸入のばく露限界値が設定できない物質には、GHSの分類区分から管理目標値を設定し、気中濃度からリスク判定を行う方法を提案しています。
これは、欧州の有害性のカテゴリー(リスクフレーズ)にGEV(Generic Exposure Value)を設定する方法に近く、リスクフレーズを使用しないわが国ではGHSの分類区分に対応して設定され、スクリーニング的なリスク評価(Tier 0)には利用できますが、正確さが必要な評価(Tier1.2)では、対象物質の有害性試験結果をもとにした有害性評価値の収集が必要となるでしょう。GHSは急性毒性の半数致死量(LD50など)や特定臓器毒性のガイダンス値のように、数値を基準として区分を行うだけでなく、発がん性や変異原性のように情報の信頼性を基準に区分する有害性もあるので、そのような物質に対してもGHS区分から管理目標値を設定することには少し違和感を持ちます。また、gあるいはmLの少量のスケールで取り扱われる物質の多くは、ドラフト内で秤量・小分け作業が行われることが多いので、工業的規模で取り扱われる手法の延長線上でリスク評価を行うことが適切かどうかを考える必要もあります。
推定ばく露濃度(EHE)は、作業温度による補正を考慮した飛散性・揮発性と取扱量から求めた初期ばく露濃度範囲に、含有率・作業内容・換気状況及び作業時間・頻度及び呼吸用保護具着用の有無による補正係数を掛けて求めます。B.が評点の総和からばく露濃度を推定するのに対して、補正係数をかけて評価する点に違いはありますが、ばく露濃度推定で考慮したい外部要因(ばく露係数)を計算に取り込んで、作業現場の実態を反映させることができますし、外部要因を変えて作業環境を改善しようとする事業者の方策の結果を、リスク評価に反映させることができます。
経皮の長期毒性は使用できるデータが少ないことを考慮して、吸入毒性をもとに体内残留係数と平均的な呼吸量から、経皮の許容ばく露量を設定することとしていますが、吸入の許容量(閾値)も経口ばく露に比べてデータが少ないだけでなく、経口毒性値からの推論で求められているものがあるので、推論に推論を重ねて経皮の長期毒性を見積もることが適当かどうかという点は考えさせられます。
このように考えると、CREATE-SIMPLEは、長期毒性の考え方への新たな問題提起ではありますが、実際には事業者は既存のリスクアセスメント手法との併用を行うことになるのではないかと思います。
F.コントロール・バンディング
英国安全衛生庁で開発されILOでも取り入れられた手法で、労働者へのばく露は化学物質の物性と取扱量から推定し、GHSの有害性の分類区分(ハザード)からリスクを見積もります。厚生労働省のホームページにアクセスし、指定された項目の入力でリスク判定結果ととるべき対策が出力されます。入力項目が少なく化学物質の有害性に詳しくなくてもSDSがあれば実行可能です。しかし、入力項目が限られており、より安全な物質に変更するか、取扱量を減らさなければリスク評価の低減につながりません。実際には事業者はそのどちらも選択できないことが多いので、現在の使用状況を前提に考えられる最大限のリスクを認識し、それを下げるためになすべきことを知るスクリーニング的手法と考えることができます。
Ⅰ-2. 消費者製品のリスクアセスメント
消費者用製品には、容易に化学品と認識できるものだけでなく、プラスチック成形品のように、すぐにはわからない形で添加物を含有するものがありますが、どちらの場合も使用中の化学物質の放出・放散で使用者に健康影響を及ぼす可能性があります。欧州のREACH規則は化学物質登録時に製造・輸入者は想定した使用方法に応じたリスク評価を必要とすることから、消費者製品からの健康影響の評価を目的とする手法の開発が進みました。
消費者製品による使用者の健康リスクの評価は、有害性とばく露(摂取)量から見積もる手順や化学物質の発散源とばく露対象者が近接していることは労働衛生の場合と同じですが、それに加えて消費者製品には次のことへの配慮が必要で、使用の態様は千差万別ですので、それに応じた手法を考える必要があるでしょう。
(a)特に考慮したいこと
① 予期できる誤用・転用
消費者は業務で取り扱う労働者よりも化学物質に対する知識も経験も乏しいだけでなく、労働安全衛生法の労働衛生教育にあたる安全教育を受ける機会もないので、供給者にはそれだけ情報伝達と安全衛生の確保に大きな責任があるでしょう。製造・販売者は意図された目的に相応した使用方法を想定し、取扱説明書や容器・包装上で適切な取扱い方法を使用者に伝えますが、例えば屋外の通風の良い場所の使用が推奨されていても、実際には換気の悪い屋内で使用されることもありますし、効果を高めたいと洗浄剤を過剰に用いることもあります。その結果、想定外に多いばく露量から使用者の健康に障害をもたらすことがあるので、そのような予期できる誤用や転用をも考えたリスク評価が求められます。「混ぜるな 危険」と記されている塩素系漂白剤に他の洗浄剤が混入して有毒ガスが発生した事故も多発しているので、安全情報の伝達にはリスク評価結果を踏まえた、簡潔でわかりやすい方法の工夫が必要でしょう。
② ばく露経路の多様性
労働現場の主要なばく露経路は吸入と経皮ですが、消費者製品では経口ばく露(摂取)も考える必要があります。食品に直接接触する容器・包装資材の添加物質は食品へ移行する可能性があるだけでなく、習慣的・本能的に手を口に持っていく、あるいは何でも口に入れようとする子供や乳幼児用の製品では、経口ばく露の可能性が高くなります。おもちゃ類の化学物質が食品安全衛生法で規制されていることを想起すれば理解できるでしょう。家庭生活用の製品も、床を素手でハイハイした赤ちゃんがその後手指をしゃぶることもあることを考えることも必要でしょう。
③ 個人用保護具
労働現場で化学品を取扱う時は、有害性の有無にかかわらず個人用保護具の着用が原則です。労働衛生のスクリーニング的なリスク評価では個人用保護具の効果は考慮しないことが多いのですが、安全衛生の維持・管理にはどのような場合でも着用が必須です。しかし、消費者用製品を使用する消費者は、有機溶剤などが放散される塗装作業でも呼吸用保護具の着用が習慣化されていないのが実状です。事業者にはそれを前提として安全側に立った製品設計とリスク評価が求められているでしょう。
④ ばく露条件の時間的・空間的変動
労働衛生では、所定の勤務時間中に作業現場でばく露を受けながら勤務を継続したときの健康影響(長期毒性)と、短時間であっても吸入・接触からの急性毒性や皮膚・眼の腐食性や刺激性などを評価します。一方、消費者製品の使用では、同一物質からの長期間・継続的なばく露になることは稀なことでしょう。このように考えると、消費者用製品のリスクアセスメントでは、短期ばく露とそれによる即時的(急性)な健康障害を考えることが重要であることがわかります。繊維製品への添加物質や洗浄で使用された洗剤や柔軟剤が残った衣類の終日着用からの皮膚接触の影響は、生涯にわたる時間軸の視点では短期ばく露と考えることができますが、繰り返し使用される消費者製品では長期ばく露の一種と考えることもできます。長期ばく露のばく露限界値は短期ばく露よりも低いので、それは安全側に立ったリスク評価とも言えます。
現場施工などの例外もありますが、一般に生産現場の作業環境は管理されています。しかし、消費者用製品は様々な形態で使用され、作業環境の多くは管理されないので、そのことを想定して最悪のケースを想定することが必要です。
⑤ ばく露対象の多様性
労働衛生の対象は作業現場の労働者ですので、特別な場合を除いて健康上の弱者への影響は考慮しません。しかし、不特定多数の消費者用製品の使用者の中には、小児・乳幼児・妊婦・高齢者などの健康上の脆弱な集団のこともあります。有害性評価値からのばく露限界値の導出ではそれを考慮した安全係数を用いることになります。
(b)消費者製品からの化学物質のばく露評価方法
消費者製品のリスク評価でばく露評価を正確に行うことは難しい課題です。作業環境測定や個人のばく露測定が行われることはほとんどないので、製品の標準的な取扱い方法を想定して推測することになります。「消費者製品のリスク評価に用いる推定ヒトばく露量の求め方」(製品評価技術基盤機構)(以下「NITE」と略)や「ConsExpo」(RIVM)などの公表されているシステムに、必要なパラメーターを入力して計算することができます。ここでは、これらのシステムの利用に際して、事業者が用意しておきたい情報を整理したいと思います。
① 吸入ばく露の評価
NITEの方法は、European Union Technical Guidance Document (EU TGD) 2nd Edition Part1 (European Commission 2003)のAPPENDIX Ⅱ 3.1.1 Inhalation exposure をもとにしています。平均空気中濃度、呼吸量、取扱い1回あたりのばく露時間、1日あたりの使用回数から得られる摂取量に体内吸収率を掛け、これを体重で除して吸入ばく露量(mg/kg/day)を求めます。体内吸収率はデータがなければ100%とします。消費者製品の使用時の平均空気中濃度の実測値がなければ、使用製品重量、対象化学物質含有率、空間体積、換気回数、ばく露時間などのばく露係数と、製品からの揮発性、放散速度、蒸気圧などの対象物質の特性に依存するパラメーターを用いて、製品からの放散様式に対応した式で計算されます。
ConsExpoも同様のパラメーターを用いて計算されますが、使用温度の考慮もできるとともに、製品のカテゴリー入力でデータが入力されなければ、予め設定されたデフォルトのばく露係数で計算が進められます。製品カテゴリーごとのデフォルト値が設定されている点は、他のばく露経路からの推定ばく露量の計算でも同様です。
② 経皮ばく露の評価
NITEの方法は、「ConsExpo4.0 Consumer Exposure and Uptake Models Program Manual」(RIVM 2005)をもととしており、経皮ばく露量(mg/kg-bw/day)は、皮膚に接触した製品体積(接触面積x接触層厚)に対象物質濃度(mg/cm3)を掛けた対象物質の接触量に、1日あたりの使用回数、皮膚を経由する移行割合、体内吸収率を掛け、体重で除して求めます。体内吸収率はデータがわかっている場合を除いて100%とすることは吸入ばく露と同様です。経皮吸収速度がわかっていれば、経皮ばく露量はばく露身体面積と経皮吸収速度、ばく露時間、1日当たりの使用回数を掛け、体重で除して求めることもできます。
ConsExpoで用いるパラメーターは、接触(付着)面積、皮膚透過率(速度)、重量割合・濃度、使用量、使用時間、付着量、接触時間、浸出割合、拡散係数、接触時間、水-オクタノール分配係数等です。
③ 経口ばく露の評価
NITEの方法は②と同様に、基本的にConsExpoと同じです。食事で口内に入れた物質はすべて体内に摂取されると考えますが、非意図的な摂取では体内に取り込まれる割合(摂取率)を設定する点に違いがあり、習慣的に口にする、あるいは舐めることが考えられる便箋の封や切手等の接着剤やのりが付着する製品を挙げていますが、乳幼児・小児用の玩具も同様に考えることができるでしょう。欧州REACH規則の制定で化学品の製造・輸入者に要求されるリスク評価の概要を説明したEU TGDには、非意図的な経口ばく露の例として、口腔内ケア製品・玩具なども挙げられています。
経口ばく露量(mg/kg-bw/day)の算出に使用されるパラメーターは、製品(食物)重量・対象化学物質含有率・非意図的摂取率・使用頻度・体内吸収率と体重で、体内吸収率は特にデータがなければ100%とする点は、これまでの吸入ばく露や経皮ばく露と同じです。市民生活で、非意図的な化学物質の経口摂取で最も関心が持たれるのは、食品(食材)の容器・包装材に含まれる化学物質の内容物への滲出・移行で食事からの体内摂取でしょう。
NITEの方法は、容器・包装から内容物への、移行速度と接触時間の積、あるいは移行率を用いていますし、ConsExpoでは、容器・包装材料(材質・厚み・接触面積)、製品とその可食部分の量、移行速度とのべ接触時間をパラメーターに使用します。
(c)リスク評価の考え方
一般に有害性の重篤度はGHSの区分で考えますが、これは影響量依存性だけによっているものではありません。NITEとConsExpoでは、リスク評価は有害性評価値と推定ばく露量の比較でリスク評価しますが、”mg/kg-bw/day”の単位で有害性評価値と推定ばく露量を表現できるのは、長期毒性では反復投与試験からの特定臓器毒性や生殖発達毒性などです。
Ⅱ. 短期ばく露からの即時的有害性
Ⅰは長期・継続的なばく露による健康影響のリスク評価の手法でしたが、化学物質の刺激性・腐食性などで、労働者や消費者は短期のばく露であっても、即時的・局所的に健康上の好ましくない影響を被ることがあります。
Ⅱ-1. 労働衛生での短期ばく露からの健康影響
労働現場では眼や皮膚の薬傷が絶えません。化学物質による健康障害の80%に近い発生件数で、多くは短時間あるいは非定常作業で起こっています。眼や皮膚への刺激性・腐食性による健康障害は、長期毒性からの健康障害に比べて重篤度は低い、すなわちリスク評価結果は相対的に低くなりがちですが、失明等の不可逆的な障害に至ることもあるので軽視できません。長期毒性の箇所で記したGHSの分類区分に基づくハザード評価(格付け)”S”は、経皮の即時的な有害性(腐食性・刺激性)をあらわしていると言えるでしょう。
化学品の危険有害情報は、SDSで伝達されることが一般的で、発行者には最新の情報をもとにした適切な内容の記載を、受領者には有効な活用が望まれます。眼や皮膚の健康障害の原因物質の取扱いでは、労働安全衛生法は施行規則や特別規則で保護具の着用を定めています。対象物質は告示(基発第0811002号 平成15年)にありますが、多くのSDSの法規制欄にはこの告示の記載がありません。刺激性や腐食性を示すピクトグラムもあり、有害性・取扱いの注意欄には関連の記述がありますが、一般的な化学品の取扱い方法と変わらない定型語句なので、告示による格別の注意喚起は伝達されない懸念があります。前述のとおり、すべての化学品の取扱い時には習慣的に保護具を着用すべきですが、厚生労働省の告示に関する記載があれば、一層の使用者への注意喚起となるでしょう。SDSの法規制欄には、法・政令・省令までの記載が一般的ですが、告示その他の具体的な事項の記載を考慮することも一つの方法と思います。
Ⅱ-2 . 消費者製品からの短期ばく露による健康影響
消費者製品から使用者への化学物質による健康影響を考えるうえで、一般的にばく露が短期であるだけでなく継続性も無いので、リスクアセスメントの手法にはなじまない側面があります。スプレー製品や塗料・接着剤からは吸入ばく露、洗濯・清掃用の資機材の含有物質や繊維処理剤からは経皮のばく露だけでなく、食品からの意図的なあるいは特に小児・乳幼児にみられる非意図的な経口ばく露など、想定ばく露経路は多岐にわたります。米国では、子供が鉛製の子供用のアクセサリーを飲み込んで死亡する、という事故も起こりました。
リスクアセスメントの手法のConsExpoが、”mg/kg-bw”の単位で出力するばく露限界値は、半数致死量で評価する急性毒性と、単回投与の特定臓器毒性に適用されますが、眼や皮膚の刺激性・腐食性や感作性の指標とはなりません。急性毒性物質を含有する消費者用製品もありますが、想定される使用形態で健康障害を引き起こす量(割合)で上市されることも無いでしょう。小児や乳幼児の事例を除けば、多くは供給者の想定外の誤用・転用がその原因となることが多いこともうなずけます。想定可能な誤用と想定外の誤用の区別の客観的な基準は無く、ばく露シナリオを思い描くことも難しいので、過去の事例などを参考として供給者は事故を想定することになります。消費者製品による健康障害の予防と消費者への注意喚起は労働現場の短期ばく露の場合と同様に、ハザードベースの記載になるものと思います。
2018年の改正食品衛生法は、食品に直接触れる可能性のある熱可塑性合成樹脂製の容器・包装材料の規格基準を、使用制限(禁止)物質を示すネガティブリスト方式から、許容する物質を定めるポジティブリスト方式に変更しました。これは1970年代から、厚生省(当時)の指導の下で、熱可塑性樹脂を製造・使用する業界団体の設置した三衛生協議会が、安全性試験の実施や、国内外の安全性情報の収集・精査から、順次追加補正しながら運用してきたものですが、2018年の法改正はこれを取り入れたものです。
最後に、事業者による化学物質の自主管理の意味を、法規制と対比して考えます。
①リスクベースの化学物質の管理
環境経由のリスク評価では、広域の環境情報を持つ国が主導的に進めますが、近接した発生源からのばく露対象へのリスク評価には、事業者の持つ用途や使用方法に関する情報が必要です。化学品(物質)が身近であればあるほど、リスクベースの管理には、事業者の関与が欠かせないと言えるでしょう。
②化学物質管理の目的と手段の整合
法規制は、社会的な強制力や信頼性があり、環境側面ではリスク評価(国)とリスク管理(事業者)の役割分担で妥当性が検証されてきた実績があります。一方で、法整備には時間が必要で、時宜を失することもあります。製品や事業形態の特質の違いは幅広く、一律の規制で実施が困難な業態を配慮しすぎると効果が薄れますし、法は遵守されることで効果を発揮するので、遵守できない(実施が困難な)規制は無いに等しくなるという側面をもちます。
これに対して、自主規制は制度の整備に時間がかからない、事業者(団体)の業態に即した現実的な取組が可能であるだけでなく事業者が自らに課した規制なので、制度の維持整備のインセンティブになることなどのメリットがある反面、制度を設計した事業者(業界団体)が社会的な信頼を得ていないと、活動自体が信頼されないことで活動の減衰・停止となるおそれもあります。
このように、法規制と自主管理にはそれぞれの得失がありますが、多様な使われ方をする工業製品(化学物質)のリスクベースの安全管理では、事業者の果たす役割がこれからも高まっていくでしょうし、そのためには事業者は社会的に信頼される存在となることが求められているでしょう。