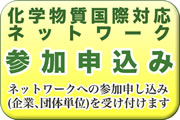企業に求められる化学物質管理活動-法規制と企業の自主的な管理活動-
- このコラムは、化審法(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を指す。以下同様。)見直し合同委員会のメンバーでもあった北村卓氏に、化学産業界の第一線で過ごされてきた豊富な経験に基づき執筆をいただいたものです。
- このコラムに記載されている内容に関し、法的な対応等を保障するものではありませんのでご了承ください。
- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
→ご意見・ご感想電子メール送付先:
化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@env.go.jp)
目次
- 第1回 化学物質の法規制とは
- 第2回 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
- 第3回 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
- 第4回 労働安全衛生法(安衛法)
- 第5回 化管法(PRTR制度)
- 第6回 SDS制度(1)
- 第7回 SDS制度(2)
- 第8回 消防法
- 第9回 大気汚染防止法、水質汚濁防止法
- 第10回 土壌汚染対策法、廃棄物処理法
第1回 化学物質の法規制とは
1) はじめに
世界的に化学物質の安全管理に関心が高まる中で、1992年のリオデジャネイロ環境サミット以来、化学物質の規制は既に法制度を持つ先進国ではハザードベースからリスクベースに変化していますし、途上国もこれに倣って法制度の整備を進めています。法規制は強制力が強く、違反して処罰されれば事業の継続が難しくなることもあります。反面、法の規制は社会に対する影響も大きいので次のような制約もあります。
① 未規制の物質に起因する事故災害が認められてから、その物質が規制対象に追加される「後追いの規制」になりがちである。
② 規制対象とするには、事故災害との因果関係の科学的な証明が求められるので適用が遅れがちとなる。
③ 多くの事業者が遵守可能で現実的なものであることが求められる。
④ 多様な業種や取扱い方法が対象となるため、詳細な部分を定めることが難しい。
このような理由から、化学物質を取扱う企業にとって、法の遵守だけでは、化学物質に起因する事故や災害の未然防止には十分でないことがわかりますし、上のような制約から規制をどんなに強化してもそれは変わらないでしょう。法の規定は最低限の基準を示したものにすぎないので、企業の自主的な管理活動の必要性は高くなっています。
世界各国・地域の化学物質に対する法規制は、それぞれの国や地域が抱える喫緊の課題やポリシーの違いを反映するので決して一様ではありません。時として自国産業の保護・育成の手段に用いられることもあります。本連載では、国や地域によって違いのある法規制を日本の法制度と比較しながら、企業の対応における課題を考えたいと思います。
日本では多くの法律が独立した体系で化学物質を規制しているので、全てに遺漏なく対応することが実務的に難しくなっています。気が付かないうちに違反状態となることもあるでしょう。事業の多様化が進めば、それまでよりも広い範囲の法規制への配慮が求められるようになります。そのためコンプライアンスに関わる専門家を確保し、必要な部署に必要な人員を配置することが難しくなっているだけでなく、担当者も対応に日々追われているのが実状でしょう。
化学物質の法規制というとまず考えるのは、各国・地域で整備が進んでいる化学物質の登録制度です。多くの国や地域で、化学物質の製造・輸入のために予め物質の登録が求められるようになってきました。その物質がその国や地域で取り扱えるかどうかという点は確かに大きな問題で、登録ができなかったり大きく遅延したりすることで、事業に大きな影響を及ぼします。また国や地域によって異なる登録の手続きとその煩雑さは規制の仕組みを理解していないと煩わしいものでもあります。しかし、一般的には一度登録が済めばその後は製造・輸入が継続できるので、同じ作業に悩まされることはないでしょう。それに対して、化学物質の持つ特性、特に人の健康や環境に対する有害性にもとづく規制は、新しい知見や社会の関心の強さによって常に影響を受けますし、規制は厳しくなることはあっても緩和されることはほとんどありません。そのような理由から、筆者には化学物質の登録制度よりも環境規制・安全規制の方が、事業に対する影響が大きいように思われます。このような規制では強化されるときにその都度対応を考えるよりも、先手を打った対応を考えるほうが結果として効率的になることもあります。それは自主的な対応の場合もありますし、日本を含んだ先進国の規制への対応を途上国で先行して実施することもあります。将来的にその国や地域で法規制がどのような方向に変わっていくのか考えておくことは好ましいことと思います。
日本企業がまず考えなければならない日本の法規制の中には、世界的な制度とは異なった仕組みのものもあり、日本での法令遵守の手法だけでは、海外での有効な解決策とならない場合もあります。そのため、日本の法規制の基本的な考え方を理解し、それが海外の法規制対応に有効であるのかどうかを考える必要があります。類似する法規制への対応でも、日本国内で行った対応が必ずしも海外でも通用するとは限らないのです。
法令違反は企業の経営リスクとなります。該当する法令の条文を十分に読みこなすことが必要であることはいうまでもありませんが、条文は慣れていないと読みにくいこともあり、理解しづらいこともあるでしょう。法規制への対応では、細かくそして多くの場合は読みにくい法律の条文の解釈だけにとらわれて思い悩むよりも、原点にかえって規制に至った背景や法律の目的や構成を知ることが、より深い理解の助けとなり現実的な解決方法を見出すことにつながることもあります。しかし、国内の法規制ですら、制定から時間が経過したり改正が度重なったりしている場合は、そのような歴史的な背景は伝承されないこともありますし、まして海外の法律ではその背景などはなかなかわからないことがあり、適切な判断が難しいことがあります。それでもグローバルな規制の方向と国や地域の課題を関連付け、さらに日本国内の法規制対応がどのように応用できるのか、という点を考えておくことは、企業の安定した海外事業のためには必要であるように思います。
このコラムでは、そのような動きの中で、地球サミット以来重要性が指摘されている自主管理活動をどのように位置付けることができるのかという点についても考えてみます。
2) 化学物質を規制する法律の仕組み
日本では多くの法律が化学物質を規制していますが、そのおおまかな仕組みを知ることは法律を理解するだけでなく適切で効果的な対応を容易にします。
化学物質の法規制の仕組みは、
① 特定の化学物質をリスト化し、その物質あるいは含有する製品を規制の対象とする。
② 危険有害性のクライテリアを設定しそれに合致する化学物質(製品)を規制の対象とする。
という方法に大別されるでしょう。二つの手法を組み合わせることもあります。これまでは化学製品(化学品)に含まれる化学物質のみを対象とすることが主流でしたが、近年は成形品中の化学物質も規制対象とされることがあります。そのため化学企業以外の企業も、化学物質の規制を無視することができなくなっています。
① 特定の化学物質を対象とする規制
毒物及び劇物取締法(毒劇法)・労働安全衛生法・化学物質排出把握管理促進法(化管法)などの多くの法律がこれにあたります。化学品を購入し使用する企業は、含有化学物質を知ることで対応の要否が判断できます。ここにあげた三つの法律はSDS(Safety Data Sheet;安全データシート)などで対象物質に関する情報の販売先への提供を義務づけているので、対応に不都合は生じないはずです。しかし、それ以外の法律の規制物質や海外の法律への対応では、対象物質にSDS等による告知義務があるとは限らないので、必要があれば購入先に問い合わせて確認することになります。特に消費者用製品に対して含有物質の規制がある場合には、社会的影響が大きく、製品の回収や代替品の開発や提供で対応が困難な場合もあるので、注意が必要です。製品分野を限定せずに成形品全体に規制を拡張した欧州のREACHが、わが国のサプライチェーンにも大きな影響を与えたことは記憶に新しいところですが、その傾向は世界に広がろうとしています。
② 特定の危険有害性のクライテリアに合致する場合の規制
消防法化学品や輸送に関係する船舶安全法の危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)・航空法などがこれにあたります。化学物質による健康影響だけでなく環境影響や火災・爆発などの物理的危険性にも配慮すると、このタイプの規制になるようです。規制への該否は原則として化学品の有姿としての試験結果からの評価によるので、該否の判定では混合物化学品と単一物質化学品との間に区別はありません。海外の規制法規と違いのある消防法と異なり、危規則や航空法の該否判定方法は海外の輸送法規とほぼ整合しています。物理的危険性の試験方法は国によって異なることがあるので、測定値の微妙な部分が気になるのであれば試験方法の確認が必要になります。法規制ではありませんが、世界的に普及が進んでいるGHSもこのタイプに分類されるでしょう。
このように化学物質の法規制は二つのタイプに分けられますが、①のタイプの毒劇法・労働安全衛生法・化管法に、危険有害性のクライテリアで判断する②のタイプのGHSが取り込まれているので、これらの法律への対応では両方を考慮することが必要となることもあり複雑な作業になります。GHSは法規制というよりも企業の自主管理活動に近い性格をもっていることが、その原因の一つであるように思いますが、その対処法はそれぞれの法律の項で考えたいと思います。
第2回 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
我が国の化学物質を規制する法律では、毒物及び劇物取締法が最も古く、1912年(明治45年)の「毒物劇物営業取締規則」に始まります。当初から製造業・輸入業が届出制、販売業が許可制となりました。1947年(昭和22年)に「毒物劇物営業取締法」となり、販売業では事業管理人を置いて、その事業所における毒物又は劇物の取扱いに関する業務を管理することが求められるようになりました。1950年(昭和25年)に名称が現在の「毒物及び劇物取締法」(毒劇法)となり、製造業・輸入業は厚生労働大臣、販売業は都道府県知事への登録制で、販売業者に加え、製造・輸入業者に対しても、資格を持った毒物劇物取扱責任者を置くことが求められ、規制対象になりました。[1]
毒劇法の目的は「保健衛生上の見地から必要な取締を行う」ことですが、毒劇法には海外を含めて他の化学物質を規制する法律とは異なった特徴を見ることができます。
第一の特徴は、法の歴史からわかるように販売行為に関する規制です。販売事業者は、販売時の記録を作成・保管し、購入者(譲受人)には譲受証の発行が定められています。この規定は、偶発的な化学物質による事故災害だけでなく、意図的な誤用・悪用の防止にもつながります。現在世界的な広がりを見せている、サプライチェーンを含めた化学物質の管理につながる考え方に近いといえるでしょう。海外では類似の販売行為に明示的に規制を定めている例は少なく、中国の猛毒化学品に対する規制(危険化学品安全管理条例)があげられるくらいでしょう。[2]
第二の特徴は盗難や紛失を防ぐための、施錠管理、非対象物質との区分管理や在庫・使用量の定期的点検などです。毒物・劇物はその判定基準[3]に従えば半数致死量(経口)が成人で数g~20g程度と見積もられるので、少量の紛失からも重大事故や事件につながる可能性があります。汎用的な溶剤が劇物である場合には、貯蔵数量やバッチ式の反応で一度の使用数量が数十トン以上になることもあり、さらに蒸留・回収・再使用などの複雑な工程を経ることもあるので、上記の半数致死量に相応する量までの厳密な在庫管理は技術的に困難な場合もありますが、少なくとも事業者はそのような管理が可能となるシステムを事業所内に構築・運用しなければならないと考えることができます。また、考慮すべき量としては、桁は異なりますが、原材料の在庫管理はコスト管理や放出抑制による環境管理にもつながります。漏洩・流出を防止するための施設・設備・容器あるいは運搬方法に関する基準などは、消防法などの基準とも重なる部分がありますが、取扱者の安全衛生の確保だけでなく、毒劇法の視点からは在庫管理を適切に実施することが求められ、漏洩・流出を放置することは不適切な在庫管理につながると考えることができます。
第三の特徴は、急性毒性及び、腐食性/刺激性という限られた健康有害性をもとにした判定基準から毒物・劇物が指定されることです。いうまでもなく、この判定基準に合致する物質の全てが指定されているわけではありませんし、判定基準から外れていても社会的な影響の大きさから劇物に指定されることもあります。かつては人の生死にかかわる急性毒性が化学物質の健康有害性にかかわる最大の関心事でしたが、現在では、ばく露された個体(人)が死に至らなくても、発がん性・生殖毒性・変異原性などの特定の臓器に重篤な影響をもたらす遅発性の毒性や次世代に及ぶ可能性のある影響についても考慮するようになっています。我が国ではそのような有害性に関する規制は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)や労働安全衛生法(安衛法)などに委ねられていますが、海外では化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に示される健康有害性を総合的に考えるようになっているので、毒劇法のような特定の健康有害性にかかわる化学物質の法規制の形が途上国を含めてこれからも世界に広がることはないように思われます。
毒劇法は、法の目的を達成するために事業者の自主的な規範として、「毒物劇物危害防止規定」の作成を勧めています[4]。厚生労働省が公開している書式はどちらかといえば取り扱う作業者への健康影響の未然防止に重点が置かれているように見えますが、海外事業所でも同様に危険有害性を持つ化学物質の管理を進めるのであれば、労働安全衛生管理システム(OSHMS)に危害防止規程の考え方を組み込むことが現実的でしょう。国内では既に多くの事業所がマネジメントシステム(MS)の仕組みを取りこんでいるので、海外展開に同様の仕組みを適用することは、それほど難しい問題ではないと思います。毒劇法が早い時期からMSに近い考え方を取り入れてきたことは注目できます。特に重大でない限り事故災害事例が公表・報道されることはないので、実際に海外事業所で化学物質に起因する事故災害が発生した場合に、事業者が法律的・社会的にどのような責任を問われるのかは推測の域を出ませんが、国内の事例を参考にすれば、重大事故や災害の発生で事業者は経営上の大きな痛手を被ることになるでしょう。そのような場合にも、適切に運用されている労働安全衛生管理システム(危害防止規程など)を持っていれば、事業者としての安全配慮への努力が認められ過度に事業者責任が問われることが抑制できるかもしれません。
毒劇法は、毒物・劇物を定めた場所に施錠して管理するとともにそれ以外の化学物質(品)からの区分を求めています。多くの種類の化学物質(品)を取り扱う立場、特に大学や企業の研究室などでは、毒物・劇物と同等以上の急性毒性を持つ物質を使うことも多いのですが、これらをどのように管理するのが適当なのか工夫が必要でしょう。毒性物質が法規制によって毒物・劇物とその他の物質のように区別されていない国や地域では、結果として事故災害のもととなれば、事業者の責任は同一視されるので同等の管理が必要となるでしょう。
毒劇法は化学物質把握管理促進法(化管法)や安衛法とともにSDSの配付を義務付けているので、法規制とGHSの関係を考えたいと思います。化学品による危険有害性からの影響の最小化を目指して、リオデジャネイロの環境サミット(1992)で採択されたアジェンダ21以来、危険有害性を関係者にわかりやすく理解できる形で周知するとともに、世界各地でその仕組みを調和させていこうとする活動が始まり、ラベル等の表示やSDS等で危険有害性情報を提供するときにGHSの利用がされています。
GHSの基本的な枠組みは国際連合やその他の国際機関で構築されますが、実際にそれを使うのは化学品の製造事業者であり使用事業者です。化学品を含めて工業製品は自由に世界中を移動する時代ですので、化学品を規制する仕組みを持たない国や地域にも出荷されることもありますが、その場合でもGHSにもとづいたSDSやラベルであれば、安全を確保するために化学品の危険有害性情報の伝達と理解が進むことが期待されます。
GHSの仕組みは着実に世界に広がっており、ラベル表示から化学品の危険有害性の概要がわかるようになっていますが、一方で既に法規制のある国や地域では、事業者はGHSに基づく表示とともに法の要求に応えることが必要となります。法規制の根拠とされる危険有害性データは、国や地域によって異なることもあり、同一の物質であっても危険有害性の分類・区分が事業者によって異なることもあります。したがって、既存の法規制への対応がGHSによる化学物質の危険有害性の判定結果とは異なることがあることも承知しておくことが必要でしょう。このような事例は、このコラム連載の中で考える法規制に則して、その都度触れますが、今回は毒劇法に関係する部分を記します。
毒劇法の「医薬用外毒(劇)物」の表示が求められる毒物・劇物の判定基準はそれぞれGHSの急性毒性の区分1、2及び3に一致していますが、毒劇法ではそれ以外の要因も考慮して指定するので、区分1、2及び3に使用される「どくろ」マークが必ずしも「医薬用外毒(劇)物」の表示に対応するものではありません。混合物製品に対してはGHSでは、急性毒性は加算式を用いて判定するのに対して[5]、毒劇法では調剤規定に従うので[6]、判定結果には食い違いが生じやすくなります。これまでの事業者の関心は、法規制に違反しないことやそれによる刑事・民事的な罰を受けないこと、行政処分を受けないことなどありましたが、これからは、社会的責任として、製造・輸入・使用・輸送・廃棄など、全てのライフサイクルでのリスクアセスメントを自主的に実施することが求められるようになるでしょう。そのときには、GHSで表示される危険有害性と化学品の物理的特性などを用いたリスクアセスメントが世界各地で求められるようになると思われます。
[1] 各法令の出典は次のとおり:
毒物劇物営業取締規則
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788083/62(国立国会図書館)
毒物劇物営業取締法
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/
00119471218206.htm(衆議院)
毒物及び劇物取締法
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/009/0512/00912070512008a.html(国会会議録検索システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html(e-Gov)
[3] 毒物劇物の判定基準:毒物:LD50:50mg/kg以下、劇物:LD50:300mg/kg以下
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/kijun.pdf(国立医薬品食品衛生研究所)
[4] 毒物劇物危害防止規定について
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/51520_1332107_misc.pdf(岡山県ウェブサイト)
[5] GHS第3.2章 皮膚腐食性/刺激性 3.2.3 混合物の分類基準 表3.2.3
[6] 毒物劇物の判定基準
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/kijun.pdf(国立医薬品食品衛生研究所)
第3回 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
わが国は世界に先駆けて化審法で新規化学物質の事前審査制度を導入しました。この制度は、インベントリーに収載されていない新規化学物質の上市を予定する事業者に、安全性の審査のために危険有害性(ハザード)データなどの提出を求めます。この制度を円滑に進めるためには、制度の施行時までに事業者からの情報をもとに、国(地域)は流通する化学物質を網羅しなければなりませんが、それには事業者が化学品に含有される化学物質を特定できることが前提となります。化審法は昭和43年(1968年)の米ぬか油に混入したポリ塩化ビフェニル(PCB)による健康被害を契機として、昭和48年(1973年)に制定されましたが、40年以上も前で現在のようにはコンピューターの普及していない時期に、そのようなデータを集約してインベントリーを作成することは大変な作業であったでしょう。米国のTSCA(1976年承認、1977年発効)など、海外でもこの制度を導入していますし、化学物質の危険有害性に対する関心の高まりから、途上国を含め同様の制度の導入が進んでいます。
この制度が人の健康と環境を守ることにどのような効果があったのかという点の検証は難しいのですが、社会の要求に応えて科学技術が進歩するに従って、新たな機能を持つ多種多様な化学物質が求められ、そのために新規物質が開発されている現状を見れば、無秩序な新規物質の開発からの人の健康や環境への好ましくない影響の未然防止に何らかの形で寄与してきたと考えることができるでしょう。
もし、新規化学物質が難分解性で高蓄積性であれば、法律の仕組みからは「監視化学物質」となりますが、実際にはその段階でがん原性試験などの長期毒性試験の実施が求められ、それには多額の試験費用と長期の試験期間が必要になるだけでなく、その結果長期毒性を有することが明らかになれば、「第一種特定化学物質」となります。さらに、長期毒性試験からは何らかの有害性が認められる可能性があるので、事業者が事業化を断念して届出を取り下げることで、難分解性で高蓄積性の新規化学物質は、毒性試験の結果を待たずに事実上製造・輸入ができなくなります。このような仕組みで、化審法は毒性が明らかとなっているかどうかにかかわらず、長期間の環境からのばく露で人や環境(動植物)に悪影響を及ぼすおそれのある、難分解・高蓄積性の新規物質が国内に流通することを抑止してきました。
化審法は既存の化学物質に対しても、物質固有の性状をもとに製造禁止や制限の措置を取ることができるので、基本的な化学物質規制の性格を持っているということもできますが、海外の類似制度とは異なる点があります。化審法は制定の背景を反映して、人や動植物に悪影響を及ぼすおそれがある化学物質による環境経由の汚染の防止を目的としますが、海外では環境を経由するか否かと問わずに、人の健康や環境(動植物)への好ましくない直接的な影響の防止をも目的としているものが大勢です。海外で新規化学物質の登録を計画する日本企業はその違いを知っておくことが海外制度の理解になるでしょう。
最初の改正(昭和61年; 1986年)では、高蓄積性ではない物質も難分解性で長期毒性が認められれば第二種特定化学物質として規制対象となり、予備軍は「指定化学物質」とされました。二回目の改正(平成15年;2003年)では、OECDから「生態系保全」の考え方を導入すべきという勧告をうけ、動植物への影響を考慮した「第三種監視化学物質」の制度が新設されました。直近の第三回改正(平成21年;2009年)では、難分解性ではない化学物質も人健康又は生態のリスクが十分に低いと認められない場合には、優先的なリスク評価の対象である「優先評価化学物質」に指定されることになり、評価の枠組みを大きく変えることになりました。それとともに、これまでその存在が許容されなかった第一種特定化学物質について、他に代替物質がなく、人健康等にかかる被害を生ずるおそれがない用途に限り、厳格な管理のもとでの製造・使用が認められるようになりました。これは化審法がストックホルム(POPs)条約の国内の担保法であったことから、その規制物質は化審法では第一種特定化学物質として、製造・輸入・使用を禁止するという運用をとってきましたが、条約でPFOSを代替ができない特別の用途を許容することになったため、全面的な禁止によってわが国の産業が関連分野で競争力を失うことが懸念されたことによります。これは規制の緩和に見えますが、このような物質の製造事業者や使用事業者には極めて厳格な管理が求められており、用途も拡張されないように、環境汚染につながらないような形で運用されていますし、将来的には代替物質の開発などにより廃絶となるような事業者努力も求められています。2009年の改正は化審法にハザードによる規制に加えてリスク管理の仕組みを明確に導入したものといえるでしょう。
事前審査制度を持つ国(地域)では、新規化学物質の登録で提出が必要なハザードデータを定めることが多いのですが、米国のTSCAでは特に項目を指定せず手持ちのデータの全てとしています。化審法は分解性、蓄積性、変異原性、亜慢性毒性試験などを要求し、急性毒性試験の結果は求めませんが、これは先に記したように「環境を経由した化学物質の人の健康や環境への好ましくない影響」の未然防止を目的としていることによっています。直接・間接を問わずに好ましくない影響の予防を目的とする国(地域)では、急性毒性試験や腐食性・刺激性試験などの有害性データとともに物理的危険性に関するデータも必要とされることがあります。国や地域ごとに必要な試験項目は異なりますが、それを解説した文献も容易に入手できますし、登録を予定する国のホームページなどからも調べることができるので、ここではそれについては触れません。一般に、上市直後の数量が少ないときに必要な試験は、それほど長い試験期間も多額の試験費用も必要としないものが多いので、海外に出荷を計画するときは、化審法で実施した試験項目以外にいくつかの必要な試験を試験機関で追加実施すれば支障はないものと思われます。しかし、それとは別に海外の事前審査制度への対応では、法律で明文化されていないことも含め、注意したいこともあります。
①有害性の試験方法
事前審査制度を持つ国(地域)では、試験項目の評価用データを取得するための試験方法を定め、これにはOECDのテストガイドライン(TG)の試験方法が許容されることが一般的です。化審法準拠の試験方法はOECDのTGでもあるので、化審法の登録に用いた試験結果はそのまま海外でも受け入れられる、と考えたいのですが、実際にはそれだけでは手続きが円滑にすすまないことがあります。中国のように固有の魚種を用いた魚毒性試験を求める事例も珍しいのですが、その国(地域)でデータが蓄積されている試験方法による追加データの提出が求められることもあります。
そのような要望に対応しなければ登録作業が遅れることがありますし、対応するのであればそれだけ追加の試験期間と費用が必要になるので、登録作業に入ってから遅れがでないようにできるだけ早い時期に当局と打ち合わせを行ったり、その国(地域)の事前審査制度に詳しい専門家に相談しておくことが良いように思います。
②リスク評価への対応
日本を含め世界では化学物質管理がハザードベースの管理からリスクベースの管理に移行が進んでいます。リスク評価は、最終的には規制当局の判断によりますが、どのような形で使用され環境に放出される可能性があるのかという情報は事業者が保有しているので、どのようにリスクを評価して軽減策を考えるべきなのか把握しておくことが必要になってくるでしょう。リスク評価のために行う追加試験の実施には、費用と時間がかかるだけでなく、追加試験結果の提出で規制が緩和される保証も無いので、事業者は当局の要求に対応すべきかどうかの判断に苦しむこともあります。追加情報の提供は適切なリスク判断を行うためですので、事業者も当局が懸念するリスクを理解し、必要があれば事業者としてのリスク評価情報を提供することもできます。
リスクベースの管理では、事業者もばく露情報をできる限り正確に把握しておきたいものです。これまで日本では化学物質の規制では事業者と当局の間で意見交換の機会があまりありませんでした。ハザードベースでは定められた基準から規制の要否が判断されることもあってその必要もありませんでしたが、リスクベースの管理では行政と事業者の間で、「リスクコミュニケーション」が必要になることもあります。そのためにもこれからは事業者自身によるリスク評価が必要になってくるものと思われます。
法規制のリスクベースの管理重視への変化は、既に同様の規制を持つ先進各国の法制度の改正だけでなく、途上国・経済移行国で制定が進む規制にも見ることができます。2006年に制定され2007年から施行された欧州のREACH規則による、世界の化学物質管理政策に対するインパクトは強く、化学品に留まらず製品(成形品)に含まれる化学物質についてもリスク管理の観点から規制を考えるようになリました。
欧州のREACH規則のもととなった欧州委員会の白書(2001年)には、①安全責任を産業界に課し、意図された用途では、安全な物質のみを生産・上市していることを保証するとともにサプライチェーンにそってダウンストリーム・ユーザーに情報を提供するこ、②ダウンストリーム・ユーザーもまた、製品の安全性に関する責任を負い、用途及びばく露に関する情報を提供すること、としています。このようにリスクベースの管理では、情報の伝達が重要になりますが、改正化審法でも製造・輸入業者は第二種特定化学物質またはその含有製品の表示義務や監視化学物質・優先評価物質等の名称等の情報伝達の努力義務が課せられており、これらの情報は国のリスク評価に用いられるだけでなく、ダウンストリーム・ユーザー自身のリスク管理にも用いられることが期待されています。このようにリスク管理の視点を入れたことは、化学物質の製造者だけでなく使用者にも大きな影響をおよぼすことになりました
③ハザードデータを取得するための試料の調製
純物質からなる化学品でも、微量の不純物を含みます。分析技術の飛躍的な向上は、化審法制定時に比べてはるかに微量の不純物の検出・同定を可能にしました。そのため、事前審査制度のもとでは、どのような試料でハザードデータを取得するのか、という点を考慮する必要があります。
化審法では純度の高い試料を用いて物質固有のハザードデータを取得するので、製造者によって評価結果が異なることはほとんど考えられません。海外では実際に流通する製品(有姿)の試料を用いる傾向があります。試験に用いるために、評価用の高純度試料を試験に必要な量を調製することは事業者にとって負担になることもありました。流通製品をデータ取得用の試料とするほうが容易であることはいうまでもありません。この違いは化審法が環境を経由した間接ばく露からの影響を考えるのに対して、海外では直接ばく露も考えているからと言えるでしょう。しかし、このことは同じ化学物質であっても、製造方法の違いで含まれる不純物の違いから、評価結果が異なる結果となることもあります。
④物質の特定(同定)
新規化学物質登録の作業は、対象の化学物質が既存化学物質であるかどうかを調べることから始まります。化審法の施行時には化学物質をCAS番号で特定することは、国内ではあまり一般的ではなかったので、化審法番号が付与されたのだと思います。欧州ではEINECS番号でインベントリーを作成しました。その後、TSCAではインベントリー作成にCAS番号を用いたことから、全世界でCAS番号の使用が普及したものと思われます。日本や欧州では化審法番号やEINECS番号とCAS番号の対照が進んでいます。海外で新規化学物質の登録が必要とするときには、CAS番号の確認が必要です。化合物群をまとめて一つの化審法番号としていることもあり、化審法番号とCAS番号の対照は簡単ではありませんが、多くの物質ではその作業がすんでいます。正しいCAS番号がわかれば、登録の要否は容易に判断できるようになっています。なお、これとは逆に一つの物質が複数のCASを持つこともあるので注意が必要です。
⑤化学物質の定義
国(地域)によって規制される「化学物質」の定義は異なります。化審法では「化学物質」とされなかった物質が海外では化学物質と見なされることや、その逆のケースがあります。一般的には、すでに化審法と同様な規制が行われている又は行うことが可能となっている他の法律で規制される物質は化審法の適用除外になるように、海外でも特定の目的で規制にある状態では適用除外となるのが多いのですが、必ずしも除外対象が一致しているわけでもないので注意が必要でしょう。
高分子化合物や結晶構造の違いから異なる物質として見なすことができる無機化合物、元素(単体物質)などは、運用が国(地域)によって異なることもあり、海外の化学物質の定義(適用範囲)を理解することが必要です。日本のようにポリマーフロースキームで簡略化されてはいるものの届出が必要な場合もあれば、TSCAのように事業者が責任を負う形の免除規定があるもの、欧州のようにモノマーの登録でよしとするもの、などさまざまな形があり、化学物質を規制する法律の整備を進めている国(地域)では、これらに類似した仕組みを導入しているようですので、事前にその国(地域)の実状を調べておくことが必要でしょう。
将来の問題ではありますが、世界の各地で健康障害が懸念されている「ナノマテリアル」について、化学物質を規制する法律がどのようにかかわってくるのか注目したい分野でもあります。個人的にはアスベストと同様にナノマテリアルを化学物質の規制法で管理することには難しい点があるように思います。
このように同じ新規化学物質の事前審査制度でも、法律(規則)の目的の違いやその他の理由から運用が異なることもありますが、日本で世界の法律・規則を完全に理解することは至難の業ですので、繰り返しになりますが法制度の実状を熟知した現地のコンサルタントなどの協力を得て円滑に対応を進めていくことが良いと思います。
化学物質の事前審査制度は、環境と安全を守ることだけでなく、その国(地域)の産業の保護育成をも目的としているので、少し理不尽ではないか、と思われる制度や運用の実状もありますが、そのような背景もあることを承知しておくことが必要でしょう。
最後に、違反に対する罰則にも注意が必要です。わが国では化審法違反で多額の罰金が科せられた事例を私は承知していませんが、海外特に米国のTSCAでは、違反1日に対していくら、という罰金が科せられます。違反を知ってからぐずぐずと対応に遅れをとると、巨額の罰金が科せられる可能性があります。反面、当局(米国EPA)との交渉で情状の酌量や誠意ある対応が認められることで、罰金の減額もありますので、制度とその運用の詳細を十分に知ることが難しい海外では、ここでも現地の状況をよく知るコンサルタント等を活用して、的確なそしてすばやい対応をとれるように考えておくことが必要でしょう。
第4回 労働安全衛生法(安衛法)
労働安全衛生法は昭和47(1972)年に「職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進する」ことを目的に労働基準法から独立しました。同じ時期に目的を同じくする法律が米国(OSHA, 1970年)と英国(HSWA:Health and Safety at Work etc. Act, 1974年)でも制定され、その後世界各国・地域で同種の法制度が整備されていますが、現在でも労働基準法に相当する法律の中に労働安全衛生を守る仕組みを入れている国もあります。
労働者を守る労働安全と衛生の活動は、前者が主として物理的な危険性からの死亡・傷害事故を、後者は好ましくない労働環境からの健康障害の予防活動です。化学物質に起因する労働災害に限れば、それぞれ爆発・火災と有害性を持つ物質へのばく露からの健康障害の予防活動となります。爆発・火災には事業者は労働安全衛生法と合わせて消防法や高圧ガス保安法などの他の法規制の遵守が安全活動の第一歩と考えるでしょう。一方、労働者の健康有害性に関しては、労働安全衛生法に詳細な規定が定められています。そこで、今回は化学物質に関わる労働衛生活動を考えることにします。
労働安全衛生法は、作業環境測定結果とその評価に基づき局所排気装置などの設置や稼働で作業環境中の有害要因を取り除く作業環境管理、作業内容や方法を適切に管理することや保護具の着用の徹底などにより暴露を低減させる作業管理、そして労働者の健康状態を把握し作業環境や作業との関連を検討して健康障害を未然に防ぐ健康管理を基本の三管理としています。労働安全衛生法の規制は、有機溶剤中毒予防規則(有機則)や特定化学物質障害予防規則(特化則)などの特別規則では、対象の物質と作業を指定します。有害物質と作業内容を関連づけて規制を考える仕組みは米国のOSHAなども同様ですが、労働安全衛生法の特別規則の特徴は規定が詳細でありかつ具体的であることといえるでしょう。
健康障害の原因となる化学物質のばく露経路には、呼吸器系を経由する吸入ばく露、接触などによる経皮ばく露と消化器系を経由する経口ばく露の三通りが考えられますが、労働現場では特に吸入ばく露からの労働者への影響を考えなければならないことが特徴的といえます。作業環境の状態を評価するために、有害物質に対して管理濃度が設定されており、これは作業環境管理の基本的作業である作業環境測定結果をもとに作業場の管理区分を決定するための指標です。海外で指標として用いられことの多い許容濃度(ばく露限界値)は規制値とはなっていません。しかし、管理濃度と日本の産業衛生学会の許容濃度は、目的は異なりますがこの二つが設定されている場合には大きな差異がないので、どちらも作業者のばく露状態を管理する指標と考えることができます。リスクアセスメントを義務(努力義務)化した改正労働安全衛生法とそれ以前に公表されているリスクアセスメント指針の解説では、許容濃度(ばく露限界値)を管理指標に用いることも管理活動の事例の一つとしています。管理濃度は100物質弱(化合物群として一つに数えているものもあるので、実際の物質数はもっと多い)に設定されているのに対して、産業衛生学会の許容濃度(粉じんは除く)は200物質強、米国のOSHA規則が引用するACGIHは400以上の物質に設定しています。英国やマレーシアでは600物質以上に許容濃度が設定されています。海外事業を計画する時には、立地国(地域)での許容濃度の有無の確認が必要です。
労働災害に対する事業者責任の追及の考え方が日本と異なり、米国OSHAでは労働者の健康と安全を守る事業者の一般的義務の違反(事故災害の発生)に対して罰則を定めており、罰金(penalty)も極めて高額です。同様の考え方をとる途上国もあることを考えると、許容濃度を超えた状態で定常的に作業することは避けるべきです。一般論で言えば、わが国の労働現場での化学物質に対するばく露管理の歴史は長くその水準も高いので、特にその国・地域の法律が手法を特定していなければ、日本国内で採用しているばく露低減の対策を海外(特に途上国)にも適用して許容濃度未満に作業環境を納めることも一つの考え方です。しかし、日本で管理濃度の設定されている規制物質は限られているので、それ以外の物質にも適用するときには、後に記すSDSで提供される健康有害性や物性などの情報を考慮しなければならないでしょう。
管理濃度や許容濃度は作業環境からの吸入ばく露による健康障害の防止に考える指標です。しかし、最も重篤な労働災害の例である化学発がんを考えても、最近の事例ではアスベストからの肺がん、1.2-ジクロロプロパンによる胆管がんなどは吸入ばく露によるものと考えられますが、昨年公表された芳香族アミンによる膀胱がんでは経皮吸収によるばく露が疑われていることです。経皮ばく露に対しては、換気などによる作業環境管理というよりも接触を回避するための、作業手順の見直しや個人用保護具の着用の徹底などの作業管理で予防することになります。吸入ばく露以外の経路についても無視することはできないことをこの事例は示しています。
平成26年(2014年)の改正労働安全衛生法は、リスクアセスメントを義務化しました。義務化対象は法規制の640物質に限られていますが、GHSで有害性に分類・区分される未規制物質については努力義務としています。未規制物質に起因する労働災害の発生件数も多く、労働安全衛生を考えるうえでは、規制対象物質と異なり法令が取り扱い方法を詳細に定めていない未規制物質を適切に取り扱うにはどうしたらよいか、ということは大きな課題です。事故災害が発生してから原因の未規制物質を規制対象とする、いわば後追いの規制では事故災害を抜本的に減少させることには限界があるとして、事業者による自主的な管理活動の第一歩となるリスクアセスメントを労働安全衛生法に取り込んだものと考えることができます。リスクアセスメント指針は既に平成18(2006)年に公表されていましたが、今回はそれを改正しました。
リスクアセスメントに関する規定は、多くの国の労働安全衛生法令に見ることができます。欧米の労働安全衛生法をひな型として作成されたと思われる途上国でも、既にリスクアセスメントに関する規定を入れていることがあります。背景には国際機関であるILOの170号条約(日本は未批准)や177号勧告が、化学物質の危険有害性に関する情報を販売者は提供し、受領者はそれを労働安全衛生に活用することを求めていることにもあるでしょう。
化学物質の危険有害性情報は、GHSの仕組みに基づいてSDSで提供することが、世界的な趨勢になろうとしています。化学物質を規制する法制度が整備されていない国でもGHSの導入が進んでいます。リスクアセスメントとGHSの世界的な広がりは互いに関連しているといえるでしょう。
海外の法規制を考えるとき、法律の条文を正しく理解して適切な対応を取ることだけでなく、その法律がどのような考え方を背景に持ち、それがどのような形で強制力のある規制になっているか、ということを理解することも重要です。雇用する労働者の健康と安全を守ることは事業者の責務であるのは自明ですが、既に記したように「労働者の健康と安全を守る一般的義務」の不履行、すなわち結果として事故災害を発生させたという事実に対して、罰則が適用されるかどうかという点は国によって考え方が異なります。労働安全衛生法には「一般的義務」の不履行に対しての罰則規定が有りませんが、米国のOSHAや英国のHSWAには罰則があります。それは、欧米の労働安全衛生法を手本として作成されたと思われる途上国においても同様の傾向です。一方で、法律あるいは社内で運用する安全規定からの労働者による意図的な逸脱に対しては、日本よりも労働者に厳しく責任を問うこともあるので、責任と権限に対する考え方は国によって異なるように思います。
「一般的義務」の不履行に対する罰則の有無とは別に、事故災害が発生し被災者がでれば、民事訴訟で責任所在が争われることもあります。事業者の社会的責任が問われれば操業の継続が難しくなることもあるでしょう。事故災害の事業者に与える影響は、国によって大きく異なり、その国の社会的な背景に依存するので、不幸にして労働災害が発生した時の善後策は日本の場合とは異なることもあります。法律に対する考え方が国(地域)によって異なれば日本の常識が海外では通用しないこともありますが、それについては個別の事情によるところが大きく、化学物質に起因する事故災害を考えることを主題としているこのコラムの範囲を逸脱しているので、ここでは触れません。
化学物質の関係する労働安全衛生問題は、日本だけでなく世界でも大きな課題であり、ILOも対策が重要であることを指摘しています。化学物質の製造と使用が先進国から途上国に拡がろうとしている中で、これまでに様々な体験を持つ日本企業は、類似の事故災害を途上国で発生させないために、その国や地域の法律による規定の有無とは別に、自らが培ってきた安全衛生を確保する手法、さらにいえば「安全の風土」を積極的に途上国に拡張展開することが必要でしょう。
第5回 化管法(PRTR制度)
1999年7月に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」は、PRTRと(M)SDSの二つの制度を柱としています。SDSには化学品の供給者から需要者への危険有害性に関する重要な情報が記されているので、受領する購入・使用者には、リスク評価は不可欠な文書ですが、PRTR制度への対応という点では、その中の組成成分情報を用いることになるでしょう。SDSは化管法とともに労働安全衛生法と毒劇法が義務化しているだけでなく、一般的には消防法や化審法などの他の化学物質規制の法律に関する情報についても作成者は配慮することが多いので、これについては稿を改め、今回は化管法のPRTR制度を考えます。
PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) 制度は、事業者が取り扱う化学物質(化管法では第一種指定化学物質)の排出量(大気、公共用水域、土壌、事業所内の埋立処分)と廃棄物(下水道、外部委託)中の移動量を把握し届け出る仕組みで、事業者の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。廃棄物による環境影響は処理業者の処分方法に依存しますが、排出量は化学物質を取り扱う事業者から環境中に放出された量で、排出量の削減で環境影響の低減が期待できます。環境負荷を考えれば、排出量は少なければ少ないほど好ましいことは自明のことといえるでしょう。
筆者の個人的な思いから記すことになりますが、当時勤務していた企業で、環境・安全と化学物質を規制する法律への対応を担当する部門に異動したのが1996年でした。同じ年にOECDが加盟国にPRTR制度導入の勧告をしました。その後、国は検討会を開催し1997年に報告書を受けてパイロット事業の実施と併行して法制化の準備を進め、1998年の中央環境審議会の中間答申を受けて化管法が制定されました。筆者はこの過程を業務として注視してきました。それというのも、従来の化学物質を規制する法律では、事業者は国の定める規制値の遵守が求められ、違反すれば罰則が適用されるという形でしたが、化管法では事業者は排出・移動量の国への届出だけが義務化されているだけで、規制値に相当するものは定められていません。このような法律の枠組みのもとで、事業者の自主的な取り組みがどのような成果を上げるのかが課題となっていたからです。またPRTR制度がどのような形で運用されるのか、そして排出・移動量を算出し届け出るという作業が事業者にとってどの程度の負担になるのか、という点にも関心がありました。筆者は運用開始5年を経過した2007年からの見直し合同会合では、途中からではありますが専門委員の一人として参加しましたが、そこに参加する関係者がそれぞれの立場から、化管法をどのように考えまた期待しているのかを知る機会を持ち、その後産業界は化学物質の管理として何をしなければならないのか考える契機となりました。
強制力のある数値目標を設定せずに、単に排出・移動量の報告の作業から、環境中への放出量をどの程度低減できるのかということは、化管法の開始時の課題でしたが、その後の公表データを見ればわかるように、総届出排出量は平成15年度の29万tから平成25年度の16万tに45%減少しています。減少の割合を5年ごとに区分して前5年と比較すれば、平成20年度は平成15年度から32%の削減、平成25年度は平成20年度から20%の削減とその削減割合は鈍化してはいるものの、排出量の削減は進んでいます。排出量の大部分(約90%)を占める大気への排出量だけを見ると、第1位のトルエンは平成15年度の12万tから平成20年度には8.2万t、平成25年度には5.4万tになり、それぞれ平成15年度に比べて、31%と55%の削減となっています。第2位のキシレンも同様に排出量が削減されていますが、トルエンのような単調減少とはなっていません。これは、SDSの普及で工業的に用いられている「混合キシレン」には少なからずの量のエチルベンゼンが含まれていることの認識が進み、キシレンの排出量の一部がエチルベンゼンに振り分けられた結果と思われます。キシレンとエチルベンゼンの排出量の和を見れば、平成15年度の6万tから平成20年度の5万t(13.1%減少)、平成25年度の4万t(36.1%減少)とトルエンと同様の減少傾向を示しています。総届出排出量の減少からもわかる通り、減少の傾向は物質によって異なるものの、ほとんどの物質で排出量の削減が進んでいることがわかります。このように、具体的な削減目標(規制値)を設定しないでも、PRTR制度の目的は達成されているように思われますが、そのことは化管法の制定時にも予想できたことで、データはこれを実証したことになります。
削減がすすんだ第1の理由は、化管法以前に事業者は大気や公共用水域への排出では、大気汚染防止法や水質汚濁防止法の排出濃度規制値の遵守に努めるものの、排出総量の算出はあまり行っていなかったことがあり、化管法の施行で多くの事業者が実態の把握を始めたことにあるでしょう。
第2の理由は、平成8(1996)年5月の改正大気汚染防止法で、事業者の責務が追加されたことに伴う有害大気汚染物質の自主的な削減を図る「自主管理計画」の策定の要請を業界団体が受け入れ、第1期(平成 9 (1997)年度~11(1999)年度)と第2期(平成13(2001)年度~15(2003)年度)の2期にわたり自主管理計画を実施したことです。第1期は化管法施行以前の活動で、対象物質は大気汚染防止法の有害大気汚染物質(12物質)に限られていましたが、基準年(平成7(1995)年度)の排出量合計の35%削減を目標として活動をはじめ、第1期の終了時に削減率は約40%と目標を上回る成果が達成されていました。第1期で自主管理計画に参加した企業はそのときの手法をPRTR活動に応用できました。自主管理計画は国(旧通産省・旧環境庁)の主導で行われフォローアップもされたので、純然たる「自主」活動とは言えない部分もありますが、それでも罰則の規定がない形で事業者の「自主活動」を促したことには違いありません。法規制という最も事業者にとって強制力を持つ形をとらなくても、環境汚染を防止する活動は実績を上げることができる、ということを示しているように思います。
第3の理由は、先行して1988年から実施された米国のTRI制度でも1997年までの10年間で、事業所からの排出・移動量が4割以上も削減されたことから、化管法のPRTR制度でも削減が期待されたことです。TRI制度とPRTR制度は、対象物質数も対象事業者数も異なるので、単純に削減率の数値を比較することはできませんが、この例も事業者の自主的活動が、環境への化学物質の排出・移動量の削減に繋がることが示されています。TRI制度は1986年の「緊急計画および地域住民の知る権利法(EPCRA)」によっているので、事業所周辺の住民に対して事故災害時に好ましくない影響を及ぼす可能性のある物質も取り入れられています。これが、化管法を検討する数次の会合で取扱量あるいは貯蔵量の届出を求める意見や、環境を経由した長期的な健康影響を懸念する物質だけでなく急性毒性物質も対象とするべきではないかという意見にもつながったと思われます。しかし、米国のTRI制度と日本のPRTR制度の目的は異なっているので、米国がこのように進めたのだから日本も同じ枠組みでしなければならない、ということにはならないでしょう、実際、世界の各地で実施されているPRTR制度(類似も含む)は国によってまちまちです。なお、自主管理活動には環境マネジメントシステム(ISO14000)の普及が進んでいたことや、化学業界を中心としたレスポンシブル・ケア活動なども後押しをしたといえるでしょう。
制定時の検討会と見直し会合の立場の異なる参加者(行政・産業界・市民)のそれぞれの化管法に対する思いは、必ずしも一致していたとは言えないかもしれませんが、施行後10年を経過した結果を見れば、期待通りあるいはそれ以上の成果を上げていることは否定できないと思います。もし、PRTRの排出・移動量の総量が環境濃度やその他の環境上好ましくない影響に相関があると考えられれば、大気汚染防止法や水質汚濁防止法などの既存の環境法規による新しい規制につながっていたはずですが、幸いにそのような事例もありません。限られた特定の地域での環境上の問題は残されているのでしょうが、日本の化学物質による環境影響は悪化しているとは言えず、むしろ良化しているということができるでしょう。
このように、PRTR制度のもとで化学物質の環境への排出量は着実に低下していますが、施行から10年以上を経過したこの制度が、今後どのような形で運用が進められるのか興味があります。産業界、とりわけ届出を求められる事業者には、この制度は定着してきたように思われますが、一方でそのような作業が求められない事業者や環境からの影響を被る可能性のある市民の間には、この化管法の趣旨は十分に浸透しているとはいえないように思われます。成果と意義を確認して今後の化管法を考える時期にあるように思います。
PRTRのデータを検討するときに、データの精度が気になります。PRTRデータは多くの場合、化学物質管理指針にある方法で求められています。物質収支による方法によれば、使用量から製品としての出荷量と消費量を差し引いた差として求められます。国内のトルエンの流通量は約150万tで届出排出量は約5万tですから3%位が環境中に排出された計算になります。政府による推定の届出外排出量(約4万t)から移動体由来の2.4万tを差し引いた1.6万tを加えると、流通量の約4.5%になります。このように「差」として求められた排出量の精度には限界があります。届出排出量で2桁の精度を求めるためには、使用量や出荷量・消費量には4桁の精度が必要で、この精度のデータの取得は簡単ではありません。また、モデル実験等から得られる排出係数を用いた方法でも、モデルと実際のプラントの間の差異を考慮すれば、高い精度を求めることは難しいといえます。届出事業者には、自らの排出量と例えば同業他社の工場を比較して、よりよい成果につなげたいという思いもありますが、データの精度が不十分な状態であり、さらにその同業他社の取り扱い方法も排出量の算出方法もわからない状態では、細かい数値の差異を必要以上に気に掛けることもないでしょう。届出事業者は自らの事業所の実態の把握を優先し、実現可能な方策によって、よりよい結果を得るようにすることが重要でしょう。
海外では理事会から勧告を受けたOECD加盟各国だけでなくアジアなどの途上国でも類似制度の導入が進んでいます。しかし、対象物質や対象事業所の種類は国によってまちまちですし、実施の規模も異なります。日本のようにPRTR制度として対象物質を定める場合もあれば、既存の化学物質を規制する法律にある物質や新規化学物質を対象としている場合もあります。全体としてみれば海外に比べて日本は対象物質数も対象事業所数も多いといえますし、政府による非届出事業所や非点源からの発生量の推定も進められています。このように複雑で手間のかかる制度が、比較的順調に動いていることは、各方面の努力の結果であり、日本の特質ともいえるでしょう。海外での事業化では、PRTR制度を持つ国での対応の詳細な部分は、それぞれの国の規定に対応を図りますが、排出量抑制の活動は日本の事業所に準じて行うことで、多くの場合は対応が可能と思います。
化管法の制定時とその後の検討会の席上で意見が交わされたテーマの一つにリスクアセスメントがあります。PRTRデータを活用したリスクコミュニケーションの強化として、国及び地方公共団体は化学物質の性状、管理、排出の状況に関する国民の理解を深めるように努めること、また取扱事業者は化学物質管理の状況に関する国民の理解を深めるように努めることが規定されています。個々の事業所の排出・移動量が開示(のちに化管法の改正で公表)されることで、事業所を誰でも知ることが可能となり、その結果例えば事業所と近隣の市民との間の環境中に排出される化学物質に関するリスクコミュニケーションから、事業者と市民の間で情報とリスク認識の共有化が進むことが期待されていました。しかし、PRTR制度が施行されてからも、なかなか期待されたようなリスクコミュニケーションの実施には至っていないようです。化管法の制定後は、事業者あるいは業界団体主催のリスクコミュニケーションの場は増えていますが、市民の参加も限定的であるだけでなく、意見の交換というよりも、主催者である事業者(業界団体)の想定するシナリオに沿って淡々と進められることが多いように思われます。
リスクコミュニケーションがなかなか活発に行われないことには、①一般市民には化学物質の名称や健康有害性に関する専門的な用語が入ると理解が難しいこと、②事業者の側でもリスクをわかりやすく説明する人材が不足していること、③日常的に市民が化学物質からの環境リスクを意識することはほとんどないこと、などが理由にあげられるでしょう。しかし、事業者にはリスクコミュニケーションは、事業所が社会に受け入れられ安定した操業を継続する一つの手段となりうるものですので、できる限りわかりやすい形でリスクコミュニケーションを進めることが求められています。そのためには事業者と市民の間にファシリテーターを入れることなどで、市民の理解を助けることも必要となります。
リスクコミュニケーションは(化学物質の)リスクをテーマに関係者とコミュニケーションをとるものですので、「コミュニケーション」を日頃から実施していなければ、「リスクコミュニケーション」がうまくいくはずもないということができます。昔から地域の市民との関係を密に保つように事業所に招待して、事業所と市民の距離を縮める活動を進めることもありましたが、そのようなコミュニケーションの中で、「化学物質のリスク」を語る機会をリスクコミュニケーションに位置付けることも必要でしょう。なお、事業所の周辺の市民にとっては、事業所からの悪臭や騒音・振動あるいは煙突からの煙の色の変化なども関心のあることですので、化学物質の健康有害性だけでなく、物理的危険性(火災や爆発)や操業の安全配慮などについても質問がでればわかりやすく説明できるような準備も必要になるでしょう。
第6回 SDS制度(1)
今回と次回で化学品の包括的な危険有害性(ハザード)情報の伝達文書であるSDSとその制度を考えます。SDSは労働安全衛生法、化管法および毒劇法による義務化で化学品を取り扱う産業界では徐々に定着してきていますが、十分に活用されているとは言えないように思われます。法の規制を守ることだけでなく、SDSのハザード情報を活かして化学品による事故・災害あるいは環境汚染などを未然に防止し、製品の使用者(消費者)の安全を守る自主的な活動がより一層推進されることを期待します。SDSは多くのハザード情報を収集したうえで、化学品の安全に関して知見や経験を有する専門家が作成する文書ですので、安全管理のために活用することができる文書です。今回はSDSとはどのような文書であるのか整理したいと思います。
1) SDSの歴史
1970年代に米国で使用が始まり、その後日本でも同様の書式を「化学製品安全データシート」などの名称で用いる事業者がありました。危険有害性周知基準(HCS)の制定を受けて、OSHA(米国労働安全衛生庁)が1985年に書式を定めました。1990年にILOが170号条約で「職場における化学物質の安全」を採択したことは、国際的に化学品のハザード情報を取り扱う労働者への伝達が重要であることの認識が進んだ結果ということができます。1992年の地球環境サミットは、化学品を取り扱う労働者だけでなく、市民を含めた幅広い利害関係者にもハザード情報の伝達の重要性を示しました。同年に日本では通商産業省・厚生省・労働省(いずれも当時の名称)がSDSに関する告示を公表しました。米国のANSI(米国国家規格協会)が新たな書式を定め、この時に記載項目がそれまでの7項目から環境影響情報などを含めた16項目に拡張されました。2000年に日本でも労働安全衛生法でSDSの提供を義務化し、JISが書式を定め、2001年の化管法と毒劇法による義務化で、民間で使われていたSDSが法律の枠組みに取り込まれ定着することになりました。SDSの歴史は40年以上に及ぶものですが、日本での認識が進んだのは法制化以降ということができます。
2) SDSの役割
SDSは労働安全衛生を目的として始まり、現在でもその役割の重要性は失われておらず、労働安全衛生とそのリスクアセスメントに利用しやすい書式になっています。しかし、そこに記載される情報はそれにとどまらず、環境影響や化学物質を使用した製品による消費者への影響の評価などに用いることが期待されています。リスクアセスメントは、SDSにある化学物質のハザード情報とばく露の状況に関する情報を用いて実施されますが、通常ばく露情報は化学品の製造者よりもそれを用いた製品の製造者のほうが詳細な情報を持っているので、化学品のリスクアセスメントは使用者の役割となります。
SDSには化学品の法規制情報を伝達する役割もありますが、法律で提供が義務付けられているのは、化管法の指定化学物質、労働安全衛生法の通知対象物質、毒劇法の毒物・劇物などで、ハザードが懸念される物質の中でも一部にすぎません。日本のSDSには消防法の危険物分類や化審法の規制物質、労働安全衛生法のその他の規制物質に関しても記載されることも多いのですが、SDSを義務化していない法規制に関する記述は作成者の判断に委ねられています。受領者は必要があれば供給者に確認することになります。SDSには主として化学品固有のハザード情報が記載されていますが、役割が多様になったことで情報が多すぎて読みにくいとか、必要な情報がどこに記載されているのかわかりづらいという声も聴かれます。
例えば、SDSの第3項の「危険有害性の要約」と、第4項「応急措置」から第8項「ばく露防止および保護措置」までと、第10項「安定性及び反応性」から第13項「廃棄上の注意」には、同じような文言が出てくることがあります。第3項では危険有害性の分類・区分に応じて定型的な文言が記載されますが、第4~8項と第10~13項では作成者がその化学品の使用方法や使用目的に応じて、必要と思われる事項を自由に記載することができます。その化学品を大量に取り扱っている製造者の持つ様々な知見が活かされる部分であり、そこにはより実践的な記載が可能です。しかし、SDSの中にはほとんどが第3項の繰り返しになっているものもあり、これが記載の重複の原因の一つであるとともに、リスクアセスメントとリスクマネジメントに活用しにくい原因にもなっているようにも思われます。さらに詳細な情報や具体的な情報が必要であれば、作成者に記載内容の確認や追加の情報を求める、すなわちコミュニケーションが必要でしょう。
3) SDSの作成と配布の責任
SDSは原則として化学品ごとに作成され、混合物製品であれば製品全体としての危険有害性を記載します。単一物質から成り立っていると思われる化学品でも、特性を維持するために、酸化防止剤・重合禁止剤・紫外線吸収剤などの少量の添加剤を含んでいることもあり、その場合にはそれらを含めた製品の有姿としての危険有害性が記載されています。
SDSの提供と作成の責任は販売者にあるとはいえ、販売者が化学品を直接取り扱うことのない輸入業者や販売代理店などの場合には、製品の組成などから独自の観点からハザードを評価することはあまりないでしょう。輸入製品であれば仕入先の製造者の作成したSDSの翻訳やJISの書式に整理しなおすことで顧客に配布することのほうが多いでしょうが、その場合でも販売者としての責任を免れるわけではありません。
4) SDSの改訂
日本ではSDSの改訂版の購入者への配布は法規制では努力義務とされていますが、最新の知見と法規制情報を利用するほうが望ましいことは言うまでもありません。改訂SDSは改訂後の最初の出荷の際に提供されることが多いと思いますが、出荷と受領者での使用時期には時間差があり、その間にSDSが改訂されることもあります。供給者には受領者が化学品を使用するタイミングがわかりませんので、受領者が長期の在庫後に使用するときには供給者にSDSの改訂の有無について問い合わせてもよいのではないでしょうか。
5) SDSの課題
SDSは化学品の販売者から需要者に提供される文書です。化管法の制定時あるいは見直しの検討会では、消費者用の製品でも同様に危険有害性の情報の提供が必要ではないかという指摘もありましたし、欧州のREACH規則の制定を背景に、成型品にも化学品のSDSのように化学物質の危険有害性を伝達する仕組みが必要ではないか、との指摘がありました。化学品に限らず、化学物質へのばく露が考えられる非化学品を含めて危険有害性の情報を伝達することは好ましいことのようにも思われますが、利害関係者の安全を守るという目的を考えれば、必ずしもSDSが最良の情報提供手段であるとは限りません。成型品や消費者用の製品は特定の使用目的を持って製造されているので、生産者は購入者がどのようにその製品を使うのかということを、好ましくない誤った使用方法も含めてある程度予測できます。製品のリスクアセスメントを生産(供給)者の側でも可能ということができるので、含有する化学物質の情報を開示するまでもなく、取扱説明書などでリスクマネジメントを含めて、適切な取り扱い方法を伝達することで適切な使用方法を示すことができます。むしろ、受領者が見てもよくわからない化学物質名が羅列されるよりも、利害関係者の安全を守る上では有効性の高い情報伝達の手段ということができます。家庭用漂白剤のラベルには、細かい条件を書かずに「混ぜるな危険」とありますが、これは異なる製品と混合すれば危険な状態になる可能性があることを簡潔に記した例と考えます。
さて、SDSでも本来の目的から考えると、流通しているSDSにも課題が残されているようにも思います。受領者がSDSの枚数が多すぎるなどと、不満を持っていることの背景の一つには、わかりやすさや使いやすさといった点で改良したほうがよいということがあります。含有する化学物質の危険有害性を伝えるだけでなく、その製品あるいは類似の製品による事故やヒヤリハットの事例などの記載が進めば、受領者は定型的な文言の羅列以上にわかりやすい安全な取り扱いのための情報を受け取ることができるでしょう。ネガティブ情報、それも公表されていない自社の情報を記載することは、多くの事業者にとっては躊躇することでしょうが、化学品の取り扱いに慣れていない事業者(受領者)にとっては、安全な取り扱い方法や用途、そしてリスクアセスメントに使いやすい情報ではないかと思います。かつてのMSDSにはそのような情報が第16項「その他の情報」に記載されていましたが、SDSのJIS化や法制化に伴って、定型的な文言が主体のSDSに代わっていき、そのような身近な安全情報の記載が減少しているような気がします。使いやすいあるいは使って役に立つSDSのためには、このようなことも考えることが必要ではないか、と思われます。
第7回 SDS制度(2)
前回はSDSの成り立ちとビジネス文書としての役割を記しましたが、今回はSDSの受領者が考えておきたいことを記します。
SDSは化学品を取り扱う事業者が人の安全と健康や環境への影響を考えるうえで、重要な情報を記載した文書です。用語は平易ですが記載される内容は専門的で、正確に理解するためにはある程度の予備知識も必要です。国連のGHSに基づいた危険有害性の分類区分に対応する定型的な文言とともに、GHSで分類区分されていない危険有害性や特別に考慮したい事項は、作成者が自由な文言で注意喚起を促すようになっています。受領者もSDSにはこの二種類の文言が用いられていることを知っておけば、より適切な理解の助けになるでしょう。十分に理解されないままでファイル化されることは避けたいものです。
経済産業省が公表している作成者のためのガイドラインを読めばどのような手順でSDSが作成されているかということがわかります。しかしこのガイドラインを一読しただけでは、流通件数の多い混合物化学品のSDSを使いこなし、リスクアセスメントなどに利用するのは難しいと感じるのではないでしょうか。単一物質からなる化学品であれば、特殊な物質を除けば多くの物質の危険有害性情報はインターネットなどから入手可能となっているので、SDSに記載された事項に加えてそれらを補足で使用できますが、一般に個別の混合物化学品のSDSを公開の情報として入手することは困難です。また、混合物化学品の含有する化学物質では法律が記載を義務づけているもの以外では、受領者が必要とする法規制の情報が必ずしもSDSに記載されているとは限りません。購入者の受領したSDSの情報のみから適切な対応を図ろうとしても情報の不足から解決に至らないこともあります。今回は混合物化学品のSDSを念頭においてこのような問題点を考えていきますが、混合物化学品といってもその成り立ちは多種多様ですので、「混合物化学品」にはどのような製品があるのかということから簡単に解説します。
1) 単一物質化学品を混合して製造された混合物化学品
身近な混合物化学品としては、塗料・インキ・接着剤・洗剤などがあげられます。これらの製品群は同じ原料を使用していても、配合比を変えて数多くの製品(品番)ができることが特徴です。近似する配合比の製品群は法律の要求事項を満足している限りで、一連のSDSとしてグループ化されることもあります。このような製品では、SDSに詳細な配合組成が開示されているとは限りませんが、微量の副生物や不純物に関する情報を別にすれば、製造者は配合比を承知しているので、受領者が製造者に問い合わせれば組成を知ることも可能です。しかし、組成比はノウハウの一つと考える事業者もいるので、法律の定め以上の情報を問い合わせる時には、その理由の説明が必要となる場合もあるでしょう。
2) 構造が類似した化学物質が混在した混合物化学品
化学物質のレベルまで精製せずに構造の類似した複数の化学物質が混在した状態の製品があります。分離精製に付加的なコストをかけずに混合状態でも利用可能であればそれで十分、という製品です。メタ/パラの二異性体からなる混合キシレンなどがその例です。工業的に確立したプロセスから生産される製品であれば組成も安定しているので、その製品の有姿で安全性試験が実施されていることもあり、購入者は単一化学物質からなる製品と同様に考えることが可能です。アルキル鎖長の異なるエステル類の混合物やエチルベンゼンを多量に含有した工業用キシレンなどもこの型に分類できます。このような混合物化学品は精製のコストをかけずにより安価な製品の提供を目的とするだけでなく、購入者の使い勝手を配慮してあえて混合物化学品として製品設計された製品もあります。事業者は化学実験をしているわけではないので、物理的その他の特性が満足できれば純物質までの精製コストのかからないそのような製品が用いられているのでしょう。
3) 多数の物質が混在した状態の混合物化学品
石油留分の一定の沸点幅から取り出された炭化水素系の溶剤は、極めて多くの物質を含有しています。天然物を化学的に処理した製品も、原料それ自身が多くの化学物質から成り立つことを反映して、特に分離精製の工程を入れなければ、多くの化学物質の混合物となります。原料産地などの影響で組成が変動することもあります。このような製品の中には混合物化学品の状態でCAS番号を持つこともあり、2)と同様に有姿で安全性の試験が実施されていることもあり、単一物質化学品と同じ手順でSDS記載の情報をリスク管理に用いることができます。
4) 高分子化合物 (ポリマー)
一般的にはポリマーは分子量分布を持つだけでなく、完全に規則的な繰り返し単位と結合状態のみから成り立っているとも限らないので、混合物化学品と考えることもできます。日本の化審法・安衛法ではモノマーの組み合わせをもとにして化学物質として取り扱いますが、ポリマーを安全性の審査の対象である化学物質とはみなしていない国や地域もあります。分子量が大きければ生体中に取り込まれにくく、健康に好ましくない影響は起きにくいと考えられているのでしょう。環境有害性という点では、水中に浮遊するポリマーの微粒子や膜などは、小さな水生生物の生態に悪影響を与えることも指摘されており、環境有害性の一つと見ることもあります。世界の各国や地域ではポリマーの法規制は千差万別ですので、対象の国や地域に応じて適切な対応を考えることが必要になります。日本から海外に製品を輸出する場合でも同様です。
混合物化学品のSDSの特徴
SDSにはGHSの仕組みの下で評価された危険有害性の分類・区分が記載されます。混合物化学品でもその原則は変わりませんが、購入した混合物化学品(一次混合物化学品)を原料に製造した新たな混合物化学品(二次混合物化学品)の適切なSDSの作成では事業者の方々は苦労されているのではないでしょうか。
混合物化学品では、不純物を度外視しても含有するすべての化学物質の名称が記載されているとは限りません。安衛法・化管法・毒劇法は記載を義務付ける物質を定めていますが、それ以外の物質に対してはJIS Z 7253が「GHS分類に寄与する成分が濃度限界以上含有する場合には情報を伝達することが望ましい」としています。これに準拠したSDSを用いれば混合物化学品の危険有害性の評価は組成の化学物質のすべてがわからなくてもある程度の評価ができます。濃度限界値未満の健康有害性物質しか含まない混合物化学品は区分外と評価され、区分外の混合物化学品を混合しても濃度限界値未満であることが自明ですので、その製品の健康有害性も区分外となります。とは言っても混合物化学品の危険有害性の評価は、単一化学品に比べて不確実性が高いことは否定できません。製品の評価が区分外でも健康有害性に対するリスクが無いということにはならないだけでなく、実際に製品を使用する状況で想定される化学物質のばく露経路と有害性試験を実施したばく露経路が異なれば発現する(あるいは発現しない)健康有害性は異なる可能性があるので、リスク評価では取扱者あるいは使用者の化学物質へのばく露経路を想定しておくことも必要になります。
GHSの分類区分の濃度限界値を超えた一次混合物化学品を用いた二次混合物化学品の健康有害性は、先の事例よりも健康有害性への懸念が高くなるので、GHSの手順に従って分類区分を行うためには、原料の一次混合物化学品中の分類・区分に寄与した物質の名称と含有量が必要となることがあります。混合物化学品では、配合・希釈・濃縮などの様々な工程を経て化学品の危険有害性の分類・区分が変わる可能性があるときに、一次混合物化学品の組成情報を必要とすることがあります。しかし、混合物製品の配合比率は重要な企業秘密やノウハウと考える事業者も多く、組成情報の入手には困難な場合もあるでしょう。そのような場合には、安全サイドに立った(健康有害性を過少評価しない)判断にならざるを得ないこともあります。一次混合物化学品の組成情報を入手するためには、例えば秘密保持契約を交わして情報の開示を求めるなどの手段も提案されていますが、決め手となるのは販売者と購入者の間の信頼関係や両者のコミュニケーションの良否によるでしょう。
GHSの分類区分がSDSの作成者によって異なる可能性もあることを考えると、化学品の安全管理を考えるうえで、一次混合物化学品の組成を詳細に知ることが、必須のあるいは決定的な条件であるのかどうかは疑問の余地があるように思われます。配合量により製品が区分されるか区分外となるか、というような状態に自社製品がおかれることは、危険有害性の分類区分を考えるうえでは大きな問題であるように思われますが、例えば濃度限界値を0.1%という極めて低い値を持つ健康有害性の分類では、多少の希釈では区分1や区分2が区分外になることはあまり期待できません。製品設計の段階で微妙な配合比率を採用することで健康有害性評価を区分外にすることを考えるというのは、効率のよい製品設計の方策とは言えないでしょう。そのような細かいことに神経を注ぐよりも、使用する原料が適切か否か、それを使用することに必然性があるのかという原点から考え直したほうが合理的と思います。
健康有害性の分類区分だけでなく、取り扱いの実態や製品の用途を考え、作業者や製品の使用者に対してのばく露形態を考慮して、そのような健康有害性が実際に影響を及ぼす可能性を考えることも必要です。それには健康有害性の試験を行ったときのばく露経路と自社製品からの労働者や購入者へのばく露経路との関係を考えます。健康有害性を示す化学物質は何か。そしてばく露の可能性を考えるうえで、その化学物質の揮発性や飛散性などの物性をSDSから理解することが必要になります。
SDSは取り扱う労働者や製品を使用する購入者の健康を守るためだけでなく、残余の原材料を廃棄する場合での環境負荷を考えるときにも使用されます。環境負荷を考える場合には、生態系への化学物質のばく露経路と試験方法の間に大きな違いがないので、ことさらにばく露経路による影響の有無や、混合物状態での環境への放出の有無について考える必要はないでしょう。環境負荷物質が含まれていれば、たとえ速やかに水と反応する物質であっても、未処理での公共水域系への排出は環境負荷につながるものと考えることができます。
SDSに記載された法規制物質の考え方
SDSの第15項:適用法令には含有する物質の法規制に関する事項を記載します。最近は物質の指定時に名称だけでなくCAS番号も併記されることが多くなってきたので、以前に比べれば法規制への該否の判定も容易になっていますが、それでも法律により同一の物質でも異なる名称が使われることがあり、化学物質の取り扱いを専門としているわけではない事業者にはわかりにくい場合があるようです。名称から化学物質を特定するのは、一定の規則(命名法)によるものが確実ですが、残念ながら命名法で表現された名称は化学を専門に学んだ人々以外には馴染みが無く、一般には汎用の名称や通称が好んで用いられています。この場合には同じ物質でも記述に違いが生じることがあり、同一の物質であるかどうかの判断に迷うこともあります。また、その逆によく似た名称を持っていても異なる化学物質という場合もあります。すべての法律で同じ化学物質に同一の名称を用いていれば混乱は回避できますが、現実にはそうなっていません。将来的には整合していない部分が整理され、物質の特定が容易になることが望ましい形と思われます。十分に物質が特定されないのであれば、専門家のアドバイスを受けることや国や民間の事業者の作成している化学物質のデータベースを参考として判断する必要があります。
最後に、SDSを完全に理解し適切な設備的な対応を行ったとしても、事故災害を完全に予防することは難しい、ということを指摘したいと思います。GHSに基づくSDSは考慮すべき危険有害性が整理されていますが、化学物質の危険有害性はそれにとどまるわけではありません。また、人が取り扱う際の合理的に予測できる誤用・転用についても配慮した記載が望まれていますが、SDSの作成者(製品の製造者)がそのような状態を完全に予測することは不可能に近いことですし、化学品を取り扱う工程の非定常的作業についても予測は難しいものです。事故や災害を可能な限り予防するためには、最近はSDSに記載されることが少なくなってきた事故や災害に関連する情報の提供(製造者)と入手(購入者)がSDSあるいはその他の手段で積極的に行われることが必要と思われます。
第8回 消防法
昭和23(1948)年制定の消防法は、業種を問わず多くの事業者になじみ深いもので、事業に関係する部分については、規制の内容だけでなく遵守方法あるいは施設・設備などへの対応も熟知されていると思います。そこで、今回は火災・爆発などの物理的危険性を有する化学品の、事業者による自主的な管理活動について記します。消防法の規制物質(「危険物」)に代表されるこのような性状を持つ化学品を日常的に取り扱う事業者は、火災発生のリスクをゼロにすることは極めて難しいことを前提に、法規制への対応に加えて自主的な活動で発生の抑制とともに重大化の防止を考えることが必要ではないかと思います。
消防法に類似する法律は世界各国で整備が進んでおり、事業者の火災予防活動を日本のように住居などの一般火災と同じ法律で定める国もあれば、「工場法」などの別の法律によることもあります。消防法の施行令と施行規則とは別の「危険物の規制に関する政令」と「危険物の規制に関する規則」(昭和34年制定)の二つの政省令に、事業者の取り扱う「危険物」の規制が具体的に定められています。「工場法」では火災・爆発からの労働安全に関する事項が含まれることがあります。
消防法は、火災の予防・警戒・鎮圧などによる社会公共の福祉の増進を目的としています。防火・防災では火災の発生抑制(減少)を重視する日本型に対し、重大事故の発生防止に力点を置くのが欧米型といわれることがあります。どちらにしても一方だけしか考えないというのではないのですが、条文を比較するとそのような違いが感じられます。東南アジアを含めて海外では欧米型のほうが多いように思われます。
事業者の使用する化学品には、可燃性・引火性・発火性・爆発性などの、火災の発生や拡大の危険性を持つものが多くあります。火災・爆発は発災事業所に甚大な被害をもたらすだけでなく、周辺地域にも多大な影響を及ぼすこともあり、事業所内の被害、損害とともに事業所外への影響も考えておくことが必要でしょう。
消防法はSDSの作成と配布を義務づけてはいませんが、化管法・労働安全衛生法・毒劇法によるSDSの制度化前から、事業者間の取引では消防法に関する情報をSDSで伝達することが一般的でしたので、現在も多くのSDSには第15項の適用法令欄に消防法に関する情報が記載されているだけでなく、GHSの分類・区分に従った物理的危険性の情報もあります。事業者のリスクアセスメントを制度化していない消防法では、その活動は自主的な対応となります。石油コンビナートにある事業所には防災アセスメントの指針がありますが、一般の事業所にはリスクアセスメントに関係する通知・指針はなく、これまでの主たる事業者の防火防災活動は法規制の遵守でした。
危険物令では、「危険物」を第一類(酸化性固体)、第二類(可燃性固体)、第三類(自然発火性物質及び禁水性物質)、第四類(引火性液体)、第五類(自己反応性物質)、第六類(酸化性液体)に分類しています。名称からわかるように、消防法は固体あるいは液体の化学品を対象としており、同じ危険性を持っていてもガスは高圧ガス保安法の規制です。
消防法はGHSの危険有害性分類との整合化を進めていません。事業者も消防法に対しては化学品管理の仕組みだけでなく、施設や設備のハード面の整備を行ってきたこともあり、「危険物」規制の枠組みが変わっても簡単に対応を変えるわけにはいかないというのが実状でしょう。中にはGHSに基づくSDSの情報からリスクを判断し、法規制の枠組みを超えて化学品管理の取り組みを進めている事業者もあるでしょう。GHSは世界的な潮流となってきていますので、結果は海外の関連会社にも展開が可能となる利点もあります。しかし、国内の事業所の活動だけを考えるときには、多くの事業者にはGHSの分類・区分による物理的危険性を消防法の規制の枠組みに読み替えて考えることが現実的と思われます。
危険物令は別表に対象物質を示していますが、それ以外の化学品では他の法律と異なり、「危険物」への該否は政令の定める危険性判定のための試験結果によります。例示物質の含有量の濃度限界値などをもとに判定するのではないので、混合物化学品では類似製品からの類推で判定できない場合には、必要に応じて試験を実施することになります。物理的危険性を判定試験の結果に基づいて分類・区分する仕組みはGHSでも同様ですが、試験方法が異なるので消防法の試験結果がそのままGHSの分類・区分に適用できるとは限りません。同じ名称の危険性でもGHSと消防法では意味が異なることもあります。しかし、ここではそのような違いを承知したうえで、大雑把に消防法とGHSの対比を試みます。
消防法(一部は高圧ガス保安法)とGHSの分類の対比は、経済産業省が公表している「事業者向けGHSガイダンス平成25年度改訂版(ver.1.1); (平成27年3月)」にある物質の中でSDSが公表されているものについて行いましたが、GHSの分類・区分の責任は作成者にあるので、事業者により異なる場合がありますし、意図的に混合工程を経て製造された混合物化学品のSDSは公表されることが少ないので、主に単一物質化学品が選ばれています。
1) 爆発性物質
爆発性を示す可能性のある特定の原子団を持つ物質の多くは、消防法第五類に対応しています。
2) 可燃性・引火性ガス
高圧ガス保安法の一般高圧ガス保安規則で可燃性ガスに分類されます。
3) 支燃性/酸化性ガス
高圧ガス保安法ではこの分類は独立していないので、高圧ガス保安法の圧縮ガスや液化ガスに分類されるだけです。高圧ガス保安規則の毒性ガスに該当するものもあります。
4) 高圧ガス
定義は異なりますが、ほとんどの高圧ガス化学品は実質的に高圧ガス保安法の対象物です。
5) 引火性液体
GHSも消防法第四類危険物も引火点を基準として区分しますが、区切りとなる引火点は異なります。GHSでは93℃以上の引火点は区分外ですが、消防法は230℃までが「危険物」です。どちらにしても、取り扱いで最も注意する点は着火源となるものを近づけないことです。裸火だけではなく、電気設備からのスパークや静電気あるいは高温物体も着火源となります。引火性液体から発生する可燃性蒸気の挙動にも配慮することが必要です。
消防法とは異なり、GHSの引火性液体ではアルコール類や水溶性・非水溶性の区別がありません。これは引火性そのものの危険性というよりも、着火した際の消火薬剤の選定には重要な情報です。
6) 可燃性固体
可燃性固体の考え方は、消防法とGHSでは異なります。GHSでは三角柱状に成型した試料に着火させ燃焼状態から区分されますが、消防法では着火あるいは引火の可否から危険性が判定されます。そのためGHSで可燃性固体と判定されるものでは、消防法で第二類危険物と判定されるものもあれば、指定可燃物の可燃性固体となるものがあります。
7) 自己反応性化学品
この分類に該当する可能性のある特定の原子団を持つ物質の多くは、消防法第五類第二種自己反応性物質に分類されますが、既に記したようにその中にはGHSと労働安全衛生法で爆発性物質に分類されるものもあります。
8) 自然発火性液体・固体、水反応可燃性化学品
空気と接触して発火する性質が自然発火性で、水(水に濡れたろ紙)との接触で発火あるいは可燃性/引火性ガスを発生する化学品が水反応可燃性化学品です。この分類の化学品の多くは消防法では第三類です。固体の化学品は、形状や試験条件により判定結果が変わることがあります。
9) 自己発熱性化学品
GHSの判定試験方法に従えば、常温常圧で固体の化学品が対象です。消防法には対応する危険物の分類はありませんが、指定可燃物に分類されるものがあります。
10) 酸化性液体・固体
GHSでは、試料とセルロースとの混合物の燃焼時間を、臭素酸カリウムと比較対照して1から3に区分しますが、消防法では混合する可燃物は木粉で対照物質には過塩素酸カリウムを使います。そのため、消防法の第一種、第二種、第三種がそれぞれGHSの区分に対応しているわけではありませんが、危険性の考え方の基本は同じと考えらます。消防法の酸化性固体の判定に用いられる落球式打撃感度試験はGHSでは採用されていません。酸化性液体と固体は、それぞれ消防法の第六類と第一類に対応しますが、危険物に分類されない化学品もあります。
11) 有機過酸化物
二価の-O-O-結合を持ち過酸化水素の水素を炭化水素に置換した構造です。消防法の第五類第一種自己反応性化学品に相当します。
GHSと消防法の対比を参考として、適切な取扱方法による火災・爆発の予防と消火(初期消火)方法を考えることができます。危険物の管理に関する技術上の基準は、危険物令第24条が、危険物一般の貯蔵・取扱いに関する着火源・危険物とその容器、取扱場所の管理を、同第25条が各類ごとの共通事項を示しています。そのほかに個別化学品には特有の危険性があるので、SDSの特記事項が参考になります。
物理的危険性(火災・爆発)を持つ化学品のリスクアセスメント
労働安全衛生法は、事業者による火災・爆発等の物理的危険性を含めて化学品のリスクアセスメントを努力義務としています。リスクアセスメントは、危険有害性を把握し顕在化の可能性(頻度)とその時の影響(被害)からリスクを評価することですが、指針はその後のリスク低減のための優先順位付けとその措置の決定を一連の手順としています。労働安全衛生法の下では、労働者や事業所の施設・設備に対する影響を考えることになります。中国天津の爆発事故に見られるように、化学品の性状と取扱量にもよりますが、取り扱う事業所にとどまらず周辺地域にも影響を及ぼすことがあります。事業所外に影響が及ぶときには、同時に発災事業所でも何らかのダメージは避けられないのですから、消防法を念頭に置いたリスクアセスメントは労働安全衛生法のリスクアセスメントの延長上で考えることになるでしょう。影響がどの程度の空間的広がりを持ち、その結果として周囲にどのような被害を及ぼすのか、ということを評価できればよいのですが、実際には事故災害の大きさには不確実性があり正確な予測は困難です。そのため影響範囲が推測できたとしても対策をその予測区域だけに限定することは難しく、事業者の経験や知見も利用します。
労働安全衛生法は、1976年(2000年改正)に「化学プラントにかかるセーフティーアセスメント」を策定しました。使用する物質、容量、温度、圧力と操作を要因とし、エレメント単位で要因ごとに危険度に四段階の評点をつけ、総和からエレメントとしての危険度を評価します。物質の要因としては、施行令別表第一の危険物に評点が付けられていますが、消防法の対象となるような同種の危険性を持っていても、ここに例示されない化学品のアセスメントを試みるのであれば、その評価は取扱者の経験と知識に委ねられます。この方法は定量的な危険物の基準が示されていないので、事故災害時に被害が及ぶ範囲の推測はしません。
定性的な手法の一つであるダウケミカル法では、燃焼熱から物質係数(MF)を求め、それに一般および特殊工程の要因に設定された係数をかけて求められる火災・爆発指数(F&EI)が危険性の指標となります。日本で用いられるものとは異なる米国の単位系で表現されているので使いやすくはありませんが、MFの公開されていない物質も計算で求めることができることがあります。F&EIから被害の及ぶ領域の最大半径(R:領域)を求める式も提示されているので、最悪の事態を予測することもできます。実際にはMFは同じ分類の危険性を持つ物質の間ではそれほど顕著な違いはなく、危険性の解析は定性的にならざるをえません。実際の被害の及ぶ範囲は事業所の施設・設備の配置や大きさあるいは地形・風向などの自然現象に依存するので正確な予測は困難です。しかし、物理的危険性は多量のエネルギーが短時間に放出されることで起こるので、ダウケミカル法のMFの考え方には、一定の合理性があるともいえるでしょう。労働安全衛生法のセーフティーアセスメントもダウケミカル法もその仕組みで工程の危険性を考慮しますが、リスクアセスメントを行うためには、事故や災害の起こりやすさを考慮する必要があります。そこで二つの手法で得られた危険性の指標を使って、FTA (Fault Tree Analysis)やETA (Event Tree Analysis) などの手法を併用してプロセス全体のリスクアセスメントを行うことになります。
この二つの方法は、GHSの仕組みが整備される前に提案されている方法なので、危険物の分類は労働安全衛生法の定める危険物あるいは米国防火協会(NFPA)の分類を利用していますが、JISHA(中央労働災害防止協会)方式の労働安全リスクアセスメントと厚生労働省のリスクアセスメント入門(ガイドブック)は物理的危険性の判断にGHSの分類・区分を用います。JISHA方式では影響の重大性(S)、異常現象発生の頻度(F)、化学品固有の危険性からの危険源発生要素の可能性(P)の3種の要因からリスク評価ポイントを求めます。この方式は化学プラントだけでなく、化学品を取り扱う事業場の作業全般に照準を合わせているので、広い範囲の事業者が使用できます。厚生労働省のガイドラインでは、SDSの危険性の分類・区分に対応した、安全対策・応急措置・保管方法・廃棄方法に係る注意書きの利用も考慮しています。SDSにGHSの「危険有害性」の分類・区分が特定されていない場合は、事業者自身がそれを行うための手順をチェックフロー型で示しています。しかし、単一化学物質からなる化学品はともかく、流通する化学品の多くを占める混合物化学品のうち、意図的に製造された混合物製品では、製品情報が公表されている事例は少なく、化学品(SDS)の受領者には簡単な作業ではないでしょう。必要であれば、化学品の供給者とのコミュニケーションから情報の取得を考えざるを得ないでしょう。
今回は化学物質の消防法の物理的危険性のリスクアセスメントを、GHSや労働安全衛生法との関係から考えましたが、事業所内にとどまらない広域の火災・爆発事故の影響をあらかじめ評価することは難しいことがわかります。しかし、完璧ではないにしても、事業者の社会的責任の見地から、事故災害で事業所の周辺にどのような影響が及ぶ可能性があるのか、ということをあらかじめ考えておくことは重要なことと思いますし、リスクコミュニケーションの場では、そのような活動は事業所の安全管理活動への好ましい評価につながるのではないかと思います。
第9回 大気汚染防止法、水質汚濁防止法
1 大気汚染防止法
大気汚染の防止を目的としたこの法律は、1962年のばい煙の排出の規制等に関する法律(ばい煙規制法)に始まります。経済成長とともにエネルギー消費が飛躍的に増加し、そのころは主なエネルギー源が石炭であったため、燃焼から発生するばいじんによる環境(大気)の汚染が社会的な問題となりました。その後、エネルギー源の石油への転換が進むと、硫黄酸化物や窒素酸化物による大気汚染が問題となりました。そこでばい煙規制法を廃止し大気汚染防止法になり、ばいじんだけでなく大気中に放出される化学物質の規制も加わりました。化学物質には産業活動に伴って「化学品」から放出されるだけでなく、自動車などの内燃機関の運転で生じる排気ガスも含まれますが、本稿では化学物質(品)の取り扱いに関する事業者の管理活動を主題としていますので、ここではそのことは扱いません。また、ばいじんの規制から始まっていることもあり、特に健康有害性の高い特定ばいじんとして石綿を規制の対象としていますが、規制により現在では新たに用いられることはなく、主な発生源は規制以前に使われた建築物などの解体作業などですので、やはり本稿では取り上げません。
1996年の改正で大気汚染防止法による化学物質の規制が始まりました。この時、有害大気汚染物質として234物質が中環審で例示され、中でも対策を急ぐ必要がある優先取組物質として22物質があげられました。対象の物質数も多く、またその使用方法も多岐にわたっているので、法令でこれらの物質の取り扱い方法を詳細に規定することが難しかったこともあって、改正法の施行と同時に産業界には有害大気汚染物質の「自主管理計画」の策定と実行が求められました。この自主管理計画の対象物質は13物質に過ぎなかったのですが、実行を求められた業界団体とそこに参加する企業は、実状に応じて効率的な有害大気汚染物質の放出を抑制する活動を行いました。「自主管理計画」は1997年から1999年までの第一期と2001年から2003年までの第二期に分かれて実施されましたが、それぞれ自主管理計画開始の二年前の実績を基準とした35%, 39%の削減目標に対して41%, 49%の削減という結果になりました。
第一期の自主管理計画が実施される中で、1999年には化学物質排出把握管理促進法(化管法/PRTR法)が公布され、354物質の排出・移動量登録(PRTR)制度が始まり、事業者は2001年度から実績の報告が求められるようになりました。自主管理計画の対象物質は少ないものの削減目標を設けての活動でしたが、PRTR制度では削減目標を設定しないものの、事業所ごとの排出実績が公表されることが活動のインセンティブになりました。
大気汚染防止法は規制される化学物質として、有害大気汚染物質と揮発性有機化合物(VOC)をあげています。有害大気汚染物質は人の生活環境の中で呼吸により体内に摂取されることによる健康被害を、VOCは大気に放出されてから凝集等により浮遊性微粒子(SPM)を形成することや光化学オキシダントを生成することが懸念されています。このような性質は、大気汚染防止法の対象物質だけに限られているわけでなく、多くの化学物質にも考えられるので、化学物質の大気放出が少なければ少ないほど好ましいことは明らかです。
化学物質の大気放出の抑制には様々な手法がありますが、事業者はいろいろな理由で制約を受けるので、実施可能で最も効率的な方法を選択しますし、それが多くの種類の化学物質に対応できればそれに越したことはありません。PRTR制度により化学物質の大気放出は大きく削減されましたが、事業者はそれ以前に改正大気汚染防止法への対応として検討を進めてきた化学物質の大気放出の削減方法を進化させました。この二つの法律で大気環境への化学物質の放出防止には大きな効果を上げたということができます。
2 水質汚濁防止法
水質汚濁防止法(水濁法)は、工場・事業場から公共用水域への排出水と、地下浸透による地下水の汚染を規制して水質の汚濁防止を図り、国民の健康の保護と生活環境を保全し、排出される汚水・廃液から人への健康被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任を定めて、被害者保護を図ることを目的としています。
水濁法は、有害物質として28項目に排出基準を定めており、生活環境の12項目にも化学物質に関係するものがあります。このほかに指定化学物質56項目があります。化学物質の公共用水域への流出原因には、無害化処理を行わずに、あるいはその処理の工程が不調となって放出されることが考えられますが、地下浸透による地下水汚染が最も起こりやすいのは、事故その他の理由により事業所敷地内で化学物質が漏えいして、土壌中に放出された結果だろうと思います。
PRTRの集計結果を見ると、2003年から2013年の10年間で大気放出は42%の削減であるのに対して、公共用水域への排出は38%の削減にとどまっていますが、これはもともとの公共用水域への排出量が大気の5%程度でしかないことを考えれば、削減率が若干低くなることはやむを得ないことでしょう。化管法と水濁法は法律の性格だけでなく、対象とする事業者も異なるので、単純に並べて考えることも難しいのですが、事業者からの公共用水域等への化学物質の排出抑制は着実に進んでいると考えます。
公共用水域に排出された化学物質が社会的な問題となった最近の事例に、2012年の利根川水系に放出されたヘキサメチレンテトラミンが下流の浄水場の滅菌工程で塩素と反応して発生したホルムアルデヒドが水道に混入したことで、上水道の供給が停止したことがありました。ヘキサメチレンテトラミンの固有の健康有害性は低く、水濁法の規制物質ではありませんでした。この物質はアンモニアとホルムアルデヒドの脱水縮合で製造されますが、ホルムアルデヒドは分子間に脱水縮合でメチレン架橋を導入するために多用されています。そして、ヘキサメチレンテトラミンはホルムアルデヒドの徐放性を利用する使い方も知られていたように、加水分解でホルムアルデヒドを発生する可能性があることも知られていました。2012年の問題では浄水場での塩素滅菌という特殊な工程で、急速に起こった反応で問題が顕在化したことになります。この事例は健康有害性が低く物理的危険性の少ない物質でも、特殊な条件のもとでは想定外の問題を引き起こす可能性があることを示しています。ヘキサメチレンテトラミンはその後、指定物質になりました。このように、健康有害性が低く、規制されていない物質でも特別な条件では社会的に影響の大きい事故を招くことがあります。それゆえ、有機化合物の取り扱いでは環境中に放出する以前に、無害化さらには二酸化炭素と水まで分解する無機化などによる前処理が必要でしょう。種々雑多な化学物質が混在し組成もはっきりしない廃棄物には燃焼以外の方法の適用が難しいように思われますが、分別などを行えばより適切で効果的な前処理を採用することが可能になるのではないでしょうか。
第10回 土壌汚染対策法、廃棄物処理法
1 土壌汚染対策法
平成14(2002)年制定の土壌汚染対策法は、「土壌中の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること」を目的としています。ここで、規制の対象となる「特定有害物質」は、政令で定められた、鉛、砒素、トリクロロエチレンなどの25物質です。
土壌中の化学物質による人の健康影響は、①有害物質が溶け出した地下水を飲んで口にする(間接)リスクと、②有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取するリスクが考えられますが、①の観点から25物質に土壌溶出量基準が、②の観点から25物質のうちの9物質に土壌含有量基準が設定されています。
空気(大気)からの健康リスクに対しては大気汚染防止法が、水系(飲料水)からの健康リスクに対しては水質汚濁防止法が制定されていたので、土壌汚染対策法の制定で私達をとりまく環境全体からの化学物質へのばく露による健康リスクを低減するための法体系が整備されたことになります。
化学物質を取り扱う事業者にとって、法律の規制とそれへの対応を考えるうえで、土壌汚染対策法が大気汚染防止法(1968)や水質汚濁防止法(水濁法、1970)とは性格を異にするように思われるのは、大気・水系・土壌の三種類の環境の中で、土壌中の化学物質の挙動が他の場合とは異なるからでしょう。大気に放出された化学物質は拡散が早く、排出源近傍の高い化学物質濃度も短時間に減少するだけでなく、特に難分解性の高い化学物質を除けば、一般的には光分解や湿気による加水分解などにより有害性が緩和されます。同様に、開放系の河川等の水系に放出された化学物質も、拡散・希釈されるだけでなく、加水分解や水中の生物や汚泥による生分解で有害性が緩和すると考えられます。拡散・希釈されるということは別の言い方をすれば、汚染領域が拡大することであり、化学分解や生分解からの生成物質は必ずしも元の物質よりも有害性が低くなるという保証もありませんので、それはそれで問題が無いとは言えないのですが、大気中と水系では汚染源周辺の化学物質の濃度は比較的速やかに減衰することになります。土壌中でも加水分解や生物分解を考えることもできますが、土壌への吸着もあり拡散しづらく、比較的長期にわたってその場所に留まることになります。大気や水系などは公共財と考えられるのに対して、土壌(土地)は多くが私有財産で法による規制も進みませんでしたが、土壌汚染対策法の制定で事業者は自らの責任による、あるいはそれ以前の負の遺産や自然的要因に基づく事業所敷地内の土壌の汚染の問題に直面することになりました。一般に土壌の汚染は「時が解決する」ことを期待することはできず、汚染状態の解消には何等かの形で人為的な浄化作業が必要になります。
土壌汚染対策法の目的はリスクを限りなく(許容可能なレベルまで)低下させることにあるので、ハザードの除去(汚染物質の除去あるいは無害化)だけでなく、人へのばく露の防止によるリスクの低減も有効な方法としています。土壌中の化学物質の大気や水系への移動を防止するための封じ込めや土地表面の被覆がそれにあたり、それによって土壌中の化学物質による人の健康リスクを低下させることが可能ですので、汚染土壌が存在していてもそのような方策で工場従業員あるいは近隣住民へのリスクを低減し、工場の操業を継続することが可能です。
しかし、この措置では敷地内の汚染源は残ったままです。先に記したように、時が経過しても自然の浄化や無害化はあまり期待できないので、汚染が明らかになれば工場敷地の資産価値は下がり、売却時の価格下落は容易に想像できます。工場の移転・拡張あるいは事業の売却などは、企業の発展のためには避けられないことですが、汚染土壌の浄化に費用をかけて資産価値の維持を図るのか、それとも将来の売却価格の低下を承知のうえで、ばく露防止対策のみで当面の汚染土壌の問題の解決を図ることが適当なのか、という難しい選択を迫られることになります。
土壌汚染の実態を知るためには、地歴調査から汚染のおそれが考えられなければそこで調査は終了しますが、汚染の可能性があれば該当の区域を格子状に区切り試料の採取・分析で汚染状態が特定されます。地歴調査からは過去の自工場に関係する事実はわかりますが、それ以前のことには調査が及ばないことがありますし、自然的要因による汚染はサンプリングを行って初めて気づくこともあります。土地の売却にあたっては、購入者からは土地利用の履歴調査だけでは土地の汚染に対して安心できない、あるいはより正確な状態を知りたいということで、詳細なサンプリングデータを求められることがあります。自然的要因が汚染の原因である時に、浄化を所有者に求められることには納得のいかないこともありますが、土壌汚染対策法は自然的要因であっても基準値の超過は「汚染」とみなしています。日本は火山国ですので、自然の状態でも基準を超えた重金属や無機物が検出されることがありますが、それが自然的要因によることを証明することは簡単ではありません。自然的要因による汚染は、比較的広い領域で敷地全体に一様に分布していることや、特定の地層に分布することで深い部分まで特定有害物質が検出されることがあるものの、一方で汚染と見なされるレベルではあっても特定有害物質の濃度はそれほど大きくないことも特徴といえます。しかしこのようなことがわかるのは、多くの場合は試料の採取・分析を行った結果であり、自然的要因であることがわかるまでに事業者(土地の利用者あるいは所有者)には大きな負担が強いられることになるでしょう。そこまでの手間とコストをかけて土壌調査を行い、なおかつ売却時に購入予定者と価格交渉をするのであれば、最低限の対策を行ったほうが時間的にもコスト的にも得策と考えることもあります。
以前は、自工場敷地内に不要物や廃棄物を埋め立て処理することが違法とされていなかったので、地歴調査の段階で汚染が予測できることもあります。最も使い勝手の良い敷地の中心部に不要物の埋め立て処分を行うことはあまりないので、往々にして敷地の周辺部から汚染が認められることがありますが、周辺部の土壌調査は行うものの中心部の調査を省略するというわけにはいかないので、結局敷地全体の調査を実施することになるでしょう。
土壌汚染対策法の特定有害物質は、第一種(揮発性有機化合物)、第二種(重金属等)、第三種(農薬・PCB)に区分されます。第二種と第三種は国・地域によって多少の違いはありますが、おおむね一致しているといえるでしょう。しかし、第一種の揮発性有機化合物は、国や地域により事情が異なります。揮発性有機化合物といえば、まず思い浮かべるのが有機溶剤ですが、土壌汚染対策法の指定物質は、ベンゼンを除けば塩素系炭化水素溶剤で、汎用的な脂肪族・芳香族炭化水素やアルコール類・ケトン類などは入っていません。世界標準の一つと見なされるオランダの規制では、芳香族炭化水素やフタル酸エステルなども規制の対象としています。使用量が多いトルエンやキシレンなどの炭化水素系溶剤は、取り扱う作業場の下や近傍の土壌から検出されることもありますが、大量に貯蔵され日常的な保守点検も難しい地下タンクの周辺で高濃度の検出が認められることが多いようです。そのため、米国などの土壌中の溶剤による汚染に対する規制の厳しい国や地域では、地下タンクを廃止し地上のタンクに移設する動きもあるようです。日本では土壌汚染対策法の特定有害物質ではないので、汚染の指標となる指定基準もなく土壌の浄化は求められませんが、本来存在するはずのない有害な化学物質が土壌中に認められれば、土地の売却時に購入者から浄化を求められる可能性もあります。環境の汚染問題に社会的な関心が高くなっている現在は、将来の資産価値への影響や世界的な土壌汚染に対する考え方の変化を受けて、B to Bの関係の中では法律の規定だけに限った議論だけにとどまらなくなってきているように思います。中でも、環境基本法の環境基準で「要監視項目」にされている物質には、なんらかの対応が必要になることが予想されます。
このように化学物質の土壌汚染については、様々な問題が提起されるようになりました。汚染土壌は、管理のうえでもまた土地の資産価値のうえでも継続的な課題となるでしょう。ここで考えておきたいのは、「汚染状態は困る、しかしどのくらいの汚染であれば許容するのか、あるいは浄化するのであれば、どの程度まで浄化すべきなのか」という点で、社会的なコンセンサスが成立していないことでしょう。全く汚染が無い程度に浄化を求めれば、化学物質を含んだ土壌を持つ敷地の売買は成立が難しくなるでしょう。しかし、私有財産であると同時に公共財とも考えられる土地の有効利用を進めるためにも、汚染された土地(ブラウンフィールド)をどのように再利用していけばよいのか、社会的なコンセンサスが必要になってきているように思います。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
昭和29(1954)年の清掃法は、ごみ問題とともに事業活動から発生する産業廃棄物に対処するために、昭和45(1970)年に廃棄物処理法になりました。それから半世紀近くが経過しましたが、産業廃棄物の管理は合理的な処分を進めるとともに、資源の有効利用の見地、そして3Rとの関係からも、現在でも重要な社会的課題になっています。
産業廃棄物のうちで「爆発性・毒性・感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」は特別管理産業廃棄物とされ、その中でも「特に有害性の高い物質あるいはそれを含む廃棄物」は特定有害産業廃棄物です。ダイオキシン類や廃PCB及びそれが混入・付着した廃棄物などがそれにあたります。廃油・廃アルカリ・廃酸は特別管理産業廃棄物ですが、特定の有機塩素系化合物・重金属・農薬類が判定基準以上含まれていれば特定有害産業廃棄物になります。この特定有害産業廃棄物に指定される物質は、PCB・ダイオキシンを除けば、土壌汚染対策法と水質汚濁防止法の規制物質に一致します。このように産業廃棄物に含有される化学物質からの人の健康影響では、水系あるいは土壌からの人へのばく露を念頭に置いた規制となっていることがうかがわれます。
産業廃棄物といってもいろいろで、例えば残余化学原料のように、含有物質の種類が限られていて、有害性も比較的容易に予測でき、適切な処理方法も決めやすいものから、化学反応を行って目的物を取得した後に反応器中に残された窯残やそれを取り出すのに使用した処理液のように、プロセスから発生する中で、どんな物質がどのくらい含まれているのか、またどのような有害性を持つものであるのか、ということが極めて分かりにくいものまで様々です。
かつては発生する廃棄物を事業所にある焼却炉などを使って事業者自らが減量化・中間処理を行うこともありましたが、ダイオキシン類対策特別措置法によって焼却炉からのダイオキシンの発生を最少化させるために、焼却炉としての能力の向上と運転条件の最適化が求められるようになりました。そのため、事業所内で焼却処理等を行っていた事業所も、廃棄物の事業所内処理を停止し、外部に委託するようになりました。適切な産業廃棄物の処理には、廃棄物を発生させた事業者から廃棄物への処理業者に対して必要な情報の提供が求められています。マニフェスト制度で、廃棄物の種類・数量などは書面で情報の伝達が行われていますが、産業廃棄物の危険有害性の情報を伝えるためには、マニフェストだけでは十分ではないことから、化学品のSDS(Safety Data Sheet)に倣った廃棄物データシート(WDS: Waste Data Sheet)が用いられるようになっています。
環境省から提示されているWDSの書式に、必要な情報を記載して処理業者に交付すれば、廃棄物の処理に伴う不測の事故などを抑制することができるでしょう。当初のWDSは廃棄物処理法への対応に必要な情報を記載するようになっていましたが、水濁法の稿で記したように、廃棄物として処理が委託されたヘキサメチレンテトラミンが河川に流出した事例を受けて改訂された書式では、水道水源における消毒副生成物前駆物質に関する情報を記載する欄があります。
また、化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律;PRTR法ともいう)のPRTRは廃棄物としての移動量の報告を求めているので、これに関する情報も記載するようになっています。残余の化学原料が廃棄物として処理業者に委託される場合には、その化学原料に添付されていたSDSを利用してWDSの作成が可能ですが、組成の定かでない不要物・プロセスから発生した処理物のWDSを適切に作成することは簡単ではないでしょう。そのため、WDSも、その可能性があるかもしれない、という安全サイドに立った立場からの作成となることがあります。
廃棄物による事故災害では、人の健康や環境に対する影響だけでなく、廃棄物処理場での物理的な危険性による火災・爆発や不適切な化学物質の混合からの有害性物質の発生もあります。このような事故・災害は、産業廃棄物処理業での労働安全衛生の問題ですが、事故事例の発生は現在でも無視できず、このような労働災害の予防にもWDSの利用は有効です。
廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物の「廃油」は、引火点が70℃以下とされていますので、火災の予防には消防法の第四類引火性液体の第二石油類と同様の配慮が必要となります。
【まとめ】
これまで環境汚染防止のための法律として、大気汚染防止法・水質汚濁防止法・土壌汚染対策法・廃棄物処理法を見てきました。人の健康影響を考えるうえでは、大気汚染防止法が呼吸器(大気)を経由したばく露を想定しているのに対して、他の三法は消化器(飲料水)あるいは直接ばく露の経路を考慮しているという違いはありますが、規制物質は互いに共通していることがわかります。また、これらの法律で規制される物質の毒性は、シアン化合物を除けば長期毒性あるいは環境毒性が主ですので、これは化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の化学物質規制とも共通しているということもできます。
環境中に存在する化学物質による人への健康障害は、影響が顕在化するまでに長い時間を要するだけでなく、因果関係の科学的な証明も困難です。それゆえに、化学物質を取り扱う事業者には、法規制物質であるか否かに関わらず、自主的な管理で環境への放出を抑制することが望まれているといえるでしょう。