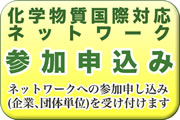ポストSAICMに求められる化学物質管理
- このコラムは、化審法(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を指す。以下同様。)見直し合同委員会のメンバーでもあった日本ケミカルデータベース株式会社アドバイザーの北村卓氏に、化学産業界の第一線で過ごされてきた豊富な経験に基づき執筆をいただいたものです。
- このコラムに記載されている内容に関し、法的な対応等を保障するものではありませんのでご了承ください。
- このコラムについてのご意見・ご感想を下記までお寄せ下さい。今後の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見は、個人情報等を特定しない形で当ネットワークの情報発信に活用(抜粋・紹介)する場合もあります。あらかじめご了承下さい。
→ご意見・ご感想電子メール送付先:
化学物質国際対応ネットワーク事務局(chemical-net@oecc.or.jp)
目次
第1回 SAICMと事業者の活動 (1)
1.SAICMの採択
2006年の第1回国際化学物質管理会議(ICCM-1)で採択されたSAICM(国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ:Strategic Approach to International Chemicals Management)は、2002年のWSSDの「2020年までに化学物質が健康や環境への著しい影響を最小とする方法で生産・使用されるようにする」ことを実現するための具体的な活動内容を示しており、以下の三文書からなっています。
- ドバイ宣言:政治的宣言です。
- 包括的方針戦略:「科学的なリスク評価に基づくリスク削減」、「有害化学物質に関する情報の収集と提供」、「各国における化学物質管理体制の整備」、「途上国に対する技術協力の推進等を進めること」、「違法な国際取引の防止」を目的としました。
- 世界行動計画:活動内容を記載したガイダンス文書です。
既に目標年の2020年は過ぎ、とりまとめを行うはずのICCM-5は、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響で開催が延期されていますが、SAICMの目的を再確認しながら、その延長線上で事業者(産業界)に望まれる化学物質管理の姿(ポストSAICM)を考えたいと思います。
産業界のSAICMに沿った活動には、主として「業界団体」が政府関係機関などと連携を取りながら行う活動と、個々の「企業」あるいは「事業所」の活動がありますが、ここではポストSAICMを後者の活動の中心に考えたいと思います。
2.SAICMの背景
SAICMの成立の背景を振り返ることは、事業者がポストSAICMの管理活動を行ううえで参考になるでしょう。20世紀の終わりから今世紀にかけて、化学物質の管理政策は世界的に大きく転換しています。原点となるのは、WSSDの10年前にリオデジャネイロで開催された地球サミット(1992年)です。そのアジェンダ21の第19章は、
A:化学物質のリスクの国際的評価の拡充と促進
B:化学物質の分類と表示の調和
C:有害化学物質及び化学物質のリスクに関する情報交換
D:リスク削減計画の策定
E:国レベルでの対処能力の強化
を課題としました。具体化は各国に委ねられましたが、SAICMはこれを加速化して国際的に連携した活動として進めるものとして位置づけたものと言えます。「国際化」と「リスク削減」の二つが活動のキーワードと考えることができます。
【国際化】
工業化学品やそれを用いた製品は、先進国・経済移行国・途上国を問わず、地球上の隅々まで商品として流通していますが、世界には化学物質の危険有害性から人や環境への好ましくない影響を予防するための法制度が十分には整っていない国・地域があります。そのような国・地域に市場を求めて工業製品が流入することや、廃棄物規制が未整備の国・地域に、危険有害物質を含有する廃棄物や実質的には廃棄物同然である中古品などが流入することなどで環境汚染が問題となりました。現在の言葉を使えば「SDGs」に適合しないもので、化学物質に関する「南北問題」ともいえる状況です。この問題の解決には、すべての国・地域で管理制度が整備され、適切に運用されることが必要ですが、そのためには整備のための能力向上・技術協力、あるいは知識や情報の共有化などが必要となります。これらの活動は規制の進んでいる国が主導して進められますが、経済移行国や途上国に、関係会社や協力会社を持つ企業には無関心ではいられないことでもあるでしょう。
【リスク削減】
化学物質のリスクは「有害性(ハザード)」と「ばく露」の二つの要因で評価します。ハザードだけから考えるよりも手順は複雑ですが、リスク評価からは様々な不確定要因から発生する質の異なる問題の解決において、優先順位を決めることが容易になるので、これからの化学物質管理には習得しておきたい手法です。
近年は、法規制もハザードベースからリスクベースに移行が進んでいます。最初に、欧州のREACH規則(2006年)が制定されたときは、世界中に大きなインパクトがありました。その後の各国で制定・改正された法規制は日本の改正化審法を含めリスクの概念を取り込むようになりました。ハザードベースの規制の対象は主として製造事業者でしたが、リスクベースの規制では化学品の購入・使用者も化学物質(品)からの人の健康や環境への好ましくない影響を考慮することが求められるようになり、それを実行するためには、商流に沿ってハザード情報の伝達が的確に行われることが前提となります。
3.SAICMの世界行動計画と産業界の活動
「ドバイ宣言」と「包括的方針戦略」は、主として国レベルで化学物質管理政策をどのように進めるべきか、ということを示していますが、「世界行動計画」の273の行動項目には行動主体に「産業界」を挙げているものがあり、ここでICCMが産業界に期待することがわかります。該当する多くの項目から、要点を抽出すると以下のようになるでしょう。
①ハザードデータの収集と安全データシート(SDS)やラベルによる情報の周知・交換・提供
日本の化審法は既存化学物質のハザードデータの収集は国が行うこととしていましたが、日本の企業もOECDの高生産量化学物質点検プログラム(HPVプログラム)や日本政府による官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(Japanチャレンジプログラム)への参加を行うことなど、化学品のハザード情報の取得と整理やリスク評価に一翼を担ってきました。化学品管理のリスクベースへの転換で、ばく露情報を持つ産業界の果たす役割は重要です。
②クリーナープロダクション:よりクリーンな製造
これまでも化学品の製造・使用事業者は、生産工程からの環境負荷を低いものとすることに心がけてきましたし、原材料やエネルギーを効率的に利用することは経済性の面で事業者にメリットがあることの認識は進んでいます。環境に負荷を与えない化学的な生産プロセスは「グリーンケミストリー」と呼ばれ、アカデミアでも研究が進んでいますが、産業界も新しい手法の開発とともにそれを実際に実現するための、企業化の応用研究に取り組んでいます。
③高ハザード物質には代替物質の使用
化審法の特定化学物質や労働安全衛生法の製造禁止物質などが代表的な高ハザード物質で、代替物質の開発が進められてきました。これからは特定の条件で懸念される化学物質(例えば、乳幼児・高齢者・妊産婦等の社会的弱者が使用する可能性のあるもの)についても、リスク管理の視点から、代替物質の開発・使用が求められるようになるでしょう。しかし、重要な用途で使用されているものの、残念ながら必ずしも直ちに代替物質の開発ができるとは限りません。そのときには、リスク評価・管理の考え方を適用することになります。化学反応では高ハザード物質が意図しない形で副生することもあります。それらを抑制する技術の開発は、②のクリーナープロダクションの一つの形態と言えるでしょう。
④廃棄物の発生の抑制、PRTR
廃棄物は化学物質とは別の法令で規制されています。廃棄物は出所が明らかでな場合や、由来が不明確になりがちで、しばしば廃棄物の処理工場では火災の発生源となることもあり、有害物の含有状況が処理業者に伝わり切れない事例も報告されています。クリーンな形で処理されても、廃棄物処理工程はそれ自体がエネルギーや資源を必要とするので、環境負荷の低減には廃棄物の発生量を抑制することが望ましいことは自明のことと言えます。PRTRデータは制度の開始以来相当量の削減効果となりましたが、それでもなお環境中に放出される化学物質があることを示しています。PRTR制度は罰則を伴いませんが、実質的にこの制度が開始されてから環境への排出量は削減されていることは、事業者の自主的な活動も環境負荷の低減には有効であることを示しています。
⑤化学物質のライフサイクル管理
マイクロプラスチックによる海洋汚染が問題となっています。プラスチック類に代表される化学的な工程を経た材料は、製品として使用されるときの利便性だけでなく、ライフサイクル全体を考慮することを社会が求めるように変化は進んでいます。役割が終了した時に適切な管理を考えるだけでなく、製品の開発・設計時にリサイクル・リユースなどのライフサイクル全体を組み込むことが求められています。
⑥労働安全衛生管理
労働安全衛生管理は、日本の労働安全衛生法や国際労働機関(ILO)の条約等で必要な事項が明文化されています。労働者の安全衛生を確保するためには、事業者はそれを遵守することが基本となります。規制する法の条文にリスクベースの化学品管理を具体的な形で記載することが難しいこともあるので、事業者は作業現場の実態に即した方策を必要とします。このためには関係者間の情報の共有と参加が必要になります。
⑦関係者の化学物質管理の訓練
化学物質の管理に限らず、緊急時の対応等、いざという時には座学や文献からの知識だけで充分ではないことがあります。関係者間の共通の認識や情報の共有とともに訓練が重要であることをSAICMは指摘していますし、訓練を重ねることで、その対策の実行可能性が初めてわかることもあります。
このように、世界行動計画には、事業者が会社あるいは事業所として、これからの化学物質管理で求められることが的確に記載されていると言えるでしょう。また、ここに記載された活動は、いずれもSAICM以降に開始されたものではなく、従来から事業者が考え実践してきたことでもあります。
次回は、これまで日本の事業者が行ってきた化学物質の管理活動を振り返りながら、これからの活動を考えます。
第2回 SAICMと事業者の活動 (2) 
1.法規制遵守と自主管理
日本では化学物質を規制する法制度の整備が進んでいるため、事業者はそれを遵守することが化学物質管理の初めの一歩であることは、改めて記す必要はないでしょう。「環境」と「環境を経由したばく露からの広い領域と不特定多数の人の健康を守る」ことを目的としては化審法・化管法や大気汚染防止法・水質汚濁防止法などの環境法制がありますし、食品衛生法や建築基準法などの、特定の製品からの好ましくない影響の予防を目的とする法律もあります。しかし、法の規制だけで化学物質からの好ましくない影響を未然に防止することは、以下の制約もあって簡単ではないように思います。
- 法の規制は広範な事業者が対象となります。遵守しようとしても、それが経済的あるいはその他の理由で難しければ、守られない規制となって有効性が損なわれることになります。そのため、規制の範囲と実施項目は、多くの事業者が対応しようとすれば、それが可能なレベルに留まることがあります。
- 化審法の新規物質の事前審査制度は、制定以来高毒性・難分解性・高生物蓄積性物質は登録を認めない原則で運用されていますが、市場で流通している化学物質を健康障害が認められない段階で厳しい「蛇口規制」を行うことは、社会の混乱を招く懸念もあり、実際に問題が発生してからの「後追い」の規制となりがちです。
このような理由で、事業者によるリスクベースの自主管理活動は、これからの化学物質管理で重要な役割を果たすようになるでしょう。事業者は自社で用いる原料の化学品や製品がどのように使用されているかということを知ることができ、ばく露状況を想定して好ましくない使用方法を特定できる立場にあるからです。SAICMが事業者の役割を示す以前に、化審法や化管法の見直しの検討会でも、化学物質の安全管理は法規制と事業者の自主管理を車の両輪としてすすめることが望ましいことが指摘されていました。
2.事業者の自主管理
一方で、利潤の追求が目的である事業者の自主性に任せておいて、適切な化学物質管理ができるのだろうか、という疑問を持つ見方もあります。しかし、事業者から国への報告を基にして運用されている化管法のPRTR制度や、大気汚染防止法の有害大気汚染物質の自主管理計画では、環境中に放出される化学物質の削減実績があるので、日本では罰則による強制力を持たない事業者の自主的な取り組みも一定の役割を果たすことが期待できます。ここに挙げた二つの活動は、ともに化管法と大気汚染防止法の枠組みのもとで実施されたので、事業者は自らが対象の化学物質を決める必要はなく、国が定める物質の環境排出量の削減だけを考えればよかったのですが、自社製品からの消費者への影響や取扱い現場での労働衛生を考えるときは、対象物質・ばく露対象・ばく露経路などのリスク評価に係る因子を自らが特定して実施することになります。
同じことを法規制で行おうとすると、対象物質を一つに限定しても、想定できる多種多様なばく露対象とばく露経路に対してリスク評価を行うことになり、それには極めて多くの情報と作業が必要となります。さらに代替を考えるときには、代替物質についても同様の作業を行い、さらに代替効果を正当に見積もるためにリスク評価結果の比較作業(代替リスクの評価)も必要となるので、実質的に法規制化は難しくなります。
事業者が自社からの周辺領域への影響をリスク評価したのちに対応を考える、というリスク管理の手順を環境リスクに適用して考える必要のあるケースはそれほど多くないように思います。自社(事業所)だけから排出される物質が周辺環境に影響を与えることが懸念されるのであれば、リスク評価を行う前に排出量の削減を図るべきでしょうし、リスク評価結果が許容可能なレベルであったとしても、そのまま放置しておいて良いということにはならないと思います。多くの排出源から同一物質が放出されている地域では、自社の排出実態を正しく把握して国や地方自治体の定める環境基準や排出基準を遵守することや、必要であれば実施事項を策定すること、すなわち「ハザード管理」の手法を応用することが現実的でしょう。
3.リスク評価とリスクベースの化学物質管理
リスク管理活動は、リスク評価の結果からリスク低減を目指す活動です。「交通事故」と「化学発がん」による死亡などのような、全く性格の異なるリスクを比較することに意味があるかどうかについては議論があります。例えば、労働現場で使用する化学物質による労働衛生リスクや、消費者商品の表面処理剤からの消費者への健康影響リスク、などのようにばく露対象やばく露経路が特定可能な場合、リスク評価結果の比較は、事業者の対策の優先順位の決定に用いることができます。
危険有害性については、国際的にGHSの分類・区分が定着し始めているため、リスク評価の作業が容易になっただけでなく、恣意的でない結果を得ることが可能になりました。化学物質の有害性データも近年は整備がすすんでいるだけでなく、国や専門機関は多くの化学物質の分類・区分を公開しています。それを用いれば、数値で示されるリスク評価結果とともに相対的なリスクを判断できる定性的なリスク評価を行うことが容易になりました。ここからは法規制への対応と異なり世界的に通用する評価結果が得られるため、海外でビジネスを展開する事業者にとっても使いやすいものとなります。
4.リスクコミュニケーション
世界行動戦略は、リスクコミュニケーションがリスク管理に重要な役割を果たすことを指摘しています。事業者の安全管理活動では、リスク評価結果とリスク削減結果を、リスクコミュニケーションに参加する利害関係者に伝達し理解を求める場ではなく、さらに続くリスク管理活動のステップの一つとして考えることができます。
リスクコミュニケーションでは、事業者は自らのリスク削減活動の結果を報告し、社会的責任を全うしていることの理解を得て円滑な事業活動の継続と発展を目指します。そのこと自体は誤ってはいませんが、結果だけでなくリスク評価プロセスの開示が、より利害関係者の理解を得ることにつながるでしょう。科学的な考察を経たリスク評価プロセスが、利害関係者に理解されるかどうかと訝る向きもありますが、そこはそれほど気にする必要もないでしょう。正確な情報を論理的に説明することで、完全とはいかないまでも理解は得られるものと考えます。保有するデータの開示は信頼関係の醸成に役立ち、その後の良好な関係を保つことにつながります。リスクコミュニケーションを、事業者から出席した利害関係者に対する「説得」の場としてはならないでしょう。
事業者とは立場の違いがあるため、利害関係者がコミュニケーションの場でリスク評価結果に同意するとは限りませんが、信頼関係を築くことができれば、継続的な対話も可能となります。データの開示と対話の過程で、事業者にとっても新しい気づきが生まれそれが化学物質の安全管理活動につながることも期待できます。
5.リスクの考え方
最近は「リスク」という言葉を耳にする機会が増えているようですが、「まだ起こってはいないが起こると困る事象」を指していることが多いように思います。しかし、数値化あるいは相対化された複数の異なる事象の「リスク」を考えることは、限られたリソースを用いて対策(リスク削減)を行う際の優先順位の決定を容易にすることになり、事業者にとっては利用価値が高いものです。リスク評価の手順に習熟して、これからの化学物質の管理活動に生かすことが事業者には求められているように思います。